パネル3「核拡散抵抗性の高い原子力システム技術開発の現状と将来展望」
| ・座 長 | : | アレックス・バーカート | 米国 国務省 国際安全保障不拡散局 原子力政策・安全・保安部 次長 |
| ・パネリスト | : | ウィリアム・オコーナー | 米国 エネルギー省 国家核安全保障庁 防衛核不拡散局 核解体・透明性課 課長代理 |
| ジャン・カザレ | 仏国 原子力庁 原子力開発局 原子力技術開発本部 副本部長 | ||
| ウラジミール・カグラマニャン | 露国 物理エネルギー研究所 副所長 | ||
| 佐賀山 豊 | 日本原子力研究開発機構 次世代原子力システム部門 副部門長 |

パネル3では、第4世代原子力システム(GEN-IV)、米国国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)、IAEAのINPRO(International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles)、原子力機構を中心とした高速増殖炉サイクル実用化戦略調査研究(FS)、及びフランス等において検討が進められている将来の原子力システムにつき、その開発の状況と各々のシステムにおける核拡散抵抗性の高い技術について紹介された。露は、こういった国際的な取り組みの中で、いかに技術的及び制度的に核拡散抵抗性を向上していくかを述べた。その後、抵抗性を軸にした開発のあり方、経済性との関係、国際協力の方向性について議論が行われた。概要は以下の通り。
(なお、各パネリストの発言につき、国名、もしくは機関名でこれを表示しているが、あくまで個人の資格としての発言である。また、この概要は核不拡散科学技術センターが編集したものであり、その内容については座長・パネリストの確認を得たものではない。)
パネルの冒頭、座長は「核拡散抵抗性は技術的な問題としてよく議論されるが実際には政治的なもの」と述べ、2002年にIAEAが次世代原子力エネルギーシステムの核拡散抵抗性に関して開催した技術会合の結果について、同会合にIAEAの立場で参加したカグラマニャン氏が紹介した。この中で核拡散抵抗性は「原子力システムの中で国家が核兵器あるいは他の核爆発装置の獲得を目的として、技術の誤用、核物質の転用、あるいは未申告の生産を行うことを阻止するもの」と定義され、対象は国家のみであり、非国家主体については、別の活動としている。抵抗性の度合いは、「内在的特徴」* 1 と「外在的措置」* 2 の組み合わせに依拠し、これらが最適に組み合わされる時、費用対効果が最大になる、原子力エネルギーシステムの開発の早期段階で外在的措置の1つである保障措置が考慮されることで抵抗性が強化される、抵抗性の考え方には、国の政治状況の違い、技術的な状況の違いが係わってくる、と述べた。
続いて、米、仏、日のパネリストから各国で検討されている核拡散抵抗性の高い先進燃料サイクル技術等につき紹介があった。
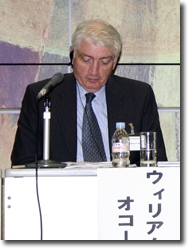 米:(配布資料:Global Nuclear Energy Partnership Technology Demonstration Program)
米:(配布資料:Global Nuclear Energy Partnership Technology Demonstration Program)
国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)は、核不拡散を要とする将来の原子力の新しいパラダイム。国家による拡散リスクと非国家主体によるテロの双方を視野に入れている。設計の中に核不拡散の概念を織り込んだ技術開発を行い、米国内で主要技術を実証し、国際的なパートナーと様々な技術の開発・確立を行うもの。この中には先進的な保障措置技術の開発も含まれる。
様々な分野で共通の関心がある部分について、色々な研究パートナーと協同していく。今後、技術実証と開発が実施されるが、各国との協力が成功の鍵となる。
 仏:(配布資料:Future nuclear cycle systems and technology enhancing proliferation resistance)
仏:(配布資料:Future nuclear cycle systems and technology enhancing proliferation resistance)
原子力の拡大のための必須条件は、放射性廃棄物と放射線毒性の最小化、天然資源の保持、及び核拡散抵抗性を備えた持続性(sustainability)であり、この持続性を満たす一番よい原子力のオプションとして、仏は、クローズ燃料サイクルと高速炉(ナトリウム冷却炉もしくはガス冷却炉)を追求する。2006年1月のシラク大統領の声明では、CEAによるGEN-IV原型炉の設計を開始して2020年に運転開始を目指すというターゲットと、産業界及び国際パートナーとの協力を推奨する方向を示した。
GEN-IVが描く統合型燃料サイクルは、グローバル・アクチニド・リサイクル、つまり国際協力の下に実施するアクチニド・リサイクルで、再処理と燃料加工の統合施設で使用済燃料の再処理と燃料加工を行い高速炉でこれを燃焼させるというリサイクルである。ウラン、プルトニウム、マイナーアクチニドをグローバルにリサイクルするため、天然ウランや劣化ウラン等を原料として投入すると最終的な廃棄物はFP(核分裂生成物)のみとなる。このグローバル・アクチニド・リサイクルは輸送に伴うリスクが低減する、プルトニウムが単体で存在しない、プルトニウムが蓄積しない、また濃縮ニーズも低減する、という意味において核拡散抵抗性の観点からは非常に優れたシステムである。
さらに、燃料サイクルと原子炉技術を包括的に考え、最初の概念設計の段階から保障措置を考慮していく、すなわち核拡散抵抗性の内在的特徴と外在的措置の組み合わせを検討していくことが重要であり、その点は安全性と同様の手法が応用できる。
 日:(配布資料:高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究における核拡散抵抗性について[日]、Nuclear Proliferation Resistance in Feasibility Study on Commercialized Fast Reactor Cycle Systems[英])
日:(配布資料:高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究における核拡散抵抗性について[日]、Nuclear Proliferation Resistance in Feasibility Study on Commercialized Fast Reactor Cycle Systems[英])
原子力機構を中心に実施している「高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」(FS:Feasibility Study)のフェーズIIは今年3月に終了し、現在、文部科学省で評価が行われている。今後は、フェーズIIの成果を元にフェーズIII(採用する革新技術の決定)、フェーズIV(実用の具体像と実用化への研究開発計画の提示)へと研究開発を進めていく。
フェーズIIでは、核拡散抵抗性を含む5つの目標を掲げ、複数候補概念の研究開発と評価を実施した。核拡散抵抗性については、3つの設計要求を(1)核物質防護・保障措置への対応を考慮した設計、(2)プルトニウムが単体の状態で存在しないこと、及び(3)低除染・TRU燃料の使用に伴う高線量化による接近性の制限とした。保障措置の技術的要件については、FSが主概念として採用した先進湿式法について成立する見通しを得た。本先進湿式法では、プルトニウムを単離することは実際上不可能と考える。さらに抵抗性を高める取組みとして、高速炉においてプルトニウムの品位を下げる、再処理において全てのアクチニドを一括回収する方法も検討している。
FSにおいては今後も核拡散抵抗性を重要な開発目標と考え、国際協力の下、核拡散抵抗性の内在的特徴を高める技術開発を行い、一方で保障措置概念や手法を検討して施設の設計段階からこれを取り入れることで核拡散抵抗性の外在的措置を高めていくことが可能と考えている。時代と共に変わる核不拡散環境に対応するためにも、IAEAや各国との国際協力が必要である。
 露:(配布資料:Global nuclear energy initiatives - new opportunities for addressing non-proliferation challenges through optimum use of institutional and technical measures)
露:(配布資料:Global nuclear energy initiatives - new opportunities for addressing non-proliferation challenges through optimum use of institutional and technical measures)
露ではここ1〜2ヶ月以内に高速炉概念を含めた国家開発計画が策定される予定である。
現在の各国の原子力システムは軽水炉ベースであり、コスト効率が高いが、天然ウランの利用が非常に非効率かつ濃縮やプルトニウム貯蔵等の核不拡散の観点でデメリットがある。これをグローバルなエネルギー開発シナリオにあてはめると、ウラン-235の枯渇、多くの国が濃縮技術を開発する必要が生じる、また、使用済燃料が多くの国で蓄積するという問題がある。これの対処として3つの長期的なシナリオが考えられるが、どのシナリオにおいても使用済燃料が蓄積されてしまう。これらの技術的問題に対処するためGEN-IVやINPROイニシアティブがある。技術的な対処だけでは核不拡散の課題、特に中期的な課題に対処できないため、エルバラダイIAEA事務局長の多国間管理構想(MNA)、露の国際燃料サイクルセンター構想、米ブッシュ大統領提案とそれを受けた米国GNEPなどの構想が提案されているが、どれも中期的な解決策がすぐには見出せない。現状での問題解決への取り組みとして、米のアイデアである燃料サイクル国のコンソーシアムと仏の再処理技術+露の高速炉のコンビネーションをアプローチとし、高速炉の開発・建設を早めるのが適しているのではないか。
核不拡散の要件は国(核兵器国/非核兵器国など)によって異なり、すべての技術(再処理、原子炉など)に対して同一に考慮されるとは限らない。また、各々の国のグローバルなビジョンにも依存してくる。そのような現状において、今必要なのは、各国での相違を考慮しつつも、世界的な利益のために協力して検討を行っていくことが必要と考える。
上記、各国からのプレゼンテーションの後、パネリスト間での討議が行われた。
先進燃料サイクル技術における核拡散抵抗性向上の目的(どういう脅威を想定して核拡散抵抗性を向上させようとしているか)については、核兵器国と非核兵器国では核拡散抵抗性の意味が異なり区別して考える必要があり時代によっても異なる、GNEPでは当該技術が米国だけでしか使えないのではGNEPの目標が達成されないので核兵器国と非核兵器国双方で使えるものであるべき、GNEPでは燃料サイクル全体に対する保障措置技術を開発しようとしているがそれは保障措置をどう適用するかはIAEAが決めるべきこと、誰が施設や技術を使うというより技術開発を行う上では国やテロの脅威を含めて核拡散抵抗性の高い技術を使うことがその技術が世界にも通用する技術である、との意見があった。また保障措置のあり方については、概念設計段階から保障措置の検討を取り込むことが重要、等との意見があった。
GEN-IVとGNEPの進め方については、米から前者は共通の技術を長期的に研究開発するプログラムである一方で、後者は比較的短い期間で実際にシステムや技術を構築するものであり、例えばGNEPでは先進燃焼炉(ABR)が考えられているがGEN-IVでは増殖炉が想定されている、GNEPの研究開発は米国だけでなく国際的なパートナーによって実施されGEN-IVにも役立つものとなるだろうし、お互いのインターアクションが利益になる、と説明があった。また燃焼炉と増殖炉では炉のターゲットは異なるが高速中性子の利用という技術的観点から見た場合かなり合致しており、GNEPの仕組みや進め方が明らかではないが、分離した形でなく、お互いに協調し補完しつつ進めていくのが望ましい、との意見があった。
パネリスト間での討議の後、フロアからを対象としてパネリストとの質疑応答が行われた。
核拡散抵抗性と経済性は相反するものではないか、との質問に対しては、再処理/高速炉サイクルは経済性を十分にあげられるシステムである必要があり経済性は開発目標としている、核拡散抵抗性は内在的特徴と外在的措置を組み合わせることにより経済性を考慮した可能性が模索できる、核拡散抵抗性と経済性は相反するものではなく、例えば燃焼度を上げることは、経済性を上げる点及び抵抗性の観点からも意味があり、施設の数を増やす等により競争力を持たすことが可能であろうし、また目指すべき方向である、等との回答がなされた。
また、GNEPにおける高速炉や再処理技術開発の国際協力のパートナーとなれる国については、米から、分離技術に関しては既にフルスケールの再処理プラントを所有している国に限られる、しかしそれ以外は内容に合わせてパートナーを求めて協力したいし、コスト削減にもつながる、との回答がなされた。
さらに、どこまで核拡散抵抗性を高めていく必要があるか、については、核拡散抵抗性は安全性と共通点があり、原子力エネルギーを利用する限り、リスクゼロはありえず一定のレベルは受け入れる必要がある。受容可能な拡散リスクのレベルは国ごと(核兵器国/非核兵器国など)、その時の状況、時代によっても異なる、との回答がなされた。
GNEP等のイニシアティブでは、ユーザー国から供給国への使用済燃料の輸送頻度が増加することが考えられるが、核拡散抵抗性上問題がないといえるか、の質問に対しては、輸送頻度と経路、要する時間は限定的で合理的に監視できる、との回答があった。
最後に座長より、核拡散抵抗性については、まだ沢山の議論すべき問題があり、今後もいろいろな場でさらなる議論が必要である、とまとめがあった。


* 1 内在的特徴 (intrinsic characteristics):核物質そのものの特徴や技術的な設計により抵抗性に影響するもの、例:同位体組成、放射能、転用検知性、等
* 2 外在的措置 (extrinsic measures):制度として外部から措置して抵抗性を高めるもの、例:保障措置、核物質防護、等
