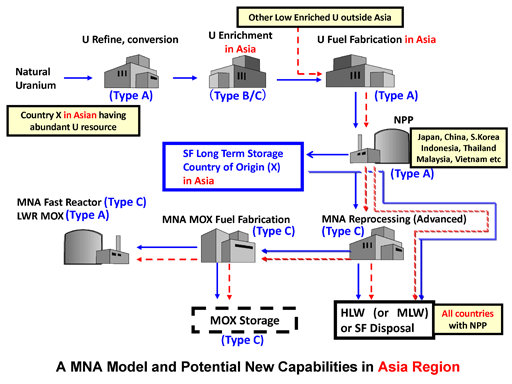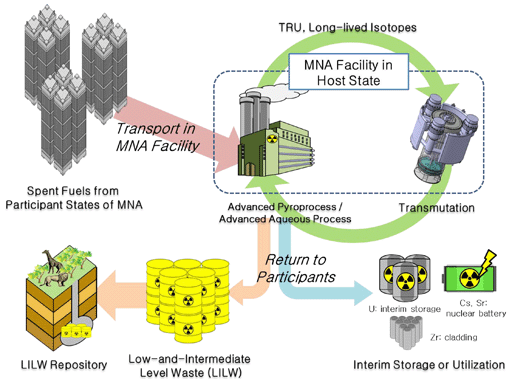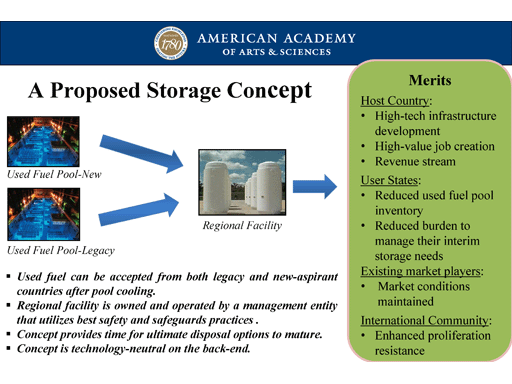原子力と核不拡散、核セキュリティに係る国際フォーラム
−核燃料サイクルのバックエンドにおける核不拡散、核セキュリティ確保とアジアにおける地域協力−
結果報告
平成24年12月12日(水)、13日(木) 東京大学 伊藤国際学術研究センター 地下2階 伊藤謝恩ホール
開会挨拶
鈴木 篤之 日本原子力研究開発機構理事長
 鈴木理事長
鈴木理事長「原子力と核不拡散、核セキュリティに係る国際フォーラム」の開催に当たり、主催者を代表して、一言ご挨拶申し上げる。本フォーラムにお集まりいただいた皆様、特に海外の様々な国や国際機関から、また、国内からも講演者及びパネリストとして多くの専門家にご参加いただいたことに感謝申し上げる。
本フォーラムが国内外の方々から様々な御意見を頂戴することにより、真に有意義で建設的なものになることを期待する。本フォーラムは、年末のこの時期に毎年開催し、今年は東京大学の元総長で、参議院議員として文部科学大臣にも就かれ、日本の科学技術行政の総帥として陣頭指揮していただいた有馬朗人先生に、お忙しい中御出席頂き最初の基調講演を引き受けて頂いた。先生は原子核物理学の泰斗で、原子力に関するご造詣が深く、また、その科学技術的本質を洞察されておられる。本日は、福島第一原子力発電所事故以降、その教訓を生かすべく取り組みつつも、なかなか先が見えない原子力の現状に対し、厳しくも温かいご叱責をいただけることを期待している。日本以外からは、IAEA、米国、仏国、韓国から、基調講演をお願いしており、事故以降の情勢変化を踏まえた状況を御紹介いただける予定である。
福島第一原子力発電所事故の結果、原子力安全の徹底的強化が図られつつあると同時に、いわゆる3Sのうち、原子力安全以外の2S、すなわち、保障措置及び核セキュリティも原子力利用を進める上において必須であることは言うまでもない。実際、2012年9月に、我が国で新たに設立された原子力規制委員会及び原子力規制庁は、2013年4月にその所掌範囲を拡大し、核セキュリティ、保障措置を含むすべてに係る規制機関として、その役割を担うことになっている。
核不拡散・核セキュリティの不変的重要性に鑑み、原子力機構は今後とも、平和利用と核不拡散に関する社会的理解の増進と国際的議論の促進を目的として、このフォーラムを、毎年開催し、その時々のトピックスに関する課題とその解決策を率直に話し合って行くことを考えている。
今年のフォーラムでは、国際的に話題となっている2つの課題を取り上げる。一つは核燃料サイクルのバックエンドであり、もう一つはアジアにおける原子力発電の拡大である。
福島第一原子力事故以降、原子力政策が見直されているが、いかなる政策をとったとしても、核不拡散及び核セキュリティを確実に維持して行くことの必要性に変わりはない。核燃料サイクルのバックエンドはその観点からもっとも注意を払うべき領域と考えられ、本日午後に予定されるパネル討論1では、バックエンドに焦点を当てた討論をお願いしている。
また、原子力発電の拡大が想定されているアジアにおいて、核不拡散と核セキュリティを確保しつつ原子力発電を進めて行くことが地域全体にとって極めて重要である。この観点から、明日の午前に予定されるパネル討論2では、アジアの原子力平和利用確保策及び、同分野における日本等の原子力先進国を含む多国間協力の枠組みの実現性について、供給国側の視点からの議論をお願いしている。
いずれのテーマも、原子力平和利用を世界的に進めて行く上で解決せざるを得ない問題であり、極めてチャレンジングな課題である。もとより、一日や二日で議論を尽くすことはできないが、今後の方向性を考える上で貴重なご示唆をしていただけることと期待している。
基調講演
日本の原子力利用と核不拡散
有馬 朗人 学校法人根津育英会武蔵学園長 / 元科学技術庁長官 / 元文部大臣
 有馬 朗人氏
有馬 朗人氏一次エネルギー資源が非常に少なく、自給率が僅か4%に過ぎない日本にとって、エネルギーセキュリティの確保は極めて重要な課題である。また、地球温暖化の危機を避けるためにも、日本は再生可能エネルギーの開発を早急に進めなければならない。同時に安全性を十分に確立し、核不拡散を完全に守りつつ、原子力の利用についても将来計画を立てなければならない。
2011年3月11日の福島原子力事故は国民の原子力に対する不信感を生むことになったが、一時的な感情やポピュリズム的立場からでなく、理性的、科学的な議論を行い、冷静に将来を決定して行かねばならない。
福島原子力事故について更に調査研究を進め、事故の状況を十分に分析、反省し、将来への対策を立案する上で大いに教訓を学び取るべきである。2012年9月の原子力規制委員会の発足により、(1) 原子力規制と利用の分離、(2) 規制の一元化、(3) 透明性の高い情報公開、(4) 重大事故対策の強化、最新知見に基づく原子力安全規制の実施、40年運転制限の導入等の原子力規制の転換、(5) 原子力防災体制の強化、を柱とした原子力規制体制の改革が進んでいるが、この改革を強力に遂行すべきである。
長年原子核物理学を研究し、更に科学技術庁長官として原子力に関係してきた人間として、いくつかの反省点を述べたい。1997年頃、当時の橋本首相が行政改革を進めたが、文部省と科学技術庁が合併し文部科学省となったことにより、文部科学省の中の原子力の優先順位が相対的に下がったという点、原子力の推進と規制の分離が不十分であった点が反省点として挙げられる。また、核燃料サイクルのバックエンド技術の確立をもっと進める努力をすべきであったと考える。廃炉、再処理、最終処分等のバックエンド技術の研究や開発は、今からでも遅くなく、早急に推進すべきである。特に急ぐべきは、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の決定である。更には、原子力発電所における津波対策については過信があったことも反省点として指摘しておきたい。
原子力利用と核不拡散について、日本は国際的な責任を有する持ということを忘れてはいけない。日本は既に2011年末現在、国内で9.3ton、仏国と英国に合計35tonのプルトニウムを保持している。日本には、このプルトニウムをどのように使用して行くかについての国際的な説明責任がある。日本は今日まで原子力平和利用に対する国際的な信頼に基づいて、原子力利用を進めてきた。我々はこのような信頼を失う行為をしてはならず、信頼を維持すべく慎重に行動すべきである。
再生エネルギーの開発には時間がかかること、比率を増やそうとしても一定の限界があることはドイツの例が示す通りであり、引き続き原子力を利用していく必要がある。日本では長期的な研究開発の努力の結果、原子力の技術的水準は世界的に最も高い国の一つになっている。国際的見地から、日本の技術力かつ人的基盤を維持、強化することが我々の責任である。 将来のために私が提案したいことは、
- 日本は、廃炉、事故処理、高レベル放射性廃棄物の最終処分、核不拡散・核セキュリティ、高速炉など次世代の原子炉や核燃料サイクルの研究開発の分野で活躍すべきこと
- 福島第一原子力発電所の現場に、国際的な原子力研究所を作り、廃炉処理の研究や、安全性の研究を国際的に行うべきこと
- 大学や、原子力機構等、原子力研究機関の研究基盤を強化すべきこと
- 原子力の規制及びそのための研究開発は、相互の連携を確保する観点から一つの機関で実施すべきこと
- エネルギー安全保障の長期的展望の観点から、原子力エネルギー政策を議論する場として、原子力委員会の役割を保持すべきこと
などである。
核燃料サイクルのバックエンド:保障措置に係る現在及び将来の課題
ハーマン ナカーツ 国際原子力機関(IAEA) 保障措置担当事務次長
(代読:ピーター ランス 国際原子力機関(IAEA) 実施A部 調整支援課長)
 ピーター ランス氏
ピーター ランス氏1970年〜80年代にかけて、IAEAによる申告核物質の検認は概ね関係者を満足させるものであったが、1991年に露見したイラクの秘密裡の核兵器計画により、未申告の核物質及び原子力活動の検知能力の強化が提起された。これを契機に導入された追加議定書は、国家の原子力活動に関する追加的な情報をIAEAに提供、またIAEAに対し幅広いアクセス権を認めることにより包括的保障措置を補完するものとなっている。またIAEAは、保障措置の実施及び評価について国全体を対象として見る国家レベルの保障措置手法(国レベルのアプローチ)を導入した。このような国家を「全体として」見る手法は、保障措置上最も重要な課題にその資源を集中するもので、保障措置の強化とともにその有効性と効率性の向上の要求にも応えるものである。
2010年9月に保障措置担当事務次長に就任した直後から、私は、国レベルのアプローチを更に発展させ、より広範に適用するプロジェクトを開始した。このプロジェクトは統合保障措置が適用されている国だけでなく、保障措置協定を締結する全ての国に対して国レベルのアプローチを適用しようとするものである。こうしたアプローチにおいては、保障措置の適用にあたり、核燃料サイクル能力、保障措置協定、IAEAとの協力の程度といった、保障措置適用に関連する当該国特有の要因が考慮される。
核燃料サイクルのバックエンドに適用される保障措置手法も、以上、述べたような最近の保障措置に関するアプローチの変化に鑑み、保障措置の実施に関連する当該国特有の要因を勘案したものになるであろう。
再処理に関してIAEAが有する保障措置の経験の殆どは、日本の2つの再処理施設に対する保障措置適用により得られたものである。再処理はプロセス中において、核兵器に転用可能なプルトニウムを分離することから、保障措置上、よりチャレンジングな側面を有するが、様々な手段によって効果的に保障措置を適用する手法が確立している。また、核セキュリティの観点からは、使用済燃料の中間貯蔵やそれに続く再処理、これらのための輸送に係る脅威や脆弱性に対する考慮が必要となる。
使用済燃料の処分場に適用される保障措置概念は既に構築されており、当該国の状況も勘案して適用されることになる。使用済燃料に対する保障措置は、定置期間中及び処分場が閉鎖されて以降も継続することになる。使用済燃料の処分に適用される保障措置の手法は、定置された使用済燃料の再確認ができないことから、システム故障の可能性を回避し、かつ知識の連続性を確実にするように、採用された措置が十分な冗長性、多様性及び堅牢性を含むことが重要である。具体的な保障措置の手法として、建設前の段階においては、処分サイトに関する知識の確立、建設段階では、設計情報の検認、運転段階では移動や在庫の検認、処分場閉鎖後は地上のモニタリング(目視や遠隔監視等)等が含まれる。
使用済燃料を直接処分するか、あるいは再処理するかを国家が決定する際には、核セキュリティの観点からの考慮も必要である。具体的には各オプションについて、関連施設や輸送の際の核物質防護措置の基礎となる脅威を評価することが必要である。また、個々の施設の防護システムと防護方法の設計は最新の脅威評価に基づきなされる必要がある。
2013年7月にIAEAは閣僚級の核セキュリティに関する国際会議を主催する予定である。各国政府の閣僚に加えて、規制当局、法執行機関及び事業者が参加する予定である。参加国や参加者の多様性を確保するだけでなく、核燃料サイクルのバックエンドも含めた、核セキュリティに関連する全ての分野を対象とする意味において、内容においても包括的なものとなることが期待される。
米国の原子力利用と核不拡散の取組み
ピーター ハンロン 米国エネルギー省(DOE) 国家核安全保障庁(NNSA) 防衛核不拡散局 核分裂性物質処分担当次官補代理
(代読:ガイ ランスフォード 米国エネルギー省(DOE) 国家核安全保障庁(NNSA) 核分裂性物質処分部 国際プログラム課長)
 ガイ ランスフォード氏
ガイ ランスフォード氏原子力利用が拡大するアジア地域における主要課題の一つは、核燃料サイクルのバックエンド対策であり、再処理技術の拡散に付随するリスクと、プルトニウムの分離及びその最終処分に付随する核セキュリティの懸念である。我々が力を合わせ、原子力利用と核不拡散及び核セキュリティのバランスをとっていくことが必要である。
国家のエネルギー戦略の如何に拘わらず、核物質が存在する限り、高濃縮ウランとプルトニウムがもたらす核セキュリティのリスクを認識し、核物質の安全性とセキュリティを確保しつつ、これらを処分する道筋を明確に定めることが重要である。米国は、安全保障上、余剰とされた核兵器を解体して生じた高濃縮ウランとプルトニウムの処分方法を開発してきた。本講演では日米間の核不拡散に係る協力と、米国による高濃縮ウランとプルトニウムの処分の取組みについて紹介する。
DOE/NNSAと日本は、長期に渡り原子力の平和利用が安全、セキュリティ、保障措置を確保しつつ行われるよう、協力してきた。原子力機構との保障措置、核セキュリティ及び核不拡散に係る協力は、その前身組織も含め、来年で25周年を迎える。また2011年1月、日米両国は新たな核セキュリティ作業グループを設置し、原子力機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センターや核鑑識、国際保障措置、IAEA核セキュリティ勧告(INFCIRC/225 Rev.5)の敷衍等を含む9つの分野で協力し、注目すべき成果を達成した。
余剰核兵器の解体から生じた高濃縮ウランとプルトニウムは、安全とセキュリティを確保しつつ、不可逆的な方法で処分することが重要であり、米国では高濃縮ウランを希釈して低濃縮ウラン(LEU)とし、国内の商用原子炉燃料として使用している。また米国は、2011 年のIAEA 総会で「米国による保証された核燃料供給1」と称するLEU備蓄の可用性を発表した。このAFSは、解体核兵器から生じた17.4MTの高濃縮ウラン(HEU)を希釈した約230MTのLEUを備蓄するものであり、新興の原子炉利用国に対しLEUの供給を保証することにより、ウラン濃縮技術開発の必要性を低減させるものである。
米国は露国との間で、余剰核兵器の解体から生じた高濃縮ウランやプルトニウムの処分につき協力を行っている。
高濃縮ウランについて、1993年に米露は、高濃縮ウラン購入協定2を締結し、2013年末までに露国の解体核兵器に由来する500MTの 高濃縮ウランをLEUに希釈して米国に売却することに合意した。2012年11月現在、470MTの高濃縮ウランが希釈され、2013年11月には500MTに達する見込みである。
一方プルトニウムについて、2000年に米露は、プルトニウム管理・処分協定(PMDA)3を締結し、両国が少なくとも34トンのプルトニウム(計17,000発の核兵器に相当)を不可逆的かつ透明性をもって処分することを約束した。次いで両国は、2010年の第1回核セキュリティ・サミットの際、PMDAの改正議定書(改正PMDA)に署名した。両国における処分を確実にするためにIAEAが検認することとし、現在、検認に係る米/露/IAEAの三者間協定につき協議が行われている。改正PMDAの鍵は、高速炉利用を含む露国の原子力利用戦略との整合性であり、露国は核不拡散に係る一定の条件の下で高速炉を運転しプルトニウムを処分すること、具体的には、(1)高速炉の増殖比を1未満としプルトニウム量を減少させること、(2)いかなる兵器級プルトニウムも生産しないこと、を改正PMDAで確約している。一方米国は、サウスカロライナ州に建設中のMOX燃料加工施設でプルトニウムを劣化ウランと混合して混合酸化物(MOX)燃料とし電力会社へ売却、軽水炉燃料として使用する。このように米露は、国家のエネルギー戦略や使用する原子炉の相違はあるものの、兵器級プルトニウムの処分を安全とセキュリティを確保しつつ、不可逆的な方法で達成する。
本フォーラムが、原子力と核セキュリティにおける対話を広げ、核燃料サイクルのバックエンド並びに高濃縮ウランとプルトニウム処分に関する専門技術を活用する上で、新しい機会を提供することを希望する。
1American Assured Fuel Supply (AFS)
2Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Russian Federation Concerning the Disposition of Highly Enriched Uranium Extracted from Nuclear Weapons
3Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Russian Federation Concerning the Management and Disposition of Plutonium Designated as No Longer Required for Defense Purposes and Related Cooperation (PMDA)
仏国新政権の原子力エネルギーと核不拡散政策
フレデリック モンドロニ 仏国原子力・代替エネルギー庁 企画・渉外局長兼国際本部長
(代読:クリストフ グゼリ 在日フランス大使館 原子力参事官)
 クリストフ グゼリ氏
クリストフ グゼリ氏2012年初めに行われた仏国大統領選挙及び国民議会選挙により政権が交代し、社会党のオランド氏が大統領となったが、仏国のエネルギー及び原子力政策に大きな変化は見られない。
仏国はエネルギー資源に乏しく、1970年代はエネルギー需要のほぼ全量を輸入するという日本と類似した状況にあり、石油ショックは仏国経済を脅かした。石油の代替として安定的な供給が可能なエネルギーは原子力のみであり、エネルギー安全保障とエネルギーの自立の確保のため、仏国政府は原子力エネルギーを仏国での電力供給の柱とすることを決定した。原子炉技術としては、米国起源の加圧水型原子炉(PWR)技術を採用し、また長期的な視点から、再処理や核燃料リサイクル、高速炉開発を行うこととした。技術の標準化と産業界の献身的努力により、現在、仏国の電力価格は欧州で最も安価となっている。
2000年代に入り、気候変動とCO2の削減の必要性が欧州の人々に深刻に受け止められるようになり、欧州連合(EU)は2020年までに、CO2排出量を20%削減し、エネルギー効率を20%上昇させ、さらにエネルギーミックスの中で再生可能エネルギーの割合を20%にするとの野心的な目標を設定した。これは拘束力のあるものであり、仏国を含む欧州各国はこれに同意している。仏国新政権や新国民議会が新政策を立案したとしても、欧州のコミットメント及び仏国の基本的なエネルギー政策の原動力は変わらない。原子力は仏国の全発電量の75〜80%を占め、CO2を排出せず、価格競争力もあることから、原子力に係る決定を軽々しく行うことはできない。
2011年3月の福島原子力事故は衝撃的な出来事であったが、仏国原子力安全機関(ASN)は直ちに国内全ての原子力施設の外部事象に対する抵抗力の徹底的なチェックを指示した。また同様の「ストレステスト」は欧州レベルでも実施された。ASNは1月初めに、仏国内の全ての原子力発電所に関し、安全を更に強化すべきであるが、運転を継続するに十分な安全性を有しているとの結論を出し、この結論は仏国民から支持されている。
大統領選挙においては福島原子力事故を受け、2020年代半ばまでに現在の電力発電量における原子力の割合を75%から50%に削減すると公約した(ただしリサイクル路線は維持)オランド候補が当選した。新政権の主要な原子力政策、核不拡散政策は以下に要約できる。
- 既存の稼働中の原子炉は運転を継続する(フッセンハイムの原子炉は、現地の送配電のバランスを改善することを条件とし2016年までには運転を停止する)
- フラマンビルのEPRの建設は継続し2016年に発電開始予定
- 再処理とリサイクル路線を継続(ラアーグの再処理施設とメロックスのMOX燃料製造施設は運転を継続)
- エネルギー転換の国家的議論の開始(欧州のコミットメント及び発電価格を維持しつつ、原子力の全発電量に対する比率をどのように50%までに削減するかを含む)
- 原子力の比率を50%以下には下げないというのが政府の強い意志である。エネルギー転換の方策は2013年春までに発表される。
- 最高レベルの安全性を維持したEPRや日本と仏国の合弁会社によるATMEA炉の輸出の継続
- IAEA追加議定書の普遍化への支持、原子力供給国グループ(NSG)の活動への支援
- 原子力を導入する国が自ら濃縮、再処理を実施する必要性をなくす観点からの使用済燃料管理サービスや濃縮サービスの提供の継続
- 包括的核実験禁止条約(CTBT)や核兵器用核分裂性物質の生産停止に関するコミットメントの継続
- イラン、北朝鮮、シリアの核問題の解決への取組みについては前政権の政策を継続
仏国と日本は50年近く原子力の分野で協力してきている。仏国には、日本が保有するプルトニウムが存在するが、日本が仏国に対するコミットメントを維持し、将来的に当該プルトニウムが仏国でMOX燃料に加工され、日本国内の原子炉に装荷されることを期待している。また、より広い意味で、最近の日本の政策決定が原子力分野や核不拡散分野における日仏間の協力の妨げになることがないよう願っている。今後も原子力エネルギーは、エネルギー供給の重要な柱であることに変わりはない。原子力利用に関し、既に確立した基盤と多くの経験を有する日本や仏国は、原子力の平和利用に関し、新興の原子力利用国を支援する義務がある。
韓国の視点:原子力エネルギー、核不拡散、原子力安全
パク ノビョク 韓国外交通商部 エネルギー資源大使
 パク ノビョク氏
パク ノビョク氏I 韓国のエネルギー政策と原子力
韓国は日本に次いで世界第3位のエネルギー輸入大国で、約97%を輸入に頼り、その額は年額で約1,710億ドルに達する。韓国のエネルギー計画では、2030年までに化石燃料への依存度を減らし、原子力と再生可能エネルギーへの依存度を約40%までに引き上げることを目標としている。再生エネルギーの開発には多くの時間と費用を要することから、短期的には原子力にプライオリティが置かれている。
II 韓国における原子力開発
韓国の原子力に係る研究開発と産業は、過去40年間に飛躍的な成長を遂げた。現在では23基の原子炉が稼働している。ウェスチンクハウス社から導入した技術を基に、OPR1000やAPR 1400といった国産炉の開発、標準化に成功した。韓国はエネルギー安全保障の観点から、特にバックエンドにおける核燃料サイクル能力を強化したいと考えており、米国との新たな原子力協定が、それを実現し、国際的な核不拡散を促進しつつ、継続的な経済成長を保証するものになることを期待する。
III 韓国の核不拡散に係る責務
韓国は原子力の平和利用の権利を核兵器製造目的に濫用しないことを確約している。こうした韓国の核不拡散に対する厳格なスタンスは、北朝鮮の核兵器開発の全面的放棄に不可欠である。韓国は核不拡散に関する全ての法的な措置をとっているが、核不拡散を達成するには法的、技術的手段だけではなく、政治的なコミットメントが必要であり、日本や韓国は米国との信頼関係と安全保障上の協力関係を継続していく必要がある。
韓国では、2006年に、韓国核不拡散管理院(KINAC)が、昨年には韓国原子力安全・核セキュリティ委員会が、それぞれ設立された。
IV 原子力安全と韓国及び日本の課題
2011年3月の福島原子力事故以降、原子力安全は原子力利用国の間で最も関心の高い問題となった。韓国では、大規模地震が発生する可能性は極めて低いものの、地震災害に対する様々な安全対策を原子力プラントに施した。日韓両国では議会選挙、大統領選挙が予定されており、その結果は両国の原子力政策に大きな影響を与える可能性があるが、選挙の結果如何にかかわらず、両国は原子力に対する公衆の信頼の回復、使用済燃料の管理、中国の台頭等、アジアにおける原子力に関する勢力地図の変化への対応という、共通の課題を有する。
V 韓国と日本のエネルギー協力
韓国と日本は、原子力の研究開発の分野、具体的には、(1)原子力安全の強化、(2)核燃料サイクルのバックエンドと関連する原子炉、(3)地層処分技術開発、(4)グローバルな保障措置と核セキュリティの強化、(5)廃止措置、の5つの分野で協力することができると考える。さらにグローバルな視点と現実を見据えた取り組みとして、韓国と日本は、中国の原子炉におけるより高い安全基準の維持につき協力していく必要があり、地域の多国間枠組みも考える必要があるだろう。日中韓のトップは、既に原子力事故の防止につき議論を開始しているが、さらに幅広い協議が必要であろう。
まとめ
現在原子力は、一般公衆の信頼を回復しなければならない状況にある。これは非常に重要なことであり、日韓両国は、エネルギー安全保障や持続可能なエネルギー等の分野で協力が出来ると考える。本フォーラムが上記に関し、様々なアイディアを生み出し、将来に有望な道を切り開くことに繋がることを期待する。
パネル討論1「核燃料サイクルのバックエンドにおける核不拡散、核セキュリティ確保の方策」

- 座長
- 伊藤 隆彦 日本原子力文化振興財団理事長 / 核物質管理学会日本支部会長 / 中部電力顧問
- パネリスト
- ガイ ランスフォード 米国エネルギー省(DOE) 国家核安全保障庁(NNSA) 核分裂性物質処分部 国際プログラム課長
- ピーター ランス 国際原子力機関(IAEA) 実施A部 調整支援課長
- シャロン スクワッソーニ 米国戦略国際問題研究所(CSIS)拡散防止プログラム部長兼上級研究員
- クリストフ グゼリ 在日フランス大使館 原子力参事官
- 遠藤 哲也 日本国際問題研究所「新しい核の秩序構想タスクフォース」座長
- 持地 敏郎 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部長
 伊藤 隆彦氏
伊藤 隆彦氏論点
核燃料サイクルのバックエンドにおける核不拡散及び核セキュリティの観点からの課題と対応方策
- 再処理、直接処分に伴う核拡散、核セキュリティ上の課題及び対応方策
- 我が国の状況に鑑みた核不拡散、核セキュリティ上の課題及び対応方策
- 再処理の継続、稼働原子炉の減少により分離プルトニウムの蓄積量の増加が想定されることに対する核拡散上の懸念への対応
- 直接処分の研究開発を行うにあたっての長期的な保障措置、核セキュリティ確保の方策の検討
- 海外に保管されているプルトニウムの処分方策
パネル討論1の概要
パネル討論1では、我が国の原子力政策も踏まえつつ、核燃料サイクルのバックエンドにおける核不拡散、核セキュリティ確保の方策について議論した。まず一般論として、再処理、直接処分という2つのオプションに関して、核不拡散、核セキュリティ上の課題及び対応方策が議論された。使用済燃料の直接処分は、プルトニウムを取り出さないため、再処理する場合と較べて核拡散リスクが低いという認識が一般的である。本パネルの議論の中で複数のパネリストから、使用済燃料は処分後、数100年経過すると放射線レベルが減少し、使用済燃料中のプルトニウムへのアクセスが容易になる、いわゆる「プルトニウム鉱山」と呼ばれる課題が存在すること、従って、直接処分についても、保障措置アプローチの検討及び核セキュリティ対策が必要となることが指摘された。また、地層処分の分野で検討されている回収可能性(retrievability)という概念は、核不拡散、核セキュリティの観点からは、使用済燃料へのアクセスを長期間にわたり可能性にする側面があることから、地層処分の専門家と核不拡散・核セキュリティの専門家の間で、将来世代に負担を残すことの是非という倫理も含めた社会科学的観点からの検討が重要であるとの認識が示された。他方、使用済燃料の再処理には、プルトニウムを溶液で扱うことに由来する検知の難しさという課題を指摘する意見がある一方、既に日本の再処理施設において、効果的な保障措置が適用できることが実証済みであるとの見解も表明された。
次に、日本の原子力政策、特に、2012年9月14日にエネルギー・環境会議が決定した「革新的エネルギー・環境戦略」において、脱原発(2030年代原発稼働ゼロ)を進める一方で引き続き再処理事業に取り組むことが言及されている点につき、核不拡散、核セキュリティの観点から議論が行われた。日本の参加者からは、日本はエネルギー安全保障の観点から核燃料サイクルを維持すべきであり、プルトニウムの蓄積に対する核不拡散上の懸念を払拭するために、短期的な措置として軽水炉での利用、中期的措置として高速炉での利用、更に長期的な措置としては、多国間管理の検討により、プルトニウム利用を進めるべきであるとの見解が示された。他方、海外からの参加者からは、日本のこれまでの核不拡散の取組みについては評価する見方が示されたものの、再処理の継続には、軽水炉や高速炉でのプルトニウム利用の促進等の方策により利用計画のないプルトニウムが蓄積することに対する国内外の懸念を払拭すること、そうした利用計画を、透明性をもって国内外へ説明すること、プルトニウム利用計画が想定通りに進まない場合のバックアッププランを用意しておくことなどの重要性が指摘された。
【論点1:再処理、直接処分に伴う核拡散、核セキュリティ上のリスク】
 シャロン スクワッソーニ氏
シャロン スクワッソーニ氏- 伊藤座長:論点1に係る過去の議論として、国際核燃料サイクル評価(INFCE)、民生原子力利用の核拡散抵抗性向上のための技術的可能性(TOPS)4及び先進燃料サイクルイニシアティブ(AFCI)5、2004-2005年の日本の原子力大綱策定の際の議論を紹介。それらの議論において、再処理オプションにおける核拡散抵抗性は、ワンススルーオプションと較べて、長期的に見て有意な差はないことが結論付けられていることを説明。
- スクワッソーニ:使用済燃料の取扱いの2つのオプションに対する核不拡散及び核セキュリティリスクに関する考え方を説明(米国にある考え方の一つで、政府を代表するものではない)。最大のリスクはプルトニウムであり、プルトニウムがどんな形態をとるかで核拡散、核セキュリティ上のリスクは異なる。核拡散リスクの評価にあたっては、核兵器への転用の観点からの魅力度と検知のし易さが重要な要素となる。核不拡散コミュニティでは、一般的に、直接処分が最も核拡散抵抗性が高いアプローチと見られている。しかしながら直接処分にも、100年以上後には使用済燃料の放射線レベルが減少し、アクセスが容易になる、いわゆる「プルトニウム鉱山」という問題が存在する。一方、再処理オプションには再処理施設やMOX燃料製造施設といった、いわゆる「バルク取扱い施設」が含まれることから、核物質の少量転用の検知が難しいという問題がある。
4Technological Opportunities To Increase The Proliferation Resistance of Global Civilian Nuclear Power Systems (TOPS)
5Advanced Fuel Cycle Initiative (AFCI)
質問1:使用済燃料の再処理と比較した場合の直接処分の核不拡散・核セキュリティ上の課題
 ピーター ランス氏
ピーター ランス氏- ランス:バックエンドにおける保障措置の課題を説明。IAEAは、ワンススルーと再処理、両方のオプションに関係する施設(使用済燃料の貯蔵施設、再処理施設)に保障措置を適用しており、使用済燃料の処分場に関しても既に保障措置アプローチを構築済みで、近い将来、適用を開始する予定。直接処分の場合、処分された時点で保障措置が終了するわけではなく、保障措置協定が有効である限り、保障措置は永久的に適用される。再処理によるプルトニウムは、少量の核物質を正確に計量するという課題はあるものの直接的に測定することができるのに対し、直接処分による使用済燃料は間接的な手段により確認する必要がある。ただし、保障措置の目標や一般的な意味での保障措置手法(施設の設計を考慮に入れること、核物質の量の把握など)については両者に共通性がある。国レベルでのアプローチは、保障措置の適用にあたって、当該国に特有の要因を考慮することを意味し、処分場に対する保障措置に国レベルでのアプローチを適用する場合、例えば、当該国における再処理施設の有無により、保障措置の適用の方法が変わり得る。
- 持地:時間経過に伴い、処分後の核物質へのアクセス可能性が増加することによる将来世代に対する潜在的な核拡散リスクを説明。直接処分された使用済燃料中の核分裂生成物の減衰に伴い、処分後100年から数万年後は、使用済燃料中に大量に残存するプルトニウムへのアクセスが容易となるため、新たな保障措置アプローチの開発等対策が必要である。これまで地層処分の専門家と核不拡散・核セキュリティの専門家の間での議論はあまりなされて来なかったが、両者のインターフェースが重要であり、将来世代に負担を残すことの是非に関する倫理も含めた社会科学的観点からの検討も必要である。
質問2:使用済燃料の直接処分の課題に対する考え方
 持地 敏郎氏
持地 敏郎氏- 持地:2012年9月に日本学術会議が原子力委員会に提言した高レベル放射性廃棄物(使用済燃料を含む)の処分の取り組みを説明。国民的合意に基づく処分政策の抜本的見直しが必要であるとし、数十年〜数百年の暫定保管と総量管理を柱とした政策枠組みの構築等を提言している。暫定保管は回収可能性を備えた形で深地層あるいは地上に保管するもので、中間貯蔵とは異なり保管終了後の扱いを予め確定せず将来の時点での選択を可能にするもの。原子力委員会は、提言を受けて11月に見解案を発表したが、見解案では、暫定保管を採用するかどうかについての判断は先送りされた。回収可能性と可逆性は米国・仏国・スイス等でも想定されており、日本においても、処分場閉鎖の際の安全評価で妥当性が確認されるまでは回収可能性を確保することとされている。
- ランスフォード:米国における解体核起源のプルトニウムの処分の取組みについて説明。冷戦終了後の核兵器の解体により、余剰となった約60トンのプルトニウムをいかに処分するかが課題となり、DOEは米国科学アカデミーに対し、処分のオプションの検討を依頼した。米国科学アカデミーは、固化処理、深地層処分(deep borehole)、MOX燃料としての原子炉での照射という3つのカテゴリーに属するオプションを提案した。国立研究所による検討後、深地層処分は除外され、原子炉での照射及び固化処理という、いわゆる2トラックアプローチ(dual track approach)が採用された。その後、更なる検討の結果、同位体組成の変更を伴わない固化オプションが除外され、MOXオプションのみを追求していくこととした。MOX加工施設はAREVA社の設計に基づいて建設中。原子炉での照射の後、使用済MOX燃料は再処理されることなく、IAEAの検認下で貯蔵される。使用済燃料のリサイクルを含むエネルギー戦略を有する国は、再処理によって生じるプルトニウムについて明確な利用計画を有していることが重要であり、米国は、解体核プルトニウム処分におけるこれまでの知見を生かし、これらの国と協力する用意がある。
質問3:再処理の核不拡散・核セキュリティ上の課題と対応策
 クリストフ グゼリ氏
クリストフ グゼリ氏- グゼリ:仏国はプルトニウムをリサイクルすることにより電力を生産する資源(asset)として捉えている。核不拡散の観点から、再処理により生じたプルトニウムは迅速に再利用する政策をとっている。大規模な再処理施設やMOX燃料製造施設に効果的な保障措置を適用することは可能。
- 遠藤:日本はプルトニウムを資源と位置づけ、非核兵器国の立場から原子力委員会決定に示される「利用目的のないプルトニウム、すなわち余剰プルトニウムは持たない」との政策のもとで、プルトニウム分離の際に、プルトニウム利用の場所・時期を明確化することを求めている。
- ランス:再処理施設への保障措置の適用に関しては、使用済燃料から溶液になった後の監視に難があるといわれているが、日本では1970年代から東海再処理施設での保障措置適用の経験があり、より規模が大きい六ケ所再処理施設においても保障措置が精度よく適用可能 (年間のプルトニウム生産量の0.1%の検知が可能) なことが実証されている。プルトニウムの正確な計量管理の実施が商業的な再処理プラントの運用に妨げとならないような手法も重要である。
【論点2:現在の日本の原子力政策における、核不拡散及び核セキュリティ上の課題】
 遠藤 哲也氏
遠藤 哲也氏- 持地:2012年9月14日にエネルギー・環境会議が決定した「革新的エネルギー・環境戦略」の概要として、原発に依存しない社会の一日も早い実現、グリーンエネルギー革命の実現、エネルギーの安定供給の3つの柱を示していることを紹介するとともに、脱原発(2030年代原発稼働ゼロ)を進めること及び一方で再処理事業に取り組むことに対する国内外の反応について紹介した。
質問1:日本が核燃料サイクルオプションを維持することの意義
- 遠藤:日本は、原子力利用を導入した当初から有限な資源であるウランの有効利用のため核燃料サイクル政策を採用してきた。現在、ワンススルー政策をとる米国でさえ、ウラン供給がひっ迫した折、日本が核燃料サイクルを進めなければウランを供給しないという政策をとっていたことがある。このような背景から、日本は核燃料サイクルを維持するべきである。エネルギー・環境会議の政策では、原子力発電を減らす一方で、再処理を継続するとしており、既に国内外に有する分離プルトニウムや今後、再処理により発生する分離プルトニウムの利用方法を示しておらず、諸外国が懸念を表するのは当然であり、問題の多いものであると考えている。
質問2:日本が核燃料サイクルを維持することに対する各国の見方。日本が原子力平和利用と核不拡散のモデルであるという議論についての見方
質問3:プルトニウム蓄積に対する国際的な懸念への対応方策について
質問4:海外に保管されているプルトニウムの取扱方策
 ガイ ランスフォード氏
ガイ ランスフォード氏- グゼリ:仏国は、日本が、国内における核不拡散の取組みだけでなく、輸出管理政策に関しても、核不拡散に真剣に対処していると考えている。追加議定書、統合保障措置、国内の核燃料サイクル施設に対する保障措置の適用等、IAEAの保障措置に対し先導的役割を果たしている。プルトニウムに関して、利用政策が明確でない状況の中で、蓄積されることは良くない。フランスにあるプルトニウムのMOX燃料製造については、すでに日本の電力会社との間で契約が終了しており、既に3基の原子炉に装荷済み。日本の原子力政策では、安全性が確認された原子力発電所は活用していくとしており、英仏に保管されているプルトニウムや六ヶ所村再処理施設で分離されるプルトニウムが、大間発電所も含め、日本の軽水炉で利用されることを期待している。現在、予定されている以外の軽水炉でもプルトニウムを利用していくことが考えられる。軽水炉でのMOX利用は高速炉への移行期の中での活用方策であり、本命は高速炉である。高速炉ではより効率的にプルトニウムを消費することができ、燃焼炉とするなど長期的な視点での検討も必要である。
- ランスフォード:米国はIAEAの保障措置に対する日本の取組みに感銘を受けている。DOEと原子力機構間の保障措置等に関する協力は来年で25年を迎え、最近では、日米核セキュリティワーキンググループへの参加、核不拡散・核セキュリティ総合支援センターによるトレーニングの開催などの実績がある。日本は、原子力平和利用のモデルであるとともに、核不拡散及び核セキュリティについて良く努力しており、米国は敬意を表する。
- スクワッソーニ:日本が核不拡散のモデルであることついては同意する。しかし、原子力利用の道筋が不透明な状況の中で再処理を継続することは簡単ではない。コメントとして4点挙げたい。一点目は、プルトニウムの利用計画についての透明性が必要である。二点目は、地元との協定等、再処理を継続させようとする国内の圧力について国外により上手く説明する必要がある。三点目は、プルトニウムの消費について、バックアッププランが必要である。高速炉での燃焼も有効であるが、すぐには不可能であり、即応した対策も検討が必要である。最後に、六ヶ所再処理施設を多国間管理施設とすることは、六ヶ所再処理施設の再処理容量や他の国が再処理を委託する意思を有するか否かという点から現実的ではないと思う。
- 遠藤:短期的には地元の反対を乗り越え、プルトニウムを消費する軽水炉を増やしていくこと、中期的には、高速炉の導入が有効である。幸い、革新的エネルギー・環境戦略には、もんじゅでの研究を終了させた後の高速炉の将来については述べられておらず、将来的には高速炉の導入も有り得ると解釈している。また、長期的には、多国間管理も検討していく必要がある。これらプルトニウム消費の方策をグランドデザインとして打ち出していく必要がある。
- 持地:エネルギー自給率が低い日本にとって、プルトニウムは貴重な自前のエネルギー資源である。プルトニウムの利用方策としては、軽水炉でのMOX燃料利用に加えて、プルトニウムの専焼炉等の可能性も含め、高速炉でのMOX利用、長期的観点からの核燃料サイクルの多国間アプローチなどをオプションとして検討していくことなどが必要である。いずれにしても、我が国が保有するプルトニウムの利用方策について、透明性を持って明確に国際社会に示すことが必要である。
【会場からの質疑と応答】
- 質問1:仏国は、CO2削減と電力料金を低く抑えるために原子力を推進していくとしている。再生可能エネルギーによるCO2削減策もあるのに原子力への依存が高いのは、安全よりも経済性を優先しているということか?
- グゼリ:仏国は、エネルギー利用の効率化、省エネも合わせて進めており、これらは日本も同じであろうし、両国で協力している。また、風力発電やバイオマスの開発を始め再生可能エネルギーの導入も進めている。私が属する組織が、かつての「仏国原子力庁」から「仏国原子力・代替エネルギー庁」に名称変更したことは、原子力とともに再生エネルギーの開発も推進していることを端的に示している。原子力発電炉は国内に58基もあり、安全第一であることは言うまでもない。独立性、透明性、技術的能力を有する安全規制機関を有し、ベストプラクティスの導入に努力している。仏国の安全規制機関がストレステストの後、原子炉の継続は認める一方で、100-300億EUROを要する原子炉の安全性の改善を指示したことは安全第一の考え方を示している。全ての技術にはリスクはあり、完全なものはあり得ないことから常に改善を進めている。
- スクワッソーニ:本件について悩んでいるのは日本だけではない。原子力に関する見方は対立する傾向にある。原子力はビジネスであり宗教ではない。ビジネスである以上、投資された費用があり、慎重に進めていく必要がある。また、民間だけに任せるのではなく、政府の役割も重要である。日本だけでなく原子力を利用している国には廃棄物、安全性等、全て同じ問題がある。これらについて、感情的でなく、冷静な議論を行うことが重要で、そのためには、両者に透明性が求められる。
- 質問2:政策を変更した日本が、核不拡散に関して国際社会にどのように貢献するのか?
- グゼリ:日本はこれまで国際的な核不拡散の取組みに大きな貢献をしてきた。今回の政策の変更により、日本の核不拡散上の国際的な影響力が低下する恐れがあるが、日本は核不拡散に関する知識・人材等の資産を有しており、これにより国際的に貢献すべきである。
- スクワッソーニ:核不拡散上の国際貢献には輸出管理、外交、資金的措置等の手段がある。専門技術等、現在有するものを維持した上で、新しい政策に対応した方策を探していくことが必要である。日本は核不拡散上、重要なパートナーであることに変わりはない。
- 遠藤:日本が北海道洞爺湖サミット以来提唱してきた3Sを基本的な考え方として国際的に推進していくべきである。
- ランスフォード:日本はユニークな知見により核不拡散に貢献しており、引き続き貢献することを期待。また、最近、米国のY-12プラントでは施設への不法侵入が発生したが、NNSAのダゴスティーノ長官は施設を停止するのではなく、この事件の教訓を生かし、安全やセキュリティの改善を命じた。今回の福島原子力事故においても、その教訓を国際的に生かすことが重要で、プロセスの改善等により、今後さらに深刻な事故が発生することを防止する可能性につながる。日本が原子力から撤退するのではなく、米国に対し、事故の教訓を踏まえて安全性を強化するための協力の機会を与えてくれるのを期待する。
- ランス:日本がこれまで核不拡散に関する国際的な信用を保ってきたのは、原子力政策を国際的に明確に説明してきた点にある。現在の原子力政策は、混乱の中にあるが、できる限り早く明確にし、国際的に説明をするべきである。プルサーマルの利点はプルトニウムの蓄積を解消できることであるが、いかに実現するか詳細に詰めて人々に理解し安心してもらうことが重要である。
- コメント1:3Sの構想は、日本が提唱して、北海道洞爺湖サミットの合意文書に盛り込まれたが、当初は、非同盟運動(NAM)諸国に受け入れられず、2010年のNPT運用検討会議において漸くNAM諸国が同意した経緯がある。このように日本が国際的なルール作りに貢献できる分野もある。また、日本は保障措置に関するIAEAへの支援プログラムを実施してきたが、今後もIAEAが直面する技術協力、特にsafeguards by designの分野で協力すべきである。
- 質問3:地層処分の研究者と保障措置関係者との考え方に相違がある。地層処分では、最初の100年間程度は取出し可能な状態にすることが世界的に主流であるが、保障措置の観点では、100年後に放射線量や発熱量が低下するとアクセスが容易になり、核拡散上の問題が生じることになる。両者が参加した国際的な議論はなされているのか?
- ランス:処分場に適用される長期的な保障措置の概念検討に関する議論はまだ開始されたばかりであり、一般的な概念は既に構築されているが、どういう要素が含まれるべきかなどの議論が現在、行われている。今後、徐々に進化していくものと考えている。国家が、使用済燃料を取り出して、核兵器に転用することを抑止するに十分な、厳格な保障措置の適用が可能と考える。
- 質問4:解体核処分では、兵器級プルトニウムをMOX燃料として燃焼させても、原子炉内でウランからプルトニウムが生成されるため、プルトニウムの総量としては減らないのではないか?原子炉の燃焼によるプルトニウム処分のメリットは、同位体組成の変化にあるのか、あるいは使用済燃料にすることに意味があるのか。
- ランスフォード:兵器級プルトニウムにはPu-239が90%以上含まれており、原子炉での燃焼によりこの割合を50%程度に減らすことができ、また、プルトニウムを使用済燃料の中に留めておくことで核不拡散上、意義あるものとなる。

パネル討論2「アジアの原子力利用における核不拡散、核セキュリティ方策及び多国間協力枠組み」
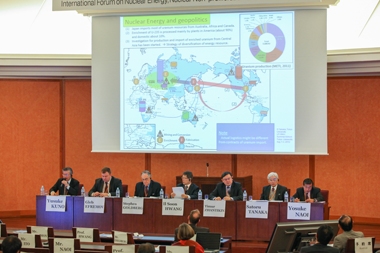
- 座長
- 久野 祐輔 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部次長
- パネリスト
- グレブ エフレモフ 露国国際ウラン濃縮センター部長
- ステファン ゴールドバーグ 米国芸術科学アカデミー 世界の原子力の将来プロジェクト 研究コーディネーター
- イル ソン ホワン 韓国ソウル国立大学工学部教授
- ティムール ジャンチキン カザフスタン原子力庁委員長
- 田中 知 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻教授
- 直井 洋介 日本原子力研究開発機構 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター次長
 久野 祐輔氏
久野 祐輔氏論点
アジア地域における原子力利用の推進と核拡散及び核テロのリスクの低減方策
- 核燃料サイクルのバックエンドに係る課題を含むアジア地域の原子力発電の現状と今後の見通し
- 原子力供給国の原子力輸出管理政策:特に原子力資機材の輸出にあたって、受領国側に求める核不拡散、核セキュリティ担保措置
- 供給国による保障措置、核セキュリティに関する支援の取組み
- 核燃料サイクルの多国間アプローチ(MNA)の実現可能性:地域的な3S(原子力安全、核不拡散、核セキュリティ)確保のための枠組みに関し、供給国及び受領国側のメリットとデメリット、枠組み参加を促すための誘因
パネル討論2の概要
福島原子力事故後も、アジア地域では、新規の国による原子力発電の導入や既存の国による原子炉増設の動きが続いていること、核燃料の供給に関して、従来の欧米諸国による供給だけでなく、露国やカザフスタンといった中央アジアを起点とし、それ以東のアジア諸国へ供給するという流れが生じつつあることを踏まえ、本パネルでは、アジアの原子力利用における核不拡散、核セキュリティ確保の方策、そうした方策の一つとして、核燃料サイクルの多国間アプローチ(MNA)の意義や実現に向けた課題を議論した。
核不拡散、核セキュリティを確保する手段として、欧米諸国を中心に、輸出管理や二国間原子力協力協定といった手段を通じて、受領国に要件を課す、いわゆるサプライサイド・アプローチがとられてきた。本パネルの議論の中では、供給国の多様化という現状やサプライサイド・アプローチが「持つ国」と「持たざる国」を峻別する考え方を内包していることに鑑みると、サプライサイド・アプローチだけでは限界があり、受領国側に、機微技術の追求の自制を促すインセンティブを与えるようなアプローチ、すなわちディマンドサイド・アプローチが重要であるとの見解が示された。そうしたディマンドサイド・アプローチの一方策が核燃料サイクルを多国間で運営し、フロントエンド、バックエンドのサービスを提供することにより、受領国、参加国による自発的な機微技術の放棄を促すMNAであり、既に様々な研究がなされている。本パネルでは、バックエンドにおけるMNAに関して、東京大学の検討チームを代表して田中教授、ソウル国立大学のホワン教授、米国芸術科学アカデミー 「世界の原子力の将来プロジェクト」を代表してゴールドバーグ氏が、それぞれの提案の説明を行った。バックエンドにおけるMNAは、地域における3S(原子力安全、核不拡散/保障措置、核セキュリティ)強化に貢献する潜在的可能性を有しており、その実現にあたっては、参加の自発性の確保、参加国間の信頼醸成、将来の技術開発を取り入れる柔軟性等が重要であるとの見方が示された。他方、MNAに加盟を促すインセンティブの付与、一般公衆からの受容の確保、施設のホスト国の存在、MNAの資金調達、核物質の輸送、参加国の政策の一貫性の確保等、多くの国が関与するが故に多くの課題を有していることが指摘された。参加者の1人からは、アジア・太平洋地域でタスクフォースを立ち上げ、MNAの実現可能性について検討すべきとの提案がなされた。
【論点1:アジアにおける原子力利用-特にバックエンドに係る課題】
- 久野座長が論点1の導入として以下の説明を行った。
- 既存の核不拡散及び核セキュリティへの国際的な取り組みとしては、サプライサイド・アプローチとディマンドサイド・アプローチがある。前者は、原子力供給国が受領国に対し、NSGガイドラインや二国間原子力協力協定等に基づいて核不拡散に係る要件を課し、受領国が機微な技術や施設を所有することを困難にする措置を維持、強化するもの。後者は、受領国に対する核燃料や役務等の供給保証や核燃料サイクルの多国間アプローチ(MNA)等により、受領国が機微な技術や施設を所有することへのインセンティブを減じる措置である。
- 昨今の原子力事情を鑑みるに、アジアでは、福島原子力事故にも拘わらず、新規の国による原子力発電の導入や既存の国による原子炉の増設の動きは衰えていない。また、従来の豪州や加国に加え、天然ウランの新たな供給源として中央アジアのカザフスタンが台頭し、露国もその豊富なウラン濃縮能力を背景に低濃縮ウランの備蓄を開始した。この2つの変化は、従来の欧米を中心とした核燃料供給体制から、ロシアやカザフスタンによる供給体制へのシフトを示している。
- 日本、韓国及び台湾では、蓄積する使用済燃料の取扱いが課題となっており、早急な対応方策が求められている。
 ティムール ジャンチキン氏
ティムール ジャンチキン氏- ジャンチキン:現在カザフスタンは、多様な原子炉に適応可能な種々の核燃料の成型加工を行うべく、ROSATOMやAREVA等と協力し、燃料成型加工の技術の獲得とそのビジネス展開を図っている。アジアで原子力ネットワークが構築されれば、カザフスタンは中断されることのない長期の核燃料供給を保証できるが、カザフスタンはアジア大陸内部に位置するため、陸上輸送に頼らざるを得ない。
原子力関連の輸出管理に関し、カザフスタンはNSGガイドラインを遵守し、受領国にはNPT加盟(ただし、1国6のみ例外扱い)、計量管理システムの維持、原子力の平和利用の担保、IAEA保障措置の維持、IAEA勧告に沿う核物質防護措置等を求めている。
MNAとしては、すでに露国の国際ウラン濃縮センター(IUEC)や、カザフスタンに設置予定のIAEA核燃料バンクが存在し、将来のMNAのモデルケースとなり得るだろう。
- エフレモフ:露国の国営原子力企業ROSATOMは、ウラン採鉱から露国内外での原子炉の建設に至るフロントエンド事業を幅広く行うとともに、「ブレークスルー」と呼ばれる高速増殖炉(BN-1200)を中心とし、燃料成型加工及び再処理を原子炉サイトで行うプロジェクトを推進している。また、アジアでの原子力利用の増大に鑑み、TENEX社はアジア地域への核物質の輸送のために、ロシア東方のボストチヌイに至る新輸送ルートを確立しようとしている。
核燃料サイクルのバックエンドに関しては、露国は使用済燃料をリサイクルする方策を採る。
原子力関連の輸出管理に関し、非核兵器国への機微技術の輸出に際しては、一般の原子力資機材の輸出の際の受領国要件に加えて、NPTへの加盟・遵守、IAEA保障措置追加議定書の締結、IAEAとの保障措置協定の下での義務の違反がないこと、NSGガイドラインの遵守、国連安保理決議1540の下で義務づけられている報告書の提出、原子力安全に係るIAEA勧告やその他の国際法上の規則の遵守、機微技術の複製や改良の禁止、安全及び保障措置に係る露国の受領国への査察の権利の付与等を受領国要件としている。
6インド
質問1:アジアでの原子力利用拡大に鑑みた核不拡散及び核セキュリティの懸念と課題
 直井 洋介氏
直井 洋介氏- 直井:アジアの中でも、新たに原子力発電を導入する国と既存の原子力国に分けて考える必要がある。前者に関しては、原子力安全に加え核不拡散及び核セキュリティ文化の醸成が必要。一方、日本、韓国及び台湾等の原子力先進国では蓄積する使用済燃料に伴う核セキュリティの確保が課題となっている。
輸出管理については、多国間の枠組みよりも二国間原子力協力協定での原子力供給国側からの管理が重要であり、供給国全てが輸出管理基準につき一定のレベルを確保し足並みをそろえる必要がある。
質問2:核不拡散、核セキュリティの担保措置としての輸出管理や二国間原子力協力協定などサプライサイド・アプローチによる核不拡散対策の有効性とその限界
- 田中:今まで欧米を中心とする原子力供給国によるサプライサイド・アプローチで機微技術等の拡散防止が図られてきたが、中央アジアからそれ以東への核燃料供給という供給体制のシフトにより、今後も同アプローチで核不拡散を担保できるか不透明。そもそも国家を機微な技術や施設を「持つ国」と「持たざる国」に分けるサプライサイド・アプローチには限界があり、原子力平和利用を推進しつつ核不拡散を担保する新たな方法、例えばディマンドサイド・アプローチの一つとして、核燃料サイクル施設を多国間で管理するとのMNAを模索する必要があるのではないか。
昨年改定されたNSGガイドラインは、一定のクライテリアを満たした国に対しては濃縮・再処理品目の移転を認めており(クライテリアベースト・アプローチ)、この改定は従前のサプライサイド・アプローチの考え方を見直したものと考えられる。
質問3:アジアにおける効果的な原子力平和利用の推進と3S強化の両立方策
- ゴールドバーグ:核燃料サイクルのバックエンドに係るMNAの利点は、3Sの各々の文化の普及を図り、ベストプラクティスを提供できることである。
- ホワン:現在、アジアは転換期にあり、原子力利用が増加する一方で、既存のNPTを中心とする核不拡散体制が揺らいでいる。原子力反対派の存在、情報技術(IT)の発達、原子力供給国数の増加、十分なインフラ整備がなされないままに原子力利用が進むなど、核不拡散や核セキュリティを脅かすリスクが存在し、安全管理も大きな問題である。将来、悲劇につながらないような3Sの確保のための革新的方策が必要である。
【論点2:多国間協力の枠組みについて】
- 久野座長より、3Sを経済的に達成可能とする方策の一つにMNAがあるが、フロントエンドに係るMNAは実現あるいは実現途上にあるものの、バックエンドに係るMNAは議論が進んでいない現状を紹介した。次いで田中、ホワン及びゴールドバーグの3氏が、各々が携わるバックエンドを含む具体的なMNA提案を説明した。
 田中 知氏
田中 知氏- 田中:東大の研究チームでは、原子力ルネサンスと核不拡散の希求、核燃料供給体制のシフト等に鑑み、アジア地域をターゲットとし、加盟国間で差別がなく、3Sを維持強化できる枠組みを提案する(図1参照)。枠組み構築においては、核不拡散や核燃料サイクルサービスの提供など12の要件を定め、3つの枠組み(地域における3Sの強化のみを目指す枠組み(タイプA)、核燃料供給と役務の提供をMNAの合意の下各国所有施設で行う枠組み(タイプB)、MNA施設の所有権を多国間管理組織に委譲し行うもの(タイプC)を提案している。
核不拡散については、NSGガイドラインや米国原子力法123条の核不拡散要件の遵守でこれを担保することとし、また多国間枠組みを一つの国と捉えて他の原子力供給国等と協定を締結することにより、既存の二国間原子力協力協定に規定される同意権が原因で核物質等の供給や移転が阻害される事態を防ぐことができるとしている。コストについては、輸送費用も含め、各国が固有の核燃料サイクル施設を有する場合より経済的になるとの試算を得ている。
 イル ソン ホワン氏
イル ソン ホワン氏- ホワン:先進湿式プロセス/先進パイロプロセスと核変換をMNAで行うことを提案(図2参照)。アジアでの使用済燃料の蓄積に関し解決策が急務であるが、使用済燃料の直接処分は処分後数百年を超えると人間がアクセス可能な放射線量率までに低減する一方で、処分後数万年程度は処分体中に大量のプルトニウムが残存し「プルトニウム鉱山」となってしまう。再処理も、純粋なプルトニウムの抽出により核拡散抵抗性が低下する時点があり、その際は制度的な措置で補完する必要性があることが2004年に米国DOEが設置した専門家の委員会で指摘されている。その後は高速炉でリサイクルを繰り返すことで、放射線のバリアによる核拡散抵抗性は向上することから、プルトニウムの分離の時点の核拡散抵抗性の低下という問題を多国間アプローチ等の制度的措置により克服できれば、再処理は直接処分に較べて優位に立つことになる。ただし、再処理にも経済性や輸送時の3Sの確保、高レベル放射性廃棄物(HLW)処分の課題がある。
高レベル放射性廃棄物に関しては、先進湿式プロセス/先進パイロプロセスと核変換の導入により、最終処分を要する廃棄物を高レベルから中レベルに変えることができれば、原産国による廃棄物の受入れ可能性が高まる。また、経済性の問題は施設のスケールアップにより克服できる。アジア・太平洋地域でタスクフォースを立ち上げ、当該MNAの実現可能性につき検討すべき。
 ステファン ゴールドバーグ氏
ステファン ゴールドバーグ氏- ゴールドバーグ:我々の研究では、ビジネスの実例としてのバックエンドのMNAの姿と、一般公衆やステークホルダーのMNAへの係わりに焦点を当てている。バックエンドのMNAを構築する上での課題は、核燃料やサービスの供給国側と受領国側双方が協力する場としての市場の存在、バックエンド施設は「債務(liabilities)」でなく国家やコミュニティの「資産(asset)」であるとの認識、機微な技術の管理をいかに行うかという問題、コストと便益のバランス等である。
我々は、使用済燃料の中間貯蔵施設の設立を提案している(図3参照)。当該施設は、地域の施設であり、規模の経済性から1万トンの使用済燃料を100年まで貯蔵するとし、将来的な先進技術も取り込む柔軟性を備える。そのような施設のメリットとしては、顧客国にとっての使用済燃料の蓄積圧力の緩和、ホスト国にとってのインフラ整備、雇用機会の増大、収入の確保、国際社会にとっての核拡散抵抗性の向上が挙げられるが、一方で施設のホスト国国民の受容性、長期間にわたる持続可能性、権利、特権や責任等の法的問題、原子力平和利用の権利の保持、使用済燃料直接処分を志向する国と、リサイクル路線を志向する国の利益の融合、最終処分方策、参加国の費用負担や利益配分、組織や協定の仕組みをどうするか、等の課題がある。
質問1:アジアにおける多国間協力の枠組みを追求する意義
- 直井:アジアの新興の原子炉導入国は、使用済燃料の取り扱いにそれほど関心を有せず、先進国による議論の活性化が必要。またMNAは3Sを向上させる上でも有益と考える。
- ジャンチキン:核燃料サイクルのフロントエンドとバックエンドの施設では、公衆の受容性という点で格差がある。どんな国も自国での廃棄物処分を望まず(NIMBY)、カザフスタンも外国の放射性廃棄物の輸入を法律で禁止している。使用済燃料の暫定貯蔵施設は最終処分場にはならないという厳格な法的保証が必要。カザフスタンはFBR使用済燃料管理の経験があり、こうした経験をMNAによる使用済燃料の貯蔵に提供できるだろうが、公衆の受容性の問題は残る。
- ゴールドバーグ:貯蔵が最終処分につながるものと認識されれば、一般公衆の受容を得ることは難しい。我々は欧州のARIUS(Association for Regional and International Underground Storage)と協力しているが、まず、地域の住民がバックエンドのMNA施設はどのようなものか、ということを理解する必要がある。
質問2:アジアにおけるバックエンドに係る多国間協力は可能か。
 グレブ エフレモフ氏
グレブ エフレモフ氏- エフレモフ:可能と考える。しかし、課題は使用済燃料の貯蔵や処分施設をいったいどの国がホストできるかである。露国もカザフスタン同様、他国で発生した使用済燃料を最終処分目的で受け入れることはできず、公衆に対して、使用済燃料の暫定貯蔵目的の受入れであり、最終的には発生国に戻ることを確約する必要がある。
* 使用済燃料に係るMNAを議論する上で、最終廃棄物の責任は発生国にあるという認識を持つことが重要との基本的考え方がパネリストにより確認された(久野座長)。
質問3:多国間協力の枠組みは経済的に成り立つか
- 田中:我々の試算によれば、少なくとも各国毎での燃料サイクルの実施よりも高価になることはない。多国間協力により港湾整備や輸送ルートのインフラ整備がなされ、スムーズな輸送が可能になれば経済的メリットは増すはずである。
- ホワン:エネルギーの大部分を海外に依存し、再生可能エネルギーが解決策にはなり得ないアジアの多くの国にとって経済性は必ずしも最大の指標ではない。使用済燃料の暫定貯蔵も最終的にはどうなるのか、そのライフサイクルが未だ明らかでない。MNAも長期的な視点に立てば経済性の問題にも対処できるようになるだろう。
質問4:輸送問題の解決策
- エフレモフ:ROSATOMのブレークスルー・プロジェクトは、発電所のサイトに核燃料サイクル施設も立地することにより輸送の必要性を無くすもの。現状では、核物質の輸送にあたり、輸送ルートの最適化、輸送物質や量の可能な限りの秘匿化、核物質防護の観点からのノンストップでの輸送等の措置を講じている。
- 田中:輸送時の核セキュリティの確保は重要であり、その点、MNAが構築できれば輸送の際に各国の協力が得られメリットとなり得る。核物質等の輸送時の核セキュリティ確保を認識しつつMNAを設計していくことも必要。
質問5:供給国側、受領国側から見た多国間協力の枠組みのメリット、デメリット
- ゴールドバーグ:多国間アプローチにより使用済燃料の中間貯蔵を集中的に行うことで、安全性の向上を図ることができる。
- ジャンチキン:輸送の経済性については、MNAによって運営される施設のタイプによって異なる。例えば付加価値を伴う燃料集合体の製造施設であれば、輸送コストは、燃料集合体そのもののコストに較べて十分安いため、大きな問題にはならない。
【会場からの質疑と応答】
- 質問1:多国間協力が成立するためには、加盟国の原子力政策が首尾一貫していることが前提となる。我が国のように急激な政策転換を行うような国や国際約束を翻す国は、多国間協力に加わることができるのか。
- ゴールドバーグ:MNAへの参加は自発的なものであり、途中で参加することも脱退することも可能。日本のように原子力の資産も負債も抱えている国は、協力してくれる国を見つける必要があるのではないか。仮に六ヶ所再処理工場を800トンという容量の限界までフル稼働させたとしても解決できない問題は残る。例えば、10年経てば政策が変わり得るという前提で、多国間アプローチに関し他の国と協力することも有り得るのではないか。自発的かつ柔軟性のある多国間アプローチにより日本はメリットを享受できる。
- ホワン:原子力政策の不安定さはアジアのどの国にも存在する。どんな国にとっても使用済燃料は解決策を必要とする共通の課題であり、小規模の実証プロジェクトから協力を始めることが必要であろう。
- 質問2:使用済燃料を「ゴミ」でなく「宝」として預かることが出来る国は、使用済燃料のリサイクルが可能な露国と仏国、そして疑問符が付くが日本。またプルトニウムを含む使用済燃料を預けても核不拡散上問題ない国は露国と米国。実際問題として、これらの国に1トンの使用済燃料を幾らで預かってくれるのか。
- ゴールドバーグ:米国では280億ドルが廃棄物基金として集まっているが、無限大の資金がかかる。我々の研究では、0.5ミル/キロワットアワー程度で、ユーザーとしては吸収できないコストではないと考える。
使用済燃料を「宝」と見るか否かについては、例えば核変換などの技術的進歩があれば、バックエンド施設をホストする国のインセンティブにもなる。
- ゴールドバーグ:米国では280億ドルが廃棄物基金として集まっているが、無限大の資金がかかる。我々の研究では、0.5ミル/キロワットアワー程度で、ユーザーとしては吸収できないコストではないと考える。
- 質問3:NSGは、NPT非加盟国であり、事実上の核兵器国であるインドを例外化し、原子力関連の輸出を認めたが、これをどう思うか。
- スクワッソーニ:インドとの協力に対する米国の対応はNSGにおける各国の輸出管理政策の調和の取組みに不利益をもたらすもの。(米印問題は複雑であり、本パネルの論点を越える(座長))
- 質問4:エフレモフ氏の資料によれば、機微技術の輸出に関し、当該技術が受領国でコピーあるいは改良されないことが要件となっているが、当該要件は、ブラックボックス方式での移転を求めるNSGガイドラインの要件とは微妙に異なるのではないか。NSGグループ間で規制の調和が必要だと考えるが、ロシアのブラックボックス対策について聞きたい。例えば露国が中国に輸出したウラン濃縮施設に対してはどのような規制をかけているのか。
- エフレモフ:資料に記述した機微技術の受領国要件は非核兵器国に対する輸出に適用されるもので、核兵器国の中国には該当しない。露国のウラン濃縮技術は中国にはブラックボックス方式で移転されている。当該施設はIAEAの保障措置下にあること、露国も中国に対し査察を行うことで、中国がロシアの設備、技術を複製しないことを確保している。露国は昨年中国から4つ目のウラン濃縮施設の発注を受けており、そのこと自体がそもそも露国のウラン濃縮技術がコピーされていないことを明示している。
- 質問5:各国が多国間協力の枠組みに参加するインセンティブは何か。使用済燃料だろうがHLWだろうが、一般公衆は相違を認識しないのではないか。
- 田中:各国毎の事情により、多国間協力の枠組みに加盟するインセンティブは異なる。相手国のバックエンドに係る問題を丁寧に説明していくことで信頼関係を構築していくことになる。
* 最後に久野座長から、本問題は簡単に解決できる問題ではなく、今後も議論を継続していく旨の言及があった。

閉会挨拶
田中 知 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻教授
 田中 知氏
田中 知氏「原子力と核不拡散、核セキュリティに係る国際フォーラム」に国内外から多くの方々にご参加頂いたことにお礼を申し上げたい。
アジアにおいて原子力を巡る状況は変化しており、次のステップに入ろうとしている。原子力の平和利用を行う上では、どのような段階にあっても、またどのような国においても、3Sの重要性を十分に認識し、その確保に努める必要がある。
本フォーラムを主催、あるいは共催する3つの組織は、研究機関や大学であり、そのような機関から議論を始め、日本の政策に反映されていくことを希求する。
このようなフォーラムは来年度も開催予定であり、来年度の討議テーマについても是非、御意見を頂戴したい。
* この報告は、フォーラムでの基調講演の要旨、パネル討論の概要及び発表資料を収録したものである。なお、基調講演の要旨、パネル討論の概要の文責は事務局にある。