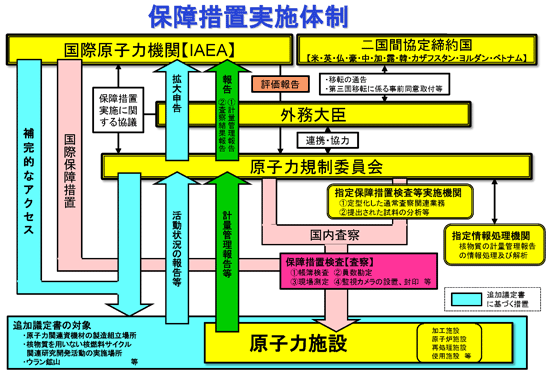保障措置
保障措置とは、ウランやプルトニウムなどの核物質その他の原子力資機材の使用が平和利用に限定され、核兵器等の核爆発装置やその他の軍事目的に転用されていないことや未申告の核物質がないこと、原子力活動が行われていないことを確認するための検認制度です。核兵器不拡散条約(NPT)は、非核兵器国である締約国が国際原子力機関(IAEA)と包括的保障措置協定を締結し、IAEAが行う保障措置を受諾することを定めています。
IAEAとの保障措置協定には、以下のものがあります1。
(1) 包括的保障措置協定(Comprehensive safeguards agreement (CSA))
NPT締約国である非核兵器国が、NPT第3条1項に基づきIAEAとの間で締結することを義務づけられている、当該国の平和的な原子力活動に係るすべての核物質を対象とした保障措置協定。「NPTに基づく保障措置協定」又は、「フルスコープ保障措置協定(Full-scope Safeguards Agreement)」とも呼ばれています。この協定は、IAEA作成文書INFCIRC/153がモデル協定となっています。
(2) 対象物特定保障措置協定(Item-specific safeguards agreement)
二国間原子力協定やIAEAとのプロジェクト協定に基づき、核物質又は原子力資機材を受領するNPT非締約国がIAEAとの間で締結、あるいは、核物質又は原子力資機材の供給国も含めた三者の間で締結する、特定の核物質又は原子力資機材のみを対象とした保障措置協定。「三者間保障措置協定(または保障措置移管協定)」及び「一方的受諾協定」と呼ばれるものがこれに該当し、「個別の保障措置協定」とも呼ばれています。IAEA文書INFCIRC/66に基づいて作成されます。包括的保障措置協定の締結以前に各国が締結していましたが、NPTが包括的保障措置協定の締結を締約国に義務付けているため、現在この協定はNPT未加入国が締結するのみです。
二国間原子力協力協定とは、当該二国間の原子力平和利用協力の推進及び協力に伴う核不拡散確保の観点から,核物質、原子炉等の主要な原子力関連資機材及び技術を移転するに当たり,移転先の国からこれらの平和的利用等に関する法的な保証を取り付けるために締結するものです。
(3) 自発的提供協定(Voluntary offer agreement)
NPTで認められた核兵器国(米、露、英、仏、中)が、自発的にIAEA保障措置の適用を受けるために、IAEAとの間で締結する協定で、5核兵器国は全て締結済です。
日本は1976年にNPT、1977年にIAEAと保障措置協定(INFCIRC/255)を締結し、NPTに基づくIAEA保障措置を受け入れています。
1993年、イラク及び北朝鮮の核兵器開発疑惑等を契機に、IAEA保障措置制度の強化及び効率化の検討が行われ、その結果として、未申告の核物質や原子力活動がないこと及び保障措置下にある核物質の軍事転用がないことを検認するためにIAEAが追加的に必要とされた権限等を盛り込んだモデル追加議定書(INFCIRC/540(corrected))が、1997年5月にIAEA理事会で採択されました。
この追加議定書(AP: Additional Protocol)とは、IAEAと上記(1)〜(3)のいずれかの保障措置協定を締結した国との間で追加的に締結される保障措置強化のための議定書です。追加議定書を締結した場合、IAEAは、その国において保障措置協定よりも広範な保障措置を行う権限を与えられます。具体的には、追加議定書を発効させた(1)の国は、モデル追加議定書の全ての規定を受け入れる必要があります。また追加議定書を発効させた(2)及び(3)の国は、モデル追加議定書の措置を受け入れ、実施することができます2。
2023年12月31日現在、154ヶ国と1機関(EURATOM)がAPに署名していますが、うち12ヶ国は未発効です3。日本は、1998年12月4日に追加議定書(INFCIRC/255Add.1)に署名、1999年12月16日に発効しています。
追加議定書により、IAEAは既存の包括的保障措置協定でアクセスが認められていない場所等に補完的アクセスすることが可能になりましたが、一方、IAEAの保障措置に係る予算を効率的に活用するため、包括的保障措置及び追加議定書の下で利用可能な保障措置手段を最適に組み合わせ、最大限の効率性を達成するために生み出された概念が統合保障措置(IS: Integrated Safeguards)です。具体的には、従来の計量管理を基本としつつ、短期通告査察(IAEAから当事国に提供される査察の事前通告が、規定されているものよりも短時間の、施設又は施設外の場所で行われる査察)、または無通告査察(IAEA査察員が到着するまではIAEAから当事国への事前通告が提供されない、施設又は施設外の場所で行われる査察)を強化することで、IAEAの検認能力を維持したまま査察回数の削減を可能とするものです。この統合保障措置が適用されるためには、当該国が包括的保障措置及び追加議定書双方に基づく保障措置を一定期間に亘って受け入れ、その結果、IAEAが当該国に対して、「保障措置下にある核物質の転用」及び「未申告の核物質及び原子力活動」が存在しない旨の「拡大結論」を導出する必要があります。日本について、IAEAは2004年6月、「拡大結論」を導出し、同年9月、統合保障措置の実施が開始されました4。
このように、日本は、原子力の平和利用の確保をより確実なものにするために、IAEAの保障措置を受け入れるとともに、以下の図に示すような国内保障措置体制を作り上げています。
1 IAEAホームページ: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB2003_web.pdf
2 外務省ホームページ: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/iaea/kyoutei.html#section2
3 IAEAホームページ: https://www.iaea.org/sites/default/files/20/01/sg-ap-status.pdf
4 外務省ホームページ: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/iaea/kyoutei.html#section4