原子力平和利用と核不拡散、核軍縮にかかわる国際フォーラム 結果報告
平成21年12月3日(木)、4日(金) 浜離宮朝日ホール 小ホール
岡﨑理事長開会挨拶

- 本フォーラムは、毎年、原子力平和利用と核不拡散に関する今日的課題をテーマに開催しているものであり、今年は、原子力機構と日本国際問題研究所、東京大学G-COEとの共催により、核軍縮も含めたNPTの3本柱を包括的に取上げ、それぞれの課題について掘り下げた議論を行うことを意図。
- まず、本年就任されたオバマ米国大統領は、4月のプラハでの演説において「核兵器のない世界」というビジョンを提示され、9月の国連安全保障理事会における核不拡散・核軍縮に関する決議1887号の採択、更には、米露間のSTARI Iに代わる新たな核軍縮条約の交渉の進展等、核軍縮に係る大きな動き。また、先般の日米首脳会議で、核不拡散、保障措置、核セキュリティ分野における協力が合意されるなど、来年の核セキュリティ・サミットやNPT運用検討会議に向けて、核軍縮、核不拡散の機運が高まっている状況は歓迎すべきこと。
- 他方、エネルギーの安定的確保、温室効果ガス削減の要請の中で、原子力エネルギーの重要性への認識は国際的にますます高まっており、中東や東南アジアにおいて、原子力導入への関心が増大、欧米諸国において原子力への回帰が見られ、原子力ルネサンスを実感
- このような中、原子力発電の拡大が核拡散リスクの増大を伴わないような形で実現すること、すなわち原子力平和利用と核不拡散の両立が人類の持続的発展にとっての重要課題
- 核兵器国による核軍縮への一層の取組みによって、国際的な核軍縮、核不拡散の動きが加速されると期待
- NPTの3本柱である、核不拡散、原子力平和利用、核軍縮は相互に密接にリンクしており、この3つの柱を総合的に推進する取組みが重要
- 本フォーラムでは3本柱について、特に原子力平和利用を国際的に推進する観点からの議論を期待
- 中身の深い議論を期待するに相応しい、政府機関や国際機関の責任者や多くの専門家をお招きすることができ、喜ばしく思っている。
- また、今回のフォーラムでは、従来とは異なり、円卓討論という方式を採用。プレゼンテーションは最小限にとどめ、パネリスト相互の議論やフロアとのインターアクションをより重視
- 基調講演として、まず、12月1日にIAEAの事務局長に就任されたばかりの天野之弥氏からビデオメッセージをいただく。原子力平和利用の推進、核不拡散の確保の両面に関し、IAEAが果たすべき役割が改めて認識されているこの時期に、事務局長という重要ポストに就任された天野氏に心から祝意を表したい。
- その後、原子力平和利用の観点から、原子力委員会の近藤駿介委員長、核不拡散の観点から米国のボニー・ジェンキンス大使、また、軍縮の観点では、核不拡散・核軍縮に関する国際委員会の報告書に関して、阿部信泰日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター所長にそれぞれスピーチをいただく。
- 初日の午後の円卓討論では、核不拡散、原子力平和利用、核軍縮を包括的に議論。特に、原子力平和利用推進の重要性とその課題、核不拡散/保障措置、原子力安全、核セキュリティ、いわゆる3S確保のための新規原子力発電導入国への支援のあり方、追加議定書の普遍化をいかに進めるかなどについて議論
- 2日目の午前中の円卓討論では、特に、保障措置、核セキュリティ、核拡散抵抗性の視点に立って核拡散抵抗性技術と保障措置等の制度的措置をいかに組み合わせて核の拡散を防ぐことが出来るのかという点、核拡散抵抗性と経済性の両立、核拡散抵抗性に関する国際的な評価基準の在り方等について討論
- また、2日目の午後の円卓討論では、核燃料サイクルの多国間管理をテーマ。現在、国際的に議論が進められているフロントエンドを中心とした具体的提案に加え、バックエンドも含めた多国間管理について多面的な議論を期待
- 本フォーラムは、政府関係者含め全て個人の立場で自由に意見交換をすることを意図し、セカンドトラックとして開催されるものであるが、2日間の議論を通じて、浮かび上がった課題や一定の方向性が、来年4月のNPT運用検討会議はもとより、関連する多くの国際的な議論につながることを期待
基調講演
原子力平和利用と核不拡散の両立(ビデオメッセージ)
天野之弥氏(IAEA新事務局長)
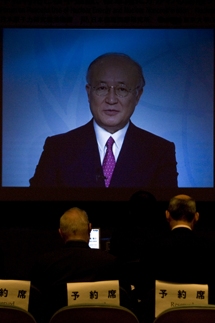
経済成長と気候変動の観点から、エネルギーミックスの一部として原子力の役割は今後重要となる。経済危機にも関わらず、殆どの国々は原子力利用計画を後退させておらず、また、IAEAの予測では、2030年までに原子力発電の設備容量は現在に比べ、116%、拡大する。原子力発電の拡大はIAEAに新たな挑戦をもたらすことになり、原子力の利用に関する加盟国への援助を求められた場合に、IAEAはより適切に対応できるようにする必要がある。核燃料供給保証は一層の関心が示されるべき項目である。追加的な核物質・施設に対して保障措置を適用するに足る能力の保持は重要で、また追加議定書は現在90ヶ国以上と締結しているが、一層の普遍化が必要である。
本フォーラムは将来の原子力エネルギー、核不拡散、及び核軍縮にとって大変重要な時期に開催されている。現在進展中の米露の戦略兵器削減交渉では、核軍備を現在の1/3に削減するとしている。達成されれば、国連安保理決議1887号(核兵器のない世界に向け2009年9月に採択)のフォローアップとして歓迎すべきものになる。来年5月にニューヨークでNPT運用検討会議が開催されるが、NPTは国際安全保障にとっても礎石であり続ける。5核兵器国は核兵器の廃棄に向けた努力を約束し、非核兵器国は原子力を兵器目的に使用しないことを約束する。NPTが直面するチャレンジにも拘わらず、運用検討会議での成功に貢献する進展を期待するものである。会議の成功はNPTにおける信頼強化と、原子力の平和利用・核不拡散・核軍縮の分野における持続的協力の基盤に貢献するであろう。
本国際フォーラムが世界各国からの出席者を得て、原子力平和利用の推進・核拡散防止・核軍縮促進に向けた有益な貢献をもたらすことを確信する。
我が国の核不拡散政策の当面の課題
近藤駿介原子力委員会委員長

冒頭、最近行われた事業仕分けについてコメントしたい。原子力政策大綱(2005年)第6章は「原子力に関する施策、特に研究開発は、不確実な未来に向け長期的視点に立った総合的推進が必要との観点から国が実施。国はその取組の意義について国民に説明し、信頼される推進者となることを心がけることが大切」としている。委員会としては政策評価活動を通じてこのことに取り組んできたところ事業仕分けにおける議論を見ていて、原子力政策に係る取組に関する評価に際して国民の多面的な意見を聞き、総合調整を行う取組を強化しなくてはと感じたので、今後の政策評価に当たってはそのように心がけたい。
世界の原子力発電規模は、緩やかに拡大を続け、2009年には30ヶ国で436基、372GWの発電設備が運転され、世界の電力の約15%、一次エネルギーの5.5%を供するまでになった。最近では、新興国で原子力発電所の新設活動が盛んで、IAEAによれば現在、60以上の国が新たな原子力発電に関心を表明し、12ヶ国が具体的な発電所新設計画に取り組んでいる。その理由としては、(1) 各国で原子力発電所が安全に運転されていること、(2) 各国で電力需要が高まっていること、(3) 原子力発電の経済性が高まっていること、(4) 有力な低炭素エネルギー源として評価されるようになってきたことが挙げられている。
国際エネルギー機関の「エネルギー技術展望2008」は、2050年の世界の温室効果ガス排出量を2000年の半分以下にするシナリオとして、同年の世界電力の25%を原子力発電が供給する姿を示している。この姿の実現には、今後40年間、毎年約25基のプラントを運転開始させ、2050年には現在の3倍強の1400GWの原子力発電所を運転していることが必要になる。
我が国の原子力発電は、化石燃料の火力発電を置き換えているとすると、年間二酸化炭素排出量を約20%、量にして約3億トンを削減していることになる。我国は、原子力発電が安全で経済的なエネルギー源として広く利用され、エネルギー安定供給の確保と地球温暖化対策に一層貢献している社会を実現するべきと原子力委員会は考えており、そのため次の7つの取組を並行して進めることを求めている。
- 原子力の平和利用と安全の確保
- 放射性廃棄物の適切な管理・処分
- 原子力発電所の建設、運転、廃止措置の着実な推進
- 再処理で回収した燃料を当面軽水炉で使用し、並行して使用済燃料の中間貯蔵能力を整備
- 高速増殖炉、核融合等の革新的原子力エネルギー技術の研究開発
- 国際社会が、原子力の研究開発利用を安全、核不拡散を確保しつつ、効果的・効率的に推進できるよう連携・協力
- こうした取組に必要なインフラ、知識、人材の供給を確立し、国民の信頼を確保
核不拡散に関する取組はこのうち第7の取組に属するものである。我国は、原子力基本法で原子力活動を平和利用に限定し、IAEAの包括的保障措置を受け入れるとともに、濃縮・再処理技術を実用化する過程でこうした技術に対する保障措置のあり方もIAEAや関係国と共同して開発、実装してきた。また、モデル追加議定書の整備に協力し、その後これを率先して受け入れ、各国にこれを慫慂している。そして、2004年よりは施設タイプ毎に統合保障措置を実施するに至っている。また、原子力供給国グループ(NSG)が定める外国との原子力交易に関するガイドラインを順守し、この公益は二国間協定締結国に限って推進するとともに、追加議定書の締結も条件に加えてきている。
原子力委員会は、我が国の核不拡散に対する姿勢と透明性を確保するため、行政機関には核物質の管理状況の報告を求め、事業者にはプルトニウム利用計画の公表を慫慂しており、さらに、関係組織のトップマネジメントに対し、安全の確保と並んで保障措置活動が最優先に遂行される組織文化を核不拡散文化と名付け、これの浸透に力を尽くすことを要請している。
核セキュリティの確保に関しては、第1に妨害破壊行為に対する物的防護と行為者の処罰に至る一連の国の措置、第2に国境管理の取組、第3に国の統制がおよばない国際組織活動への国際的な対処が求められていると認識。国内問題について委員会はIAEAの勧告INFCIRC225を核物質防護対策整備の参考とすることを求めており、実際、その改定4版を踏まえ、施設の防護機能を設計する際に用いる「設計基礎脅威(DBT)」を国が作成して事業者に提示することを制度化するとともに、核物質防護検査制度及び核物質防護に係る機密保護制度も整備している。核物質防護条約を1988年に批准し、核テロリズム防止条約(2005年採択)を、放射線発散処罰法を成立させて国内体制を整備した上で2007年に批准した。さらに、非国家的行為主体の大量破壊兵器使用の抑止に向けた国際協調体制の構築を謳う国連安保理決議1540の採択を受け、所要の取組みを実施している。核テロに対抗するグローバルイニシアティブ(米露主導)には政府を含む関係者が全面的に協力(高濃縮ウラン回収、テロ活動の防止・検知・対応)している。また、委員会は、核セキュリティの確保には施設等の現場における規則の遵守、改善等に取組む姿勢がいつも高い水準に維持されていることが肝心と考え、そうした組織文化である核セキュリティ文化の醸成を各方面に依頼している。
国際社会において原子力発電に関心を有する国が増えることに対応して、核不拡散体制の強化に向けて、以下の3種類の提案がなされている。
- 追加議定書プラスに代表される、各国の情報や施設にIAEAが接近する義務と権限の強化
- 情報駆動型保障措置活動を通じたIAEAの査察能力の強化
- 核拡散ポテンシャルの増大を抑制する要因(国連安保理への通告制度)やこれを減少させる誘因の用意(多国間管理による核燃料サイクルサービス提供の仕組みの整備、核拡散抵抗性技術採用の制度化)
第3のカテゴリーの取組に関する新しい動きとして、本年4月、米国のオバマ大統領がプラハにおける演説で、諸国が核拡散リスクを増大させることなく原子力の平和利用を享受できるよう、国際核燃料バンクを含む原子力平和利用のための新しい枠組みの構築することを提案したこと、その後米国国務省やエネルギー省高官から、ゆりかごから墓場までの核燃料サービスの実現に向け真剣な検討をとの発言がなされていることに注目している。
我が国は、濃縮や再処理、MOX燃料加工施設の建設にあたってSafeguards by designの考え方の先鞭をつけるとともに、保障措置や核セキュリティに係る革新的技術開発、新興国の保障措置体制の確立のサポートに取り組んできた。我が国は、今後とも関心を有する国々と共同してこうした取組みを推進するとともに、核不拡散と原子力の平和利用を両立させる新しい国際フレームワークの形成活動にも積極的に取り組んでいくべきと考える。
主に核不拡散推進の観点から
ボニー・ジェンキンス(米国国務省 国際安全保障拡散防止局 脅威削減プログラム 大使)
代読:リチャード・ストラットフォード(米国国務省 原子力安全・セキュリティ部長)

NPTの3本柱の1つである核軍縮について、核兵器国の削減努力に加え、非核兵器国が核兵器を取得しないことも重要であり、厳格かつ効果的な国際管理のもとで普遍的かつ完全な軍縮に導くよう全加盟国が努めるべきである。近年、原子力が見直されている背景として、(1) とりわけ発展途上国における人口増加、産業の発展に伴う、かつてない電力需要の高まり、(2) エネルギー安全保障の観点からのエネルギー供給の多様化の要請、(3) クリーンエネルギー技術への指向がある。オバマ大統領のプラハ演説にあるように、「気候変動に立ち向かい、平和を推進するために原子力を利用すべき」である。
カーネギー国際平和財団の調査によると、トルコ、フィリピン、エジプト等が改めて、ヨルダン、UAEが新たに、原子力導入を検討している。最近のIAEA事務局長報告によると、IAEAに対し原子力発電プログラムの導入に関心を示した国々は60ヶ国にのぼる。原子力利用の拡大に伴い、原子力安全、保障措置、核セキュリティを意味する3Sの概念が重要性を増してきた。核テロリズムの脅威が現実のものとなり、核セキュリティの重要性はかつてないほどに大きくなり、オバマ政権でも優先度が高い。
拡散リスクに関しては、転用を阻止するための厳格な管理が重要で、濃縮・再処理技術が広がることに制限を設けることが重要になる。既存あるいは将来の施設については透明性の担保と追加議定書を含む保障措置の的確な適用が必要である。保障措置(特に未申告活動の検知)に関するIAEAの権限強化が重要で、天野新事務局長の手腕に期待する。
改正核物質防護条約発効の暁には、基本的な核セキュリティのインフラ基盤整備が期待できるので、署名・批准を各国に要請したい。INFCIRC225に基づく核物質防護も効果的な措置で、2010年rev.5として改訂されるものは国際的な基盤となるであろう。
核燃料バンク構想に関して、アンガルスク濃縮センターのロシア提案が先週IAEA理事会で承認されたが、新事務局長のもとでの更なる進展を期待する。
原子力は大気汚染とCO2排出が無視できるほど少ないという大きな利点がある一方、3Sに関する高い標準を設定して平和利用を担保することが重要である。3Sに関する米国の取組みとして、法規制、人材・資金調達、安全への取組み、核物質管理、新規導入国のインフラ整備に対する支援、IAEAとその技術協力に対する最大の支援、アジア原子力安全ネットワークへの資金面、人材面での支援(ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンにおけるインフラ整備)を提案するとともに、国際燃料バンクへの取組みも行なってきた。米国エネルギー省(DOE)、国家核安全保障庁(NNSA)、原子力規制委員会(NRC)が技術協力協定を40ヶ国以上と締結している。原子力安全条約について、ベンチマークの設定とピアレビューを通じた強化を図り、使用済燃料管理の安全と放射性廃棄物管理の安全に関する合同条約についてピアレビューを通じて改善を図り、より多くの国の参加を慫慂している。
2010年4月の核セキュリティ・サミットでは、核物質のセキュリティを担保する効果的な措置、核物質管理、および核物質のストック削減のコミットメントを参加国に求めたい。核鑑識も重要な議論項目で、日本をはじめ核鑑識ライブラリの枠組の開発などで各国と協力を拡大していきたい。
大量破壊兵器・物質の拡散に対するG8グローバルパートナーシップ、核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ、国連安保理決議1540等の多国間構想を通じた核テロリズム防止(11月の日米首脳会談でも確認)も重要である。
原子力供給国グループ(NSG)では、濃縮・再処理設備、技術の移転に関する議論が行われており、新たな提案の草案をまとめ、2010年6月クライストチャーチ(ニュージーランド)での総会において合意が得られることを期待している。
いわゆる「ゆりかごから墓場まで」という包括的核燃料サイクルの枠組により、新たに濃縮・再処理を実施するインセンティブの低下を期待する観点から、米国は本枠組みを追求したい。また、並行して、米国は原子力協力協定に原子力安全、保障措置、核セキュリティを担保する条項として盛込んでいく。
国連安保理決議1540を全面的に支援(輸出基準の強化、密輸へのリアルタイムでの対応)しており、拡散に対する安全保障構想(PSI)に基づく陸海空軍演習は過去にリビアの核開発断念に奏効した。NNSAは核テロリズムへの対抗に主要な役割を果たしている。
ロシア解体核からの兵器級プルトニウムをMOX燃料に転換(17年間で34トンを処理する予定)して処分する。
国際社会との協同による平和と安全保障の実現に向けた大きな成果を確信し、偉大な物理学者A.アインシュタインの言葉を引用して終りたい。「原子力エネルギーの解放は新しい問題を創出したのではなく、単に既存の問題解決の緊急性を高めたに過ぎない」
「核不拡散・軍縮に関する国際委員会」の概要報告
阿部信泰(日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター所長)

本来、参加の予定であった同委員会の共同議長である川口順子元外務大臣に代わって発表するが、内容は自分(阿部氏)なりの解釈である。
2008年6月のオーストラリアのラッド提案に始まり、10月、エバンス、川口両外相を共同議長としてこの国際委員会が発足し、2009年10月まで4回の会合に加え、中南米.北東アジアにおける地域会合を開催してきた。委員は、5核兵器国、インド、パキスタンを含み、15人で組織、更に20名前後の諮問委員、および、世界各国の軍縮・不拡散研究機関が協力・助言に加わった。2009年10月の広島会合で報告書がまとまり、同年12月半ばに完成・出版(A4版約300ページ)、両議長より、日豪両国首脳に提出される予定である。
具体的な報告書の内容であるが、核兵器国の政治指導者に対する説得力が重要との観点からの勧告になっている。核兵器の破壊力(広島・長崎で10万人超の犠牲者、現存の何万発もが使用されれば人類破滅、100発程度の使用でも世界的気候変動・環境破壊等の惨状)、実際には使用が難しいという核兵器の現実(倫理的・政治的・感情的なタブー)、無差別の破壊をもたらす、使用できない兵器をなぜ保有するのか?更新・強化するのか?との呼びかけを通じて、核戦力の強化、あるいは密かに保有を企図する国々に訴えている。
現実に実施し得る削減の方策として、以下の2段階の核軍縮を提案している。
- 最小化段階:2025年までに「最小地点」まで削減(廃棄の困難さと抑止力としての役割に配慮し、先ず、現在の10%に相当する2000発以下に削減)短期的行動計画(2012年まで)を前段階として設定、これは「核のない世界」を提唱したオバマ大統領の1期目の任期終了までに実施してほしいことを意識している。中期的行動計画(2025年まで):核兵器の役割低下・削減(抑止のみに限定、その後に、先制不使用を宣言:日本も米国に対して要求すべき)。抑止から先制不使用を宣言する時期を分けたのは、北朝鮮の核に対する同盟国の安全保障への懸念に配慮したもの
- 廃絶段階:2025年以降、核兵器がゼロになる時点での軍事バランス、例えば侵略があった場合の措置の担保等、国際安全保障体制の抜本的改革が必要である。核拡散の絶対的阻止及びその検証体制の確立が不可欠になる。
2005年のNPT運用検討会議が不調に終わった理由として挙げられた、(i) 核軍縮が進んでいない、(ii) 中東非核兵器地帯構想が進展していない(1995年の同会議で提唱された構想)に配慮し、2010年5月のNPT運用検討会議に対する20項目の提言を行なっている。核拡散阻止の措置として、追加議定書を全IAEA加盟国が締結することを核物質・技術供給の条件とすること、包括的核実験禁止条約(CTBT)の発効促進、それまでは、核実験の自粛をすること。兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)の早期交渉妥結・発効させ、それまでは兵器用核物質の生産を自粛することなど。核実験のモラトリアム宣言をしていない国々、および兵器用核物質の生産を続けているインド・パキスタンに対する提案も含まれている。
なお、上記の2段階の核軍縮提案について、広島の団体からは秋葉市長による2020ビジョンに比べ手ぬるいとの指摘を受けたが、現実的な実施可能性を追求したものとなっている。
円卓討論1「NPTの3本柱─原子力平和利用、核不拡散、核軍縮」

- 出席者:
- 阿部 信泰(モデレーター):日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター所長・大使
- ピーター・カーター:英国エネルギー気候変動省 核不拡散担当課長
- 遠藤 哲也:元原子力委員長代理・大使
- バレンティン・イワノフ:ロシア科学アカデミー 教授
- キャロライン・ジョラン:仏Areva社 核不拡散・国際制度担当部長
- ハン・ギュ・リー:韓国原子力安全技術院(KINS)顧問(前韓国原子力統制技術院(KINAC)理事長)
- オディロン・アントニオ・マルクーゾ・ド・カント:ブラジル・アルゼンチン核物質計量管理機関(ABACC) 事務局長
- 三又 裕生:経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課長
- 中島 明彦:外務省大臣官房審議官(総合外交政策局担当及び軍備不拡散・科学部担当)
- 岡﨑 俊雄:日本原子力研究開発機構 理事長
- リチャード・ストラットフォード:米国国務省 原子力安全・セキュリティ部長
- 田中 知:東京大学大学院工学系研究科 教授
- 谷口 富裕:国際原子力機関(IAEA) 事務次長

最初に、モデレータの阿部所長からNPTの3本柱である、原子力平和利用、核不拡散、核軍縮に係る課題について以下の問題提起を行った。
- 原子力平和利用と核不拡散の両立
原子力平和利用推進の観点からの課題
- 新たに原子力を導入する国によるインフラ整備をいかに支援するか
- 原子力の拡大に必要な若い科学、技術者をいかに確保するか
- 次世代の原子力システムの研究開発をいかに進めるか
- 原子力分野における国際協力をいかに進めるか
- 原子力平和利用と核不拡散の両立
- 3S(原子力安全、保障措置(核不拡散)、核セキュリティ)に関する新規原子力導入国への支援
- 保障措置、核物質防護、輸出管理、二国間原子力協力協定等、既存の核不拡散措置の強化
- 核燃料サイクルの多国間管理、核拡散抵抗性技術等、新たな核不拡散措置の導入
- NPTに内在する課題
- 差別性(核兵器国と非核兵器国の差別、核燃料サイクル技術保有国と非保有国の差別)をいかに克服するか
- 脱退をいかに難しくするか
- 遵守、執行をいかに確保するか。
- NPT非加盟国も含め全ての核兵器保有国による核軍縮、核不拡散の推進
- 非核兵器国に核不拡散措置の強化を受け入れさせる観点からの核兵器保有国による軍縮の進展の重要性
- NPT非加盟国を国際的な核軍縮、核不拡散体制にいかに組み入れるか
以上の課題を踏まえ、本円卓討論では、以下の6項目に焦点を絞って議論が行われた。
- 持続可能な形でいかに原子力を推進し、そのための課題を解決するか
- 新規原子力導入国による3S確保をいかに支援するか
- 核燃料サイクルの多国間管理は核不拡散の観点から有効か
- 追加議定書の普遍化をいかに推進するか
- NPTの不公平感をいかに克服するか
- NPT非締約国との原子力協力をいかに評価するか
【課題1.持続可能な形でいかに原子力を推進し、そのための課題を解決するか】
(カーター)

- 英国も原子力利用が拡大しているが、原子力利用を世界的に広めることによって拡散リスクが増大するか、そうであればどう対応するか。最近英国政府は、「Road to 2010(2010年への道のり)」という文書をまとめた。この文書には、NPT運用検討会議に向けた課題が挙げられている。核拡散リスクの増大に対する根本的な解決策はなく、この文書においても斬新な考えが入っているわけではない。この文書の中から重要な点を3点ほど示したい。
- 原子力平和利用の推進の中で、IAEAは中核的役割を果たす組織であり、特に重要である。英国はその重要性を認め、以前よりIAEAに対して、保障措置に対する支援プログラムの実施、濃縮施設に適用される保障措置の手法の開発に関する支援など、必要な支援を行ってきた。濃縮施設関連技術に関連しては、その技術のブラックボックス化が重要である。
- 英国は燃料供給保証、燃料バンク構想を支持する。英国自身も燃料供給保証の提案を行っているが、非政治的理由による途絶への対応を目的としている。
- また、人材育成に関しては、新しいスキル構築のための教育機会の提供が必要であると考えている。本文書の中で、英国において、原子力拠点(COE)を設立する予定とされており、原子力平和利用だけでなく、核不拡散(政策、技術)も対象となる。大学、原子力産業界、海外機関と協力を行うことが想定されている。
- 原子力新興国の支援に当たっては、以下の3つの方法がある。(1) IAEAが中核的な役割を演じること、(2) 二国間の枠組みによる協力、(3) 新規原子力導入国自体の責任
(イワノフ)

- 原子力に対しては新規の取り組みをしなければならない。現在、我々は大型原子炉、ウラン燃料という安定的な枠組みしかみていないが、これでは核拡散の問題は解決しない。新規原子力導入国は濃縮ウランより電力そのものが欲しいのではないか。従って、燃料バンクが効果的とは思わない。例えばロシアは浮遊型の原子炉を建設しているが、こうした100MW以下の原子炉は、使用後に供給国に戻されることから、核拡散リスクは少ない。
- 旧ソ連の時代に原子力分野の顧客だった国に対しては、旧ソ連が燃料を提供し、使用済燃料を持ち帰っていたが、2001、2年頃にこうした活動を停止した。新たに原子力を導入する国にとって使用済燃料の管理は頭の痛い問題であり、使用済燃料を持ち帰ることは核不拡散の観点から効果的である。
- もし新規に電力が必要な場合には、国際原子力発電センターといった構想が必要ではないか。第三国から新興国に対する電力供給を検討してはどうか。
- 核不拡散の確保は新しいアイデアがなければ難しい。それも提案するだけでなく、実際に最初の一歩を踏み出すことが必要である。
(三又)

- 原子力利用の国際的な拡大は必然である。原子力平和利用では核不拡散に加えて、原子力安全確保が重要である。日本は原子力の平和利用で先頭に立ち、率先して保障措置の受け入れを表明するなど、原子力安全に対する取り組みを含め、これまで多くの実績を持っている。このようなことから、日本は最も貢献できる立場であり、世界への貢献が重要な責務と考えている。
- 産業界の立場から見た場合、今年3月に日本の電力会社、関連会社が原子力国際協力センターを開設した。同センターが新規原子力導入国に対するニーズに応えるため、中心になってインフラ整備を実施する体制になっている。これは政府とも連携した活動である。核不拡散分野で産業界がいかなる役割を果たすかについては今後の検討課題である。ここで、3点ほど指摘したい。
- IAEAの役割拡大の認識があること、保障措置だけでなく原子力安全分野での活動も同様である。また、追加議定書は新規原子力導入国への適用を働きかけることが必要になる。追加議定書導入が進めば物理的にIAEAの役割は拡大する。このことに対する国際的認識を持つことが必要。
- 軽水炉(LWR)だけでなく高速増殖炉(FBR)の研究開発段階から、抵抗性を考慮した設計、核物質防護の考慮などの要素を加味していくことが必要。
- 原子力産業はボーダレスの側面が強く、大きなコングロマリットによる寡占化が進んでいる。国が主体となった枠組み作りが基本だが、企業が主体となって行動規範(Code of Conduct)のような枠組みを作ることがあっても良いのではないか。国の枠組みを補完するイメージである。
【課題2.新規原子力導入国による3S確保をいかに支援するか】
【課題3.核燃料サイクルの多国間管理は核不拡散の観点から有効か】
(遠藤)

- 3Sの各構成要素である原子力安全、保障措置(核不拡散)、核セキュリティの各要素の重要性はこれまでも議論されてきたが、3Sとして一緒に議論しだしたのは、洞爺湖サミットの首脳宣言が最初であり、その重要性はラクイラサミットでも再確認されている。3Sイニシアティブは日本が提案したことから、今後もこの議論は日本が主導すべき事項であると思うが、これまでの対応を見る限り政府の腰が重い印象がある。
- 本日の午前中のセッションでは、ジェンキンズ氏(ストラットフォード氏代読)から米国の3Sイニシアティブに対する支援表明があったが、IAEAは必ずしも3Sについて積極的ではなく、寧ろネガティブな印象を持っているようである。IAEAのかかる態度には、(1) 3Sの推進が南北問題を助長するような要素があり、途上国側が3Sの推進を新規規制制度の導入であると感じていること。(2) 新規導入国が整備すべきインフラに対しては19項目の整備項目を示した「Milestone in the development of a National Infrastructure」 をIAEAはとりまとめているが、3Sはこの内の3項目だけを取り上げたものであることから、これに対する反発といった理由が考えられる。このような情勢ではあるが、今後は日本のイニシアティブにより、米、英、仏、露、IAEA等と協力して、3Sイニシアティブの具体化に向けてその内容を詰める作業が必要である。
(谷口)

- IAEAの中でも日本のイニシアティブを受けて3Sに関する統一見解を検討している。原子力導入を進める上で重要な3つの要素の一体化を図ったところに意義があるが、原子力安全とセキュリティ、セキュリティと保障措置の間で明らかにシナジーがある。特に国以外のアクターが出てくる問題については、有効と思われる部分を積極的に生かしていくことが重要であると考えている。
- 核セキュリティ、原子力安全問題で自国のプログラムにIAEAが介入するのではないかとの懸念を途上国は持っている。これまでIAEAは、途上国側に対し、規制と開発促進のバランスの取れた推進を説明してきている。途上国における原子力導入支援は開発促進とバランスをとって進める方向であり、日本に期待するところが大きい。なお、IAEAの19項目のマイルストンから、3項目のみを取り上げたとの議論に対しては、結局19項目は全て、原子力安全、核セキュリティ、保障措置の3項目と密接不可分になっているとの考え方があるのではないかと思っている。
- 原子力の世界では、新しい発想、可能性、挑戦に対してどのように取り組むかを考えた方がよい。2030年には、原子力の発電量が倍になるという話があったが、これは上限値の話であり、導入国数で言えば20ヶ国、導入される原子力発電所の数で言えば440基程度の増加という話である。この場合の下限は5ヶ国であり、100数十基程度である。なお、ここで導入を進めようとしているのは、インド、中国、旧ソ連圏諸国といった原子力の既存ユーザー国が大半であることに留意して欲しい。
- 従来、原子力導入が計画される場合は、技術的に成熟した国での導入が進められてきたが、今の実態を見ると問題を抱えた国、技術的能力が限られた国において導入が計画されている場合が多く、核拡散のリスクは高まっているとも言える。導入に伴い発生する不確実性や変動に対してどのように対応していくかが問題である。技術的及び社会インフラに弱点を持つ国では、不確実性に対応する余裕度が重要である。なお、新規原子力導入国の動きを見ると、原子力については技術的、経済的な合理性に基づき導入を検討しているのでは無く、戦略的な意味での導入意図が多いように思われる。
- 従来、IAEAは途上国に対する支援がその業務基盤の一つであったが、原子力のような難しい技術は、そもそも自助努力が必要であり、手取足取といった支援が必要な国は原子力導入が難しいのではないか。原子力先進国(資機材供給国)に全面的に依存するような段階で、原子力導入を図ることは問題(パターナリズムでは済まない)であり、 原子力導入に対しては少し厳しめの基準を示す方が良いと考えている。
(中島)
- 3Sは原子力先進国による技術の囲い込みと一部の途上国には受けとれられているが、3Sが王道であり、原子力利用の近道であると知らせるようなアプローチが必要であると考える。このためには、マクロで視れば原子力は人類の知的財産である、との観点から、一定の条件をクリアすれば良いというパターンを押し付けるようなアプローチでは無く、その基準策定の背景を理解させるような、チュートリアルなアプローチが必要。
- これは困難な一面があるが、原子力導入の際に実施すべき全体像を適切に示すことがポイント。研究開発分野、原子力関連産業分野、原子力安全分野、保障措置のように原子力は各分野に特殊性があり専門事項も多岐にわたっているが、原子力エネルギーに携わる専門家が共通の意識を持つことが重要。各分野毎にはこの意識の共有が進んでいると思われるが、全体としてそのような意識を持てるかが問題。
- 原子力導入に向け無理なスケジュール設定は実施が困難。原子力導入に向けたインフラ整備は10年単位で行うべき事項である。原子力は広い学問分野であり、受け入れに向けた基盤整備自体が導入国にとって有益であるということがセールスポイントになると思っている。
- 3SにおけるIAEAの役割であるが、3Sアーカイブにおけるサーバー的な役割ではないかと考えている。
(ド・カント)

- ABACC事務局長としての立場から若い科学者、研究者を原子力に対して呼び込むことができるかということについて話したい。
- まずブラジルの位置しているラテンアメリカという地理的な条件が、日本、中国、韓国が位置するアジアとは異なるという点を認識して欲しい。ブラジルでは科学全般に興味が失われており、工学分野での人材不足が深刻である。ブラジルは現在、経済成長の途上にあり、工学系の人材が不可欠。高校レベルでは、理科離れが進んでいることから環境整備の改善が必要。NPTの3本柱全般に対する印象であるが、国連事務総長は、先週、兵器に対して資金が割かれすぎており、平和に対し資金が不足している旨を述べている。原子力はジキルとハイドにたとえられ、ジキルの部分、すなわち原子力の良い面を強化し、ハイドの部分、すなわち悪い部分を排除していくことが重要。そうすることにより、原子力は、各国による貧富の差を解消する方策ともなり得る。
(リー)

- 多くの国が原子力のメリットを享受している。韓国も海外技術を取り入れ、今では原子力発電所を自主的に設計できるようになった。韓国の例を見ると原子力新規導入を機微技術の拡散無しに実施することは可能であると思っている。
- 本日は主として「3Sの推進」について話をしたい。日本は非核兵器国であるが、優れた原子力平和利用の実績を有しており、そのイニシアティブに基づく新規導入国への支援を期待。3Sに関して、国際アプローチ、地域アプローチを通じた支援は必要であると考えている。また、3Sに関する指導的役割を果たす機関としてIAEAが役割を果たすべき。
- 段階的アプローチはオプションの一つである。他方韓国では、海外からの原子力発電所の導入に当たっては、運転員は訓練を受けるために海外に派遣されたということがあった。規制のための専門組織が設立された。韓国における原子力発電所の稼働率は90%以上であるが、原子炉の設計段階から規制主体が関与することにより、安全性の向上だけでなく、運転効率の向上をももたらしている。
- 核不拡散に関しては、南北非核化共同宣言に基づき、韓国では検証を担当する組織が設立された。また、追加議定書の批准にあたり、小規模の試験の申告を行った。その後、国内計量管理制度を整備するとともに、保障措置、輸出管理、核物質防護を所掌する機関を設立。従って、韓国は3Sの推進に関する経験を有している。実際にアジアの国を対象に原子力安全の専門家を育成する取組みを実施した。今後の3Sの取組みは、インセンティブの付与等により、3Sに携わる人材を育成することができるか否かに依存する。
- グローバルな原子力発電容量は2030年迄に2倍になるとの話があったが、原子力発電国の多くが機微な原子力技術を有するようになることは経済的に非効率であり、望ましくない。原子力発電実施国にとっては、妥当な価格、高い品質などが保証され、非差別的に燃料供給を受けられることが必要。また妥当な経済性を有する核拡散抵抗技術も必要である。この燃料供給保証の多国間アレンジが成功するためには、IAEA、加盟国の努力に基づく政治的コンセンサスが必要。
- 韓国では使用済燃料の管理に関する検討の結論はでていない。核燃料サイクルの多国間管理構想は核不拡散の観点だけでなく、放射性廃棄物処分の観点も含む包括的なパッケージで解決しなければならないと思っており、供給国、受領国、国際機関、非政府機関、学界を含む枠組みを形成することが重要である。
(ストラットフォード)
- 新規原子力導入国の原子力安全、核セキュリティ水準を受容可能なレベルまで向上させなければならない。核セキュリティは、米国が締結する二国間原子力協定に基づき、相手国の施設を訪問し(cooperative visitと称している)、核セキュリティの状況を確認し、是正を要求することが可能。他方、原子力安全に関しては、原子力安全条約、使用済燃料管理の安全及び放射性廃棄物管理の安全に関する合同条約の締結を求めることが有効。これらの条約では、3年ごとに開催される締約国会議において、条約の履行状況についてピアレビューを受けることが規定されており、こうしたプロセスを通じて、原子力安全の向上が図られる。良好事例の拡大やその他の安全水準向上には、自発的な行動が必要。
(岡﨑)
- 地球温暖化防止に向けたアクションを検討するCOP15に対して、原子力による貢献を考慮に入れないことはナンセンスである。さらにCOP15の対象外である2030年以降への原子力の貢献も重要。
- 原子力促進のために必要なものに関連し、新規導入国、3Sといった課題が取り上げられたが、これらに対する問題意識を共有化して、原子力利用に関する全体像を共有化することが必要。さらに燃料供給保証、次世代原子力システム、安全と不拡散からの観点を共有する信頼性のあるシステムを構築することが責務と考える。さらに地域的な協力、特に東アジアの協力体制の中で日本の貢献が必要。
(田中)

- 人材育成の重要性を強調したい。教育、研究機関、産業界、大学の何れも国際レベルでの協力推進が必要。核不拡散の観点から、客観的な判断ができる人材の育成が重要。
(ジョラン)
- 新規に原子炉を建設する政治的決定がなされる時点と実際に建設が始まる時点の間に人材育成を行う必要がある。国際協力も利用しながら、原子力開発をリードする人材を育成することが必要この中でのIAEAはきわめて重要な役割。
- 人材という意味では法律の専門家、産業の専門家など様々な種類の専門家が必要となる。
- 3Sについて、第四世代原子力研究開発国際フォーラム(GIF)やINPROにおける議論では、経済性、廃棄物管理といった要素も含まれているが、現状の3Sの議論ではこれらが抜け落ちてしまっている。
- 問題は3Sの考え方を誰に対して訴えかけていくかということ、国際社会に対してなのか、IAEAに対してなのか、産業界なのか、設計者に対してなのか、3Sを設計に取り入れることは重要
- 査察官がセキュリティや安全性も審査すべきとの考え方もあるが、これは上手く行かないのではないか。
【課題4:追加議定書の普遍化を如何に推進するか】
(中島)

- 追加議定書の普遍化推進は日本の外交の柱であり、未批准国に対し批准を働きかけるとともに、追加議定書の批准を、二国間原子力協力協定を締結する上での条件としている。追加議定書の批准を促すためのアプローチが課題であり、批准促進に向けて、どのようなメッセージを伝えるべきかが問題である。この点で、以下の3点を指摘したい。(1) 追加議定書批准国としての地位についてIAEAのお墨付きを得ることが、政治的な利益をもたらすこと。(2) 批准に向けての過程が信頼関係構築のプロセスであること。(3) 追加議定書の批准にあたっては、日本の場合も主権侵害ではないか、との声もあったが、保障措置の実体はIAEAとの共同作業に近く、このプロセスの積み重ねの結果、現在のIAEAとの(信頼)関係があること。
- 保障措置の技術コミュニティともいうべきものができ上っていると考えることができ、追加議定書の適用によって、こうしたコミュニティの技術力向上につながるのではないか。
(谷口)
- 技術的知見と実践の連携という意味で、技術的コミュニティの構築が今後の課題。査察の受入れに関し、日本は必ずしも優等生ではないが、それでも依然としてIAEA全体の査察人・日(PDI)の3分の1は日本に注がれているのが事実。この点で、日本が保障措置の認識に対するギャップを埋める役割を担うことが重要。
- 新規原子力導入国との関連で、追加議定書について「飴と鞭」の「鞭」のイメージだけが強いのは問題である。新規原子力導入国に対するメッセージとして、追加議定書批准によって得られる「飴」の部分の認識を促すことが不可欠であり、現在はこの点での努力が不十分である。
(ド・カント)
- ブラジルの元大使が執筆した論文によれば、ブラジルの立場は、ブラジルの追加議定書批准については大きな障害は無いが、核兵器国が核軍縮を推進しない限り、追加議定書の批准等、核不拡散に関する追加的な措置をとるつもりはないというものである。
(ストラットフォード)
- 追加議定書は未申告活動検知のために不可欠なツール。非核兵器国は追加議定書の批准、適用によって、透明性確保に努める姿勢を示すことに意味があると考える。
(岡﨑)

- 核不拡散体制強化のためには、IAEA、国、及び地域の保障措置の効率化が非常に重要となるが、その点で、追加議定書の適用が大変有意義であり、統合保障措置への移行のためにも必要である。さらに、「追加議定書プラス」により追加議定書を超える措置を取ることが必要。
- この認識から、追加議定書を適用することによって、如何に保障措置の効率性を達成することができるかをメッセージとして未批准国に伝えていくことが重要である。また、追加議定書に関連し、主権侵害に対する懸念について、きちんと議論を進めていくこと必要がある。
【課題5:NPTレジームにおける不平等性をどのように克服するか】
(ストラットフォード)

- 核兵器国が非核兵器国と同様のルールを守る姿勢を示す第1のステップはボランタリー・オファー保障措置協定。米国は、IAEAとボランタリー・オファー保障措置協定の下、保障措置対象の原子力施設リスト(eligible facilities list)として250の施設を指定している。その内、2つの施設に保障措置を適用しているのみではないかという主張はあり得るが、既に核兵器を有している国に対し保障措置をかけても実質的な意義は薄いという点に加え、もし、米国の全ての対象となれば、要する資源は125倍に達するという資金上の問題が生じる。また、追加議定書に関しても、核兵器国が締結しているものと非核兵器国が締結しているもので内容が異なるとの批判がある。論理的には、未申告原子力活動の探知を目的とする追加議定書を、未申告の活動を実施している核兵器国に適用することにどれほどの意味があるのかということになるが、これも不公平感を緩和する取組みの一つとして位置付けられる。
- 「軍縮の進展が非核兵器国の不公平感を和らげることになるか」という設問は設定として正しくない。非核兵器国の問題意識は、核兵器国と非核兵器国の間で差別があることではなく、核兵器を保有していることそのものがモラル上、良いことではないということではないか。モスクワ条約が履行されれば、米国は大幅に核兵器を削減することになるが、ゼロにならない限り核軍縮努力が足りないという批判がなくなることはないであろう。
- 「核燃料サイクルの多国間管理がNPTの差別的な側面を和らげるか」という設問に対しても、自分はそうは思わない。濃縮施設は民間企業により運営されており、現状の商慣行で、そうした民間企業が技術そのものを移転しないブラックボックスアプローチをとっているのは、核不拡散上の理由もあるが、商業上の機微情報を保護する観点が大きい。濃縮技術を保有しない国の不満に対しては民間企業に言ってくれと言うしかない。
- 核燃料サイクル技術保有国と核燃料サイクル技術非保有国の不公平という問題も、同様に、技術を保有する者が競争力を維持するために、技術を移転することを拒否するということに帰結し、ある国が技術を保有する権利を奪われるということではない。
(ジョラン)

- NPTレジームの差別に関して別の側面もあることに言及したい。例えば、URENCOの施設をフランスに建設しようとした際、IAEA保障措置の適用施設とするのに多くの問題の解決を要した。仮にこの施設がドイツに建設されていたならば、自動的にIAEA保障措置の対象となり、問題はなかったであろう。これは、核兵器国に対する逆差別とも言える。また、英仏両国はEURATOMの保障措置の適用を受けているにもかかわらず、日本等の非核兵器国から移転された資機材についても、それが兵器プログラムに使用されないことの担保として、特別の取決めを求められる。
- これは一つの提案であるが、将来、核兵器国に設置される多国間管理の機微原子力施設についてはIAEA保障措置の対象とし、保障措置に要する費用は関係国で負担してはどうか。また、通常のボランタリー・オファー保障措置協定の取扱いと異なり、一旦、保障措置の対象とした施設を保障措置の対象から外さないコミットメントを求めることが考えられる。また、国レベルのアプローチを採用することを通じて保障措置の効率化を図ることが考えられる。
(カーター)
- 核兵器国の核政策について、現在は過去30年間で一番透明性が高くなっているといえる。不公平は実際に存在しており、核燃料サイクルの多国間管理はこの問題の解決策の一つ。問題になるのは、こうした構想をいかに顧客にアピールしていくかであり、各種提案の非差別的性格を強調する必要がある。
(遠藤)
- 非核兵器国として、私はNPTを不平等条約と考えている。非核兵器国に課せられる法的な義務に対し、核兵器国に課せられているのは軍縮に向けての誠意といういわば精神的義務だけである。日本がこの様な不平等条約を受け入れた背景には、NPTによりこれ以上核兵器国を作らないという大義名分があったからこそである。NPTの不平等性を克服することはできない。だからこそ、核兵器国は、実質的な軍縮の努力を続け、その軍縮努力によって不平等感を減じていくことが求められていると考える。
(岡﨑)
- 保障措置における不平等性に関連し、FMCTの議論を進めることによって保障措置の不平等性をかなり低減することができると考える。
(イワノフ)
- 国際ウラン濃縮センターはIAEA保障措置の対象となり、その費用についてはロシアが負担することになる。
- 他に、ロシアでは兵器級プルトニウムの解体の問題があるが、BN800が解体プルトニウムの処分に利用されるようになれば、BN800も保障措置の対象とすることを考えている。これはIAEAにとって新たな活動領域であり、有益。
- また、NPT加盟国との協力は2つのカテゴリーに分けて考えるべき。原子力発電に関する協力に限定されていれば核拡散上、何の問題もないが、核燃料サイクルを伴う協力を伴う場合は特別のルール作りが必要
【課題6:NPT非加盟国との原子力協力をどう評価するか】
(ストラットフォード)
- 私は米印原子力協力協定の交渉担当者であり、現在、再処理に関する実施取極めの交渉を実施中。米印原子力協力はNPT違反であるという誤解があるが、正しくない。NPT第3条2項は、原子力資機材の輸出に際して包括的保障措置の適用を求めておらず、当該資機材に対し、IAEA保障措置の適用を求めているのみ。あとは政策としての良し悪しの問題になるが、30年もの間、NPT体制という塀の外側にあって、当面、核兵器を放棄する可能性がない国を更に次の30年間、そのままの状態で放置しておくのが妥当か否か。本協力の推進にあたり、考慮した要素は、(1) インドが人口10億人を擁する大国であること、(2) 民主国家であること、(3) インドの核兵器能力は不法に取得したものではないこと、(4) インドからの核拡散の実績はないこと、(5) インドの電力需要が化石燃料で賄われた場合の環境への影響
- 米印原子力協力協定の締結(2008年12月発効)に至るまで、原子力協力に関する米印の共同声明(2005年7月)、インド原子力施設の軍民分離に関する合意(2006年3月)、インドとの協力を可能にする米国内法(ヘンリー・ハイド法)の発効(2006年12月)、原子力供給国グループ(NSG)による承認(2008年9月)などの経緯があった。NSGガイドラインは法的義務を課すものではないため、NSGを迂回するというオプションもあったが、NSGガイドラインによる政治的義務を真剣に受け止め、(45カ国による)グループの中に入って説得に努めた。
- インドはこれまで30年間にわたり原子力ビジネスから孤立していたため、原子力ビジネスのルールについて理解していない部分があり、徐々に慣れていくことが必要
- 政治的に困難な問題をプラクティカルなアプローチで解決した例として以下が挙げられる。インドは自国の輸出管理をNSGガイドラインに則って実施することを約束したが、自国がメンバーでないNSGの場で頻繁に変更が行われるガイドラインに合わせて国内法を改正することに対して抵抗を示した。そこで、NSGの議長が、毎年、インドを含むNSG非メンバー国に対して、アウトリーチ活動を通じてガイドラインの変更の提案を説明するようにし、ガイドラインもそのように改正された。以上の例が示すように、米印原子力協力に関する他の問題も現実的な方策により解決が可能であると信じている。
(遠藤)
- 日本は、インドとの原子力協力の問題での議論について、IAEAの理事会における保障措置協定の議題審議、NSGでの議論の際の二つの機会で関与した。
- では日本は米国と同じようにインドと協定を締結できるかと考えると、非常に難しいと考える。インドとの協力を検討するにあたっては、少なくともインドのCTBT批准を前提として考えたい。現時点でインドがCTBTに署名・批准することは難しいが、米国のCTBT批准が、インド及び中国の批准を促すことにもなるなど大きな促進力となる。そうすると、日本政府もインドとの原子力協力の可能性を検討することができるようになるのではないかと思う。
【一般聴衆を交えた質疑応答・コメント】
(米印原子力協力について)
(一般)
- NPTは他に核兵器国を作らないことが目的であったはずだが、インド及びパキスタンは核実験を実施した。この様なインドとの原子力協力を推進することは、北朝鮮などの他の懸念国にも悪影響と考えるが、この点についての米国の見解は?
(ストラットフォード)
- 米印原子力協力合意はNSGの場でも、必ずしも積極的に支持されたわけではなく、仕方なく受け入れられた(allow it to happen)という方が正しい。しかしながら、私は、政権の一員として、また個人的にもこの合意は正しく、将来、必ず評価されると信じている。交渉にあたってインドを14ケ月で4回訪問したが、その貧しさに驚きを禁じ得なかった。インドはクリーンで二酸化炭素を排出しない原子力エネルギーを必要としている。
- インドはNPT非加盟国であるため、NPT違反の問題にはならない。ただし、当時、国際社会が、NPTにより明確に引こうとした、核兵器国と非核兵器国を隔てるラインの向こう側に自らを位置付けようとしたということは言えるかもしれない。
- 北朝鮮の問題はそれ自身が難しい問題であり、米印原子力協力合意が影響を与えるとは考えない。
- インドはCTBTを批准することを表明していないし、二国間協定の中で核実験を実施しないことを確約しているわけではない。しかしながら、米印原子力協力協定を注意深く読めば、インドが再度、核実験を実施した場合、米国は供給した資機材の返還請求権を有していることが分かる。このことは、米印合意が、インドに対するアメとともに、核実験を実施した場合のペナルティという意味でムチの要素をも含むものであることを意味しており、インドによる核実験をより難しくするという意味において核不拡散上、意味がある。
(一般)
- インドの核実験実施の際の協力撤回に関して、インドの解釈は米国のものと異なるように思う。インドは、米国が協力を撤回したとしても、他の供給国を探せばいいと解釈している。この点で米国の解釈は違うのか?
(ストラットフォード)
- インド内の解釈について、私から発言することは避けたいと思う。協定を注意深く読めば、米国が制約されない権利を有していることが分かる。インドの核実験実施にあたっての対応に関し、米国政府が核実験実施の背景を慎重に検討しても尚、インドとの認識の違いの問題が解決しなかったと判断した場合、又は解決できる問題ではないと判断した場合には、協定を終了することが可能という表現を用いている。この様な表現を用いた背景には、核実験という問題が、非常に政治的にデリケートな問題であるため、大統領に政治的判断の余地を与えているとも言える。
(NPTレジームの不平等性について)
(一般)
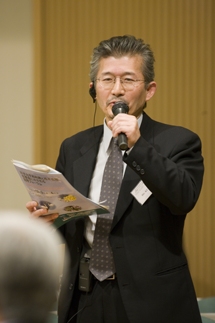
- 完全に不平等性をなくすことはできないが、不平等性緩和の意味で、核軍縮とFMCTが重要となる。また、転用検知を目的とする非核兵器国の保障措置と、核兵器国のボランタリー・オファー保障措置では、その性質が全く異なる。核兵器国に対しても非核兵器国へ輸出する核物質、あるいは輸入した核物質に対する計量管理を義務づけることで、非核兵器国における転用を防止するという意味が生じる。
- 保障措置レベルは同じである必要があるが、保障措置アプローチは各国の状況を勘案して差別化が図られても良いのではないか。
(久野)
- 不平等性という問題について、「説明責任」・「説明努力」が重要であると認識した。本日の議論を通して改めて理解したことも多い。核兵器国には、「説明責任」という点で、努力していただきたいと思う。
(村上)

- 核兵器国における査察の目的は協定に2つ明記されている。1つは、民生活動の核物質が軍事用に使用されないことを検認することである。2つめは、特殊な核燃料サイクル施設などにおける査察経験を積むこと(新しい技術等、非核兵器国にとって何か有益なものが生まれる可能性)を目的としている。また、日英原子力協力協定、日仏原子力協定に基づき日本から移転された核物質にIAEAが保障措置をかけているようなケースもある。日本の査察量が多いという指摘があったが、外から見た場合、日本は、Pu、核燃料サイクル施設、技術者が揃っており、核兵器を製造するために不足しているのは、その国家意思だけという状況である。国内の見方と国外からの観点では、認識にギャップがあることを理解する必要がある。日本が非核兵器国として唯一、商業規模のクローズド・サイクルを実施でき、何故他の国はできないのかを含めて考えることが必要。
(3Sについて)
(一般)
- 3Sが重要であるという指摘だけでは不十分である。3S確保のためのガイドラインの策定などが求められるのではないか?
(谷口)
- 保障措置に関するIAEAの権限がIAEA憲章に明記されているのに対し、安全とセキュリティについては、IAEAの活動はメンバー国からの要請に基づくアドバイザリー的なものに限定され、3Sの各項目によってIAEAの権限が異なることが問題としてある。供給国側の産業界が行動規範を策定し、3Sを順守してもらうという動き(カーネギーが中心)はあるが3S確保のためにIAEAが中心的な役割を果たすことにIAEA内でコンセンサスは得られていない。ただし、2008年、賢人会議がまとめた2020年に向けた報告書の中では3Sのアイデアが含まれている。
(核軍縮について)
(一般)
- 核廃絶のスケジュール、目標は?
(カーター)
- 英国のブラウン首相は廃絶のタイムラインは示していない。国際的な安全保障環境に依存する。
(人材育成について)
(一般)
- 原子力を専攻していた学生が別の分野に行くケースが多いが、若い世代を原子力に引きつけるようにすることが重要
(一般)
- 人材育成に関して2点コメント。(1) 数の議論ばかりではなく、質の議論も必要。つまり、原子力業界に入ってきた数少ない人材をいかにクオリティ高く育てていくかが重要ではないか。(2) 学生には、国の政策とは無関係にあらゆる国の人々と話をすることができるという利点がある。学生時代にそのような機会を与えることで、メンタリティを育成することが重要ではないか。20-30年後の政府間交渉の場で、そのメンタリティの価値が出てくると思う。
(カーター)
- 人材育成について英国の事情を話すと、特に若い男性が原子力ではなく(ビジネス)マネージメントに流れるという傾向がある。その理由として、原子力の世界では若い人が意思決定のプロセスに入りにくいという事情があるように思える。若い世代に魅力的な環境作りが必要。
- ビジネス・科学技術の観点からの原子力の魅力は増す雰囲気になりつつあり、それは、大学などのコースにも反映されつつあると思う。
(ストラットフォード)
- 人材育成に一番簡単的な方法として若い人に奨学金を出すこと、そして雇用機会を創出することである。海軍では、無料で教育を受けさせることにより、原子力潜水艦の専門家を養成しているが、民間の原子力産業界にとって原子力の専門家を養成するのは難しい。
(ジョラン)
- 原子力分野での人材育成を考える上で長期的な観点の検討が必要。また、雇用機会、あるいは政治的な支援・他の特権の享受など、原子力業界の魅力をメッセージとして伝えることも重要。
(田中)
- 若い人達には、日本の政府、産業界が原子力をどうしていこうとしているのか見えないとの不安がある。こうしたフォーラムの場等を通じて、若い人にメッセージを伝えることが重要。
(トリウムサイクルについて)
(一般)
- 核不拡散の観点からトリウムも含めて検討すべき
(イワノフ)
- ウラン233は核兵器にも転用でき、核不拡散性はウランープルトニウムサイクルと変わらない。研究としてはいいが、プライオリティはFBRに置くべき
(岡﨑)
- トリウムを排除しているわけではなく、オープンに議論していくことが望ましい。
(ストラットフォード)
- トリウムサイクルは、核融合と同様、実現に時間を要する。また、核不拡散上、望ましくない。一つはドライバー燃料としてプルトニウムが必要なこと、もう一つは、有意量が8kgであるウラン233を生み出すことになること
《円卓討論1のサマリー》

課題1「持続可能な形でいかに原子力を推進し、そのための課題を解決するか」
原子力新規導入国への原子力推進について議論が進められ、原子力新規導入国支援におけるIAEAの役割が重要であること、また原子力分野での人材育成が各国共通の課題であることが認識された。
課題2「新規原子力導入国による3S確保をいかに支援するか」
3Sイニシアティブの途上国への展開及び日本の役割について議論が進められ、3Sイニシアティブ展開に向けた具体化方策検討の必要性、3Sを受容することが途上国側にとってもメリットがあるとの認識を持たせることが重要であるとの指摘及び3Sイニシアティブにおける日本の貢献への期待に関する指摘がなされた。
課題3「核燃料サイクルの多国間管理は核不拡散の観点から有効か」
フロントエンドだけでなく、バックエンドも含むコンセプトが有効
課題4「追加議定書の普遍化をいかに推進するか」
追加議定書の性格付け及びその普遍化についての議論が進められ、追加議定書は未申告活動検知のために不可欠なツール及び非核兵器国は追加議定書が原子力活動における透明性確保や保障措置の効率化に対して有意義との認識をもたせることの必要性が指摘された。
課題5「NPTの不公平感をいかに克服するか」
この問題に関しては、核兵器国と非核兵器国との間での認識の相違が明らかになった。核兵器国側から、NPTの不平等性が問題であるとの指摘は誤り、核兵器国としての取組推進を伝えることが重要等の意見がある一方、非核兵器国側からは核兵器国は核軍縮努力による不平等感を減じる必要があること、核兵器国のさらなる説明努力が必要との指摘がなされた。
課題6「NPT非締約国との原子力協力をいかに評価するか」
具体的な例としてインドとの協力について米側交渉担当者であったストラットフォード氏より、米国がインドとの原子力協力に至った理由について説明があり、フロアとの間で、核不拡散体制に与える影響の観点から議論がなされた。また、日本がインドとの原子力協力を進めるためには少なくともCTBTの批准が必要であるとの指摘がなされた。

1日目終了挨拶

日本国際問題研究所 上級客員研究員 遠藤 哲也
- 主催機関の一つである日本国際問題研究所を代表して挨拶
- 円卓討論という新しい形式を取り入れたことは成功につながったと考える。
- パネリストの皆様、会場の皆様に感謝
円卓討論2「保障措置、核セキュリティ、核拡散抵抗性」

- 出席者:
- 内藤 香(モデレータ):核物質管理センター 専務理事
- オディロン・アントニオ・マルクーゾ・ド・カント:ブラジル・アルゼンチン核物質計量管理機関(ABACC) 事務局長
- キャロライン・ジョラン:仏Areva社 核不拡散・国際制度担当部長
- ワン・キー・ユーン:韓国核不拡散核物質管理院(KINAC) 首席研究員
- バレンティン・イワノフ:ロシア科学アカデミー 教授
- ロナルド・チェリー:米国大使館 エネルギー担当官、米国エネルギー省 日本事務所代表
- アイク・テリオス:米国アルゴンヌ国立研究所
- ジョゼフ・ピラー:米国ロスアラモス国立研究所
- ロバート・バリ:米国ブルックヘブン国立研究所 上級研究主席、GIF(Generation IV International Forum) PR(核拡散抵抗性)&PP(核物質防護)ワーキンググループ 共同座長
- 村上 憲治:国際原子力機関(IAEA)保障措置局査察実施C部 前部長
- 木村 直人:文部科学省 科学技術・学術政策局 保障措置室長
- 中込 良廣:原子力安全基盤機構(JNES)理事、京都大学名誉教授
- 千崎 雅生:日本原子力研究開発機構 核不拡散科学技術センター長
- 久野 祐輔:東京大学大学院工学系研究科 教授(委嘱)、日本原子力研究開発機構 核不拡散科学技術センター 次長
(内藤)

- 本セッションでは、事務局が用意した、3つの課題、IAEA保障措置の効果・効率化の方策、核拡散抵抗性の役割、核セキュリティの強化について、各々、最初にその概要に関する10分程度のプレゼンを行った後に、事前に用意した質問に沿って議論を行う。
【課題1:IAEA保障措置を効果・効率化にするための方策】
(村上)
- 国際保障措置は50年の歴史があり、紆余曲折を経て強化されてきた。現在、強化された保障措置が適用されているが、その強化が、効率的に実施されてきたかという視点で評価する必要がある。IAEA新事務局長の天野大使が就任する際に、IAEAに求められている新たなタスクへの対応を優先する必要があると述べていた。保障措置の目標は、正確性、つまり核物質の転用がないことと、完全性、つまり未申告活動がないことを確実にするための措置である。その保障措置が直面している7つの課題をリストアップした。

- Global nuclear renaissance and increasing workload:新規原子力導入国の増加、MOX燃料の利用拡大等による査察業務増加が予想されている。
- Safeguarding innovative fuel cycle facilities and technological development:GEN-VI、INPROで議論されている将来の施設に適用した保障措置、リモート査察に関するもの。工程の自動化や接近困難な設備などに対応するため、最新技術を導入するなど、革新的な査察活動を行うことが必要とされてくる。
- Global proliferation risk and proliferation network:イラン、北朝鮮、核密輸の問題への対応。未申告活動をいかに早く探知し、抑止能力を発揮させるか。
- Maintaining adequate and sufficient legal authority:追加議定書の普遍化、NPT未加盟国の対応。保障措置協定を結んでいてもイランのように提供される情報不十分では全体像が出てこない。また、追加議定書(AP)プラスなどさらに強化を考える必要がある。
- Possible new verification roles and missions:核軍縮、FMCTに進展がある場合には、IAEAに対する新たな役割となる。
- Improve effectiveness and efficiency of verification capabilities and operations:査察の効果性、効率性を如何に向上させるか。インフォメーションドリブン保障措置といわれる新しい保障措置における情報分析を向上、国、地域の査察体系の有効活用、欧州原子力共同体(EURTOM)とIAEAのパートナーシップ、保障措置の品質管理への取り組み。
- Effective resource development and management:現在のIAEA予算ですべての活動を実施するのが難しい。限られた人材を如何に有効に使うか、新しい人材をどのように育成するか
(内藤)
効率的に議論するために以下の6つの質問を用意した。これらを念頭に置いてコメントいただければ幸いである。
- どのように、NPT保障措置、追加議定書及び統合保障措置の普遍化を進めていくか。
- 更に効果的、効率的な保障措置を行っていくにはどうしたらよいか。保障措置の進化のためのアイデアは? R&D? 国際協力? 地域保障措置? 保障措置文化? Safeguards by design(SBD)?
- 保障措置の限界は?それを乗り越えるための方策は?
- 次世代サイクルにおいて、保障措置に係る経済的インパクトを減じるための方法はあるか?
- 核兵器国は非核兵器国と同様に保障措置の負担を負うべきか。
- 保障措置に係る人的資源について。
(ユーン)

- Asia Pacific Safeguards Network (APSN)については、オーストラリアのイニシアティブであるが、韓国も協力している。以前より、ASIATOM等の構想はあったが、APSNは、アジア地域で実現した初めての保障措置に関する多国間イニシアティブである。元々は、Asia Pacific Safeguards Association (APSA)であったが、Associationは強すぎるとの意見があり、緩やかなNetworkに変更された経緯がある。APSNは10月1日に発足し、来年4月に第1回公式会議がインドネシアで開催される予定。オーストラリア、中国、カナダ、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム、アメリカが参加予定。IAEAはオブザーバー参加となる模様。
(チェリー)
- 米国のNext Generation Safeguards Initiative (NGSI)は、今後25年で予想される保障措置のニーズに対応するための包括的なイニシアティブである。当初はアメリカが発起したものの、現在では国際的な作業となってきている。政策、アウトリーチ、技術開発、トレーニング、人材育成等多くの側面を持っており、保障措置の課題、技術の継続的な改善に対応するものである。特に人材育成については喫緊の課題である。最初の会合は2008年9月にワシントンDCで実施し、2009年10月には、文科省、JAEAの協力を得て第2回会合を東海で実施した。
(ド・カント)
- 中南米は、非核兵器地帯条約を発効した最初の地域。その中で、アルゼンチン、ブラジルが原子力活動を実施していたので、両国は1991年に原子力平和利用協定を発効し、さらに共通の計量管理機関であるABACCを設置した。IAEA、ABACC、ブラジル、アルゼンチンの4者間で、4者間保障措置協定を締結し、平和利用の核物質の転用がないことを確認している。ABACCは、IAEAの活動と重複がないことに留意しつつ、独自に評価を実施している。ブラジル、アルゼンチン両国から事務局長、次長及び主要スタッフが選任されているほか、90人の査察官が両国に対して相互に査察を実施している。強力な地域計量管理機関が、IAEAの将来の役割の一部を担い、IAEAの予算増に対応することも可能であると考えている。研究開発については、EURATOMや米国との協力も実施しており、トレーニングも検討されている。
(ジョラン)

- EURATOMに関して説明すると、EURATOM条約に基づいて、1957年に設置された機関で、最初は6カ国であったが、現在は27カ国で構成されている。EURATOM条約はいくつかの章からなっており、リサーチ、国際協力、供給、保障措置などが記載されている。EURATOMの保障措置は、申告された核物質が転用されていないこと、2者間の協定に基づく活動を実施する。3つの取り決めがIAEAとの間であり、EURATOMの保障措置は核兵器国、非核兵器国に差別なしに適用されており、IAEAへの報告の提供を実施している。本部はルクセンブルクに置かれ、ECより資金が拠出されている。ECは独自の研究開発拠点を有し、研究開発活動を実施している。欧州保障措置研究開発協会(European Safeguards Research and Development Association :ESARDA)についても技術開発を担っており、米国の研究所とも活発な研究交流が行われている。
(木村)

- 日本の保障措置は、1977年に締結したIAEAとの包括的保障措置協定に基づいて適用されており、日本はこれまで、種々の協力を実施してきた。日本では、巨大で複雑多岐な施設に対して保障措置が適用されており、世界の査察業務量の30%を占めている。今後、六ヶ所再処理施設(RRP)の本格運転、もんじゅの運転再開、JMOX等の建設・運転が控えているので、保障措置の効果を減じることなく、さらなる効率化が必要である。そのために、現在持続可能な保障措置戦略計画(Strategic plan for sustainable safeguards in Japan)を策定している。この戦略は、日本における持続可能な保障措置システムと新興国との知見の共有を目指している。この戦略は、強化された国内保障措置体制の構築、概念・アプローチ、技術開発、人事育成より構成されている。2010年に向けて、IAEAは国レベルの統合保障措置を日本に適用する予定にしており、日本としても協力を行っている。そのために、日本として、如何にIAEAの検認活動をサポートするかという観点で、日本独自で核物質の転用がないということを証明する、いわゆるState's Findingsを導き出し、IAEAに提供することを考えている。このような事を通じて、世界の不拡散体制に協力できればと考えている。
(イワノフ)

- ロシアは、新たな国家プログラムにおいて、FBR開発については、窒化物燃料、乾式再処理技術を含む新世代の技術を使う予定でありIAEAとの協力が有効なものとなると考えている。将来の燃料サイクルに適用する保障措置の開発が重要。
(村上)
- Safeguards By Designは、設計段階から保障措置を適用し、効率化を図るものである。たとえば、燃料集合体の識別番号を製造からすべてのプロセスを通して使用していくことができれば、トレーサビリティの観点で有効。ワークショップやサポートプログラム等で検討が進められている。今後、放射線等により直接アクセスできないような工程も出てくることから、設計者が、十分保障措置を理解することが重要である。GEN-IV、INPROと協力して作業を実施しており、設計者にとって有益であると考えている。
(ピラー)
- 保障措置は、これまで様々な課題、政治的な問題に対応するために約40年間進化をつづけてきたが、これからも進化をつづけていく必要がある。将来の燃料サイクルについて、スループット(工程扱い量)の増加、高放射線、高温等扱いにくい物質、不均質物質、固体・液体混合物等に対してどのように対応するかといったチャレンジがある。今まで全く予想し得なかったものに対しても、研究開発の能力を構築していくことが重要である。そして、主要国、仏、ロシア、米国、日本における技術開発、広範な国際協力が重要である。ここ10年くらいは古い技術に頼っているため、保障措置の研究開発を復活させていく時期にきており、研究開発に対する取り組みを見直すべき。日本、仏、ロシア、アメリカの技術者の高い能力を利用すれば、予期されている又は予期しない課題に対する方策が容易に導き出せるであろう。
(千崎)

- 11月に東海においてIAEAとワークショップを共催し、新しい技術開発に関する議論を実施した。JAEAは、R&Dの実施と自ら保障措置を受ける立場から、既存の技術を効率化することを考えている。核燃料サイクル施設に対する統合保障措置適用は、日本が初めてである。昨年8月に、原子力機構の、再処理施設、MOX加工施設、その他の研究開発施設を有している東海のサイトが統合保障措置へ移行した。その際、査察側の業務は大幅に削減されたが、査察を受ける側の業務は削減されていない。新規原子力導入国の状況を踏まえれば、これからは、施設者の業務の削減も重要と考えており、原子力機構はそのための技術開発に取り組んでいる。
- 保障措置の普遍化に関して、ベトナムやタイなどの新規原子力導入国に対して行ってきた対話やセミナー等による協力を通じて、追加議定書(AP)未発効国に対して、AP発効に伴う作業、コスト、人的資源や統合保障措置のメリットを説明していく必要がある。これまでの日本の取り組みをベスト・プラクティクスとして整理し、そのような国に対して説明していくことが重要。特に相手のニーズをよく理解することが大事である。
(久野)

- 堅牢な保障措置については賛成であるが、保障措置には限界がある。保障措置の目的は、完全性、確実性の確認であるが、完全ではない。制度から脱退する国や、保障措置の抜け道を模索している国もある。制度としての限界と、今後、プルトニウムを大量に扱った場合には、誤差の問題等の技術的な限界があり、従来型の保障措置では対応困難となる。一つの考え方としては、次のセッションで扱う核不拡散抵抗性である。技術的に困難にして転用できないようにする方法である。現状の計量管理ベースの保障措置は基本であるが、リモート・モニタリングやソリューション・モニタリング等を用いて活動の透明性を高め不正使用がないことを確認することによって、核物質のみを追いかけるのではなく、未申告活動が行われていないことを確認することにより、さらなる保障措置の効率化が可能と考えており、保障措置の進化を考えるべき。
(ジョラン)
- 質問に記載されている事項については、すべての取り組みが保障措置を強化するという意味では重要であると思う。国際、地域の協力についてもそうである。独立の結論を追加の検認作業なしで導き出すことも可能であると考える。いつでもどこでも査察を行うことが出来るような仕組みを担保していくことが重要。Standing Advisory Group of Safeguards Implementation (SAGSI)で検討する課題は、技術開発ばかりでなく、政治的環境についても考慮されている。多国間のアプローチにより、人的資源の有効活用も可能と考える。産業界として、リモート・モニタリングや技術に依存してしまうと、小さな問題が生じたときに査察官がその場で対応することが困難になるなど、早期解決が困難であるため、そのバックアップを対で考えていくことが重要である。
- 経済的な影響の観点からいえば、20/20計画(賢人会議が2008年にまとめた2020年に向けたIAEAの課題、あり方などをまとめた報告書)では、施設数の増加と比例して査察業務量が増えるとしているが、その多くは、軽水炉(LWR)であり、新しい技術により、保障措置が簡単になることも想定され、あまり査察業務の増加につながらないのではないかと考えている。廃炉についてはマイナスの面だけでなく、ホールドアップや、過去の措置が正しかったかどうか等を評価できるよい機会として考えることもできる。
(チェリー)

- 人材育成に関して、さまざまなレベルでさまざまなトレーニングを行うことが重要である。NGSIに関連して、アメリカでは様々なレベルでワークショップ、トレーニング、国立研究所におけるサマースクールを実施しており、大学に出向いて行うこともある。IAEAや加盟国対象のトレーニングコースを拡大している。
- 保障措置を進化させ、資源を有効に活用することは必要であるが、同時に今やれること、今やらなければならないことを考えていく必要がある。IAEAの既存の権限である特別査察などはその例である。情報へのアクセスそのものがより重要なツールとなっている。
(久野)
- 核兵器国への査察については、必要かどうかの考え方にはギャップがあり、IAEAの負担増にならない方法、かつ公平性を考慮して、平和利用の施設については、査察を受け入れなくても、受け入れる準備をしておくべきである。
(村上)
- IAEA内では、基本的にはIAEA保障措置は、差別はできないが、たとえば、イランにおいては、通常の保障措置以上の活動が適用されている。その国の保障措置制度、透明性、協力体制、技術的及び提供情報の信頼性等を考慮して、“区別“を行っていくことが必要である。
- 核兵器国に対しては、数よりも質においてのアプローチが重要。核兵器国への査察対象施設数を増やし、ランダムで行うことも一つのアイデアである。核保有国が先導して技術開発を行うことも重要である。
【一般聴衆を交えた質疑応答・コメント】
(IAEA保障措置を効果・効率化にするための方策)
(シャインマン:円卓討論3への参加者)
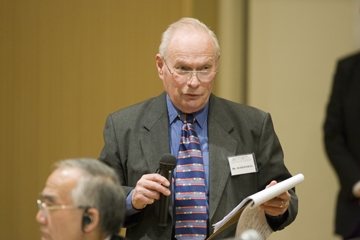
- 米国におけるトレーニングに関して、講師を行ったが、学生のレベルが上がっている。キャリアパスと考えているようである。
- Non complianceに対する措置が必要である。追加議定書は、十分であるかどうかについて、イランで行われていることを参考に、より確固とした制度を目指しても良いのではないか。イラクにおける未申告活動の発覚以降、査察の文化が変わったと考えている。疑念をもって査察を行うことが重要である。
(一般)
- 新しい保障措置技術開発に関して、まだ十分ではない。自分は国の関係者として過去、保障措置に関与したことがあるが、プルトニウム燃料製造施設(PFPF)については工程の自動化に対して、IAEA側の保障措置上の要求が高く、自動検認等の合理化のためのシステム開発をした経験がある。施設が自動化されると、コンピューター化された設備に対してのオーセンティケーションが必要となり、あえてDOEの国立研究所に依頼した。国際協力は透明性を上げるためには重要である。六ヶ所再処理施設(RRP)については、査察のやり方をLASCAR*(Large scale reprocessing plant safeguards)で議論し、その中でNRTA**(Near real time material accountancy)ができあがった。信頼性の有る国際協力が必要。IAEAは新しい技術を用いた査察に対して査察手法を変える必要がある。
*LASCAR: 大型再処理施設の保障措置を検討した会議。仏、独、日、英、米の各国とEURATOM及びIAEAが参加した。
**NRTA: バルク取扱施設に対する物質計量管理の一種で、核物質の移動の検認の他に、実在庫確認が工程内の計測器(通常、施設者の装置)を使用して、工程の操業を阻害せずに頻繁な間隔で、例えば、毎週行われる。
(ピラー)
- 未申告活動の探知機技術に加えて、既存の権限の有効活用が必要である、その一つが、特別査察を活用することである。また、新たな権限についても検討が必要である。
【課題2:核拡散抵抗性の役割】
(久野)

- 施設の増加、プルトニウム利用の拡大に対応し、核拡散抵抗性を高めることが重要。技術的に拡散が起こりにくくすること(技術的バリア:内在的バリア)に加えて保障措置など、制度による規制(外在的バリア)することが核拡散抵抗性。外在的バリアについては、保障措置が主なものである。具体的な方法には、設計情報検認、計量管理、封じ込め・監視、検出器による高い検知確率、などがある。内在的バリアについては、アクセスしにくい、扱いにくい、転用が難しい、たとえば、プルトニウムの質を下げたり、放射線が強くてアクセスできない、熱の放出が高くなる、ような方法を採る。このような方法等により、転用、ミスユースの魅力をなくすることが核拡散抵抗性である。
- 歴史的に数多く議論されてきたが、1977年から行われた核燃料サイクル評価(INFCE)*において抵抗性に関する議論が行われた。ここでは、特に拡散という観点で評価を行った。当時は東海再処理工場の操業開始時期であったため、「ワンススルー(再処理しない)かプルトニウム・リサイクルか」が一つの話題であったが、それは当時、米国がワンススルー方式を推していたためにこの評価が行われたという側面もある。先程ご説明した技術的な方法については当時から議論されてきた。そこでは、非常に有効であるが限界もあり、やはり保障措置が主であるとの結論であった。その後、INPRO, GEN−IV、仏、米、日本等で、核拡散抵抗性の議論が行われている。2002年のComo会合**において、核拡散抵抗性の定義、基本に関する議論が行われた。核拡散抵抗性が高いと保障措置の効率化が可能ではないかと行った論文もある。
*INFCE: 国際核燃料サイクル評価。核拡散防止の観点から核燃料サイクルを国際的に評価し直そうというカーター米大統領の呼びかけにより、1977年から約2年間実施された。
**Como会合: IAEAが、2002年10月にイタリア・コモで開催した国際技術会合。抵抗性に係わる技術・政策の専門家の参加のもと、拡散抵抗性の定義を含む基本的理解について議論がなされた。ここでの議論の結果は、現在国際的にコンセンサスの得られたものとして扱われている。
(内藤)
効率的に議論を行うため、以下の五つの質問を用意した。
- どのような技術が核不拡散抵抗性を高めていくことができるのか
- 核不拡散抵抗性と保障措置の関係について。トレードオフの関係or相乗効果?
- 核拡散抵抗性の高いシステムの設計にはクライテリアが必要か。
- どこまで抵抗性を高めれば十分か。
- 拡散抵抗性の高いシステムは経済的な競争力があるのか/可能なのか。
(ユーン)
- 核拡散抵抗性を高める技術については、いろいろな技術や施設があるわけであるが、抵抗性のコンセプトについてはケースバイケースで見ていかなければならない。政策とも関連してくるが、低グレードのプルトニウムを作るとかプルトニウム含有量を低める等々の方法が考えられるものの、核拡散抵抗性については、まず、設計時に盛り込んでいく必要がある。
(イワノフ)
- 核拡散抵抗性を高めるためにはリモート技術、自動化が有用。将来的には全く人間が介在しないシステムも考えられる。ロシアにおいては1982年から抵抗性の高い技術開発に取り組んできた。こういった技術は軽水炉には適さないかもしれないが、乾式再処理プロセスを用いて燃料製造を行うと、燃料中に核分裂性物質やマイナー・アクチニド*を取り込むことができ、また、このプロセスを採用することにより輸送の距離を短くすることが出来る。
*マイナー・アクチニド(MA): 核燃料の燃焼に伴い生成されるアクチニドのうち、比較的精製量の少ない元素。主にネプツニウム(Np)、アメリシウム(Am)、キュリウム(Cm)。
(バリ)
- 抵抗性に関するパラメータの数値的、定量化について重要な事は、秩序立った形で、体系的に研究、評価を行っていくことである。さらに、そこから得られたものをシステムそのものに適用し、また、拡散リスクの低減につなげていくことが必要である。
(千崎)
- JAEAは、高速炉技術開発としてFaCTプロジェクトを進めているが、核拡散抵抗性を主要課題の一つとしてとらえている。内在的バリアとしてマイナーアクチニド(MA)の混入による抵抗性の向上を検討しているが、経済性とのバランスを考慮する必要がある。どこまでやればよいのかという観点から、抵抗性の基準についても重要である。制度的バリアに関連して、抵抗性の向上によって保障措置が低下するものもあり、研究開発が必要である。
(テリオス)

- 核拡散抵抗性と保障措置はトレードオフの関係があるかについては、トレードオフの関係にある場合もあれば、相乗効果をもたらす場合もある。
(ピラー)
- 抵抗性が上がる場合でも保障措置の困難さにつながるものもあり、これでは信頼性は上がらない。safeguardabilityつまり保障措置の適用しやすさ、効率性は重要である。重要なのは、アクセスを困難にするなどの技術的な困難性を高める手法が、保障措置システムの検知可能性を低減させてはならない。そうでなければ抵抗性は上がらないということになる。そういった意味では、トレードオフが存在しているといえる。
(ユーン)
- 問題を特定することがまず必要。制度的な手段とSafeguards By Designを組み合わせることにより相乗効果が期待できる。
(チェリー)
- 制度的な手段は重要であり、核拡散抵抗性の高い核物質、施設の設計等内在的な要素に頼りすぎないことが重要。核拡散抵抗性を高めていくためには保障措置コンセプト、アプローチ等についても同時に進化する必要があり、トレードオフばかりに目を向けるのではなく、相乗効果を期待すべきである。
(久野)
- 話をするのは簡単であるが、実際どうやってやるのかが重要。保障措置は、保守的な世界が既にあり、最近Safeguards by designの議論の中で抵抗性を扱うことが出来るようになってきたところである。核拡散抵抗性を併せて議論できるようにするためにはガイダンスが必要であると考える。
(村上)
- 核拡散抵抗性は、保障措置向上のための一つのステップであり、核拡散抵抗性を高めても査察がなくなるわけではない。safeguardabilityは重要である。トレードオフの関係は存在する。現状よりもさらに難しくすれば、保障措置を大きく削減することが出来る。それが一つのメリットである。
(バリ)
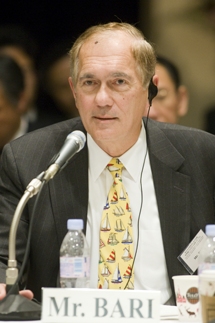
- 保障措置は、あくまでも核拡散抵抗性の一部と考えるべきである。内在的なものと外在的なものを対立させるのではなく、保障措置は核拡散抵抗性に関連するものとしてとらえるべき。
- 拡散抵抗を実現するにあたって、我々の研究の中では、拡散抵抗性やリスクについては、国家レベルの脅威である転用、脱退等に対して、国が直接対応するためには、国にはどのような対応能力があるのか等の分析が重要であり、最終的にこれらに対する結果が導き出される。
- クライテリアについては、高いレベルのクライテリアと考えると、多くの人を巻き込む必要があり、技術者だけでクライテリアを決めるべきではない。
(千崎)
- 技術者だけでクライテリアを決めるべきではない。政策者やユーザー等も巻き込むべき。経済性も重要で、ただ厳しくすればよいというものでもない。基準の置き方、どのように設計に反映していくかを考える必要がある。バランスを考慮したクライテリアの議論が必要。
(ジョラン)
- 核拡散抵抗性は、技術や施設個別ではなく、システムとして考慮すべきである。リスク評価が重要であり、設計基礎脅威(DBT)*や拡散に対して評価する必要がある。機微な施設を持つリスク、ある時点である国にそのような施設があるリスクを考えなくてはならない。最良の方法でリスク緩和しなければならないが、何か起こりつつある場合、どのように探知するかも重要な要素。商用化された施設については、経済性の側面も考慮する必要がある。
*設計基礎脅威(DBT: Design Basis Threat): 事業者が現実の脅威に的確かつ迅速に対応し、効果的な防護措置を行うためにはどのようにしたらよいかという考えに基づき、事業者が核物質防護システムの設計にあたり考慮すべき脅威を国が策定し、事業者は国から提示された当該脅威情報に基づき具体的な核物質防護システムを構築する、という考え方
(久野)
- 保障措置が十分に適用され、透明性の高い国では、確率的にブレークアウト等のリスクが低いので、経済的に抵抗性を導入することが出来るのであればよいが、そうでない場合に、それらの国に対して抵抗性を導入すべきレベルを考えていくことが重要である。保障措置で十分という議論もある。
(ピラー)

- 経済的な核拡散抵抗性というのはなかなかないのかもしれない。我々は、経済的な問題も考えつつ、必要な措置により拡散のリスクを抑えていかなければならないが、それが保障措置をいかに有効に促進していくかであると考える。Safeguards by designはIAEAをはじめ、様々なところで議論されているが、これにより、設計を最適化し、保障措置の費用を低減できるのではないかと考える。保障措置を設計段階から取り込むことにより、転用パスを減らすことができれば、保障措置の効率だけでなく、システム全体の効率も上がるため、経済性の側面からも有効である。
【一般聴衆を交えた質疑応答・コメント】
(核拡散抵抗性の役割)
(一般)
- 以前、イランの核開発問題の研究をしていた。イランが兵器級の核物質を持たない限り、核兵器を作れないので、兵器級の核物質を作れないようにする技術の可能性について伺いたい。
(一般)
- 核拡散抵抗は、国家主体ばかりでなくテロリストによる転用も考慮しているか。
(一般)
- 核拡散抵抗性の高いシステムは、現実的にはコスト高である、核拡散抵抗性をどのように途上国へ展開していくのか。
(久野)
- たとえば、再処理技術に関しては、核兵器に適した純度の高いものを作れない技術も可能であるが、すでにピューレックス法が確立しているなかで、経済性を考慮すると、経済的で、確立した技術が採用されることになるのではないか。核拡散抵抗性(PR)の高い方法を選択させるには、経済的なインセンティブが必要。
【課題3:核セキュリティの強化】
(中込)

- 技術先進国である日本においても、残念ながら核セキュリティに対する関心は低いので、この機会に感謝する。世界のセキュリティに関する動向として、7つご説明させていただきたい。一つ目の、核セキュリティに関連する文書については、ガイダンスの準備、出版が進んでいる。IAEAは、核セキュリティシリーズとして文書を整備しており、基本文書は2010年の8月に出版が予定されている。その下に位置する勧告文書については、3部作となる予定であり、2011年の出版予定である。さらにその下位文書である、ガイドブック等の指針類については、予定されている半分程度はすでに出版されたり、印刷の段階である。二つ目は輸送のセキュリティ対策についてである。輸送というのは限られた資材、人数で対応し、更に土地勘がないために脆弱であるといわれており、この輸送時のセキュリティ対策をどうするかが問題となっている。三つ目はセキュリティ・カルチャーである。セーフティーカルチャーはチェルノブイリ以降、よく言われているが、セキュリティ・カルチャーについても今後、世界的に考えていかなくてはならない。四つ目は、我が国はあまり気にしていなかったが、国境における持ち出し(核密輸)の検知及びレスポンスが国際的な問題となっている。五つ目は、Security By Designである。六つ目は3S(safety, security, safeguards)である。最後はWorld Institute for Nuclear Security (WINS) *をどう扱っていくかである。2010年4月のワシントンDCで開催されるセキュリティ・サミットでもこれらが話題になるのではないかと考えられる。
*World Institute for Nuclear Security (WINS): 2008年に設立された、核物質の管理を推進する新たな国際組織。本部はウイーン。米NGO「核脅威イニシアティブ(NTI)」の発案。核物質管理の専門家や、核関連産業、政府や国際機関が参加する。情報の収集と共有を行う会議を開催し、より安全な管理方法を実践することで、危険物質がテロリストの手にわたるのを防止する。
- 特に3Sについては、IAEAでも議論されており、我が国でも2008年7月の洞爺湖サミットにおいても当時の福田首相が3Sに触れたが、セキュリティについては、日本から発信できるものがあるのかについても考える必要がある。日本では、日本人的発想として安全を考える中に無意識のうちにセキュリティが含まれてしまっており、これが、セキュリティを個別に考える一つの障害になっているかもしれない。インサイダーの問題もある。
(内藤)
- 効率的に議論を進めるため、3つの質問を用意させていただいた。一つ目は「各国における核セキュリティを強化するための緊急課題及びその対策」である。この問題には、放射性物質のセキュリティ対策、核物質輸送のセキュリティ対策、放射性物資の不法移転に対する対策、インサイダーの脅威に対する対策、Security by designのコンセプトに対する促進、核セキュリティ文化の醸成、核物質防護条約(CPPNM)の早期批准などが関係すると思われる。二つ目、三つめは「WINSの役割として期待されるものは何か」、「来年の4月に開催されるセキュリティ・サミットにおいて、何が期待されるのか」である。
(チェリー)
- 最も重要なチャレンジは、テロリストによる核物質の盗取であり、それらに対しては核物質防護条約(CPPNM)の批准、INFCIRC/225の順守及び改訂作業の迅速化が重要、Security by designについては、核拡散抵抗性とも関連しているが、セキュリティを高めるためには設計に反映することが重要である。CPPNMに関しては、米国においては議会に法案が提出されたが、議会が閉会してしまったため、新しいパッケージを提出する予定である。
(ユーン)
- 韓国では特に大きなチャレンジはないと考えているが、能力を常に高めていく努力は常に重ねている。現在、DBTを取り組んでいるところであり、INFCIRC/225の改定作業にも加わっている。来年のセキュリティ・サミットがセキュリティ・カルチャー醸成のためのきっかけにしたいと思っている。
(ジョラン)
- 放射性同位元素のセキュリティに関しては大きな懸念があるが、核セキュリティ文化を他の物質に対しても醸成できれば効果があるかもしれない。Security By Designを放射性同位元素に適用するのは困難であろう。輸送については、仏国内で過去に問題があったことはないが、国際輸送のセキュリティについては、検討が必要と考える。CPPNMについては、新興国に対して重要だとは思うが、それ以上にガイドラインや対策の実施の部分だと思う。WINSはカルチャーの醸成を効率的に行えると考えている。また、問題があった場合などに有用な情報の提供等の役割があり、重要である。
(イワノフ)
- ロシアでは長距離輸送が多く、セキュリティよりも、環境汚染、世論に対する対応が必要である。信用を高めるような追加措置として、輸送物の位置や核物質の量等を把握する等、信頼性のある、国際輸送を管理するシステムが必要である。
(ド・カント)

- ABACCは、セキュリティは所管していないが、3Sのシナジーとして関心がある。ブラジルにおいてはNational energy commissionが所掌しており、国際的な慣行に対しては遵守している。
(千崎)
- 日本の場合には、数年前にINFCIRC/225(rev.4)に基づいた法令改正が行われ、強化が図られている、施設については、毎年、規制当局による検査、評価が行われ、必要な場合は改善が図られている。治安当局を含めた訓練も実施している。IAEAではセキュリティ強化のための文書の作成が進んでいるとの説明があったが、輸送の問題も含めて、可及的速やかに対応すべきと考えている。原子力の開発が進めば進むほど輸送は重要になってくる。その中で如何に核テロから守っていくかを考える必要がある。JAEAでは、輸送のセキュリティの研究をサンディア国立研究所と実施しており、また、コストパフォーマンスも重要であると考えている。日米共同行動計画の一つの検討テーマの中にSecurity By Designのコンセプト検討があり、これについて協力を実施している。
(中込)
- セキュリティについては、各国の考え方があり、規制も異なる。日本では、銃の保有は認められておらず、こういうことが、たとえばCPPNM等で決められてしまうと法的に取り入れることが困難になる国もあることから、各国の事情を考慮した議論が必要である。
- 放射性同位元素のセキュリティに対しては、放射性同位元素は利用の観点から使用されてきた。核物質については、核兵器の原料となるために、保障措置を含めた厳格な管理が行われてきたが、急に放射性同位元素のセキュリティの話をした場合、利用者にとっては寝耳に水ではないか。Security By Designについては、方針としては良いのだろうが、過剰設計になる可能性があり、コストの面、利用しにくくなる可能性がある点を考慮した議論が必要である。
- 核拡散抵抗性は盗取との関係はよいが、妨害破壊行為との関係についてはどうか。核拡散抵抗性の観点で、核物質に放射性の高い物質を混ぜた場合、妨害破壊行為に対してはそれが大きな魅力となってしまう。
(ピラー)
- 脅威をどう評価するのかが重要。脅威を過小評価する又は過大評価した場合、原子力産業を窮地に追い込むかもしれないので、脅威を評価する上で、我々にどういった限界があるのかを考えなければならない。核拡散抵抗性については、内在的な障害では国家の意図を阻むことは難しいかもしれないが、非国家主体に対しては核セキュリティの観点からも、重要である。
(チェリー)
- 来年のサミットが、良い転換点になればとの発言があったが、高いレベルでの共通理解が得られ、核テロや核密輸が阻止される方向に進むのではないか。理想的な有効措置は、CPPNMや安保理決議1540など、既に導入されている措置を強化することや各国に参加を呼び掛けていくことである。来年のセキュリティ・サミットではこのようなことが期待される。
【一般聴衆を交えた質疑応答・コメント】
(核セキュリティの強化)
(一般)
- セキュリティは脅威に対してどう対応していくかであるという話があったが、脅威が高い国、低い国、情報開示が進んでいる国、進んでいない国もあり、一律に考えるのは難しい。国際機関は差別をすることはできないが、その差をどのように埋めているのか、その点が考慮されているか疑問である。
(ジョラン)
- 責任をいかに定義し、認識を高め、適切な手段を適切に与えていくことが重要である。セキュリティ・サミットではそういったことが期待される。
(中込)
- IAEAにおいては、各国の規制、カルチャー、宗教を考慮した議論が行われていると理解している。
(村上)
- 前段でも述べたが、“区別“がこれに該当すると考えている。国際機関は差別はできないが、各国の実情や、透明性措置等を考慮し、共通のクライテリアを以て、“区別“することができるのではないか。
(チェリー)
- “区別“は可能と考える。WINSはさまざまな意見、ベスト・プラクティクスを共有することができるので有益である。国内の基準についてもここから導き出すこともできる。施設者や各国が対話型のプロセスに参加し、出来る限りの情報共有をし、セキュリティリスク、対応のための戦略を打ち立て対応していくこと、これがサミットの裏にもある考え方であると思うし、WINSのような機関の目的でもあると考える。
《円卓討論2のサマリー》

課題1「IAEA保障措置を効果・効率化にするための方策」
国内計量管理制度(SSAC)、地域計量管理制度(RSAC)*の有効活用、追加議定書(AP)の普遍化、非核兵器国・核兵器国の公平性、国際協力を含む技術開発、人事育成、“区別“が必要、権限の活用、追加議定書プラスについての発言があった。
*地域計量管理制度(RSAC): 自国のみの制度であるSSACに対して、地域で行う計量管理制度。EURATOMやABACCがその例。
課題2「核拡散抵抗性の役割」
核拡散抵抗性分野のR&Dが重要であり、これらを通じて先進的な保障措置にしていくことが必要である。クライテリアの必要性に関する意見があったが、技術者のみで決められるものではないとの意見があった。核拡散抵抗性はシステムとして評価すべきであり、経済性も考慮する必要がある。
課題3「核セキュリティの強化」
既存の法的な枠組みは重要であり各国がこれらを発効し、国内規制にIAEAの文書を取り入れていくことが重要である、核セキュリティ・サミットは、核セキュリティ文化を促進する上で重要。国際輸送のセキュリティ、“区別“も重要であるとの指摘があった。

円卓討論3「核燃料サイクルの多国間管理」
[投影資料]

- 出席者:
- ジョーシャン・チョイ(モデレータ):東京大学G-COE 特任教授
- ユーリー・ユディン:国連核軍縮研究所(UNIDIR) 上級研究員、プロジェクトマネージャー
- オディロン・アントニオ・マルクーゾ・ド・カント:ブラジル・アルゼンチン核物質計量管理機関(ABACC) 事務局長
- ゾンマオ・グ:中国原子能科学研究院(CIAE) 教授、科学技術委員会副委員長
- キャロライン・ジョラン:仏Areva社 核不拡散・国際制度担当部長
- カンソク・リー:韓国原子力研究所(KAERI)国際研究部長
- バレンティン・イワノフ:ロシア科学アカデミー 教授
- ピーター・カーター:英国エネルギー気候変動省 核不拡散担当課長
- ジョゼフ・ピラー:米国ロスアラモス国立研究所
- ミカ・ローウェンタル:米国科学アカデミー 核セキュリティ・安全プログラム部長
- ローレンス・シャインマン:米国モントレー国際問題研究所、不拡散研究センター 教授
- 伊藤 隆彦:原子力委員会 委員、中部電力 顧問
- 鈴木 達治郎:電力中央研究所 社会経済研究所 研究参事、東京大学公共政策大学院 客員教授
- 久野 祐輔:東京大学大学院工学系研究科 教授(委嘱)、日本原子力研究開発機構 核不拡散科学技術センター 次長
- 直井 洋介:日本原子力研究開発機構 核不拡散科学技術センター技術主席

核燃料(低濃縮ウラン(LEU))の供給保証と核燃料サイクルの多国間管理に関し、以下の論点を中心に議論を行った。
- 政治的理由による燃料供給途絶のケースに、燃料供給保証は有効か
- 国家が濃縮、再処理能力を開発する権利を放棄するのに、燃料供給保証は効果的なインセンティブとなり得るか。
- 国家が濃縮、再処理能力を開発する権利を放棄するのに、核燃料サイクルの多国間管理構想は効果的なインセンティブとなり得るか。
- 多国間管理において公平性をいかに達成するか。
- 多国間管理は核不拡散上の課題の解決に貢献できるか、どんな役割を果たすか
- 多国間管理は保障措置に係る費用を低減できるか。
- どのようにして多国間管理を実現させるか。
- 国際的な交渉による解決が求められるべきか、それとも一部の有志国が先導することが良いか。
- 多国間管理は、地域的な枠組みにより進められるべきか。
- 多国間管理の課題及びメリットは何か。
(歴史的経緯と現在の議論の状況)
(チョイ)
議論への導入として、1940年代後半から現在までの核燃料供給保証/核燃料サイクル施設の多国間管理の試みを説明。また2003年以降に提案された核燃料供給保証に関連する12の提案に言及
- 本円卓討論では燃料供給保証と多国間管理の2つのパートに分けて議論を行うが、バックエンドに、より焦点をあてた議論がなされるべき
- 現在、提案されている中で、バックエンドを取扱っている提案はロシアによる使用済燃料の回収の提案のみ
- 核燃料サイクルの多国間管理の問題は過去数十年にわたり国際的な議論が行われてきたが、実現していないのは推進力となり得る要素がなかったことによる。
- 今後、新たに原子力発電を導入する国が増えていく中で、使用済燃料の蓄積に伴う核拡散リスクをどう取扱うかということが問題になるが(特に、原子炉が運転開始してから最初に取り出される使用済燃料は燃焼度が低く、核兵器の転用が容易)、このことは、核燃料サイクルの多国間管理の推進力となり得る。
- また、高濃縮ウランの製造が多くの時間(数年)を要するのに対し、プルトニウムは再処理により短期間で製造が可能であり、国際社会の対応時間が限られていることからも、バックエンドに対し、より焦点があてられるべきである。
【課題1:燃料供給保証】
(直井)

- 2006年、日本は市場の透明性と供給途絶の予測可能性の向上、供給不安が起きにくい環境整備を目的とし、供給国が天然ウラン、転換、濃縮、燃料製造役務の保有量/供給能力をIAEAに事前登録することを内容とする「IAEA 核燃料供給登録システム」を提案。
- それ以降の進捗はないが、2009年1月に核燃料サイクルのフロントエンドに関するセミナーをウィーンで開催。
(カーター)
- 2007年、英国はLEU/ウラン濃縮役務の供給を保証する「濃縮ボンド」(債権)を提案、後にこれを「Nuclear Fuel Assurance (NFA)」と改名し発展させている。当該提案は、濃縮事業者(例:URENCO)とその政府(供給国政府、例:英国政府)によるLEU/ウラン濃縮役務供給のバックアップ・メカニズム。供給国政府が受領国政府との協定で、供給国が政治的理由により供給を途絶させないことを保証するとともに、万が一、他の国の濃縮事業者/政府が供給を途絶させた場合には、途絶を想定してあらかじめ締結する受領国との協定に基づき代替供給を保証するというもの。
- 2009年9月のIAEA理事会でNFAにつき非公式に提案したところ各国から好感を得ており、一連の保証に係る協定案を検討中。
(イワノフ)
- 国際ウラン濃縮センター(IUEC)は2年前に設立されたが、濃縮の契約は1件も締結されていない。顧客が見つかっていないのが問題。元々はイランを対象にしたものであったが、経済的な観点からは、トムスクで濃縮した方が、メリットがある。また、トルコやエジプトなどといった国をターゲットにすることが考えられるが、これらの国が原子力発電を導入するのは5-6年先
- IUECの機能として、LEUの供給保証だけでは不十分で、燃料ペレット、燃料集合体の製造や、使用済燃料管理の機能も持たせることが必要
- 低濃縮ウランの備蓄やIUECは、こうした国際的なセンターを運営する経験を蓄積するという点での意味はあるかもしれない。
(シャインマン)

- 昨今の原子力利用の拡大、特に多くの国による核燃料サイクル活動に関する関心の高まりが核拡散に繋がることを懸念
- 2004年、ブッシュ大統領(当時)は、濃縮、再処理技術を有する原子力供給国は濃縮、再処理技術や施設を、既にフルスケールの運転中の濃縮、再処理施設を保有している国以外には移転しないことを提案したが、この提案は現状の技術保有国・非保有国の区分を固定化するものであるとの懸念を引き起こした。そのため当該提案を、受領国にとって、より受け入れ易いアプローチ(注:受領国に濃縮、再処理の放棄を要求しない)に変えようとしている。
- 重要なことは、濃縮能力の拡散を予防しかつ阻むことで、新規原子力発電導入国に魅力的なインセンティブを提供し、しかしその代わりに燃料サイクル技術/施設を開発することがないようにすることである。
(ユディン)

- ロシアのLEU備蓄は、万が一の供給途絶の際に利用されるラスト・リゾート(最後の手段)であり、顧客の不在は市場が健全に機能している証拠で、それはそれで良いことである。IUECに関し、もし顧客がないとすれば、ビジネスモデルとしての検討が足りないということではないか。
- 2009年6月のIAEA理事会では、ロシアIUECでのLEU備蓄やIAEA核燃料バンク等を進展させていくとの提案がなされたが、NAM諸国等の賛成が得られず、議論すること自体が拒否された。しかしその後の11月理事会では、ロシアのイニシアティブにより同国のIUECでのLEU備蓄創設に関する提案が採択され、その実現に向けて始動することになったのはモデレータが説明したとおり。
- こうした提案に関して、法的あるいは技術的な問題があるわけではなく、進捗が遅れているのは政治的な問題が原因
- 受領国(主に途上国)は供給国(主に先進国)に対し疑念や不信感を抱き、両者の間で供給保証の必要性、仕組み等に関し共通の理解や合意が得られていない。共通理解が得られない限り、核燃料供給保証メカニズム構築の進捗は難しいと思う。
(シャインマン)
- 本件が政治問題化しているという指摘は正しい。途上国が懸念するNPT第4条に基づく原子力平和利用の権利は加盟国の奪い得ない権利。途上国は、少なくともこの権利を維持することを求めている。
- この権利には、必ずしも核燃料サイクルのすべてが対象となるわけではないという考え方、ある部分を排除しているわけではなく、全てが対象になるという考え方の、2つの異なる見解があるが、条文に明記されていない以上、後者の考え方をとるべきと考える。
- 核燃料サイクルの追求の権利を認めた上で、問題となるのは、各国がそれぞれの国内施設を建設するか、経済上のメリットを勘案した多国間管理の施設(ただし、技術はシェアされない。)を建設するかという問題である。
(直井)
- 供給保証のターミノロジーの共通理解を踏まえた議論が必要。ロシアIUECのLEU備蓄は供給保証用、つまり核不拡散以外の政治的理由で供給が途絶された場合に利用されるラストリゾートであり、この備蓄は市場メカニズムから外れたところにあるもの。一方で米国の国際原子力パートナーシップ(GNEP)やIUECは、市場メカニズムの中で供給の多様化などによりLEUの安定供給を確保しようというもの
(リー)

- 核燃料供給保証が成功するか否かの鍵となるのは、核燃料サイクル技術を保有しない国に魅力的なもので、メカニズムに是非とも参加したいとのインセンティブを与えられるか否か。例えば、常に経済的に魅力的な価格でLEUを供給すること、またLEU供給から放射性廃棄物管理まで燃料サイクルのすべての側面をカバーするものであることなど
(ピラー)
- 現在の供給保証議論は政治的なものとなり、受領国(途上国)の不信感は70〜80年代のそれと類似。
- 既存の核燃料供給保証に関する提案ではLEU供給しか保証されないが、使用済燃料の引取りや管理の保証も含めれば政治的要素や不信・疑念を取り除ける可能性はある。既存提案は詳細性や魅力度において不十分であり、政治的な対立を克服することは難しい。
(カーター)

- 不信感は避けられない。供給保証が原子力平和利用にとってどんな意味があるのか(コストの低減など)を訴えること、政治的、非商業的理由による途絶がいかなるものであるかを明確にすること、既存の市場を混乱させるようなものではないこと、それぞれの提案は相互に補完する関係にあるという認識を共有すること、押しつけるのではなく、必要性を訴えかけるアプローチなどが重要
(久野)
- 燃料供給を「保証」するシステムが今、必要とは思えない。他方、供給を強化するものとして、ブラックボックス方式で自国に濃縮施設を建設することは、たとえ技術移転がなされなくても、魅力的かもしれない。
(ジョラン)
- 産業界の人間として私見を述べる。2006年、産業界を中心とした世界原子力協会(WNA)は核燃料供給保証に関し、既存の市場による供給を補完する3つの層の保証からなる提案を行っている。
- ここで原点に立ち返ってみたい。原子力導入を考えている国の中で、濃縮施設の建設を提案している国は皆無。ウラン濃縮技術の開発や施設建設には巨額な費用を要する。現実的に考えて少数の原子炉しかない新規原子力発電導入国が、敢えてこれを行おうとするとは思えない。
- かつて、1970年代には、濃縮役務の供給者が米国とソ連だけであり、米国が他の国による燃料の確保を保証することを拒否したため、URENCOやEurodifが設立された。これに較べ、現在、4-6の濃縮事業者による、市場原理の下での価格競争が存在し、WTOが、適正な競争が行われているか否かを監視している。
- 市場メカニズムと政治的な措置の橋渡しをするものとして、当該国の核不拡散コミットメントの遵守状況のレビューを前提とした、長期(現状の2-3年ではなく、10年)にわたる輸出許可が有効
(チョイ)
- インドが1974年に実施した核爆発は、政治的な理由による燃料供給途絶が問題になったケースと言えるが、こうした政治的な要因があった場合でも、米国は、インドに対し燃料供給を継続し、更には、フランス、中国によるインドへの燃料供給を斡旋した。従って、燃料供給保証の必要性はなかったと言える。
- (従って、政治的な要因による途絶により燃料供給保証が必要となるようなケースは稀にしか起こらないと言えるが)、核拡散の抜け穴があるのであれば、それがたとえ小さなものであってもふさぐ必要があり、燃料供給保証のメカニズムが、濃縮、再処理のインセンティブを排除する上で、どんな役割を果たすのかが検討されなければいけない。
(ローウェンタル)

- 2008年9月、米国科学アカデミーとロシア科学アカデミーの合同委員会は、「核燃料サイクルの国際化:目標、戦略、課題(Internationalization of the Nuclear Fuel Cycle : Goals, Strategies, and Challenges)」と題する共同研究報告書を発表、この中で提示された核燃料供給保証及びバックエンドを含めた多国間管理核燃料サイクルに関する所見及び提案を紹介する。
- この研究の前提は、濃縮、再処理施設を保有する国が増加するほど核拡散リスクは高まるというもの(同様のことが多国間施設についても言えるか否かはopen questionであり、この研究の中で検討された。)
- 報告書の結論として示された7つのポイントは以下の通り
- 濃縮、再処理を行う権利を進んで放棄しようとする国はほとんどない。
- 供給保証に関し提案されているどのメカニズムも、それ一つだけでは、全ての国のニーズに対応することはできない。
- 少数の国が技術を保有し、サービスを提供するシステムを維持することはますます難しくなり、技術をもたない国も利益の分配に与れるようなシステムができれば、不公平感を緩和することができる。
- 供給保証が濃縮、再処理の放棄のインセンティブとして果たす役割は限定されているのに対し、使用済燃料の引取りは、はるかに大きなインセンティブを提供し得る。ところが前者に関しては多くの提案がなされているのに対し、後者を対象にしているのは、ロシアによる提案のみ。これは、他の国の使用済燃料の引取りに対する政治的な障害は大きいことによる。
- 実行可能な提案から履行すべき
- 多様なニーズに合った様々なオプションを支持
- 機微な施設を建設しないよう、追加的なインセンティブを提供すべきである。
(ユディン)
- 基本的にローウェンタル氏と同意見。
- 核燃料供給保証と核燃料サイクル施設の多国間管理とは同一ではない。前者は後者の一部。
- 現在、燃料供給保証について多くの提案がなされている理由は、新規原子力発電導入国の関心がバックエンドではなく、燃料供給の確保にあること、バックエンドが、取扱いが難しい問題を含んでいるのに対し、フロントエンドはより扱いやすいことによる。
(チョイ)
- イランに濃縮をやめさせようとしているが、燃料供給保証の提案は十分なインセンティブとして働いていない。濃縮施設を建設することが経済的に見合うものになるためには、原子炉が20基必要であり、明らかにイランの場合は、そうした環境にはない。
- 商業的理由ではなく、エネルギーの自立の観点から、濃縮技術を持ちたいという国に対してどう対処していくべきか。
(シャインマン)
- イランは会議の場で、6基の原子炉を建設する計画であると述べていたが、それでは濃縮施設は経済的に成り立たないと指摘したら、翌日には20基の間違いであったと言ってきたことがある。イランのようには、核オプションの維持そのものを目的として、濃縮活動を実施する国もある
(鈴木)
- 経済的に成立しなくとも、自国で濃縮、再処理技術を取得するための研究開発を進めることはありうる。しかし研究開発規模でも軍事転用が可能であり、研究開発の権利を認めれば各国が軍事転用できる能力を止めるのは難しい。ユーラトムは欧州全体で技術開発を共有するという仕組みを構築したが、それを世界規模で行ってはどうかと考えている。
(ド・カント)

- 昨日ストラットフォード氏が明言したとおり、(機微技術の取得の追求は)市場の問題である。
- ブラジルは豊富なウラン資源を有しているおり(世界で6番目、探鉱が進めば2番目になることが期待される。)、今後、ウラン供給の市場が数百万US$規模になることを考えると、ブラジルは、この市場から取り残されたくないと考えている。ブラジルの元大使は、論文の中で、ブラジルの立場として以下の趣旨を述べている。
- 「ブラジルその他のラテンアメリカ諸国は、核兵器を開発せず、大量破壊兵器のない世界の構築に向けたパートナーであり続ける。他方、ブラジルは、核燃料市場にキープレーヤーとして参加するという目標を放棄するつもりはなく、少数のメンバーによる核燃料供給のクラブから締め出されることを許容しない。」
(チョイ)
- ブラジルやカザフスタンなどのウラン資源国にとっては、ウラン資源に付加価値をつけて売るということが、濃縮を志向する要因になっており、供給保証によるインセンティブを働きにくくしている。
(チョイ)
- 国家による濃縮、再処理の追求を止めさせることができるか。核燃料供給保証や使用済燃料の引取りを含む核燃料サイクルの多国間管理は核不拡散に効果的な枠組みかとなりえるか。
(ローウェンタル)
- NPTの第4条の原子力平和利用の権利について議論することはNPTそのものの改正の議論につながり、正しい方向ではなく、経済的な観点から魅力的なオファーを提示することによって、多国間メカニズムへの参加を説得することが必要。
- スタンフォード大学のGeoffrey Rothwell教授が濃縮のコストを分析する論文を最近、発表
- 供給保証については、こうしたオファーは既に提示されており、インセンティブを追加する余地は少ない。他方、バックエンドについて魅力的なオファーがなされているか否かは定かではない。
(ユディン)
- 権利の放棄の議論を持ち出すと、政治的な問題になるだけであり、そうすべきではない。自ら核燃料サイクル技術/施設を開発することに代わる、魅力的な代替策を議論することが必要。
(鈴木)
- NPT加盟国の濃縮、再処理を含む原子力平和利用の権利を認めるが、自国内に施設を持たないようにする、あるいは余剰の核物質を持たないようにするインセンティブを構築すればよい。自国で施設を持たなくても研究開発を実施することは可能。例えば、私の所属する電力中央研究所は乾式再処理の技術を開発しているが、国内にはホット施設を有せず、欧州で実施している。
(久野)
- 自国での濃縮、再処理施設の保有に固執する国もあり、このような国に対して「持ってはならない」と言ってしまうと、逆効果になる可能性もある。 公平性が重要。
- 高いクライテリアを国際社会が設定し、誰でも持ってもよい、とすべきで、そうすれば、クライテリアを満たしてまで濃縮、再処理を保有しようとする国は少なくなるのではないか。それでもやろうとする国に対しては別の方法で対処すればよい。
(鈴木)
- 濃縮、再処理施設を保有する権利を否定すべきではないという点は同感。自国でこうした施設を保有しない方が、メリットがあるというインセンティブを示すべき
(カーター)
- 供給保証メカニズムを利用する段階になって始めて、それが有効か否かが分かる。
- 現状では、NAM諸国は供給保証についてあまり関心を有していない。例えば、英国の提案に関して、ヨルダンは、魅力的な提案ではあるが、原子力の導入が差し迫った段階で検討する、という程度の反応である。
【課題2:バックエンドの多国間管理】
(イワノフ)

- 使用済燃料管理に関し、早期に、政治レベル、しかもトップレベルでの決定が必要
- 例えば、リトアニアにあるRBMK炉(注:黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉)2基は運転を停止し(1基は既に停止、もう1基は近い将来、停止)、ロシア原産の使用済燃料が乾式の容器に保管される。ロシアは、自ら燃料を供給したため、使用済燃料について十分理解しており、今の段階でロシアが建設中の使用済燃料の貯蔵施設に輸送すれば、取扱いは容易であるが、時間が経てば、燃料ピンの破壊などにより、取扱いはより難しくなる。ハンガリーやウクライナも同じような状況
- こうした問題は、二国間の問題ではなく、国際的な解決が必要
- ロシアは自国原産の使用済燃料の輸入を認める法律を有しているが、自国原産以外の使用済燃料の輸入については国際的な合意が必要。米露原子力協力協定も要件の1つであるが、それだけではない。
- 中東諸国との協議において、実務者レベルでは、もし使用済燃料貯蔵のサービスが提供されるならば、核燃料サイクルの一部については放棄しても良いとの考え方も示されている。
- 核燃料サイクルの国際化は理解を得ることが難しいかもしれないが、まずはバックエンドから理解を進めていくべき。
- イランとの関係について、ロシアはイランと締結した協定の中で使用済燃料を引き取る条項を盛り込んでおり、引取りに伴う全ての政治的問題、技術的問題は解決済み。ロシアのコンテナ及び輸送技術を用いることになっている。また、2年後くらいにクラスノヤルスクで、VVER1000(注:ロシア型軽水炉)、RMBK1000用の乾式貯蔵施設が稼働する予定
(ジョラン)
- 英仏両国は商業用の再処理施設を所有しており、他の国に対して再処理役務を提供することが可能。
- ただし、2つの点に留意が必要。フランスでは国内法に従い、高レベル放射性廃棄物は返還する必要があること、また、使用済燃料管理の安全及び放射性廃棄物管理の安全に関する合同条約の締約国は、同条約の条項に制約されること。こうした条項には、廃棄物を発生させた国がその管理に責任を有すること、廃棄物を輸出する場合、輸出先の国で当該廃棄物が適切に管理される保証が得られることなどが含まれる。IAEA等が、安全の観点から、廃棄物の輸出をオーソライズするようなシステムが必要ではないか。
- 核拡散抵抗性の観点からは、使用済燃料を再処理し、MOX燃料を製造し、再度原子炉に装荷していくことが賢明。MOX燃料として燃焼させることによって、核兵器製造用としてのプルトニウムの魅力は減少する。ただし、MOX燃料の返還には、NSG等、国際的な要件を満たす必要がある。また、再処理やプルトニウム利用に関しては、二国間原子力協力協定で、供給国の同意が規定されている場合があり、同意権の行使にあたって国際的な議論が必要になるかもしれない。
- AREVAはフロントエンドからバックエンドまでのサービス(ただし、高レベル放射性廃棄物は返還)を提供していきたい。
(ユディン)
- MOX燃料の軽水炉での利用はオプションの一つであるが、使用済MOX燃料をどう扱うかという問題は残る。
- 国際的な枠組みでの使用済燃料貯蔵の検討の必要性についてはイワノフ氏に同意。100-200年にわたる貯蔵を想定。国際的な枠組みでの廃棄物処分はより難しい問題。
(チョイ)
- AREVAは、再処理の前に、200年間、使用済燃料を貯蔵することは可能か
(ジョラン)
- AREVAにはそうしたことは不可能。通常、再処理契約には再処理依頼国が放射性廃棄物を引き取るとのコミットメントやスケジュールが必要。
- また、200年にわたり、使用済燃料を安全に取り扱うことが可能かという問題がある。
(ユディン)
- 現状では、高速増殖炉導入の見通しが不透明であり、今すぐ再処理を行う理由はない。
(久野)
- 使用済燃料の管理には国際的な枠組み構築が重要であり、国際枠組みが出来れば二国間協定の下での制約も緩和されるかもしれない。また、使用済燃料の国際貯蔵をしながらプルトニウム利用を促進することが必要。高速増殖炉が必要になってから急に始めたのでは遅い。
(イワノフ)
- 我々のメインのシナリオは、次世代高速炉ができるまでは再処理せず、その間は中間貯蔵。
(ジョラン)

- 軽水炉の使用済燃料を再処理し、MOX燃料として利用するのが基本的な政策
- MOX使用済燃料は、更に再処理するか、軽水炉、高速炉用に貯蔵しておくか、2つのオプションがある。
- もし、使用済燃料の再処理を依頼する国があるのであれば、既存の再処理施設で再処理した後、MOX燃料として、再処理を行った国、あるいは、MOX燃料の使用実績があるその他の国で利用することが考えられる。その場合、ウラン燃料の形で等価のエネルギー分を、再処理依頼国に返還するか、あるいは別の資金的アレンジメントにより、双方にとって有利な状況(win-win situation)が生まれる。
- もし、再処理を必要とする国が増えれば、既存の施設の処理能力を拡張することや、多国間管理の施設を建設することも考えられる。
(チョイ)
- AREVAが使用済燃料の再処理のサービスを行っているが、実際に再処理を行うまでの間に貯蔵期間があることを考えると、実質的に、使用済燃料の中間貯蔵を行っていると解釈することも可能。問題は、その期間を延長することが可能か否かということ。その間、国際社会は共同して環境負荷低減の観点からの研究開発を行い、いつ再処理を行うのが適当かを検討することが可能になる。
(イワノフ)
- 再処理後の高レベル放射性廃棄物にマイナーアクチニドが含まれるか否かで大きな違いがある。半減期が長いマイナーアクチニドを管理するのは容易ではない。将来的にはこうしたマイナーアクチニドは高速炉で燃焼されることになる。
(ピラー)
- 多国間管理についてなされている提案が、いかなる問題の解決を意図したものなのか明確にする必要がある。
- 軍縮の推進と機微な施設の分散は両立するものなのかが問われなければならない。
(ローウェンタル)
- (ピラー氏が提起した軍縮との関連に関して)、核兵器が廃絶された状況は、不安定で検証が不可能であるという懸念があるが、濃縮、再処理施設を多国間管理の下に置くことによって、ブレークアウトを難しくし、より安定度を高めるというメリットがある。
(シャインマン)
- 同僚とともに米国政府のために行った研究の中で、国際使用済燃料貯蔵施設のホスト国になるための基準を同定した。核不拡散に関する信用度、安定性、隣国が反対しないことなど
(伊藤)

- 核燃料供給保証にしても使用済燃料の引取りにしても、NPT第4条の原子力平和利用の固有の権利を奪うものではなく、濃縮、再処理といった機微技術が拡散しないためのインセンティブを生み出そうとするものであり、より魅力的なものとすることが必要。しかし、いくつかある提案も特効薬、万能ではなく、インセンティブだけでは核拡散は防げず、技術的な障壁を高くする、制度的にしっかりしたものにする、より効果的な保障措置をする、場合によっては違反があれば強制力を行使する仕組みを国際的に整えるなど、多種多様な方策を組み合わせるべき。
- 原子力政策大綱にも記載されているように、多国間管理の議論には、日本も積極的に参画していくべきである。議論にあたっては、保障措置の低減の可能性など、新たな枠組みのポジティブな側面を強調することが重要。原子力が地球環境あるいはエネルギー安定確保のために必要であるという共通の信念の下で、それを平和利用に限定していこうという共通の認識の上で、多くの場で議論することが大事である。
(グ)

- 国際管理に関し、バックエンドはフロントエンドに較べ、より複雑であることからバックエンドに焦点をあてた検討がなされるべき。その点から以下を述べる。
- バックエンドに関して、再処理や軽水炉でのMOX利用は既に確立された技術であるが、高速炉サイクル技術は研究開発の段階。バックエンドの国際化にあたってはまずは技術の確立が必要であり、更なる研究開発及びそのための国際協力が奨励されるべき。
- ステップ・バイ・ステップで進めていくべき。特に、国際的な枠組みでの放射性廃棄物処分が、機微な技術を取り扱うものではないにもかかわらず進まないなど、難しい問題を抱えており、楽観的になりすぎないことが重要
- 米国、ロシア、日本、韓国、中国、インド等の大きな原子力プログラムを有する国は、他国にすべてを依存することは無理であり、自国内で核燃料サイクル施設を設計し、建設し、運営していく必要があると考える。例えば日本にはかなりの量の使用済燃料が蓄積されているが、ロシアに送って再処理し、放射性廃棄物を引き取るのはコストが高くつくのではないか。
- 国際的な核燃料センターを創設する際には、その国のプログラムを基盤にする必要がある。
(ピラー)

- 伊藤氏及びグ氏の言及通り、前向きな姿勢で国際的にバックエンド技術の研究開発を行う必要がある。しかし現在の供給保証及び核燃料サイクル施設の多国間管理の議論には、目的やメリットなど、そもそも論の視点が欠けている。今一度、一歩引き下がってこれらを明確にする必要がある。
(リー)
- グ氏から大きな原子力プログラムを有する国は自国内でこれを行うべきとの指摘があったが、韓国は濃縮、再処理能力を有していない。現在、韓国では20基の原子炉を運転中であり、使用済燃料は10,000トンに達している。更に、2030年までに原子力のシェアを59%に増やす計画であり、使用済燃料は2100年までに100,000トンに達することが想定される。使用済燃料管理は深刻な問題で、海外依存も必要な選択肢。従って、多国間アプローチについての国際的な議論を必要としている。多国間アプローチとしては使用済燃料の永久貯蔵、あるいは廃棄物の量を最小化し、放射性を低減する新たなリサイクリングが考えられる。
- また、韓国においては、電力が最終的に使用済燃料を他の国に搬出する決定を行うことを考えると、多国間管理構想は経済的なインセンティブを有するものである必要がある。
(鈴木)

- 同氏を中心とするグループによる研究の内容(日本政府への提言)を紹介
- 核燃料供給保証/核燃料サイクルの多国間管理が上手くいかない理由は、二重基準と不公平性、透明性の欠如、市場メカニズムが上手く使われていないこと、使用済燃料の行き場がないこと、が要因。また多国間管理を成功させるための条件としては、普遍性、透明性、経済合理性の3つが必要である。
- 多国間燃料サイクル管理に関しては、以下の5つのパッケージの提案をしたい(鈴木氏の資料:「原子力民生利用と核不拡散:核燃料サイクル拡大に伴うリスクをどう抑制するか」参照)
- 核兵器に転用可能な余剰核物質の削減:既存のストックパイルの使用、中間乾式貯蔵能力の確保、日本の余剰プルトニウムを持たないとの政策を世界的規範とすること、「国際プルトニウム処分プログラム(IPDP)」の確立
- 燃料サイクルの国際化と共同燃料備蓄:すべての核燃料サイクル施設を国際化し、供給者と消費者が天然ウランと濃縮ウランの共同備蓄を創設する
- 原子力産業界による行動規範作成、軍縮・核不拡散基金の創設:原子力産業界が、核兵器活動を行わない、機微技術を移転しない、安全と核物質防護に最善を尽くす、との3つの基本原則に関し行動規範を作成、これを満たす者にのみ基金から融資を行う
- 日本の核燃料サイクル計画の見直し:核燃料サイクルの国際化、核兵器に転用可能な核物質を使わない先進原子力システム研究開発イニシアティブ、例えば、海水からのウラン回収、高濃縮ウランを作りにくい化学濃縮法、プルトニウムを減らすためのトリウムを利用したMOX燃料、再処理不要の長寿命炉心小型炉など
- 核セキュリティの強化:日本が世界最高水準を目指して核セキュリティ対策を強化し、世界的に貢献する
(伊藤)
- 鈴木氏の提案に関しては、まだまだこれから議論していかなければならない問題が沢山あり、時間も要する。個別に議論していくことが大事で、今ここで急いで結論を出す問題でもない。そのためにも差別を作らずに相互により良くしていくことが経済・効率・核不拡散上合理性があることを認識しつつ、今後、十分な対話、議論をしていくことが大事。
(久野)

- 東京大学は、電力会社、国研、大学、その他から参加頂いたセカンドトラックの研究会で議論し、使用済燃料の国際管理とリサイクルを両立させる構想を報告書にとりまとめた。プルトニウム利用国は限定されているので、利用しない国に、金、あるいはエネルギーで補償することが特徴である。地域的にこれを行い、地域保障措置をかけることが多国間管理の大きな機能の1つになるといった提案を行っている。
(グ)
- 多国間管理化については、地域協力の方が国際的なレベルでやるよりも簡単かもしれないが、新規原子力発電導入国には後者のほうが魅力的でメリットがあると思う。
- 東アジアの国々、例えば日本、韓国、中国に関しては、各国で核燃料サイクルシステムをまず打ち立てることが必要で、そこから各国及び新興国のニーズを満たす地域センターを創設する等、協力を行っていくことができると思う。
(直井)
- 「多国間管理」といった言葉のみが先行しており、具体的にどのような形になるのか議論を始めることが大事である。また、各国毎に原子力を取り巻く状況は異なり、議論を収束させることは難しい。ステップ・バイ・ステップで実現可能な部分から始める、例えばまず使用済燃料の中間貯蔵施設を多国間あるいは地域で創設することが考えられる。
- 多国間管理は50年も前から議論されてきたが、ようやくロシアIUECのLEU備蓄が実現間近になっており、これから原子力ルネサンスで実際のニーズも高まっている現在、その議論を深めていくことが重要。
(リー)
- 国際的なアプローチより地域アプローチの方が簡単であろうが、国毎に原子力政策や方針は異なる。地域アプローチをとるのであれば、前提として国家間の政策調整が必要。韓国は使用済燃料の管理につき、まだ何の結論や判断も行っておらず種々の選択肢を検討中だが、日本はクローズド・サイクルを選択している。いずれにせよ日本、韓国、中国等の間で政策的な調整が必要だろう。
(チョイ)
- かつてIAEAにいた際、英国のプルトニウムをフランスで処分するよう求めたことがあったが、上手く行かなかったように、各国の国内プログラムにも影響される。
- 地域レベルでのアプローチは、保障措置のコストを下げる等の意図もあると考えるが、この点はどうか。
(久野)
- 同じコストで核拡散抵抗性を取り入れた保障措置システムができれば良いが、それだけだとおそらく費用が高くなる。国際管理化を導入することで、信頼醸成につながり、保障措置を低減できる可能性がある。
(チョイ)
- アジア・太平洋保障措置ネットワーク(ASPN)はアジアにおける核燃料サイクルの多国間管理に発展していく、プラットフォームとなり得るものではないか。
【一般聴衆を交えた質疑応答・コメント】
(一般)

- 使用済燃料はプルトニウムを含む重要な燃料で、プルトニウムはトリウムを使う時には核分裂性物質として利用することができる。中国には3万トンという非常に多くのトリウムがあると聞いているが、中国にあるトリウムと世界中で持っているプルトニウムを合わせて使うことができないか、グ氏に聞きたい。
(グ)
- トリウムは潜在的資源であるとは考えるが、現状のオプションとしては考えていない。トリウムは高速炉よりも熱中性子炉で使う方が適している。
(一般)
- この議論の目的は、核燃料サイクル施設の多国間管理構築そのものではなく、核不拡散の観点から多国間管理が有効か否か、いかにあるべきかの議論であることを忘れてはならない。
(一般)
- 市民にとっては電力が安価になればよく、欧州では原子力のコスト意識が生きているようだが、日本の大学その他も、行動規範やコストセイビングの点など、生活に密着した現実的な議論を展開して欲しい。
(チョイ)
- 「象牙の塔」に籠もったような、現実離れした議論を意図しているわけではない。単に理論上の話をしているわけではなく、現実の話として、電力供給源の一つとして原子力を推進するに際し、例えば、使用済燃料の管理などに関し、誰が責任を持つべきかという話をしている。もし、受領国がこうした原子力の導入に伴う問題に関し、受領国の支援、少なくとも解決策の提示が受けられないならば、原子力以外の発電手段を求めることになるであろう。
(久野)
- 我々は現実と違う次元の研究をしているわけではない。原子力平和利用と並行して核不拡散を促進していかないと日本はこの先、原子力利用で生き残れないだろう。また、核燃料サイクル施設の多国間管理化は将来的な遠い先の話に聞こえるかもしれないが、今後、核燃料サイクル施設の多国間管理化に向けた動きが強まってくる可能性があることを考えると、国際間の調整が必要で時間を要する問題であるからこそ今から議論・検討していく必要がある。
(ピラー)
- 核燃料サイクル施設の多国間管理の根本問題、何を目的に、誰を参加させ、どのレベルの多国間管理化を図るのか、技術のブラックボックス化を求めているのか、それは受領国の要求と合致するものなのか、産業界に受け入れられるものを求めているのか、それを明確にすべき。詳細を一つ一つ積み上げていくことが必要
(ジョラン)
- なぜ産業界が核不拡散に携わるべきか。COGEMA(現AREVA)には核不拡散は政治マターで本来産業界には無関係という考え方の人もいたが、核不拡散を確保することは産業界自身の利益につながるというか考えを訴えてきた。
- 一つは核物質を取り扱っているという立場に鑑み、適切に取り扱っていることを示す必要があること、原子力資機材の輸出に際して責任が生じること、また、原子炉での兵器級プルトニウムの処分など、核不拡散に関して、産業界自身が解決に貢献できることによる。産業界の行動規範は、コミュニケーション・ツールとして使用可能であり、我々の全ての活動、全ての従業員に適用すべき
- 我々が国際企業であることで、核不拡散文化の国際的普及に貢献している。
(伊藤)
- 核燃料供給保証や核燃料サイクル施設の多国間管理はステップ・バイ・ステップで順番に積み上げていくべき。原子力が地球の持続可能な発展のためにどうしても必要であると皆が信じるのであれば、国だけの問題ではなく、これに関わる産業界、研究機関、アカデミア等、すべてがその思いの下、各々がどのような責任や役割を果たしていけるのかについての認識を共有することが重要
《円卓討論3のサマリー》
課題1「燃料供給保証」、課題2「バックエンドの多国間管理」

- NPTの原子力平和利用の権利の放棄につながるような議論は生産的ではなく、受領国にインセンティブを与える魅力的なオファーを提示すべき
- 燃料供給保証は、政治的な理由による燃料の供給途絶という多国間管理の一部の部分を扱っているに過ぎず、今後の課題はバックエンドにある。
- 使用済燃料の処理は既存の原子力発電国だけの問題ではなく、今後、原子力発電を導入する国にとっても、原子力発電導入後、直面する問題であり、多国間管理も含めた国際協力のあり方を検討すべき
- 再処理を行う時期についてはパネリストの間で意見の相違が見られたが、使用済燃料の貯蔵に関する国際的な枠組みの構築の重要性については認識を共有
- 多国間管理の枠組みの構築は、国や産業界、アカデミア等、多くの関係者で議論を行い、また各国の事情を踏まえてステップ・バイ・ステップでできるところから始めるべき。特に原子力ビジネスが関係することを勘案すると、原子力産業界を議論に関与させることが重要

田中教授閉会挨拶

- 原子力平和利用を推進することが目的であり、そのためには、核不拡散、核セキュリティ、核軍縮に取り組む必要がある。
- これまで原子力平和利用と核不拡散、核軍縮の議論は政治色が強い故に、表面的な議論に終始する傾向にあったが、本フォーラムでは、研究開発機関と大学の主催であるという特徴を生かして、政治の世界を離れたアカデミックな議論を展開することが可能になった。
- 海外からの参加者をはじめ、関係者の熱い議論と協力に感謝
