包括的核実験禁止条約(CTBT)にかかわるシンポジウム
−核実験監視技術とその科学的利用−
平成21年7月9日(木) 浜離宮朝日ホール 小ホール
1.開会挨拶(10:00 - 10:10)
日本原子力研究開発機構(JAEA)理事長:岡﨑俊雄

(1)IAEA次期事務局長への期待
我が国の天野大使がIAEA次期事務局長に就任されることが決まった。核不拡散分野におけるIAEAの果たすべき役割の重要性が高まるなか、天野大使の一層のご活躍を皆様とともに期待したい。
(2)オバマ政権や北朝鮮の動き
米国オバマ大統領のプラハ演説における、CTBT*1 批准への意欲、米露間の核兵器削減交渉の進展、カットオフ条約*2 の交渉開始等の核軍縮の推進に関する発言は歓迎すべきもの。一方、北朝鮮の2度目の地下核実験の強行やイランのウラン濃縮等、核不拡散体制は依然、厳しい試練に晒されている。第2の北朝鮮のような国を出さないためにもCTBTの発効が必要。
(3)本シンポジウムの開催趣旨
CTBT発効に向けたCTBT国内運用体制の準備状況について理解を深めるとともに、CTBTに係る技術的課題や政策的課題について専門家からのご意見を頂き、国内外関連機関の連携強化及びCTBT観測データの科学的利用等の促進につなげたい。
(4)原子力機構の現状
「もんじゅ」は運転再開の準備として燃料交換を実施中で、その後プラントの健全性確認試験を実施予定。耐震安全性評価の国の審査に確実に対応し、早期の運転再開工程の確定に向けて取り組み中。高エネルギー加速器研究機構と共同建設した大強度陽子加速器施設J−PARCは、7月6日に完成記念式典を開催し、今後、基礎科学から産業応用までの幅広い分野に研究手段を提供するとともに世界最高レベルの成果を挙げていきたい。
*1包括的核実験禁止条約(CTBT : Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty): 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間での核兵器の核実験による爆発、その他の核爆発を禁止する条約
*2兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約)(FMCT : Fissile Material Cut-off Treaty):核爆発装置の研究・製造・使用のための高濃縮ウラン及びプルトニウム等の生産禁止及び他国による援助を禁止する条約
2.基調講演(10:10 - 12:10)
○CTBTについて
CTBTO準備委員会*3 事務局長特別補佐官 香川美治氏

(1)経歴等
外務省入省以来、長い間軍縮関係の業務に携わり、関係省庁の協力の下に「CTBT国内運用体制」を設立するとともに、(財)日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センターにてCTBT国内運用体制事務局の初代事務局長として本体制整備に努めた。その後、ウイーンのCTBTO機関準備委員会に採用され特別補佐官を務めている。
CTBT機関準備委員会の設立文書の目的は、「CTBTの効果的な実施の準備」と「締約国会議第一回会合の準備」の2点である。前者は、CTBTが発効するときには、国際監視制度、協議と説明、現地査察及び信頼醸成措置の4つから成る検証制度が有効に機能する状態にあることであり、後者は、議事案、手続き規則案の他、協定案、取決め案、指針案等、技術事務局の態様等の諸事項の準備をすること。
(2)暫定技術事務局の組織
暫定技術事務局(PTS)*4 は、ウイーンにある国連欧州第2本部に設置され、職員数263名、内169名が専門職員で、残り94名は一般職員。180カ国の署名国の内、73カ国から採用されており、日本人は自分を含めて4人。国際監視制度(IMS)*5 局は、世界のIMS施設を建設、維持しており、全体予算100億円の33%を執行。国際データセンター(IDC)*6 局は、予算39%、職員数69名の最大の局で、IDCの管理、運営を行っており、世界各地のIMSからの情報を6基の静止衛星で瞬時にIDCに集め、自動及び手動で解析するとともに、その結果を条約署名国に提供。現地査察(OSI)*7 局は17名で予算6%の最も小さな局。今後、現地査察が検証の最後の決め手になるので重要な業務ではあるが、OSI自体が極めて政治的であるので、多くの困難もある。以上3局が検証実施部門で、職員7割以上、予算の8割近くを占めており、これ以外は支援部門。
(3)今後の展望
PTSは設立から12年経ち、発効要件国の内、未批准国は米国を含む9カ国。保有核兵器の信頼性と安全性を確保するとして反対したブッシュ政権から、民主党のオバマ政権に移行し、CTBT早期発効に向けて議会上院と話し合う予定。これを受けてトート事務局長も2011年をターゲットに発効前準備作業を指示している。
北朝鮮核実験の発表の後に、全世界61ヶ所の監視観測所からのデータ解析により、震源地推定について現地査察実施の要件である1,000km2以内に特定することが出来、結果的に北朝鮮の核実験がIMSの精度チェックに役立つこととなった。6月にウイーンで開催された国際科学研究会議(ISS)*8 では、99カ国から600人以上の出席があり、CTBT検証制度の実効性を最先端の科学技術によって評価するとともに、高品質で世界規模で取得されるIDCデータを、他の自然科学分野へ応用すること等について活発な意見が交わされた。
*3CTBTO準備委員会:CTBTが発効すればCTBT機関(CTBTO: CTBT Organization)が発足するが、発効前であるので「準備委員会」と呼んでいる。
*4暫定技術事務局(PTS:Provisional Technical Secretariat):CTBT機関準備委員会の事務局
*5国際監視制度(IMS:International Monitoring System):地震、放射性核種、水中音波及び微気圧振動の4つの観測技術で、地球上の核実験を24時間監視する制度
*6国際データセンター(IDC:International Data Center):全世界337ヶ所(地震波170、放射性核種80(監視観測所)+16(公認実験施設)、水中音波11、微気圧振動60)に配置されるIMSからのデータを常時収集し、各締約国が平等にかつタイムリーに分析できるよう提供するセンター
*7現地査察(OSI:On−Site Inspection):CTBT違反の懸念がある場合で、説明及び協議等によってその懸念が解消されない場合、執行理事会に諮った上で、事象が発生した区域において調査出来る査察
*8国際科学研究会議(ISS:International Scientific Studies):CTBT検証制度の整備状況を技術的に検討したり、他の科学技術分野への適用を議論する国際専門家会議
○CTBTへの日本の取組
外務省 軍縮不拡散科学部長 佐野利男氏

(1)オバマ政権の動き
ブッシュ政権時代に事実上の棚上げ状態になったCTBT批准について、オバマ政権では議会上院を説得して批准を目指すとしているが、米国に行って政府関係者から情報収集した感触では、簡単ではないという感想を持っている。1999年当時に上院で否決された時の課題を克服することが可能なのか、また、議会期間中に多くの重要法案を採決しなければならない時に、日程的に可能なのかという疑問が有る。例えば、技術的な課題としては、CTBTの探知能力が本当に信頼できるのか、核兵器の信頼性維持が未臨界核実験を含めて実験無しで可能なのかという問題である。米国政府は、エネルギー省が進める核備蓄管理プログラム*9で科学的に説明して行くとしている。上院民主党60議席であり、批准に必要な2/3確保のためには7議席を共和党から持って来なければならず、100年に1度の金融法案の時でさえ、63票であった。
(2)我が国の発効促進努力
政権と良く話し合いながら進める必要があり、今回の(伊)ラクイラG8サミットの声明の中から、軍縮核不拡散に係る事項の抽出を行い、オバマのCTBT批准、CTBT早期発効と普遍化、核実験モラトリアムなどの点で整理して行きたい。国際的な機運は盛り上がっているものの、発効促進疲れが出ており、もう一度原点に帰って、発効要件国で批准していない9カ国の分析を行いたい。
(3)未批准の9カ国
中国は予定されたIMSが11ヶ所で、9ヶ所は建設が終了しており、米国が批准すれば、後を追うように批准するであろう。インドは、1998年の核実験に満足していないようなので、核実験を禁止する批准には慎重かもしれない。パキスタンはインド次第であろうし、インドネシアは、判断を官僚組織の中で積み上げると思うが、基本的には米国に追従するであろう。イランは微妙であり、エジプト、イスラエルは、分からない。北朝鮮は最後の国となるだろう。
(4)今後の取組
高村外相の時に始まった2年に1回のCTBT発効促進会議*10があり、その間にCTBTフレンズ外相会合(日本、オーストラリア、オランダ等)を開催している。今年の秋にはハイレベルの働きかけを行い、発効促進会議の後には国際軍縮会議を開きたい。
*9核備蓄管理プログラム(SSP:Stockpile Stewardship Program):核爆発実験を行なうことなく米国核抑止力を維持することを目的とするプログラム
*10CTBT発効促進会議:2年に1回開催しているCTBT発効促進に関する会議で、我が国はCTBTの早期発効を求める強いメッセージを国際社会に発信している。
○「CTBTへの日本気象協会の取組」−核実験監視に係る地震波・微気圧振動観測の現状−
(財)日本気象協会 参与 新井伸夫氏

(1)NDC*111 の概要
気象協会は、長野県の松代にあるアレイ観測施設を初めとする国内6つの地震観測点、千葉県のいすみ市にある微気圧振動観測点の合計7つのIMS観測点を維持管理している。CTBT発効後は、核実験の兆候があった時に、現地査察を実施すべきかどうかを日本政府が判断する際の参考情報を提供するという役割を担うことになる。松代の地震観測施設は14個の地震計群で構成され、それらによって得られる地震波の到来方向やみかけの伝播速度から、震源位置を推定することが可能である。微気圧振動観測施設では、ノイズの原因となる風の影響を避けるためにパイプアレイを四方に張り巡らし、パイプ先端を砂利の中に埋める等して、大気中を伝播してくる音波を観測している。
(2)地震観測
IMSの地震観測網の地下核実験検知能力は、日本国内で発生したイベントを対象に気象庁の震源とIDC発表の震源を比較した結果などから、目標とする(1キロトン規模の爆発事象を検知し、その実施位置を1000km2以内の誤差で推定しうる)レベルにあると言える。北朝鮮が実施した核実験の時には、爆発事象の特徴である明瞭な立ち上がりを有する地震波が観測され、2006年の実験時に観測された地震波と酷似していることから、今回の実施場所が2006年に実験が行われた場所と極めて近いと推定された。なお、隠すことを意図して実施された小規模な地下核実験をも検知出来るかどうか、OSIへ受け渡す探査範囲の情報の精度が1000km2以内で良いのかどうかについて疑問がある。
(3)微気圧振動観測
微気圧振動観測が対象としているのは可聴域より長周期の音波であり、この帯域の音波は、長距離伝播するので大気圏内核実験の探知に優れている。平常時には、波浪、火山噴火、地震、雷と言った自然事象や、プラント、飛行機、ロケットのような人工事象によるシグナルが探知されている。北朝鮮のミサイル発射の際にも、発射にともなうものと第一弾ロケットの落下によるものと思われるシグナルが観測されている。
(4)NDC1の課題等
今後は、隠蔽を意図した核実験をも十分に検知しうるよう、ノイズに埋もれたシグナルをいかに見つけるのか、小規模な爆発を自然地震と判別するにはどうすればよいか、などについて検討を深めていく必要がある。また、人材の育成や体制の維持も重要であり、核実験を監視するという経験をいかに蓄積、伝承するかが課題となっている。 IMSは、維持管理の行き届いた観測網であり、確実で迅速に測定データが得られるという特徴から、防災情報としての活用や科学的な研究への活用が図られている。
*11国内データセンター(NDC:National Data Center):IDCからのデータを受信してCTBT違反の核実験探知に係わる日本独自のデータ解析を行う国内のデータセンター。我が国には、地震及び微気圧振動に係るNDC1((財)気象協会)と放射性核種に係るNDC2((独)日本原子力研究開発機構)の2ヶ所がある。
○「CTBTへの原子力機構の取組」−核実験監視に係る放射性核種監視の現状−
原子力機構 核不拡散科学技術センター長 千崎雅生

(1)CTBT検証制度に対するJAEAの取組
JAEAにおける標記の活動は、沖縄と高崎における2箇所の放射性核種に関するIMS、他のIMSから収集された試料について詳細分析する公認実験施設及びIDCから受信したデータを我が国として解析評価する国内データセンター(NDC2)としての機能があり、平成9年の7月に、日本政府、即ち当時の科学技術庁原子力局長から旧原子力研究所に対する協力要請に基づいて整備してきた経緯について紹介。原子力機構となってからは中期目標に、CTBT運用体制の整備を中期目標において、核不拡散を技術的側面から支援するための技術開発テーマとして掲げ、CTBTの放射性核種観測データの解析評価に係る活動を行っており、また、技術専門家としてCTBT準備委員会の作業部会会合、国際的検証体制の構築等に関する各種会議に積極的に参加し、国際貢献に努めている。
(2)高崎、沖縄の国内監視観測所
CTBT検証制度の一部である国際監視制度の内、放射性核種監視観測所が、高崎及び沖縄を含んで、世界で80箇所あり、そこでは放射性粒子監視観測が行われている。これに加えて高崎では放射性希ガス監視観測も行われている。高崎監視観測所では、放射性核種の観測装置を設置し、2004年2月にCTBTO準備委員会より認証を取得したこと、また、放射性希ガスの観測装置については、2008年4月に機器設置の確認を受けていることの報告。放射性核種観測装置の感度については、一般の原子力発電所周辺のモニタリングと比べて、約100倍高感度であること、測定頻度が1日1回と多いこと等が特徴で、また、放射性希ガス観測装置についても、133Xeの最低検出可能濃度が約0.2mBq/m3と高感度であること、1日2回の測定結果が得られること等が報告。一方、沖縄監視観測所は、放射性粒子観測のみで、2007年2月に認証を取得。
(3)東海公認実験施設
世界各地のIMSから採取された試料を分析するために世界16ヶ所の研究所がCTBT議定書に記載されており、東海公認実験施設はその一つとなっていること、分析の国際規格であるISO/IEC17025*12 に準拠した品質管理システムを確立し、バックグランド測定、ブランク測定等の品質保証の行き届いた運用管理を行うとともに、CTBTOが主催する国際比較試験においても良好な分析結果を得ている。2006年11月に認証を取得した同施設は、年間約20サンプルの分析を依頼されており、1サンプルに調整準備期間を含め約2週間要することから、年間フル稼働状態である。
(4)国内データセンター
世界中のIMSから得られるデータを受信、解析評価し、我が国が責任を持ってCTBT遵守に係る判断を行うに際し、必要な技術的評価結果を行うこと、このために、ガンマ線解析技術や放射性希ガス等が観測された監視観測所から放出源推定を行い、地震観測から得られた震源地との整合性を調べる大気拡散バックトラッキング等の技術開発を行っている。2008年までに基本機能の整備を完了し、2009年4月から暫定運用を開始している。
(5)北朝鮮核実験時の対応、今後の課題等
JAEAでは臨時体制を組んで、北朝鮮周辺の6ヶ所の放射性粒子監視観測所及び3ヶ所の放射性希ガス監視観測所についてのデータ解析を3週間連続して実施し、震源地情報をもとに大気輸送計算を行った。JAEAの今後の課題として、放射性粒子・希ガスによる検証技術開発、全地球的な高品質データの有効利用、CTBT国内運用体制の適切な実施が必要。
*12ISO/IEC 17025:品質管理で有名なISO9001をベースに、試験所・校正機関に対する固有の要求事項を付加した国際規格。試験所・校正機関の能力を、認定機関が認定する際の基準として利用される。
3.技術セッション(13:10 - 14:45)
○「核実験監視に係わる放射性核種監視の現状」
原子力機構 核不拡散科学技術センター 技術主幹 小田哲三
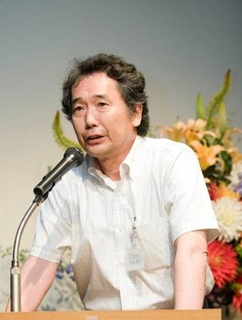
(1)CTBT国際監視制度(IMS)の現状
4つの監視技術を用いた337ヶ所の観測施設によるIMSネットワーク、IMSの設計指針、監視技術別認証数、主要国別認証数、認証済み/稼働中の放射性核種IMSに関する概況、1キロトン*13 以上の核爆発を地球上どこででも90−95%と言う高検知確率で1000km2以内の位置精度で検出するためにIMSネットワークが設計されていること、各締約国が条約遵守について評価できるように平等に適時にデータ提供されること、6月末現在で全IMSの73.3%が認証済みで観測点の多い主要国では中国とロシアの整備が遅れていること等を説明。
(2)放射性核種監視に係わる科学技術
国内監視観測所で稼働している粒子観測装置及び希ガス観測装置、それぞれの概要と動作原理について説明。特に、地下核実験では希ガス監視が重要であることから、現在優先的に整備が進められている希ガス監視ネットワーク、放射性Xeの主な発生源、133Xeの施設別放出量、Xe同位体比による核実験起源かどうかの識別等に関して解説し、希ガス監視観測所40ヶ所中23ヶ所が整備済みであること、世界に3ヶ所ある医療用アイソトープ製造施設からの133Xeのバックグラウンド寄与がかなり大きいこと、新燃料を除けば同位対比から核実験起源であるかどうかを識別可能であること等を強調した。また、監視観測所以外で機構が整備・運用を行っている公認実験施設とNDCに関しても、それらの役割と実施内容、解析に用いている各ソフトウェアの概要、放出源情報推定方法、親娘関係にある核種の同位体比による核分裂時刻の推定等に関して説明した。
(3)データの科学的有効活用
自然放射性核種である212Pbや宇宙線により生成される7Beの濃度の季節変動や希ガスの濃度変動の地域差の解明等から、地球環境科学や大気輸送モデルへの応用が期待できる。
(4)地下核実験と放射性核種の閉じ込め
核実験により発生する核爆発エネルギーに占める放射能に起因するエネルギーの割合、1963年の部分的核実験禁止条約(PTBT)*14 以後に実施された米国の地下核実験723回における放射能閉じ込め割合、サンプリング等を目的とする意図的放出や想定外の閉じ込め失敗例、トンネル型地下核実験における希ガスの漏洩経路等に関しての説明を行った。
(5)北朝鮮における核実験
観測体制や観測結果に関して説明があり、今回の実験に関しての暫定的結論として、地震波形等から人工爆発現象で規模は前回の数倍程度、震源は前回と誤差範囲内で一致、核実験起源の人工放射性核種はIMS監視観測所、米国等のサンプリング専用航空機共に検知されていないこと等を報告した。
*131キロトン:代表的な通常爆弾に使われるTNT(トリニトロトルエン)爆薬1キロトンの爆発で放出されるのと等しい
*14部分的核実験禁止条約(PTBT:Partial Test Ban Treaty):1963年8月に米、英、ソ連との間で調印された核兵器の一部の実験を禁止する条約。地下を除く大気圏内、宇宙空間及び水中における核爆発を伴う実験の禁止を内容としている。
○「CTBT現地査察制度(OSI)整備の現状と課題」
日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター 研究員 一政祐行氏

(1)OSIの現状紹介
条約上の定義に触れながらCTBT検証制度の"Last Resort" *15とされるOSIレジームについて説明し、今回の北朝鮮の核実験のように放射性核種がIMSで検知できなかったような場合に、最終的に核実験が行われたか否かを確認する手段として、特にOSIの重要性が高まることを指摘した。OSIレジームの整備ではOSI運用手引書を中心に査察手法や査察機器の開発、査察員研修等があるが、CTBT検証制度全体の中でこれら(特に運用手引書)の整備の遅れが顕著であることを指摘。政治的側面、法的側面、意思決定の側面、手続き的側面、技術的側面という5つの観点からOSIレジームの特徴を説明した。OSIを巡るこれまでの主要な争点として、運用手引書作成に係わる問題、条約未発効状況下でのPTSのOSI実施能力整備の問題、査察機器の調達・更新/査察員育成問題、米国の撤退と復帰等を中心に、各々の問題点を明らかにした。
(2)CTBTO準備委員会と署名国のOSIレジーム整備の取り組み
国家主権と国際公益の対立構造や、国の検証技術(NTM)の運用、国家安全保障に直結する秘密情報の扱いなどを巡りOSIが政治問題化してきたことを解説した。主要関心国の取り組み姿勢の違い等を明らかにした。
(3)条約発効までにOSI実施準備を完了するための課題
現時点のPTSにおけるOSI準備態勢(Readiness)の評価や、今後OSIの実施能力をどのように高めるか等の問題点について紹介した。その上で、長期的視野に立った査察員の育成・確保、査察機器の開発・調達を円滑に行うための署名国による現物供与方式の工夫、より効果的・効率的な査察手法開発のために、5核兵器国の地下核実験の実施経験をPTSにフィードバックさせるアプローチ等、OSI準備態勢とOSIの実施能力向上のための各種提案を行った。最後にCTBT発効促進とOSIレジーム整備を巡る様々な課題を踏まえて、(1)日本、(2)国際社会、(3)PTS、それぞれに対する短期的・中長期的視野に立った政策提言を行った。
*15最後の手段(Last Resort):核実験が行われたと推定される現地において、掘削を含む各種査察技術を用いて検証活動を行うことから、CTBTに対する違反の有無を調べる「最後の手段」と呼ばれる。
4.パネル(1) 科学技術的側面に関する議論(放射性核種を中心に)(14:45 - 16:15)

- モデレータ:
- 篠原伸夫氏 (東京大学大学院工学研究科 原子力国際専攻 客員教授)
- パネリスト:
- 磯貝啓介氏 (日本分析センター 分析業務部次長)
- 小田哲三 (原子力機構 核不拡散科学技術センター 技術主幹)
- 清水正巳氏 (日本経済新聞社 論説委員)
- 深澤哲生氏 (日立GEニュークリア・エナジー㈱)
- 山澤弘実氏 (名古屋大学大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 教授)
(1)パネル1の概要
CTBTO準備委員会が設立され13年が経過し、国際監視制度(IMS)は約80%が整備完了して既に運用体制に移行しつつあり、実質的な「監視体制」と「核実験抑止能力」が確立されつつある中で、地球規模で得られるデータの科学的応用や災害監視等への有効活用も始められている。IMS及びNDCが暫定運用体制に入った我が国においても、CTBTの早期発効を推進し、アジア地域及び世界の核軍縮をリードするためにも、科学技術的な側面からのCTBT検証技術への貢献を積極的に進めることは重要である。上記認識の基に、本パネルにおいては科学技術的側面より、現在の国際監視制度の技術的課題及びデータの活用等について、放射性核種観測を中心とした議論を行った。 まず、モデレータおよびパネリストからそれぞれの経歴や現在従事している仕事等に関する自己紹介の後、核実験の検知能力は十分か、放射性核種監視の重要性、最新技術をいかに取り入れていくか、観測データの有効利用、という主に4つのテーマに関連したシンポジウム参加者からの質問を基に、モデレータが問題提起する形で議論を進めた。
(2)核実験検知能力
今回の北朝鮮の核実験で放射性核種が検知されなかった理由、IMS監視観測所数は十分か、といった問題提起。これに対して、1回目の核実験(2006年10月)ではIMSおよびその他の手段により検知しており、今回の核実験では閉じ込めが(意図的に、あるいは偶然に)うまくできたことにより地上に漏れ出なかった、あるいは漏れ出しはしたが気象条件や放出条件によって、監視観測所では検出限界以下であったと推定されるとの話があった。また、監視観測所を増やしより観測ネットワークを密にすれば検知確率は上がる、国内の希ガス観測点を増やせると良い、可搬型サンプラーを使用して大気輸送モデル(ATM)*16予測地域で観測することでより検出確率を高められる、それをCTBTの枠内でできないかといった意見があった。
(3)放射性核種監視
ATMの信頼性について議論があり、地下核実験では放射性核種の放出パターンは外部からは分からないので推測するしかないが、今回の北朝鮮の核実験における解析結果から分かるように、これが実際のパターンに合っていると仮定したATMの解析結果を過信するのは危険ではないかと言う意見が出た。これに対して、現在のATMソフトウェアは、いつ放出されたかが分かれば、量的なものを考慮しなければかなりの確度で放出物の移動予測が可能であること、また、観測事実として、放出源に近い場合、放出物の分布はあまり拡散せずに固まりに近い形で分布する傾向があること等が紹介された。
(4)最新技術のCTBTへの適用
今回の核実験のように実際に核実験だったのかどうかが技術的に証明できない状況では政治的な動きに繋がってしまう恐れがあるので、CTBTの監視技術できちんと捉える技術開発を行って欲しい、一例として岐阜県のスーパーカミオカンデにおける核実験時のニュートリノの観測といった非常にユニークな案が提示された。また、希ガス観測について、検出限界は既にバックグラウンドレベルまで来ており、これ以上の感度向上を図るより観測所数を増やす方が効果的、他の技術導入の検討も必要であるとの意見や、こういった技術の問題を整理して、一般に知らしめていく努力も必要との意見もあった。
(5)観測データの有効利用
CTBTのIMSネットワークは、品質管理された高精度かつ高信頼度のデータが地球規模で毎日得られるこれまでにないシステムである。放射性核種の観測データでは、日常的に検知される自然放射性核種を対象とする研究も有効であり、広範囲の地域から得られるIMSデータを利用することで国内独自観測において通常の変動を超えた観測値が得られた場合にその原因が特定できる可能性、フィルターには放射性核種以外にも花粉や塵等が付いているので環境研究に有効、原子力災害時の広域モニタリングへの活用、このような言わば雑音の中にはいろいろな情報が詰まっており放射性核種観測データのバックグラウンドからいかにそのような情報を取り出し活用するかが重要、他の科学分野の人々との交流が大切等の意見が出された。また、観測データに対してどのようにアクセスできるのかといった質問に対しては、IDCのレギュラーユーザー・アカウントを取得すれば自由に利用でき、CTBTO準備委員会でもそうした科学的利用の広報を行っているとの回答があった。
*16大気輸送モデル(ATM:Atomospheric Transport Modelling):核実験後の大気環境中を拡散する放射性核種の飛散状況を気象データを用いて計算する数値シミュレーション方法
5.パネル(2)政策的側面についての議論(16:20 - 17:50)

- モデレータ:
- 阿部 信泰氏(日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター所長)
- パネリスト:
- 秋元 千明氏 (NHK解説委員(軍事・安全保障担当))
- 浅田 正彦氏 (京都大学大学院 法学研究科 教授)
- 香川 美冶氏 (CTBTO準備委員会 事務局長特別補佐官)
- 水本 和実氏 (広島市立大学 広島平和研究所 准教授)
- 森野 泰成氏 (外務省 軍縮不拡散・科学部 軍備管理軍縮課長)
パネル(2)の概要
本パネルでは、各パネラーがCTBTに関する政策的側面について予め設定された話題について、最初に各パネラーから意見を述べるという形で進行した。設定された話題としては、CTBT発効に向けた政策課題、米国のCTBT批准に向けた動向と各国の政策、未批准の発効要件国とそれぞれの地域情勢を踏まえた解決策、アウトリーチ活動の必要性が取り上げられた。
○秋元氏:
米露首脳会談での軍縮合意とその評価:7月7日、オバマ大統領とメドベージェフ大統領は、STARTⅠ*17 の後継条約の締結に向け、核弾頭及びICBM*18 等の運搬手段の削減に合意した。この合意内容については新聞等でも評価が分かれるが、実態は核兵器のほぼ現状維持の合意・追認であり、小さな軍縮合意で大きな核不拡散を目指した米露の演出の感が否めない。
軍縮合意の背景:露国の課題は老朽化した核兵器の廃棄と近代的な新型核兵器への転換。露国としては国防費の削減を余儀なくされている一方で、核兵器削減には米国とのバランスが必要。もし、露国が米国と核兵器削減で合意できれば、老朽化した核兵器は外国からの財政的支援で廃棄でき、浮いた分で新型核兵器を開発できる。一方、オバマ大統領も新政権の政治的得点として4月にプラハで「核のない世界」と核軍縮をアピールした。今回の米露合意は露国の政治的状況と米国の政治的思惑のベクトルが一致したもの。
米国のCTBT批准に向けた動き:オバマ大統領はプラハ演説でCTBT批准の追求を表明した。批准には上院定数の2/3(定数100の2/3で67名)の同意が必要だが、現在の上院民主党議員数は60、したがって共和党との「取引」が必要。取引材料は露国同様に「新型核兵器の開発」の可能性もある。総じて米国のCTBT批准も核軍縮も将来的にどうなるか分からない。オバマ大統領自身、軍縮を唱えつつ必要な核兵器は維持すること、また自分が生きている間の核兵器全廃は無理と認めている。そもそも核軍縮は長期的な視点でこれを見る必要があり、大統領が使うレトリックにおぼれず、クールな見方が必要である。
○浅田氏
CTBTの発効・未発効の意義:現在CTBTは未発効だが、意味がないというわけではない。未発効でもCTBTに署名・批准すれば核実験はできないとの解釈が少なくとも日米両国ではなされている。CTBT自体は発効していなくとも、すでに一定の効果を有しており、この観点からは、条約の発効/未発効にそれほどこだわる必要はない。問題はむしろ発効/未発効よりも問題国がCTBTに署名していないことだ。
CTBTの検証体制:既に核実験が行われたことのある場所で再度、核実験が実施されたら、かなり小規模であっても探知・検証が可能といわれる。まったく新しい場所での核実験の場合、それを探知・検証するために同様の精度が必要との見解もありうるが、核兵器の保有を標榜する国は核実験を公表することでそのことを誇示しており、新たな場所での探知・検証の精度はそれほど高くなくてもかまわないと思う。一方、5月の北朝鮮の核実験では、実施場所が判明しているにも拘わらず希ガスは観測されておらず、別の観点からいささかショックを受けた。以前は、CTBT未発効の下での国際監視制度(IMS)でもかなりの検証効果が期待できると考えていたが、今回のようなことがあると、やはり現地査察(OSI)が実施できることが重要であり、条約の発効が必要だとの意見に傾くことになる。
発効前の条約改正:条約が発効するまでは条約の改正ができず、したがってモニタリング・ステーションの数は増やせないといえばそうではなく、発効前でも条約の改正は法的には可能。
○水本氏:
核軍縮とCTBTへの理解促進、アウトリーチ活動:午前及び午後の最初のパネルでは、CTBTにつき技術・専門的な議論が行われたが、一方でグローバルな核軍縮をどう進展させるかという全体の目標を視野にいれておくことも重要。プラハで核のない世界と核軍縮、CTBT批准の追及を訴えたオバマ大統領の広島訪問や2010年NPT運用検討会議により核軍縮・核廃絶が進展するのではないかとの期待もあるが、不確実な部分がある。クールで現実的な視点が必要。
核軍縮を進展させるためには、NPTとCTBTを車の両輪、あるいはIAEAも含めて3本の柱を効果的に機能させ、これらを、核軍縮義務を普遍的に課すためのツールとして生かすことが重要。また、CTBTがグローバルな核軍縮に貢献しているという認識を国際社会が共有し、市民がCTBT未批准国の動向を監視する雰囲気を作りだすことがCTBTの現実の政策面の議論の後押しとなり、実際の核軍縮にも繋がるだろう。インターネット等を通じてCTBT発効に向け、各国や市民にもっとアピールすることが必要であり、外務省にも更なるアウトリーチ活動を期待する。
○森野氏
CTBT発効要件国の状況:CTBT発効には、9つのCTBT発効要件国(米国、中国、インドネシア、エジプト、イスラエル、イラン、インド、パキスタン、北朝鮮)の署名・批准が必要で、うち米国の批准が最も重要。批准には米国上院議員の2/3(67票)の条約承認が必要で、民主党分60票に加え更に7つの共和党票が必要だが、共和党はCTBT批准に反対しており、その根拠は、(1)核実験を行うことなく核兵器の安全性・信頼性を確保できるか、(2)CTBTの検証能力は十分か、(3)米国が批准後に他の未署名・未批准国が追随するかの3点。
米国での議論の論点と現状:(1)については確保出来る・出来ないにつき論争が続いている。オバマ政権は、信頼できる代替核弾頭(RRW)*19 の予算を要求していないが、核備蓄管理プログラムは継続するとの意向。CTBT賛成派は、上記プログラムで足りると主張するが、果たして議会を説得できるに足る説明ができるのかは疑問。(2)については、二つの課題があり、一つはCTBT未署名・未批准国内でのIMSのモニタリング・ステーションの設置であり、現段階では未署名国のインド、パキスタン及び北朝鮮の内、パキスタンにおけるモニタリング・ステーションは未整備、未批准国ではイランを除きモニタリング・ステーションの設置のための作業中である。もう一つの課題は放射性核種(サブキロトン)の検地可能性で、検地されない場合はOSIが重要な手段となるが、条約が発効しなければOSIの実施は難しい。検証制度の見直しについては、改善の必要性も言われており、今後、ウィーンで議論されるはずである。
米国以外の8つの発効要件国の状況:状況の概要は以下の通り。総じて各国はお互いの状況を窺っているようである。
| 国名 | 状況 |
|---|---|
| 中国 | 2000年に人民会議に提出されているとの説明のみ。 |
| インド | 08年9月、NSG(原子力供給国グループ)が、インドをロンドン・ガイドラインの例外とする決定を行うのに際し、インドは核実験モラトリアムの継続を表明(NSGを通してインドにCTBT署名・批准の圧力がかけられた) |
| パキスタン | 核実験モラトリアムを継続しているが、南アジア(インドを暗示)との関係改善が必要と指摘 |
| イスラエル | CTBTの批准を促進する要因として、(1)OSIを含む検証制度の準備、(2)中東・南アジアにおけるイスラエルの公正な地位、(3)中東諸国によるCTBT批准・遵守の必要性、を列挙 |
| エジプト | イスラエルのNPT批准とリンクさせている |
| イラン | CTBT発効促進に関する核兵器国の責任、NPT未加盟国の加盟・批准の重要性を指摘 |
| インドネシア | 米国が批准したらインドネシアも批准する旨を言及 |
| 北朝鮮 | 言及なし(国連安保理決議1874は北朝鮮のCTBT批准を要請) |
発効促進への対応策「発効促進プログラム」等:政府の取り組みとしては二つある。一つ目は今年4月の中曽根外相の「ゼロへの条件―世界的核軍縮のための11の指標」でも述べられた「発効促進プログラム」で、発効要件国に早期のCTBT批准を働きかけることと、グローバルな検証制度の整備に貢献することを目指す活動である。後者では、検証制度構築への技術面・資金面での協力や国連総会での核廃絶決議案の提出を行っている。二つ目は国内体制整備の必要性で、検証システム構築に関して関係省庁・研究機関が連携するとともに、今後は検証技術の開発の観点から民間企業との協力を考えてもよいと思う。今後もCTBTをもっと盛り立てていくため、日本の英知を結集し役立てていくことが重要で、本日のセミナー開催にも感謝する。
*17STARTⅠ(Strategic Arms Reduction Treaty Ⅰ):第一次戦略兵器削減条約、1991年に米国とソ連との間で結ばれた軍縮条約の一つ。
*18ICBM:(Intercontinental Ballistic Missile):大陸間弾道ミサイル、有効射程距離が超長距離で北アメリカ大陸とユーラシア大陸間を飛翔できる弾道ミサイル
*19信頼できる代替核弾頭(RRW:Reliable Replacement Warhead):単純で信頼性が高く長期使用が可能、メンテナンスが容易な次世代核兵器の開発調達計画。
○質疑応答:
- 質問1:今年5月の北朝鮮の核実験に関し、CTBTOは検証能力を証明したと言っているが、高崎では希ガスは観測されなかった。これで検証能力を証明したということになるのか?
- 回答1(香川氏):条約上の検証能力の限界を理解して欲しい。CTBTOの役割は、各モニタリング・ステーションからのデータを収集・分析して加盟国に提供すること。しかしそこから一歩踏み込んで、データをもとにOSIを行い、核実験を本当に行ったのか否か、したがって条約違反であるのか否かの最終的な判断は、締約国に任されている。CTBT発効以前に検証能力を評価するのは順序が逆で、このような議論をすること自体、発効を遅らせたいと意図する人に格好の批判材料を提供することになり、その点を危惧している。
- 補足1(阿部氏):今回の北朝鮮の核実験のケースを考えれば、人工的な地震波を起こすのは難しく、現実的には北朝鮮は核実験を実施したと考えられ、安保理でも制裁決議がなされた。CTBTがすでに発効しているとしても、執行理事会はOSIを決議していると推測する。
- 質問2:CTBTO準備委員会・暫定技術事務局(PTS)の負担を減らすために、例えば日本にアジア地域のCTBTOオフィスを設けてはどうか?
- 回答2(森野氏):CTBTO地域センター(regional center)を作るのはよい意見だが、先立つもの(資金)が欲しい。CTBTの検証制度が威力を発揮するのはごく限られた瞬間に過ぎないが、その瞬間のために多大な投資が必要で、例えば技術情報の共有やコストの効率的・効果的な活用が必要であり、それが課題であろう。
- 質問3−1:CTBTは発効前でも条約を改正できるだろうが、CTBTを推進していくために改正がプラスとなるのかマイナスとなるのかを考える必要があると考える。この点をどう考えるか。
- 回答3−1(浅田氏):モニタリング・ステーションの数を増やすための条約改正がCTBT発効の妨げになるとは考えにくい。検証を潜り抜けようと考えている国はそもそもCTBTを批准しないだろう。むしろ、CTBT発効推進や特にCTBTそのものにとって有害なのは条約の暫定適用である。その理由は、(1)条約が発効しなくても核実験の禁止等、CTBTはすでに一定の義務を課し、また検証上もある程度の効果を発揮しているが、暫定適用のメカニズムを導入するとした場合、批准国すべてがそれに参加するかは分からない、批准国の中から脱落者が出ればそれらの国の条約へのコミットメントの評価を下げることになる。(2)暫定適用の下でOSIを実施するとなると、既存のCTBTの組織とメカニズムとは別の暫定適用のためのOSIの組織とメカニズムが必要となるが、場合によってそれはCTBTそのものの交渉と同様に困難な作業となるかも知れない。また(3)暫定適用に同意するのは、いわゆるGood boy(模範国)であり、北朝鮮、インド、パキスタンなどが入っていない段階での暫定適用は、Good boy間でのOSIということにもなり、意味がない。そもそもCTBTはGood boyでない国が入らないと条約の意味がなく、だからこそそれらの国が入らない限り発効しないという制度になっている。暫定適用はその意図に反する。つまり、CTBTへの署名・批准が重要なのは核兵器国とNPT未加盟国であって、このような国が入っていないにも拘らずCTBTを暫定適用しても意味がない。
- 質問3−2:条約を改正せずモニタリング・ステーションの数を増やす手はないか。例えば北朝鮮の核実験とリンクさせて国連決議を出すのはどうか。
- 回答3−2(浅田氏):他の方法で対応可能ならわざわざ条約を改正する必要はない。
- 質問4:二点述べたい。(1)5月の北朝鮮の核実験で希ガスを観測できなかったなら、その理由の解析をしっかりやるべきで、技術的に何故観測できなかったかを明確にすべき。(2)悲観的な見方かもしれないが、核兵器の廃絶を目指す「グローバル・ゼロ」が無理なのは明らかで、これに変わるものがCTBTであり、その意味でもCTBTとその検証体制は必要不可欠。核実験が頻繁に行われるものでないためCTBT不要論もあり、IAEAのような査察官の常時待機も難しいが、何等かの体制は必要だろう。実効的なCTBT検証制度の確立のために、日本政府の尽力をお願いしたい。
- 回答4−1(香川氏):そもそもCTBTの検証制度は秘密裡の核実験の探知・検証を想定しており、核実験を表明した北朝鮮のケースは想定外。その例外的なケースの探知が技術的にできないからといってCTBTの検証能力に疑問を投げかけるのは拙速ではないか。CTBT発効前の現時点で検証能力につき、CTBT自体が非難されるのを懸念する。
6.開会挨拶(17:50 - 18:00)
日本原子力研究開発機構(JAEA)理事:岡田漱平

(1)講演者及びパネラー等への謝辞
朝から丸一日を掛けたシンポジムにおいて、講演をして頂いた方、パネルでのモデレータ及びパネリストの方、一日中熱心に聴講して下さった出席者の方々に感謝申し上げます。CTBTに係る技術的課題から政策的課題に到るまで幅広く議論して頂くことで、我が国のCTBT運用体制の現状について理解を深めて頂けたのではないかと思う。
(2)ニュートリノの応用
ニュートリノは核実験の核反応によって発生し、地球をも突き抜けて観測することが出来る。通常の原子力発電所の運転によっても発生するので識別する必要があるが、ニュートリノ観測を核実験の探知技術として適用出来ないか。非常にお金が必要となることは間違いないが、原子力機構はJ−PARCのような高エネルギー加速器の分野でも研究開発を行っており、核不拡散分野と原子核分野との専門家との間で有益な情報交換が行われることを期待したい。

(文責 核不拡散科学技術センター)
