「核不拡散と原子力の平和利用」*
この報告は、シンポジウムでの講演やパネルディスカッションを事務局が取り纏めたものであり、講演者やパネリスト本人の確認を受けているものではなく、その発言は、個人としての発言であり、国や組織を代表したものではない。また、脚注は、事務局が参考として付したものである。
開会挨拶
岡﨑 俊雄 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長

核不拡散問題は、国際政治の中で位置づけられるべき問題である一方、保障措置の適用や核拡散抵抗性技術の開発など、技術的アプローチも必要であり、本シンポジウムを日本国際問題研究所(以下「国問研」)と当機構が主催することにより、これまで以上に広がりのある議論が展開できる。
Atoms for Peace* 1の時代より核兵器拡散の問題が指摘され、原子力平和利用と核不拡散をいかに両立させるかが議論されてきた。近年は、核燃料サイクル施設の国際管理や燃料供給保証などの議論が活発に展開されている。
核拡散の懸念が増大する中、アジア地域を中心に平和利用が大きく拡大するという背景がある。その一方、NPT* 2を中心とする体制が核拡散防止に大きな役割を果たしてきたが、既存の枠組みだけでは対応が困難になりつつある。
日本は唯一の被爆国として国際社会に対して核廃絶を訴える一方で、平和目的に限って、原子力平和利用を推進してきた。核不拡散との両立により平和利用が国際的に推進されることに日本は大きなステークを有している。洞爺湖のサミットにおいて、核不拡散、原子力平和利用がテーマとして取り上げられるであろう。議長国としての日本がメッセージを発信するにあたり、何等かの素材を提供する場になればと期待している。

注釈
* 1Atoms for Peace:昭和28年の米国アイゼンハワー大統領の国連総会での演説(いわゆる「平和のための原子力(Atoms for Peace)」)
* 2NPT:核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)
基調講演「シンポジウムの背景等について」
遠藤 哲也 元原子力委員会 委員長代理

シンポジウムの狙い及び意義について
洞爺湖において日本が議長国となってG8サミットが開催される。このサミットにおける最大の議題は地球温暖化になるであろうが、その中で原子力の平和利用を取り上げてもらいたいと考えている。
そのために、国問研は原子力に関連する各分野の専門家を集めてタスクフォースを作り、NPTの3本柱、平和利用、核不拡散、核軍縮に関する総合的なアプローチについて構想してきた。この成果を取りまとめて日本政府に提言したいと考えている。昨日、その検討の一環として海外の専門家を集めて協議を行った。その機会をとらえ、なるべく多くの方と知識情報を共有したいと、このシンポジウムを開催することとなった。
原子力には様々な側面があるが、その重要性は高まっている。アジアを中心とするエネルギー需要の増加、石油等の価格高騰などから原子力に関心が高まり、原子力ルネサンスの時代が到来しつつある。同時に地球温暖化が世界最大の関心の一つであり、炭酸ガスを放出しないクリーンエネルギーの側面からも原子力への関心が高まっている。
これらは光の部分であり、原子力には影の部分もある。核の持つ巨大な破壊力、その影の部分が世界的に拡散の傾向にあることが懸念される。原子力は安全の問題、高レベルの放射性廃棄物の処分も避けて通れない。われわれに与えられた課題は光の部分をどう伸ばし、影の部分をどう押さえ込むか。
G8は世界での圧倒的な力を持つグループであり、NPTが岐路に立つ現在、G8の責任は大きい。G8の議長国として日本が核の問題に対する何等かの新しいアプローチ、Atoms for Peaceの現代版を提案できないかと思っている。
原子力の三要素:核軍縮、不拡散、平和利用について
原子力の平和利用は、NPT第4条にあるように、「奪い得ない権利」である。しかしこの権利は野放図な権利ではなく、NPTやIAEA保障措置をしっかり遵守するという前提に立つ権利であると認識する。現在原子力を導入したいという国がアジアや中東、ラテンアメリカなどで増加している。これ自体歓迎すべきであるが原子力平和利用の拡大に伴い、拡散のリスクも増大する側面もある。そこで、原子力を導入しようとする国には、3つのS、すなわち、Safety(安全)、Safeguards(保障措置:不拡散)、Security(核テロ、核物質防護)の分野における基準を満たすことを要求し、それを守る国に対しては原子力発電導入を支援するべきであろう。それに加えて、たとえば、原子力損害賠償責任問題(Liability)、放射性廃棄物や使用済燃料処分の問題などへの対応策も整備し、そうした条件を満たせば、国際社会として金融面についても、技術協力にしても支援するようにしたらどうだろうか。
環境と原子力の関係については、現在の地球温暖化対策の中で原子力はCDM* 3の適用外である。炭酸ガスを出さない原子力の導入プロジェクトに関し、現在は、支援国の炭酸ガスの排出量削減にカウントされていないことになっているが、それを何とか変えたい。原子力についても前向きに扱えるようにしたいと希望している。
核不拡散については、北朝鮮やイランなど大きな問題になっている。また、NPTそれ自身不備の点が出てきている。そうした不備を補い強化していくべきであろう。補強の策としては、まず保障措置を強化する追加議定書の普遍化を目指すべきで、そのためのアメとムチについて議論していくべきである。核燃料サイクルを国際的にどう規制していくか。エルバラダイ構想* 4やブッシュ提案* 5、6ヶ国提案* 6など、核燃料サイクルの国際管理や機微技術の移転の制限に関する提案が出されているし、それと同時に供給保証についての議論が始まっている。将来その方向に向かって検討が進むとみられるが、燃料供給保証スキームについて、これが本当に核不拡散に役立つのかどうか見極め、対応する必要がある。そのほかNPTからの脱退の問題、不遵守の際の国連安保理による対処のあり方などの課題がある。
これまでのG8サミットの文書には原子力問題は触れられているが核不拡散問題に集中している。核軍縮問題はほとんど触れられていない。日本が議長国として開催される来年のサミットでは、核軍縮の問題についてもぜひとも取り上げてもらいたい。NPTの3本柱の関係の中で、核不拡散を進めるためには核軍縮を進める必要があるのではないか。核軍縮に中心的に取り組むべき国は米露であり、モスクワ条約、START Iで枠組みが規定されているが、これが2012年になくなるので両国の間で新しい枠組みを作ってもらいたい。また、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効のために米国が前向きな態度を取ることを希望する。核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)についても早期交渉開始を期待している。
タスクフォースとしてはこの提言を今年中にとりまとめ、日本政府に提出し、各国に協議をして我々の考えをサミットの議論・宣言に反映させたいと希望している。


注釈
* 3CDM(Clean Development Mechanism):国連気候変動枠組条約の第3回締約国会議(COP3)(1997年12月)において採択された「京都議定書」で規定された市場メカニズムを活用する柔軟措置の一つ。非付属書Ⅰ国(途上国)で温暖化対策のプロジェクトを行い、当該プロジェクトを実施しなかった場合と比較して、追加的な排出削減があった場合、その排出削減量に対してCER(クレジット)が発行され、プロジェクトの実施によって得られたCERを付属書I国(先進国)の排出削減目標達成に用いることができる。
* 4エルバラダイ構想:ウラン濃縮や再処理は多国間管理の施設のみで行なうようにする。(2003年10月エコノミスト誌)
* 5ブッシュ提案:2004年2月国防大学での演説、ウラン濃縮と再処理技術の取得を放棄した国に合理的な価格で核燃料の供給を保証すべき。
* 6燃料供給保証に関わる六カ国(仏、独、蘭、露、英、米)提案:濃縮役務及び濃縮ウランの提供に焦点を当て、(1)市場原理による供給、(2)IAEAのエンドースによる供給保証、(3)一部の国による備蓄の3層の燃料供給保証体制を構築。
基調講演「原子力と核不拡散」
ジェームス P.ティンビー 米国国務省 軍備管理・国際安全保障担当次官付上級顧問

地球環境・エネルギー安全保障面からの原子力の必要性
現在、多くの国が原子力を導入しようと考えている。20以上の国が、将来のエネルギー需要を満たすために原子力の利用を検討している。環境の面でも、化石燃料が公害や温暖化を引き起こす一方、原子力は比較的クリーンである。
拡散のリスク
原子力の平和利用の拡大が、核兵器の製造につながるような機微な燃料サイクル技術の拡散につながってはならない。昨年7月に行われた、ブッシュ米大統領とプーチン露大統領の首脳会談では、核不拡散や核テロの問題について触れられており、将来のためのビジョンを提示した。
米露首脳が共有する目標は、今や機微な燃料サイクル技術の拡散を防止し、それに代わる平和利用促進のアプローチを作る事である。6ヶ国の濃縮国によって2006年5月には燃料供給保証について提案がなされ、米国政府は17トンの高濃縮ウランをLEUに希釈してリザーブすることを提案し、NGOのNTI* 7は、濃縮ウランの備蓄をIAEAが管理すべきという提案を出している。また、ロシアはアンガルスクに国際核燃料センターを構築する構想を示し、また、日本も供給保証登録制度の提案を出している。その他にも、英国の濃縮ボンド提案など、多くの提案が出されている。そして、このような提案について集中的な議論をするIAEA総会特別イベントが昨年9月に開催された。さまざまな議論をもとに、エルバラダイIAEA事務局長は詳細な報告書を出し、枠組みを提案することになっているが、今はもはや具体的な提案を行動に移す時期に来ているといえよう。
国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)は、2006年2月に発表された先進的な燃料サイクルや高速炉、核拡散抵抗性の高い再処理技術や保障措置技術などを開発するための多国間の技術協力の枠組みである。閣僚級会合が今年9月にウィーンで開催され、参加国は16カ国に拡大した。今後はさらに多くの国が参加するであろう。技術面からの核不拡散アプローチとして、革新的原子炉及び燃料サイクルに関する国際プロジェクト(INPRO)や第4世代原子力システム国際フォーラム(GIF)などの様々な努力を挙げることができる。
米露は、他国とも協力し、原子力を導入しようとする国に魅力的なオファーをする必要性がある。拡散抵抗性の高い原子炉の提供、燃料供給の保証、使用済燃料の管理、インフラ支援、安全文化の協力、財政的な支援、これらの具体的なアプローチを展開していくことが重要である。たとえば小型の原子炉の導入などがあげられよう。燃料へのアクセスの確保と同時に、使用済燃料処分の問題の解決策を見つけ出すにはまだ遠い。まず多国間で解決を模索すべきで、IAEAはインフラ支援や技術協力を提供するなどの役割がある。また、財政的な支援についても議論すべきであろう。供給国も受領国と対話をし、議論を深めることが大事である。
受領国への協力においては、受領国は競争的なオファーの中からパートナーを選ぶ権利を与えられるべきであり、一方、供給国と受領国の間で協力の条件となるのは安全、セキュリティに係る措置がしっかりできているかという点などであろう。また、受領国にとってより魅力的なオファーにするためには、ライセンシングのあり方を検討したり、安全規制訓練の提供などを含めて行なうことも良いであろう。つまり、供給の保証の代わりに安全などの国際的な基準を満たしつつ核燃料サイクルは追求しないというバランスのとれたコミットメントに導くためには魅力的なオファーが必要であり、現在そのような協力の在り方について構想の初期段階にある。
今の核燃料市場は十分魅力的でありその市場が燃料を提供しているということを理解してもらいたい。それにもかかわらず、また投資に要するコストにかかわらず独自の核燃料サイクルを追求しようとする国がある。こうした国に対して、インセンティブを提供し、イランの真似をさせないようにすべきであろう。
イランは20年以上もIAEAの保障措置に違反してきた。現在のイランの活動に透明性を高めることは重要であるが時間はかかるであろう。イランのIAEAに対する協力は不十分であり、IAEAとの間で合意されたWork Plan* 8は不十分である。
原子力の活動は国際社会との協力のもとで実施されるべき。機微技術を自ら追求するのではなく。最も魅力的な案を我々が提示できるようにするべきである。

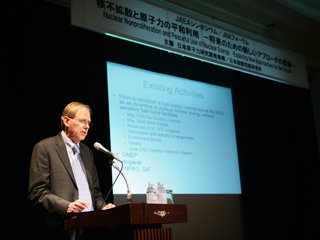
注釈
* 7NTI:Nuclear Threat Initiative、核兵器、生物兵器、化学兵器の使用と拡散のリスクを削減するために活動する米国の非営利組織
* 8IAEA INFCIRC/711 Aug. 27 2007
基調講演「原子力平和利用と核不拡散との両立を確保するための取組」
岡﨑 俊雄 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長

原子力平和利用の国際的潮流
地球温暖化について気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次評価において、地球温暖化は疑いのないものであり、加速しているということが示された。気温の上昇の多くが、人類を起源とするCO2などの温室効果ガスの増加によるもので、これが続けば気候に多くの影響を及ぼす。今後、温室効果ガスの排出が上昇し続けるとすると、今世紀末には地球の平均気温は、1.8〜4度、上昇するという試算がある。
また、近年の原油価格の上昇等、エネルギー確保の観点からも、原子力の役割について真剣に検討していく必要がある。最近の世界各国の原子力計画を概観すると、米国では新規の原子炉建設の動きが加速しており、今後数年間で、32基の原子炉の建設運転許可の申請がなされる予定になっている。欧州では、新規の原子炉の建設は途絶えていたが、フランスやフィンランドにおいて欧州型の加圧水型軽水炉が建設されている。一方、アジア地域においては、中国、インドが原子力発電を飛躍的に拡大する予定であり、インドネシア、ベトナムなど東南アジア諸国においても、近い将来の原子力発電導入の動きが計画されている。こうした状況は「原子力ルネサンス」と称することができるものである。
また、一方で、GIFやGNEP、INPROなどの国際協力の動きも活発になっている。国際的な取り組みでは日本は積極的な役割を果たしている。
IAEAによる原子力発電の設備容量の将来予測によれば、高位ケースでは、原子力発電の設備容量は、2030年までに700GWと、現在の2倍の規模になると見込まれている。その中で原子力産業にも大きな動きがある。グローバル化の中で3つの大きなグループが形成された。これら世界的な3つの企業グループにおいてはいずれも日本の企業が中核的な役割を果たしている。また、ロシアにおいても原子力産業の再編がなされ、カザフスタンでも国家規模の企業が成立している。
豪州、カナダ、カザフスタンなどウラン資源国でも「原子力ルネサンス」や産業の再編に対応した動きがみられる。自国で採掘されるウランに付加価値を高めるという観点から濃縮への関心が高まり、また、豪州は中国やインドに対してビジネスを積極的に展開しようとしている。また、日本もカザフスタンを含め資源国との関係を強化している。
日本の原子力の平和利用の現状
日本は、唯一の被爆国であり、原子力基本法により、原子力の利用は平和目的に限って実施をしていくということを法的にも規定している。また、1994年から、全面的な核兵器廃絶を目指した核軍縮決議案を国連総会に提出し、国連加盟国の大多数によって採択されてきた。日本の基本的な立場は、平和利用の促進と全面的核廃絶である。
原子力は、エネルギー安全保障面でも環境面でも基幹エネルギーとしての位置づけがなされている。エネルギーのほとんどを海外から依存し、一次エネルギーの50%を石油に、その87%を中東に依存している状況において、エネルギー安全保障という観点から、供給源の多様化に原子力は貢献する。
地球温暖化防止という観点から、安倍首相(当時)は、「Invitation to Cool Earth 50」として2050年までに現状の温暖化効果ガスの排出量を半減すべきと提案した。これを達成するためには、再生可能エネルギーの活用、省エネルギーの推進とともに原子力を活用することが不可欠である。
2005年10月に制定された原子力政策大綱においては、原子力は、基幹エネルギーとして2030年以降も、総発電量の30%から40%を占めるべきこと、核燃料サイクルを引き続き推進すべきこと、2050年までに高速増殖炉を商業ベースで導入することなどを定めている。
日本は、商業規模の核燃料サイクル計画を持つ唯一の非核保有国であり、六ヶ所村の再処理工場は2008年2月の操業開始、高速増殖炉「もんじゅ」は2008年10月の運転再開を予定している。また、日本原燃は、六ヶ所村に、軽水炉用のMOX燃料製造施設の建設を計画しており、現在、事業許可を申請中である。
将来的には、軽水炉を中心とした現在の燃料サイクルから、高速増殖炉を中心とした燃料サイクルへ移行することを想定している。マイナーアクチニドもリサイクルすることにより、環境への負荷を低減するとともに、核拡散抵抗性を高めるシステムの開発に取り組んでおり、その開発・実用化研究の中心を担っているのが日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」)である。2025年には実証炉の実現、2050年には商業炉の導入につなげたい。こうした高速増殖炉サイクルの研究開発にあたっては、高速増殖炉(FBR)サイクル実用化研究開発(FaCTプロジェクト)として、担当省である経済産業省と文部科学省、研究開発の主体である原子力機構、電気事業者、製造事業者が参加する5者協議会の枠組みで調整がなされている。
核拡散抵抗性は、安全性、経済性、環境負荷低減性、資源有効利用性と並んで、FBRサイクルシステムが具備すべき重要な特徴の一つである。
平和利用と核不拡散の両立のためのこれまでの日本の取組
日本が核不拡散に関して、国際的な信用を得るに至った要因として、(1)原子力平和利用の宣言、(2)核燃料サイクルの明白な必要性、(3)原子力計画と活動の透明性、(4)30年以上にわたる核不拡散規範の遵守、(5)核不拡散への積極的取り組み、といった要因をあげることができる。
とりわけ、日本は保障措置を積極的に受け入れてきた実績がある。日本は、1976年に批准したNPTに基づき、1977年にはIAEAと包括的保障措置協定を締結し、原子力施設に対するフルスコープ保障措置を受け入れた。また、1997年にモデル追加議定書が採択された後、1999年にいち早く発効させた。IAEAの日本に対する査察業務量は、2006年には約3,000人日(person-days of inspection)に達している。これは、六ヶ所村の再処理工場の操業開始で増加していくことになるであろう。
また、これまでのたゆまぬ保障措置に対する取り組みへの評価の証左として統合保障措置が適用になったが、統合保障措置の適用により全体として効率化を図る必要がある。
原子力平和利用の推進に伴う責任と日本の貢献
核拡散と原子力平和利用の拡大という2つのトレンドを切り離すことが必要で、そのためにNPTに加えて追加議定書、輸出管理、燃料供給保証・多国間核管理構想等の追加的措置が検討されている。
全面的核廃絶と原子力平和利用を同時追求していくことの重要性を強調したい。全面的核廃絶を達成するには、核兵器国による核軍縮を進展させるとともに、非核兵器国や非国家主体への核拡散を防ぐことの両者が必要。
NPTは核不拡散体制の根幹をなすのと同時に、NPTだけですべての問題は解決できず、NPTの枠外の措置を有効に活用していく必要がある。核不拡散に関しては、大量破壊兵器の拡散を防ぐ実効的取り組みである安全保障構想(PSI)や非国家主体への大量破壊兵器の拡散を防ぐための法的措置を義務づける国連安保理決議1540、原子力関連機器の輸出にあたっての基準を定めた原子力供給国(NSG)ガイドライン、核軍縮についてはCTBT、FMCTといった措置、手段が考えられる。さらに将来の枠組みとして、多国間管理や燃料供給保証の枠組みの構築も重要な手段になりうる。
原子力を推進していく国の責任として、3つのS(Security, Safety, Safeguards)を確保していくことをあげることができる。保障措置(Safeguards)は日本の経験が生かされる分野であるし、原子力安全の分野(Safety)でも、安全のための技術を有しており、また多くの経験もしたので、それを広く活かしていくことが必要。Securityについては、核物質防護だけでなく広い分野で取り組んでいくべき。
また、3S以外の責任として、核拡散抵抗性の高い技術の開発、放射性廃棄物の処分の問題への取組、人材育成(特に安全管理など)への積極的な取り組み、原子力の損害賠償責任体制の整備などがあげられる。ただ、原子力導入に際しての基準として、一方的に押し付ける形ではなく、そうした責任を果たすことに対し、支援をしていくということが大事である。
核拡散抵抗性の高い技術開発は、今後核燃料サイクルを進めていく上で極めて重要になってくるであろう。内在的特徴と外在的措置を合わせて核拡散抵抗性をどう評価するか、総合的な評価体制を確立すべきである。こうした核拡散抵抗性の定義や評価については、Gen. IVやINPROといった国際的フォーラムで議論されている。
日本は、原子力の平和利用の推進と核不拡散の両立のために貢献しうる。具体的な貢献分野として、軽水炉を建設して、運転してきた豊富な経験、人材育成に関する支援や原子力規制のあり方に関する支援等をあげることができる。特に、核不拡散に関しては、これまでの保障措置受け入れや核物質防護措置適用の経験があり、また、核拡散抵抗性技術開発では貢献ができると考えている。
まとめ
エネルギー安全保障、地球温暖化防止の観点から原子力の平和利用の拡大は不可避であるだけでなく、その便益は一部の国だけでなく、国際社会全体が享受すべきであるという意味において、望ましいものである。
原子力平和利用には、核不拡散を含む責任が伴うべきこと、そうした責任を果たすことにより、原子力平和利用の拡大と核拡散の懸念の増大という両者のリンクを断ち切ることができる。
日本は国際的な原子力平和利用の拡大に大きな利害を有していることから、核不拡散との両立に対し、技術的な知見を提供する用意がある。
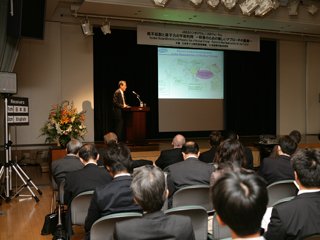

パネル1 核不拡散に関するパネル
| モデレータ | 浅田 正彦 | 京都大学大学院 法学研究科 教授 |
| パネリスト | タリク・ラウフ | 国際原子力機関(IAEA)渉外政策調整部 検証安全保証政策課長 |
| ジョン・ウォルフスタール | 戦略国際問題研究所(CSIS) 国際安全保障プログラム シニアフェロー | |
| オリバー・キャロン | 仏国原子力庁 企画・渉外局長兼国際部長 IAEAフランス代表理事 | |
| エフゲニー・ベリホフ | 露国クルチャトフ研究所 総裁 | |
| 須藤 隆也 | (財)日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター所長 | |
| 遠藤 哲也 | 元原子力委員会 委員長代理 | |
| ジェームス P.ティンビー | 米国国務省 軍備管理・国際安全保障担当次官付上級顧問 |
1.核不拡散体制の現状評価と課題と今後の方向性について、2.核燃料供給保証について、3.米印原子力協力について、の3つの議題について、議論が行われた。
1.核不拡散体制の現状評価と課題、今後の方向性について

パネルに先立ち、ウォルフスタール氏が核不拡散体制の現状の評価について以下を述べた。
現在の核拡散の懸念
私は悲観的な見解を有するが、核拡散を防ぐことはできないのではないか。我々は過去50年においては核の拡散を上手く乗り切ってきたが、今、岐路に立っている。今後20年において更に10カ国の核兵器国が出現するであろうことが考えられ、核兵器の存在が国際社会において安全保障や政治上の価値を高めていると言えよう。
イラン
NPT(核兵器不拡散条約)加盟国であるが、過去18年間に渡りIAEAに申告することなくウラン濃縮等を繰り返すとともに、濃縮活動の停止に係る3回の国連安保理決議* 9にも拘わらず当該活動を継続している。イラン問題は、IAEA保障措置の遵守の確保・強制と、拘束力ある国連安保理決議の実効性を国際社会に問うている。またイランが国家として不法な核技術の取得を通して核兵器製造能力を持ち得るということが、他の国、例えばサウジアラビア、エジプト、トルコ、イラクに波及し、核不拡散体制を脅かしかねないことを憂慮している。
北朝鮮
六者会合では、昨日、北朝鮮の核施設の無能力化が合意されたが、果たして北朝鮮は真剣に自ら核兵器を放棄しようとしているのか。金正日が権力維持のために、その後継者に核開発プログラムを継承させようとしているか否かは分からないが、核兵器を放棄させるために、国際社会は様々な選択を追求していくべきであると考える。
核の闇市場
A.Q.カーン博士を中心とした「核の闇市場」の脅威はなくなったとの見解もあるが、それは楽観的過ぎる。パキスタンの核活動は継続しており、「核の闇市場」のネットワークが再構築される可能性は否定できず、核の闇市場の全体活動を明らかにする必要がある。
核軍縮
今年1月に、キッシンジャー元国務省長官ら4名が、「核兵器のない世界」を目指した見解を表明した* 10が、このような主張は数年前にはあり得なかった。民主党の大統領有力候補のオバマ氏もこの見解を支持しており、今後の当該議論の動向を注視していく必要がある。核軍縮は、アメリカの核の傘下にある国や、露国、中国及びインドとの関係も考える必要があり、核兵器国と非核兵器国の双方との討議が必要と考える。
上記を踏まえて、(1)NPT体制内からの挑戦((i)イランの核関連活動、(ii)北朝鮮のNPT脱退問題)、(2)NPT体制外からの挑戦(非国家主体による核拡散への影響:核の闇市場や核テロ)、についてパネリストから言及がなされた。
(1) NPT体制内からの挑戦
(i) イランの核関連活動
キャロン氏

NPTは核不拡散体制にとって重要であり、イランの現況は困難でデリケートな課題である。イランに対してウラン濃縮活動の停止を求めること、また国際コミュニティが団結し、国連安保理を通じてイランに対処する必要があることを強調したい。EU3カ国(英、独、仏)に露、中、米を加えた六カ国の「包括的見返り案」* 11がイランに提示されており、国際協調の下で当該提案の意図を達成する必要がある。
ティンビー氏

イランは18年間も秘密裡の核開発活動を行い、IAEAに虚偽報告を行うとともに施設への査察を拒んできた。更にIAEA理事会によるウラン濃縮活動停止への要求や、国連安保理決議にも拘らず当該活動を続けている。六カ国の「包括的見返り案」に対しては必ずしも良い結果が出ず、それが安保理の制裁決議に結びついたが、当該制裁決議、特に経済制裁は、非常に効果的となっており、まだできることは沢山あると思う。
遠藤氏

NPT第4条における平和目的の原子力利用の権利は、IAEA保障措置の遵守を前提としている。イランの核関連活動は未申告のウラン濃縮活動等を実施してきたこと、ブシェールに建設中の軽水炉のためのウラン濃縮は経済合理性の観点から説明がつかないこと、イランの行動の不透明性等に問題がある。上記の点からウラン濃縮をサスペンドすべしとの国連安保理決議は理屈に適ったものであり、当該決議を遵守していないイランの濃縮活動を認めるべきではないと考える。
ラウフ氏

イランは2003年12月に追加議定書に署名したが批准しておらず、IAEAはイランが申告した核物質や活動に対しては転用されていないことを確認しているが、未申告のものに対しては検証ができない。2007年8月、IAEAとイランとの間で行動計画「未解決問題の解決のためのモダリティーに関するイランとIAEAの理解」* 12が合意された。行動計画の目的は、申告に基づく核関連活動への保障措置の履行であり、ウラン濃縮活動の停止は盛り込まれていない。濃縮活動停止やそれに伴う制裁等の措置は国連安保理の場でなされる必要がある。IAEAは唯一技術的な検証ができる機関であり、イランに対して出来得る限りの活動を行っている。
須藤氏

イランの核兵器開発の意図はイラン・イラク戦争に起因する。イランは、フセイン失脚後もウラン濃縮活動等を行っており、当該活動が純粋に平和目的であるということは信用しがたい。一方で、欧米各国は、イランが国家として核兵器の製造を決定していると言っているが、イラン国内では核兵器保有のメリットとデメリットは議論されておらず、イラン大統領も核兵器は必要ないと言っている。イランは核兵器を作り得る能力を確立しようとしている一方で、米国との関係や、北朝鮮の六者会合の状況等を慎重に見極めつつ自国の方向性を考えているようである。イランが核兵器を持たないようにするチャンスはまだあると思うし、そのためには濃縮活動等だけに焦点を当てて交渉するだけでなく、核兵器を持たねばならないという動機を外交交渉によって手当てする必要があると考える。
(ii) 北朝鮮のNPT脱退問題
ウォルフスタール氏
北朝鮮は、NPTにおける保障措置遵守と核兵器製造等の禁止に違反しているにも拘らずNPTからの脱退の権利を履行できるのか。本問題は2005年のNPT運用検討会議の議論の中で出てきたが、十分な議論がなされずに終わり、2010年のNPT運用検討会議まで待たざるを得ないだろう。
遠藤氏
実際問題として、脱退できない条約に加盟する国が果たしてあるだろうか。今、我々ができることは、脱退を難しくすることと、脱退した場合は加盟中に得た利益を返還させる等の間接的に「脱退の利益をディスカレッジすること」だと考える。NPTの改正は非常に難しくNPT運用検討会議等で上記を決議する等が現実的な措置として考えられる。
(2) NPT体制外からの挑戦(非国家主体による核拡散への影響:核の闇市場や核テロ)

モデレータから、非国家主体である私人を規律するには国内法しかなく、国連安保理1540* 13や、PSI(拡散安全保障イニシアティブ)* 14の有効性を確保するためには、国内法である刑法や輸出管理規制の整備と強化が必要ではないか、との言及があった。その後、パネリストがそれぞれの意見を述べた。
ウォルフスタール氏
国連安保理決議1540は全ての国家にとっての普遍的な義務であるが、国家は当該決議を国内法に反映させる義務を負うのか。この問題がゆえに、国連安保理決議1540はまだ受け入れられない面がある。しかし、非国家主体の活動とて、ある国家の領域内で行われるものであり、国家として対応していく必要がある。核兵器に転用可能な核物質については、最も高いセキュリティ基準を満たすとともに、当該核物質の移転途中で何等かの行動をとることができるようにすべきである。PSIは、米国を中心として国際協力の下に行われているが、国際的に正当性を持つまでには行き着いていないようだ。
須藤氏

核の闇市場は、アジアのドバイやマレーシアが拠点であり、アジア諸国の中で輸出管理体制が十分に整備されていない国があることを露呈した。彼らは、自由貿易への阻害や国境観念の欠如から輸出管理を必ずしも好ましく思っていないようだ。日本政府は、これらの国々に対して、IAEA追加議定書の締結の促進、輸出入管理に関する国内実施体制整備と能力向上、PSIへの支持拡大、ASTOP(アジア不拡散協議)* 15の開催、貿易管理実務者へのアジア輸出管理セミナー等で協力を行っている。この際に傾注すべきは、彼らに安保理決議1540に基づき輸出管理を行政的な義務として押し付けるのではなく、テロ対策や核不拡散という共通利益のために皆が一緒に考えるという“thinking together”のスタンスで、彼らの自発的な努力を引き出す態度が必要と考える。
ティンビー氏
PSI構想の発表から4年を経て、「阻止原則宣言」に基づく活動は、国連安保理決議1540に則って実施されており、大量破壊兵器等の不正移転の防止に重要な役割を果たしている。実際に「阻止原則宣言」に則って活動する国が増加しているとともに、現実的な効果が出てきている。目立った報道はされていないが、スロベニア、日本、ウクライナ、英国、ニュージーランドで演習、訓練、セミナー及びワークショップが国際法や各国の国内法の制度に基づき行われている。今後は、中国、韓国、マレーシア、インドネシア及びタイにもPSI活動を普及しようと考えている。
2.核燃料供給保証について
討議に先立ち、ラウフ氏が核燃料供給保証の目的、定義、検討の経緯及び検討の課題につき紹介した(資料「ASSURANCES OF SUPPLY: A NEW FRAMEWORK FOR THE UTILIZATION OF NUCLEAR ENERGY」参照)。
現在、核不拡散を確保しつつ、原子力平和利用の拡大を促進していくことが必要となっている。NPT下では平和目的の原子力利用である限り、濃縮・再処理活動は違法ではないが、既存の濃縮・再処理技術の保有国をこれ以上増やすべきではないというのが一般的なコンセンサスとなっている。核燃料供給保証は、新興の原子力利用国が自ら濃縮・再処理を行うことなく核燃料にアクセスできることを保証することを目的としている。
核燃料供給保証に関しては、現在、14の提案がなされており、このうち核燃料バンクの創設については、1〜2炉心分の燃料(低濃縮ウランで約65〜130トン程度)を備蓄することが提案されている。これは、新興の原子力利用国で必要な核燃料の量、既存のマーケットへの影響、核燃料供給保証が利用頻度の少ない、保険的機能であること等から勘案されたものである。
昨年IAEAで開催された核燃料供給保証に関する特別イベントでは、どのような国であれNPT上の原子力平和利用の権利の制限を望まないということが明らかとなった。IAEA事務局長は今年6月理事会に対して報告書を提示した。当該報告書の中では、核燃料供給保証に関していくつかのクライテリア案が提示されている。供給途絶が核不拡散以外の政治的な理由であること、供給される核物質が平和目的のみに利用されること、IAEAと保障措置協定を締結していること、消費国が追加議定書を発効させていること、等である。
IAEAはすでにIAEA憲章の下で核燃料の供給を行う権限、知識及び経験を有している。現在IAEAは、IAEA事務局長に核燃料備蓄を含む核燃料供給保証メカニズムを構築するための権限やリソースを与える等、より実質的な議論を行う準備をしているところである。
パネリストらの見解
ティンビー氏
核燃料供給保証は機微技術の核拡散防止に大きな貢献になると考える。核燃料バンクも最後の手段として重要であり、その点、米国は解体核起源の17.4トンの高濃縮ウランをダウン・ブレンディングした低濃縮ウラン約290トンを核燃料バンクに提供する準備がある。当該分量は平均的原子炉の炉心燃料10回分の取替分に対応するものである。現在提案されている核燃料バンクのうち、上記の米の解体核起源の低濃縮ウランを備蓄するバンクは米国の法律に、NTIが提案する核燃料バンクはIAEAの規制に、露の国際濃縮センターでの備蓄は露の法律にそれぞれ従うことになる。各々の法律や規制があっても、上記のいずれかのバンクからの供給は可能と考えられ、米としてもIAEAや露のバンクを支持している。消費国にとっては、低濃縮ウランの取得を国際的な市場に依存するか、濃縮技術を自主開発するかの選択肢があり、前者に対してはエネルギー・セキュリティの観点から反対する人がいるかもしれないが、核燃料供給保証メカニズムにより、たとえ政治的な理由で供給の途絶が起こっても安心して核燃料の供給が保証されることになる。消費国にはそれをメリットとして考えて欲しい。
キャロン氏
現在、世界では約30カ国が原子力を利用しているが、そのうち、数カ国しか核燃料サイクル能力を有していない。既存の核燃料市場は、既に十分に確立・成熟しており、エネルギー安全保障上も既存の市場に依存することは価値があると考える。さらに核燃料供給保証メカニズムにより、消費国は、核燃料の供給保証という国際的なベースでバックアップを得ることができる。今こそ核燃料供給保証に関する提案が具体化されるときであり、仏国はIAEAで行われている核燃料供給保証に関する議論を支持するとともに、具体的な成果が合理的な時間内で出されることを期待している。欧州委員会では、ウラン供給確保を目的として設立されたEURATOM* 16やその他の欧州のメカニズムとの整合性も勘案して、核燃料供給保証メカニズムが議論されている。種々の提案の中で、何処の国の主権にも属さない場所に濃縮施設を作り、国際機関にその管理を委ねるとの提案があるが、実利的な選択であると思う。
ベリホフ氏

核燃料供給保証メカニズムの最終目標は、核燃料サイクル全てを国際管理下におくことであり、これが信頼醸成にもつながると考える。また、メカニズムの構築は、ステップ・バイ・ステップで進めていく必要があると考える。露国は、アンガルスクの国際ウラン濃縮センター(IUEC)* 17を提案しているが、これはフロント・エンドだけでなくバック・エンドも含めたもので、核不拡散にとって有益であるし、露国にはソ連の時代、核燃料をリースし、その後使用済燃料も貯蔵のために受け入れた経験もある。もっとも重要なことは、核燃料のリースと使用済燃料のテーク・バックをあわせた核燃料サイクル全体の管理であり、高レベル廃棄物の最終処分にも責任を持つことができるということである。その点においては、核燃料供給保証メカニズムにおいて、いくつかの核燃料サイクルセンターを作り、核燃料サイクル全てにおいてサービスを提供することが望ましい。IUECにおいては、パイロット・プロジェクトとしてフロント・エンド部分をまず提供することを考えているが、最終的な目標は核燃料サイクル全ての分野におけるサービスの提供である。
須藤氏
核燃料供給保証は、日本としても利害関係を伴う重要な問題と捉えている。日本提案* 18では、ウラン鉱石から燃料集合体まで、各国の現状や供給能力を登録し、燃料市場の透明性を確保し、供給六カ国だけでなく、多くの国々が核燃料供給保証システムに参加できることを提案している。また、この問題を検討するために国内に核燃料供給保証に委員会を設けて、供給保証システムの態様、消費国要件、及び現物備蓄・仮想備蓄などにつき、具体的な検討を行っている。現在、種々の提案がなされているが、もはや抽象的な議論をしている段階でなく、具体的なメカニズム案を作り、その上で当該案に対する不拡散への貢献度や消費国の意見を聞き、メカニズムをさらに具体化させていくということが必要だろう。我々は核燃料供給保証に関する議論には積極的に参加していく所存である。
3.米印原子力協力について

前提として、モデレータが米印原子力協力の経緯、最新の状況、メリット及びデメリット、インドと他の国の協力について紹介した。その後、核不拡散の立場からウォルフスタール氏が、またこれらの批判に対する反論としてティンビー氏が、各々その見解を述べた。
ウォルフスタール氏
米印原子力協定はいずれ発効するだろう。当初、米印原子力協力が発表されたときは政府外においても、必ずしも否定的な見解を示す人ばかりではなく、私も米印間でバランスの取れた合意になれば核不拡散体制支持派からも好意的に受け入れられると思っていた。しかし率直に言って、現在の協定案は、核不拡散よりも、インドの戦略的重要性が優先された結果を反映したものである。
米印原子力協力によってNPTの価値が下がるのではない。米国はNPT下の核兵器国であり包括的保障措置も受け入れておらず、米国にとっては何も損なうものは無い。しかし、非核兵器国である日本が、NPTの下、保障措置面で膨大な努力をしつつ原子力利用を行っているのに比し、インドはNPTの外にいながら何らの義務を課されることなくNPT上の利益を得てしまう結果になる。この点においてNPT不要論が出てくるかもしれない。
そもそも米印原子力協力の主たる動機は、将来の中国の方向性への懸念であり、インドが中国に対する戦略的なカウンター・バランスになると考えた結果であろう。しかし私は、米国現政権がこの主たる動機よりも、核不拡散を前面に押し出してインドとの原子力協力を推進していることには疑問を抱いている。
政治的視点から見ると、共和党・民主党員の多くが核不拡散の観点から懸念を抱きつつもインドとの原子力協力を支持し、インドを例外視することを肯定的に捉えている。しかしながら、この例外視がインドだけに留まらず、イスラエル、パキスタン、引いてはNPT加盟国にも波及してくるかもしれないことを非常に懸念している。
インドへの核燃料の供給に関して、もしインドが核実験を行った場合、インドへの協力は米印原子力平和協力法(ヘンリー・ハイド法)に基づき停止されるはずであるが、現政権は当該規定をユニークに解し、米印原子力協力協定では、代替的な燃料の供給を行う手段を講じるとしており、この点、更なる幅広い議論が必要であると考える。また、インドにはCTBT(包括的核実験禁止条約)の批准が要件とされておらず、限定的に検証可能な兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT:カットオフ条約)が盛り込まれているだけである。米国の新政権がこれに関して異なる意見を有するのであれば、米印原子力協定自体について見直すことになるかもしれない。
ティンビー氏
米印原子力協力により、インドをNPTシステムに取り込み、インドが追加的なIAEA査察を受け入れ、また、インドに核実験のモラトリアム遵守のインセンティブを与えることができる。その意味で当該協力は、大きな意味でNPT体制を強化するものと考える。加えてインドをパートナーにすることによって戦略的なメリットがある。
核燃料の供給の保証に関し、米印原子力協力協定では戦略的な燃料備蓄構築への支援が規定されているが、これはインド側から提案があったものである。現在、インドの原子炉燃料は殆ど天然ウランであり、天然ウランの備蓄が想定されるが、ただし、将来的にインドが軽水炉に移行すれば低濃縮ウランの備蓄の概念も考えられ、米国がインドのために備蓄を行うことも考えていくことになる。
4.質疑応答
- 質問1:
- 米印原子力協力については、インド国内で野党の反対があると聞いているが、米政府としては、インド国内のこのような状況をどう考えるか。
- ティンビー:
- ト印原子力協力はインドにとってもよいdealと考える。今問題となっているのは、インド国内の連立政権の構造で、これが克服されればインドとIAEAとの保障措置交渉もまとまるだろうし、米国議会での承認も得られると思う。一方でNSGはコンセンサスが必要で多くの支援が必要であり、必要な合意に至らないということもあるだろう。
- 質問2:
- 例えば中国やパキスタンが核実験を行い、インドがその対抗として核実験を行った場合、米国は当該核実験を起因としてインドへの核燃料の供給を止めるのか。
- ウォルフスタール:
- 米国原子力法に従えば供給を止めざるを得ない。が、米国議会はインドが他の国への対抗としての核実験はモラトリアム違反とは言わないかもしれず、現在、米国の行政府と立法府の間で議論が起こっている。
5.まとめ

パネル終了に当たり、モデレータから、NPTを中心に発展してきた核不拡散体制は、体制の内外から重大な挑戦を受けているが、様々な挑戦に対処していくためには、NPT運用検討会議等における議論を通じ、NPTそのものの運用の改善を図るとともに、核燃料供給保証、国連安保理決議1540及びPSIといった補強手段を効果的に活用していく必要がある、と総括した。
注釈
* 9国連安保理決議1696(2006年7月)、対イラン制裁決議1737(2006年12月)及び対イラン追加制裁決議1747(2007年3月)
* 102007年1月4日にキッシンジャー元国務長官、シュルツ元国務長官、ペリー元国防長官及びナン元上院軍事委員会委員長がウオールストリートジャーナルに“A World Free of Nuclear Weapons”と題する論文を寄稿し、米国が世界の非核化に向けて具体的な行動を採る旨を主張。
* 11包括的見返り案:2006年6月に国連安保理の5常任理事国と独国が提案したもので、イランがウラン濃縮活動、再処理活動を停止する見返りとして、イランに国際共同プロジェクト下で軽水炉を建設し、燃料供給を保証するため、露国の国際核燃料サイクルセンター構想へイランがパートナーとして参加することを提案したもの。
* 12Understandings of the Islamic Republic of Iran and the IAEA on the Modalities of Resolution of the Outstanding Issues(INFCIRC/711)
* 13国連安保理決議1540:2004年4月に国連安保理で採択された決議。核兵器、化学兵器及び生物兵器とそれらの運搬手段の拡散が国際社会の平和と安全に対する脅威であり、国連憲章第7章の下、1)大量破壊兵器及びその運搬手段の開発等を企てる非国家主体に対して、いかなる形態の支援も控えるべきこと、2)特にテロリストによる大量破壊兵器及びその運搬手段の製造等を禁止する適切で効果的な法律を採択し、執行すべきこと、3)大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散を防止するため、国境管理や輸出管理措置を確立する、ことなどを内容としたもの。
* 14PSI(拡散安全保障イニシアティブ:Proliferation Security Initiative):2003年5月に米国ブッシュ大統領が発表したイニシアティブ。国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物質の拡散を防止するために、国際法・各国国内法律の範囲内で、参加国が共同して取り得る移転及び輸送の阻止のための措置を検討・実践する取り組み。こうした阻止活動の原則は、「阻止原則宣言」(Statement of Interdiction Principles)に纏められ、PSIにおける活動の指針として機能している。
* 15ASTOP(アジア不拡散協議:Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation)。
* 16EURATOM:European Atomic Energy Community (欧州原子力共同体)
* 17核燃料供給保証用のウラン備蓄及び濃縮役務提供のために、露国アンガルスクに各国の出資により国際ウラン濃縮センター(IUEC)を設立するとの提案。(INFCIRC/708)
* 18日本提案:IAEA核燃料供給登録システム(INFCIRC/683)。参加国の供給能力等をIAEAに登録することにより核燃料市場の透明性向上を図ることを意図したもの。
パネル2 原子力の平和利用に関するパネル
| モデレータ | 秋元 勇巳 | 三菱マテリアル株式会社 名誉顧問 |
| パネリスト | ダミアン・ペコ | 米国エネルギー省 原子力庁 企画・国際パートナーシップ課長代理 |
| 内山 洋司 | 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 教授 | |
| エフゲニー・P.・ベリホフ | ロシア・クルチャトフ研究所 総裁 | |
| オリバー・キャロン | フランス原子力庁 企画・渉外局長兼国際部長 IAEAフランス代表理事 | |
| タリク・ラウフ | 国際原子力機関(IAEA) 渉外政策調整部 検証安全保障政策課長 | |
| 遠藤 哲也 | 元原子力委員会 委員長代理 | |
| 岡﨑 俊雄 | 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 |
パネル2では、米国、ロシア、フランス、日本の原子力平和利用の現状を核不拡散との両立という観点から概観し、エネルギー安全保障、及び地球温暖化防止の観点から、原子力が果たす役割が改めて認識された。今後見込まれる原子力利用の拡大が核拡散のリスクの増大につながらないようにするために、原子力新規参入国にどのような協力が求められるか、原子力先進国の役割、IAEA、及び国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)等の国際協力プログラムの役割について、また原子力利用の拡大の展望における核拡散抵抗性技術の開発の重要性について議論がされた。
1.米国、ロシア、フランスの原子力平和利用の現状
(1)米国の原子力平和利用の現状:ダミアン・ペコ氏(米国エネルギー省)

米国における原子力発電の現状と原子力ルネッサンスの兆し
先週、NRG Energy社が改良型沸騰水型原子炉(Advanced Boiling Water Reactor :ABWR)2基の建設運転許可(COLs)を米国原子力規制委員会(NRC)に約30年ぶりに申請したという朗報があり、いよいよ米国でも原子力の動きが出てきたといえる。
政府による原子力発電計画の支援プログラム
米国エネルギー省は、業界との間で協力協定を結び、今後10年間の早い段階での運転開始を目指し、先進的な軽水炉の運転開始に向けた支援を行っている。具体的には、政府と産業界が50%−50%ベースで協力を行うことで、3基の発電所の許可(早期のサイト認定許可、及び建設運転許可)、AP-1000、及びESBWR(革新型単純化沸騰水型原子炉)の設計に関しての最終的な詰め、及び設計認可などにおいて協力がある。また、財政的な支援として、エネルギー省と財務省は、今後10年間の原子力発電所が建設・運転開始を目指し、早期の段階における発電所建設計画を対象とした財政支援プログラムを開始した。融資保証、一定のスケジュールの基準を満たす計画に対する税控除(2009年以前のCOL申請、2014年以前の建設開始、2021年以前の運転開始)、6基の原子炉以上を有する計画を対象としたリスク保険などを内容としている。
GNEP
このような原子力の平和利用の拡大を背景に、核拡散のリスクの増大が懸念される。米国は、この懸念に対応するためにグローバル・エネルギー・パートナーシップ(GNEP)を開始した。GNEPは、安全でクリーンな原子力利用を拡大し、世界のエネルギー需要を満たすことを目的としており、安全とセキュリティの担保された原子力のオプションを提供するプログラムとして、米国の国家安全保障戦略の重要政策の一つとなっている。具体的には、超ウラン元素(TRU)を消費するための先進リサイクル原子炉の開発、先進的かつ拡散抵抗性のある燃料サイクル技術を用いた使用済燃料リサイクルの促進、発展途上国のニーズと能力により適した拡散抵抗性の高い(小型)原子炉の開発、信頼できる核燃料サービスの確立の推進等を内容とする。
パートナーシップを発展させる
拡散はグローバルな問題であるため、技術開発の領域を超えたグローバルな解決策が求められる。その意味で、2007年9月16日のGNEP第2回閣僚級会合において、16カ国代表がパートナーシップの指針、枠組み、「原則の声明」に署名したことは大変意義深い。(他に19カ国がオブザーバーとして、IAEAも国際機関として参加している。)
GNEP第2回閣僚会議では、理事会、運営委員会、作業部会(インフラ開発WG、信頼性が高い燃料供給サービスWG、他、原則の声明で掲げられた目的を遂行するために設置されるその他のWG)からなるパートナーシップの基本的な仕組みの確立、及びアクション・プランの策定が合意された他、指導原則(「原則の声明」)が採択された。
グローバルな取組の必要性への認識の高まりから、GNEPに対する関心は広まっており、今後もパートナーシップの拡大が見込まれる。
(2)ロシアの原子力平和利用の現状:ベリホフ氏(クルチャトフ研究所)

エネルギー需要と原子力の優位性
近年、エネルギー需要は年間2〜3%の伸びを記録している。特に発展途上国におけるエネルギー需要の伸びが目覚しい。近年のエネルギー需要の増大の背景には、世界人口の増加と先進国と発展途上国におけるエネルギー消費の格差が縮まっていることの2つの傾向が理由として考えられる。世界の人口は、2050年には約90億人になると見込まれる。人口増加以外に、人口の分布もエネルギー需要を左右する大きな要因と考えられる。先進国と発展途上国におけるエネルギー需要には、かつては20〜40倍ほどの開きがあったが、2005年にはその差は大幅に縮まった。
2050年にはエネルギー需要は現在の3倍になると見込まれる。非常に楽観的なシナリオにおいても、2050年にはエネルギー不足が生じることが予想されており、先進的なエネルギー技術を駆使してもこうしたエネルギー不足は解消できないことが予想される。
次に、価格という側面から検討する。エネルギー資源の価格予測は流動的である。国際エネルギー機関(IEA)は、エネルギー資源の価格の将来予想として非常にスムーズな動きを示しているが、過去においては決してスムーズではなかった。特に石油価格は、過去25年間で大きな変動を記録している。我々はIEAより悲観的に考えており、2008年の石油価格は1バレル当たり$100近くになると予想している。我々の予想では、電力価格は今後上昇の一途にあり、エネルギー資源別に見ると、原子力に比べて、特に、ガス、石炭をエネルギー資源とした電力価格には大幅な上昇が予想される。このような結果から、原子力の優位性は明らかであり、ロシアは、この価格の違い、能力の高さを活用して原子力利用の復活、再編を推進していくわけである。
原子力利用の拡大に伴う課題(核燃料サイクルの将来の展望)
今後、原子力発電を推進していくにあたり、伝統的な1〜1.5GW規模の原子炉ばかりでなく、一般的な需要を満たす300〜400MWの原子炉も考えていく必要がある。将来、小規模の原子炉を何千と作っていくことが求められ、必然的に、原子炉のモード、及び財政面を考えて原子炉を建設することが重要となる。
そこで、エネルギー資源の消費の観点から原子炉のモードを検討する。我々の分析によると、増殖炉でない高速炉の場合、ウラン不足が問題になるが、ハイブリッドの増殖炉の場合、ウラン消費量は大幅に減る。私の見解では、ウラン供給の限界が大きな問題であり、その点で高速増殖炉は現実的な選択肢である。ウラン消費量が少ないという点で、トリウム・サイクルも有効だと考えられる。増殖炉の問題は、プルトニウムの生産量が増えるという点にある。どちらにせよ、核分裂性物質が増えるわけで、それは問題となる。燃焼炉の場合、ウランが増え、古典的な増殖炉の場合、プルトニウムが増える。その構造によって産出される量も違ってくる。燃料のパラメーターという観点から、ウランの消費量、プルトニウムの生産量、使用済燃料の取扱い、核分裂性物質の量等の問題を比較検討する必要がある。
次に、国際核燃料サイクルセンターについてであるが、このセンターの活用方法として、ウラン及び使用済燃料を受け取り、MOX燃料及びウラン燃料を製造することが可能性として考えられる。
将来見込まれる小規模原子炉の大量建設のニーズについてだが、少なくとも旧ソ連の場合は(米国も同様だが)、250隻の原子力潜水艦を製造した経験がある。その経験を生かして原子力潜水艦の解体も行っており、解体に伴う廃棄物の管理・処分の経験も持っている。この経験を活かして、ロシアが原子炉の大量建設、核廃棄物の管理・処分に貢献することも可能性として考えられる。
ロシアの原子力政策とエネルギー活用の将来に対するビジョン
ロシアのエネルギー事情について、一つだけ言及したい。ロシアには天然ガスが豊富で、その90%が中央ヴォルガ地域産である。現在、ロシアは天然ガスを欧州に供給しており、アジアへの供給も予定している。ロシアの総発電量の79%が天然ガスでまかなわれているが、天然ガスの価格の高さを考え、他の発電源を天然ガスの代替として検討している。石炭は環境の問題、CO2の問題、輸送の問題があり、最善の解決策は原子力であると考える。
このようなエネルギー事情を背景に、ロシア政府は3段階の原子力開発政策を決定した。第1段階では、原子力産業の再生を目指し、現在24GWの設置容量を2020年までに42-45GWにまで拡大する。第2段階では、高速増殖炉の開発と資源確保の基盤を確立するために閉鎖された核燃料サイクルを確立する(65-73GWの設置容量の内高速増殖炉の設置容量が16GW)。第3段階では、発電能力の増大とエネルギー需要の高い技術において原子力の利用拡大を目指している。
将来的には、廃棄物の処分にナノ技術、プラズマ技術の活用を考えており、そのすべてにエネルギーが必要ということから原子力の有用性が重要視される。原子力の有効利用と並行して、適切な形でITを活用、クリエイティブなツールを開発し活用するという将来的なビジョンを持っている。
(3)フランスの原子力平和利用の現状:キャロン氏(フランス原子力庁)

はじめに
今や、原子力ルネッサンスは勢いを増しつつあり、原子力がもたらす経済的、環境的な恩恵を否定するのは原子力反対派にとって一層困難になってきている。この意味で、原子力利用とセキュリティ、特に核拡散との関連が、原子力反対派にとって最後の砦となっている。つまり、原子力利用の推進のためには核不拡散の担保が不可欠ということである。
継続する原子力へのコミットメント
これまでフランスの原子力開発は、概ね成功してきたと言える。フランスは、今や、58基の原子炉、63GWと、総発電量の80%を原子力が担う。またフランスの原子力発電のkWhあたりのコストは、欧州でも最低レベルに位置する。過去30年間に渡り、政権の交代、チェルノブイリ事故にもかかわらず、原子力反対の圧力は、フランスの原子力政策を覆すには至らなかった。原子力に対して、特に廃棄物の管理に関して、世論に不安が全くないわけではないが、フランスが一貫した燃料サイクル戦略を維持してきたことは、間違いなくフランスの原子力政策の成功の大きな要因となっている。
一貫した燃料サイクル戦略
フランスは、商業規模の使用済み燃料の加工、及びリサイクルの実践によって、廃棄物の毒性の軽減、減量を可能にし、照射済み燃料の蓄積を防いできた。この実績は、放射性廃棄物の管理という課題における将来の自信にもつながる。
1991年、廃棄物管理の長期的解決への道を開く法律が制定され、2005年12月に発表された調査報告の結果、2006年夏に新たな法律が制定された。その法律は次の3つの政策を示している:(1)再処理とリサイクルを追及することで廃棄物の毒性の軽減と減量を推進すること、(2)リサイクルできない廃棄物は、一時的に地上で貯蔵すること、そして(3)最終的に地上で貯蔵できない廃棄物は、可逆的な地層処分を施すこと。またタイムテーブルとして、2015年までに可逆的な地層処分施設のライセンスを申請すること、並びに2025年頃の運転開始を目標とすることが設定された。また、2020年の第4世代の原型炉の運転開始を目指して研究開発を推進する。
フランスは国際的なパートナーシップを通した商業規模の原子力開発を推進してきた経験を有する。この経験を基に、フランスは、拡散懸念を増長することなく国際燃料サイクルのサービスの需要に応える能力があると認識する。
将来を予期して

フランスは現在、原子力開発に関する今後50年間の包括的計画へと移行しつつある。具体的な内容は以下の通り。(1)現在30年の寿命の原子炉を、安全性のレビューを経て10年間延長するための研究を実施する。(2)2012年に稼動開始を目指している第3世代のEPRへの移行を推進する。EPRは将来的に100%MOX燃料を使用することができるようになる可能性がある。(3)2040年代の商業ベースでの運転開始を目指し、2020年までの第4世代の原型炉の建設が発表された。第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF)への参加を通して、フランスはナトリウム冷却高速炉(SFR)、ガス冷却高速炉(GFR)、及び超高温ガス炉(VHTR)の概念に主に関心があることを表明してきた。
責任ある原子力開発のためには、経済的かつ実行可能な使用済み燃料及び廃棄物の管理の実現が求められる。そのようなサービスが将来可能になることを原子力導入や原子力利用の拡大を考える国は認識する必要がある。使用済み燃料と廃棄物の具体的な解決法として、ウランとプルトニウムの共管理を可能にする発展的な加工技術の開発を通じて、第3世代のリサイクルの研究開発に尽力している。また、将来の燃料サイクルと保障措置システムの組合せによって核拡散抵抗性を高めることは有益であり、経済性と政策的観点における原子力の展望の改善につながる。この認識から、IAEA及び他の国際的な供給保証の取組を支援する。しかし、原子力の将来を担う政策は、野心的で現実的でなければならなく、追加的な依存性を生むといったやりすぎのシステムはよくない。この点で、燃料供給に関する6カ国提案は、正しい方向にあると認識する。
結論
世界的な核燃料サイクルの開発は重要であり、フランスは資源活用と廃棄物処分といった負担の軽減のための閉サイクルの先駆者として開発を行ってきたし、今後も国内研究、及び国際協力を通じて、その燃料サイクルにおける研究開発能力を活かして、核拡散抵抗性の高いシステムの研究開発を行い、長期的かつ最先端の解決方法の提供に貢献する。
2.原子力が果たす役割
今後、原子力が果たす役割について、エネルギー安全保障及び地球温暖化防止という観点で議論された。最初に、伊藤・中部電力顧問がエネルギー安全保障(電力の安定供給)という観点から日本の原子力平和利用、核燃料サイクルの重要性、及び原子力安全について、次に、内山・筑波大学大学院教授が地球温暖化防止の観点を含めた包括的な観点から見た原子力の果たす役割について、以下の通り発表した。
(1)「エネルギーの安定供給の観点から見た日本における原子力の平和利用」:伊藤氏(中部電力株式会社)

原子力平和利用に関する課題について、まとめとして、私見も含めた以下の6つのポイントをあげる。
- 原子力だけでエネルギー供給の問題を解決することは難しいこと、
- 原子力開発の先進国にとっての課題として、プラント高経年化への対応を確実に進めること、既設炉の有効活用を図ること、さらに途上国への支援も進めることが必要であること、
- 原子力の安全・安定運転における問題は1国・1事業者内の問題に留まらないとの認識(“We are on the same boat.”, “We are hostages of one another”)から、各国・各事業者が規制面を含む制度面等の基盤での調和を図ると共に、情報・経験を共有することが極めて重要であるとの認識を、念頭に置くべきであること、
- 人材育成を図り、次世代に技術を引き継いでいくことが必要であること、
- 発電設備総点検問題や中越沖地震等により損なわれた原子力発電に対する公衆からの信頼を、透明性や対話を基本として回復すること、そして
- 人材確保、信頼確保、規制調和は国際的な視野で進めていくことが重要であること。
(2)「21世紀における原子力の役割」:内山氏(筑波大学大学院)

以下の点を強調したい。(1)世界的な原子力利用の拡大が見込まれ、特にアジアにおける原子力導入への動きは活発である。(2)化石燃料使用の発電に比べて原子力発電は経済性に優れている。(3)原子力の安全性、放射性廃棄物の管理、パブリック・アクセプタンスの確保を国際的なレベルで検討していくことが重要である。(4)原子力には発電だけでなく、淡水化技術、熱供給技術など新たな技術開発も求められてくるであろう。(5)化石燃料の枯渇、地球温暖化の問題などからも原子力の有用性は明らかで、今後、本格的に原子力が必要になってくるであろう。
3.今後、原子力の導入を目指す国に対する協力のあり方についての意見交換
キャロン氏(フランス):原子力利用の構図の変化と保障措置に与える影響
原子力開発途上国における原子力発電の導入それ自体が、特に核拡散の課題になっているという表現は避けたい。むしろ、保障措置上の影響、つまり保障措置の要件にどのような影響を与える可能性があるか話したい。
これまでの原子力利用の構図は、大規模な原子力発電所が、限られた国に集中して存在するというもので、その構図を前提とした保障措置を含む核不拡散措置が取られてきた。
しかし、将来的には、小規模な原子力発電所を持つ国が世界的に増えることが見込まれるため、原子力利用は、薄く広範に広がるという構図になる。
このような原子力利用の構図が将来的に変化することで、保障措置上への影響として、技術的には、総合的品質管理(TQM)という問題が出てくることが考えられ、そのことが原子力発電導入国の増加が今後、保障措置に与える一番大きな影響ではないか。
具体的には、規制の実施、安全文化の育成、法律・規制、国際的な約束・取決めの遵守の担保など、すべてを包括的な観点から検討していかなければならなくなる。既に発達した原子力プログラムを有する国は、新規原子力導入国に対する支援に際しては、確立された厳格な基準に則って行わなければならないが、行政機関にしてみれば、基準をどこに設定するかという難しい問題を抱えることになる。
ペコ氏(米国):包括的なグローバルな取組み、集団としての調整・連携が求められる
どのような形で支援するべきかという視点で話したい。原子力導入国の支援のためには法律、規制、安全、インフラ、保障措置、廃棄物管理、第三者損害賠償、他、多くの問題をカバーしなければならない。
支援の受領・提供に競争が生じる可能性、違った基準が導入される可能性、相矛盾する目標が設定される可能性、これら全ての可能性は悪影響を及ぼす。この状況を避けるために、包括的なアプローチ、調和の取れた方法で支援を行うことが重要であると考える。
ベリホフ氏(ロシア):過渡期を迎えるにあたって、ビジョンを持つことが重要
革新的、かつクリエイティブなビジョンが必要である。
原子力発電導入国の増加は、それに伴い原子力利用の構図が大きな過渡期を迎えることを意味し、ビジョンを持っていないと過渡期にあたっての混乱から危機に瀕する可能性もある。旧ソ連の崩壊の前後の過渡期には、混乱が生じたし、チェルノブイリの事故の要因の一つはそのような混乱期に統合された管理が危機に陥って、安全性が大きく損なわれたことにある。
遠藤氏(日本):G8サミットの場で、原子力先進国の一丸となった支援取組みの必要性を提案すべき

3S:安全(Safety)、保障措置(Safeguards)、セキュリティ(Security)を原子力発電導入国に求めていくことが必要だが、求めていくだけではなく原子力先進国が他の先進国、IAEA、G8などと協力して取組んでいかなければならない。2008年のG8サミットの場で、原子力発電導入国に対して原子力先進国が一丸となって支援する必要性を提案するべきだと考える。
ラウフ氏(IAEA):IAEAの果たす役割

IAEAは、開発のためのエネルギー開発計画を支援する。具体的な支援プログラムとして、以下がある。
エネルギー開発計画の支援:エネルギー評価の支援、エネルギーに関する査定サービス、エネルギーに関する分析、エネルギー開発に必要なキャパシティーの形成を支援
原子力を選択した国に対して、原子力発電導入に求められる基盤構築を支援:法的・規制面の整備、教育・訓練、人材育成(オン・ザ・ジョブ・トレーニングの提供を含む)、財政的援助(世界銀行などの開発援助を含める)へのアクセスを支援、安全文化の育成
脆弱なシステムを持つ既存の原子力発電国に対する支援:緊急事態対応の強化、国際的なピアレビューの実施など
内山氏(日本):市場経済を考慮した取組み・国際備蓄の確立が求められる
グローバル経済の動きは、無視できない要素であり、負の遺産(地球温暖化もその一つ)をグローバル経済にどのように取り入れていくかを考えなければならない。市場経済を考慮に入れた取組みが求められる。(CDM及びJI* 19など)
IAEA主導による国際備蓄を確立することが重要である。ウランは同量の化石燃料に比べて数百万倍にも及ぶエネルギーを発するということから、ウランの備蓄にかかる費用は化石燃料よりも大幅に安いといえる。ある程度(1年分位)の国際備蓄を作ることで、エネルギー供給に大きく貢献する。(アジアで見込まれる原子力利用の拡大を背景に)可能であれば、アジアに地域的備蓄センターを設けることが今後必要となってくるのではないか。日本は保障措置がしっかりしている国として、潜在的備蓄基地候補国となれるのではないか。
岡﨑氏(日本):日本はどの分野で協力できるか:共に取組む姿勢が重要

押付けではなく、問題意識を共有することで協力・支援を進めることが重要である。次回は、支援対象国を交えたシンポジウムにするべきと認識する。
このシンポジウムで共有された認識、すなわち、支援の必要性、及び支援における協力体制の重要性を次回のG8サミットで提言するべきである。
ペコ氏(米国):途上国への支援としてGNEPが構想する中小型炉の導入の意味
小さな国が分散的に原子力導入を進める傾向に対応したプログラムであり、送配電網が十分に整っていない国に適し、かつ安全・セキュリティが高く核拡散抵抗性に優れた中小型炉の技術開発を内容とする。
より経済的に導入が可能で、より簡素化された運転による安全性・核拡散抵抗性・セキュリティの確保を可能にする炉の開発を目標としている。
中小型炉の研究開発には、トラック1と2の二つのアプローチがある。トラック1では、より近い将来、2015年までの配備を目標とした軽水炉の設計を行う。トラック2では、先進的な技術開発により、2030年頃の市場導入を目標とし、経済性、核拡散抵抗性、安全性、セキュリティに優れた次世代の原子炉の研究開発を行う。
この取組みに対し世界的に関心が寄せられており、グローバルな協力を通じて推進していくことが望まれる。
4.核拡散抵抗性技術の開発の重要性についての議論
秋元氏(座長):核拡散抵抗性の定義、内在的特性(INTRINSIC FEATURES)と外在的措置(EXTRINSIC MEASURES)

IAEAによる核拡散抵抗性の定義(IAEA STR-332 “Proliferation Resistance Fundamentals for Future Nuclear Energy System”)によると、核拡散抵抗性とは、「核兵器あるいは他の核起爆装置の取得を試みる国家による核物質の転用、無申告生産、あるいは技術の目的外利用を妨げる原子力システムの特性」のことで、その抵抗性の程度は、システムの技術的な設計特性、運転方式、制度的な工夫、保障措置手段などの組合せによってもたらされる。これらの要素は技術的な内在的特性(Intrinsic features)と、政策・制度的な外在的措置(Extrinsic measures)に分類できる。この二つを組合せることによって、全体として拡散抵抗性を高めることができる。
岡﨑氏(日本):核拡散抵抗性の内在的特性(Intrinsic features)について説明
我々、科学技術を研究・開発する立場として、核拡散抵抗性の内在的特性(Intrinsic features)は我々が責任を有する分野であると認識する。
内在的特性(Intrinsic features)からの核拡散抵抗性を高めるための方法は、主に以下の通りである。
- 核物質における措置:核兵器転用に魅力的でない、或いは不向きな核物質を使用する。
- 高濃縮ウラン⇒低濃縮ウラン:研究炉の燃料を高濃縮ウランから低濃縮ウランに転換するイニシアティブが世界的に進んでいる。
- プルトニウムの単体での分離・取扱いを行わない:プルトニウムとウランの混合抽出、プルトニウムにマイナーアクチナイド等を混合して使用
- 核拡散抵抗性の高いプロセスの設定:できるだけ人が介在し、人が悪用することができないようなプロセスを設定、悪意を持った転用への試みに対する物理的な障壁を導入したプロセスの設定
- 遠隔監視・封じ込めなどの措置
- 検知システムの能力の開発
- 外部からの盗取を難しくさせるシステム
- 障壁の設定:盗取を難しくさせるシステムの導入
- 時間のファクター:仮に盗取が起こったとしてもそれを核兵器に転用するのに時間がかかるシステムを施すことで、核拡散抵抗性を高める工夫である。
包括的な評価が重要である。
燃料サイクルに対して、技術と条件を特定した中で核拡散抵抗性を示していくこと、我々が核拡散抵抗性の高い核燃料サイクルを自ら実践していくこと、そして透明性を持った核不拡散の取組みを国際的に明らかにすることが我々にとって大事な視点と考える。また、国際的に評価できる技術を開発するのが我々の責任と考える。
キャロン氏(フランス):核拡散抵抗性の外在的措置(Extrinsic measures)について説明

技術だけでは100%完全にはなりえないし、全体的・総合的な取組みが必要である。
核拡散抵抗性の外在的措置としてIAEAでも保障措置方法の研究に当たっているが、政治的な問題も介入して、非常に難しい。
3つの重要なポイント:(1)保障措置への協力、(2)保障措置協定をIAEAと締結する国を優先し、ベストプラクティスの移転・普及に努めること、そして(3)慎重にあたらなければならないこと。
ユーラトムの経験からの教訓:依存ではない、相互依存を必要とするネットワークを構築することが重要で、そのネットワークを発展させ、信頼醸成に寄与する。
ペコ氏(米国):核拡散抵抗性の高い技術を開発する重要性について
核拡散抵抗性のある技術とは、原子力利用の恩恵を享受しつつ、核不拡散を担保することを可能とする技術であり、グローバルな原子力利用の拡大によってその重要性が増している。
基本的な概念として、核拡散に対するバリアを高める、違法転用の魅力を減じる、よりコストを高める、もしくは違法転用をより検知しやすくするなどの方法・技術・プロセスによって、核拡散抵抗性を高めることである。
核拡散抵抗性技術も、広範に適用されて初めて意義があり、グローバルなアプローチを推進することが最も重要である。また、核拡散抵抗性への信頼性を確保するためにも国際協力は非常に重要である。
5.最後のメッセージ(原子力平和利用と核不拡散の両立)
内山氏
国際協力をあらゆる角度から推進することが重要であると認識した。アジア地域においても国際協力の推進が強く望まれている。
ラウフ氏
エルバラダイIAEA事務局長の提案にあるように、将来的には、機微技術・施設を多国間枠組みによる普遍的な管理下に置くことが大切だと考える。
遠藤氏
原子力利用がグローバル化し、国際協力が一層重要になっている。
日本の原子力界はもう少し国際化しなければならないと認識する。また、日本の原子力を取巻く社会も国際化するべきであると感じる。
岡﨑氏
我々が今後何を成すべきかについて、概ね国際協力を推進することで認識の一致が図られたと思う。この方向で、進めていきたいと思う。
ペコ氏
原子力利用によって全世界は気候変動の破滅的な状況に陥ることを未然に防ぐことができるが、原子力の利用の拡大によって、様々なリスク(核拡散リスク、安全リスク、セキュリティ・リスク)を拡大させ破滅的な状況に向かうことは避けなければならない。
それは、政治的な意志の維持、資金的な支援の継続を必要とするなかなか難しいことである。困難を乗り越えるために結束しなければならないが、今日は、なかなかいいスタートを切れたと思う。
ベリホフ氏
国際協力を推進する際には、冒頭でしっかりとしたビジョンを持って進めることが重要である。本当の意味での原子力開発の協力をもう始めなければならない。
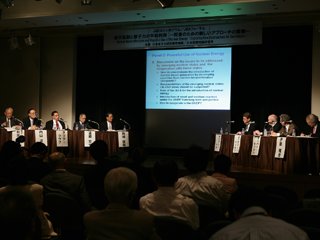
キャロン氏
原子力を使えば地球の温暖化への対抗が可能だという認識が高まっている。今や、バイオマスか原子力かの選択ではなく、原子力が必須であるとの認識が高まりつつある。
平和で安全、セキュリティが担保された原子力利用のためには、国際協力こそが鍵である。原子力利用を推進する上で、必要とされる国際協力を「投資」だと考えなければならない。
伊藤氏
相互依存の必要性を痛感した。国際協調・規制の調和が重要である。
自己満足に陥らず、次の世代に知識を引き継いでいかなければならない。
注釈
* 19京都議定書において各国の数値目標を達成するための補助的手段として導入されている、市場原理を活用する京都メカニズム(共同実施:JI、クリーン開発メカニズム:CDM、排出量取引)のこと。
閉会挨拶
長内 敬 日本国際問題研究所主幹

NPT体制を進めていく上での大きな構想として、「核不拡散」、「原子力平和利用」、「核軍縮」、の3つの柱がある。NPT体制発足時に比べると、現在はこれらの構想を推し進める意義と必要性が大きくなっていると思う。
「核不拡散」については、核兵器の拡散問題が世界の平和と安定にどういう脅威を与えているかに関する具体的な事案のニュースに毎日のように接する。また「原子力の平和利用」は、今年のハイリゲンダム・サミットで議論されまた来年の洞爺湖サミットに引き継がれる大きな中心テーマである地球温暖化問題に対処するに当たり要素のひとつとなっている。さらに「核軍縮」については、今までの、核の交渉に精通している人々の間においても究極の核廃絶が必要、との声が出てきている。
上記3つの構想を進めるためには、G8を始め各国政府・国際機関が協力していくことに加え、国際的な世論や理解の高まりが不可欠である。この面で日本がやるべきことは多々あるし、また日本だからこそ取り組める余地は大きいと思う。本日のシンポジウムがこのような方向へのステップの一つとなれば幸いであり、更にこのようなステップを色々な場所・機会において積み重ねていくことが重要だと考える。
最後に、本日の会合に参加して頂いたパネリストの方々や聴衆の皆様方に心からお礼を申し上げたい。
