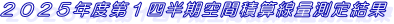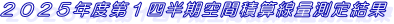| 積算線量測定 |
|
環境中の放射線を蛍光ガラス線量計によって3ケ月間積算測定し、環境安全上問題のないことを確認しています。
放射線の量(線量)は、測定地点の土質及び積雪等の影響により異なるため、地域により多少変わります(例えば、花崗岩の場合高い線量を示します)。
日本海沿岸では冬期の雷雲活動時に、線量の有位な上昇が観測されることがあります。
|
| 平常の変動幅 |
|
福井県内全調査対象地域の過去5年間(2020年度~2024年度)の積算線量の相対標準偏差(C.V)3.5%の±3倍(10.5%)に相当する積算線量の範囲です。ただし、自然放射線の変動等でこの平均的な変動範囲を上回る固有の変動幅がある地点については、地点毎に求めた過去5年間の積算線量の標準偏差の±3倍を用います。
元比田は2021年度第1四半期から蛍光ガラス線量計による測定を開始しています。平常の変動幅は2021年度~2024年度の実績を用いて算出しています。
|
| 放射線の単位〔mGy〕 |
|
ミリグレイと呼びます。放射線を受けた空気が吸収したエネルギーの量を表します。ミリグレイ(mGy)は、グレイ(Gy)の1000分の1を表します。
|
| 蛍光ガラス線量計(RPLD)の原理・特長 |
|
銀イオンを含有するリン酸ガラス(銀活性化リン酸塩ガラス)に放射線を照射し、その後紫外線で刺激すると蛍光が発します。この現象はラジオホトルミネセンス(RPL)と呼ばれ、蛍光量が放射線量に比例することから、線量計に応用されています。
特長として、繰り返し読み取りが可能で、データの再現ができます。また、フェーディング(ラジオホトルミネセンスの光量が時間の経過とともに減少すること)が少ないといった特長があります。
|
| 雷(雲)からの放射線について |
|
雷(雲)内に宇宙線等が入射することで電子の雪崩が起き、その電子の雪崩が雲下層の大気分子とぶつかって止まった際に放射線(制動放射線)が発生すると言われています。
|
| 福島第一原子力発電所事故の影響について |
|
2010年度第4四半期から福島第一原子力発電所事故に起因する空間積算線量の上昇は観測されていません 。 |