『ラテンアメリカ諸国のエネルギーセキュリティ』講演会
核不拡散科学技術センターは、2月17日(火)午後、原子力科学研究所情報交流棟に、外務省の招きに応じて来日中のJフランシスコ ファセティ Paraguay国防省高等戦略研究所教授を招へいし、教授の多忙な日程の1日を割いてもらい、講演会を開催した。

ファセティ氏は、午前中は希望でもあったJPARC、JRR-3、JRR-4等施設視察を行い、午後の講演会『ラテンアメリカ諸国のエネルギーセキュリティ』に臨んだ。中南米の水力、石油・ガス、石炭及び原子力等によるエネルギーの需給事情と核不拡散の係る取組み等について、機構職員約30名に対する約1時間半の講演で、職員からの質問に熱心に答え、午前の施設訪問と合わせて、日本の原子力開発の理解を深めた。機構側は、普段、なかなか知りえない南米のエネルギーと核不拡散に係る諸事情の理解の促進に役立てた。
中南米には33の諸国があるが、南米は水資源が豊富であるため、水力発電に関してパラグアイは100%依存し、ブラジル、アルゼンチン等も水力が中心となっている。現時点で利用可能な水資源の利用度は2割強であるが、今後100年以上にわたって諸国の需要を賄うことができる水量という。さらに、石油・ガスについてはアンデス山脈地帯と大西洋沿岸で豊富な埋蔵量があるため、ベネズエラ、メキシコ、ボリビア等はこれらを輸出できる国となっており、今後の大陸棚からの発掘の状況によって、ブラジルが主要国になる可能性がある。

原子力発電の利用は、石炭火力の5%よりも少なく、ラ米諸国全体としてエネルギー比率で2%であり、2025年まで見通してもこれが3%になる程度である。メキシコはラグナ・ベルデ1基で140万KW、ブラジルはアングラ‐1及び2で190万KW、アルゼンチンはアチュカⅠとエンバルスで100万KWの発電を行っており、ブラジルが将来的に8基程度に拡充する計画を有し、原子力が国家にとって重大であるとする国家戦略防衛政策を出している。しかしながら、他の諸国では原子力の人材や知識が不足し、また設備として高価であるため、豊富な水資源を考慮すれば、世界の積極的な原子力発電利用の方向に向かうようなことにはならないという。また、グリーンピースの活動は、気候変動のこともあり、そんなに強いものではなく、概して、南米諸国の住民は情報をあまり知らされていないこともあり、ダムなどの環境問題に過敏でないという。
最近注目を集めているバイオエネルギー開発については1973年の石油危機を契機に開始され、砂糖きびから精製されるエタノール生産が主にブラジルで進んでおり、今後数年で生産が倍増されるとのことである。トウモロコシを利用するバイオ燃料が肥料コストの高騰になっているとの参加者の指摘に対して、砂糖きびを利用したバイオ燃料であるため、この問題はないと力説した。

一方、ボリビアのモラレス政権は、4年前から電力会社を国有化し、最近ではロシア企業との提携による天然ガス開発も行おうとするなどの思惑もあることや、景気減退による低物価や投資の遠のきが社会に与える懸念なども紹介された。
核不拡散問題に関しては、キューバ危機を経て、トラテロルコ条約(ラテンアメリカにおける核兵器の禁止に関する条約)が1967年に署名され、69年に発効し、全諸国が批准国となっているが、これはフランスのサハラ砂漠での核実験に対してアフリカ諸国が起こした非核化の動きにも触発されてできたものとのことである。なお、条約の第1追加議定書には、この地域に領土を有する英、仏、蘭、米が参加している。また、第2追加議定書では、全米相互援助条約(リオ条約)の加盟国である米国を含む五つの核兵器国が加入している。
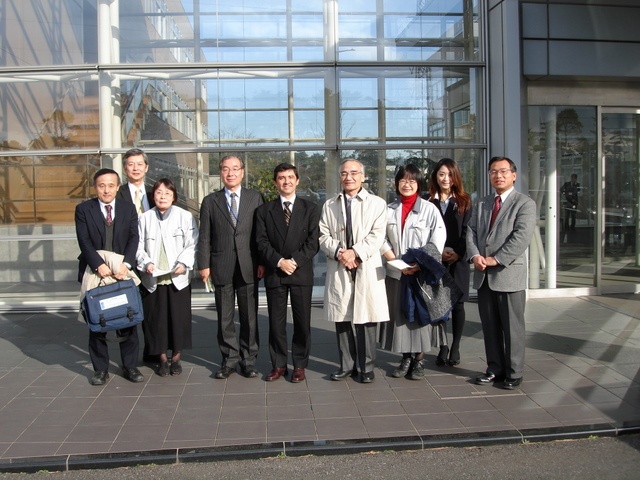
ファセッティ氏は、2006年よりエルバラダイIAEA事務局長諮問機関であるAdSec(核セキュリティーに関する諮問グループ)のメンバーでもあるが、トリウム、劣化ウラン、Am、Ir、Cs、Co等を対象にした密輸が頻発し、各国国境で摘発されている現状に触れ、各国の核セキュリティーに関する能力強化のため、IAEAの支援活動であるINSServ(核セキュリティー助言サービス)を受けている旨説明するとともに全世界各国が参加する国際枠組みについても説明した。
最後に、ブラジルとアルゼンチンが設立している保障措置査察に係る枠組みであるABACCに関連する質問に関して、南米ではブラジルのようにCentral Stateを標榜する国が現れるが、人種、言語、文化、宗教、教育等において違いがあることから、安定性、予測性がなく、EUのようなまとまりへの発展はないであろうことが説明された。
