「アジア地域の原子力利用の推進と核不拡散の両立に向けて」*
この報告は、フォーラムでの講演やパネルディスカッションを事務局が取り纏めたものであり、講演者やパネリスト本人の確認を受けているものではなく、その発言は、個人としての発言であり、国や組織を代表したものではない。また、脚注は、事務局が参考として付したものである。
1. 開会挨拶(6月24日10:00-10:05)
(日本原子力研究開発機構(JAEA)理事長:岡﨑俊雄)

- 現在、地球温暖化、石油価格高騰、エネルギーセキュリティといった世界が直面する深刻な課題を解決するにあたり、原子力の重要性が認識され、世界的に原子力ルネサンスが叫ばれている。
- 特に、アジア地域では、インド、中国、韓国で原子力発電計画が進められているほか、タイやベトナム、インドネシアも新たに原子力発電の導入を目指している。
- 一方で、北朝鮮やイランの核開発問題や核テロなどの核拡散の懸念について注視していく必要がある。原子力の平和利用と核不拡散の両立こそ世界の持続的発展にとって不可欠と認識している。
- 我が国は、唯一の被爆国として国際社会に対して、全面的な核廃絶を訴えるとともに、原子力を平和利用に限り推進してきた。原子力の平和利用と核不拡散の両立のために、我が国の経験や技術が生かされるべきであると考える。
2. 基調講演(6月24日10:05-13:00)
○アジア地域の原子力利用と日本の貢献
(東京大学大学院情報学環教授:田中明彦氏)

- 1903年、岡倉天心は、「東洋の理想」の中で、理念においてアジアは一つと主張した。現在、アジアは緊密な経済関係を構築し、一つになりつつあり、中国、インドの台頭、そして、アジア全体が台頭していると認識している。
- アジアの台頭は、エネルギー需要の増大を意味するが、需要を賄うために化石燃料ばかり使用しては、地球温暖化問題の解決にはならず、いわば原子力の平和利用の拡大は必然的である。しかし、原子力の負の側面として、核兵器の問題に目を向けないわけにはいかない。
- 近代アジアは戦争の歴史であり、1840年以降、10年ごとに戦争・紛争が勃発していたが、1970年代後半以降、東アジアでは国家間の戦争は起こっておらず、さらに冷戦終結以後、アジアでは国家間の外交関係も正常化している。このような平和があったからこそ、経済が目覚しく発展した。
- このように全般的にアジアは平和であると言えるが、(1) イラン、北朝鮮(核開発問題)、(2) アフガニスタン、パキスタン(国内の安定化問題)、(3) テロという、安全保障上の不安定要因も残っており、これらは全て核の問題に関連している。
- 核不拡散、原子力安全といった問題はあるものの、アジアにおいて、原子力の平和利用は不可欠であり、核不拡散、原子力安全を確保しつつ、いかに原子力平和利用を拡大していくかということが今後の課題となる。
- アジア地域の原子力協力の枠組みは未発達だが、既に、有効な協力の枠組みを構築する機は熟しつつある。1989年からのアジア太平洋経済協力(APEC)* 1閣僚会議、1997年からのASEAN+3首脳会議* 2、2005年からの東アジアサミット等、多国間協力の枠組みが構築されつつある。化石燃料の使用による産業革命の時代においては、アジア諸国は発展途上国であったが、アジア地域の今後の発展を支えるのは原子力であり、核不拡散の分野で多くの経験を有する日本の果たすべき役割が大きい。
注釈
* 1APEC:Asia-Pacific Economic Cooperation Conference
* 2ASEAN+日本、中国、韓国
○韓国の原子力利用の展望と核不拡散遵守に向けた取組
(韓国核不拡散核物質管理院(KINAC)理事長 リー・ハンギュ氏)

- 1981〜91年、韓国は、エネルギー消費が経済成長を上回る状況だったが、通貨危機以降、GDPの低下に伴い、エネルギー消費も低下した。現在、政府として、効率的なエネルギー消費を目指している。
- 韓国のエネルギー消費は世界でもトップ10に入り、石油では7位、原油の輸入量は世界第4位である。
- 現在、運転中の原子炉は20基、許認可中が8基である。今後、発電量に占める原子力の割合は現在の約40%から約43%に増加することが予想される。
- 韓国政府は、近々、今後25年間の新エネルギー計画を発表する予定である。同計画によれば、2030年までに平均年率3.7%の経済成長が見込まれているが、エネルギー需要は年率1.7%の伸びにとどまると予想されている。2030年までに全体のエネルギー消費を抑制し、一人当たりのエネルギー需要を抑えることは可能と考えている。同計画が国家計画として採用されれば、2030年までに韓国の原子力発電は発電設備容量で現在の26%から37〜42%に上昇する可能性がある。原子力業界は最低でも37%の発電設備容量が必要と主張しているが、その場合、更に9基の原子炉を建設する必要がある。その結果、一次エネルギー源で原子力が占める率は現在の約16%から26〜29%にまで伸びることが予想される。
- 1999年に追加議定書に署名した。実験規模のウラン濃縮が未申告であり、IAEAに当初提出した報告書の正確性と完全性について確認を受けた。
- 韓国の政策の基本は、朝鮮半島の非核化である。また、韓国の原子力政策の要は、2004年に発表した原子力平和利用の四原則である(核兵器を保有しないこと、透明性を確保すること、国際約束を遵守すること、国際社会の信頼を得つつ原子力平和利用を進めること)。
- 2008年6月、IAEAより、全ての核物質が平和利用の下にあるとの拡大結論を得て、現在、統合保障措置の導入のためIAEAと協力して作業中である。9月の統合保障措置合同レビュー会合で更に強化された覚書に署名する予定である。
- アジアは、文化的且つ歴史的に多種多様のため、即座に協力を推し進めることは難しく、原子力平和利用の地域協力については、ある程度の時間が必要かもしれない。
- ASIATOMなどの提案がされているが、このような動きは、よりよい将来を作るための土台作りになると思われる。
- アジア太平洋地域における定期的会合は有意義と考える。最終的に、IAEAの活動をサポートまたは補完する活動を行っていくことも視野に入れるべきである。
- KINACは、IAEAとの間で核不拡散に関する協力を強化することを望んでいる。また、北東アジアの原子力の透明性の向上に貢献する用意がある。韓国は、原子力を平和目的に利用しつつ経済的なメリットを享受する模範的な国になることを望んでいる。
- 互いの国から、それぞれの経験や知識を学びあうことが重要と考える。
○新興の原子力発電導入予定国における導入計画、導入に向けた規制の枠組みの準備状況、核不拡散に向けた取組
(ベトナム原子力委員会(VAEC)副委員長 レ・ヴァン・ホン氏)

- 過去10年間、顕著な経済成長を遂げてきた。年8%の経済成長率を記録し、それに伴い電力需要も拡大している。最近では、年間電力需要の伸び率は17%を上回り、エネルギー安全保障はベトナムにとって重要な課題と認識している。
- 将来の需要予測、供給体制の整備に関して検討した結果、2015年ごろからエネルギー輸入国になることが判明した。需給バランスを念頭に、2019年〜20年を目途に原子力発電所(2,000〜4,000MW)を導入する必要性が指摘された。
- 2006年、ベトナム政府は2020年までの「原子力平和利用のための戦略」を、翌年には同戦略を実施するためのマスター・アクション・プランを、それぞれ承認した。このプランには、23のプロジェクトがあり、そのうち10のプロジェクトは原子力発電に直接関係しており、残りの13は発電及び非発電双方に関係している。
- 最初の原子炉については、2010年ぐらいにはフィージビリティスタディを完了し、2015年前後に建設着手、2020年に運転開始を目途にしている。2基目については2021年ごろの運転開始を目指している。
- 年間経済成長率7%をベースとした想定によれば、水力や石油等も含めた電力量の合計は2020年に294TWh、2030年に567TWhに達する予定である。
- 今年6月に成立した原子力法(11章93条)の起草にあたっては、IAEA、日本、韓国、フランスなどの関係文書を参考とした。
- ベトナムにおいては、科学技術省が原子力の安全及び放射線防護等を所掌する監督官庁であり、科学技術省の下に、原子力委員会(VAEC)、放射線・原子力安全管理庁(VARANSAC)が設置されている。VAECは原子力政策、研究開発、対外関係を担当しており、VARANSACは規制を担当している。人員や専門性がまだ不十分で、能力強化が急務である。
- 原子力政策は、一貫して明確に平和利用を推進してきており、「原子力平和利用のための戦略」や原子力法において平和利用が明確に謳われている。
- 核不拡散政策としては、1982年にNPTに加入、1989年に包括的保障措置協定に署名、2007年8月には追加議定書に署名し、現在、批准に向けて準備中である。その他、東南アジア非核兵器地帯条約を締結している。
- 2006年に批准したCTBTは、重要な条約であると認識しているが、現在、未発効であることは残念に思う。
- 原子力安全条約、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約、核物質防護条約、等の署名についても検討している。
- 原子力関連の人材育成はますます重要であり、マスター・アクション・プランに基づき、2つのプロジェクト(原子力発電と非発電分野)を実施している。ただし、人材も将来の需要に応えられるだけの人数が確保できず、VAEC、VARANSAC、電力公社等で既存の人材(職員)の能力強化を行っている。電力公社が特に導入に向けた人材育成を行い、VAECが長期的な計画のための人材を育成している。今後、大学とも提携し、カリキュラム、教材、講師陣の拡充を図り、人材育成面の強化を図る予定である。
- 原子力の利用はベトナムの社会経済発展に多大な寄与を果たすものであり、原子力開発は増大するエネルギー需要に対応する有効な手段と位置づけられる。しかし、原子力発電は、人材、インフラ、財源面で容易に導入できるものではなく、原子力発電の導入、将来計画、推進には国際協力が極めて重要と認識している。
(インドネシア原子力庁:カリヨノ副長官)

- 2006年、大統領令5号により、2025年までのエネルギー・ミックス計画を策定し、原子力発電を国家エネルギー政策の一環として利用することがうたわれた。2025年には主要エネルギーの2%、国の電力供給の4%を原子力でまかなうことを計画している。2017年頃に最初の原子力発電所を完成させることを目指している。
- 2007年には、2005〜2025年までの国家長期開発計画が策定された。
- 原子力発電のためのインフラ開発の第1段階は終了し、現在、第2段階の最終段階である。今後、第3段階に入り、建設を開始する予定である。
- 持続可能な原子力システム(NES)の適用及び開発のための指針が既に作成されており、その指針は、経済性、安全性、環境、廃棄物管理、核不拡散、インフラ整備など原子力エネルギーの全ての面を網羅した内容になっている。
- NESの基本原則や要件は、国際規制、国際規範、世界のベストプラクティスに従った内容になっており、エネルギー・ミックスの最適化を達成することは可能と考える。また、エネルギー安全保障の実現も可能である。
- 憲法の第4章には、平和、人権、反植民地主義、国家の独立等を推進することなどの規定があり、核不拡散に関しては、NPTは1970年に署名し、1979年に批准している。IAEAとも協調しており、包括的保障措置協定は1980年に署名し、追加議定書は1999年に署名、発効している。原子力安全条約や核物質防護条約等も締結しており、アジア原子力安全ネットワーク(ANSN)にも積極的に参加している。
- 原子力分野の人材育成については、原子力庁(BATAN)及び原子力規制庁(BAPETAN)の両機関で行っており、年間約30のトレーニングコースが用意されている。BATANの人材育成コースについては、主に放射線防護に関するコースである。
- 原子力エネルギーを導入することで、コスト及び環境負荷の観点から最適なエネルギー・ミックスを導入できるだけでなく、石油やガスに対する需要の高まりを抑え、持続可能な開発が可能となる。ただし、原子力発電導入に向けて行われた調査は、まだ完全ではなく、随時アップデートすることにより達成可能と考える。
- 原子力発電の導入に向けた課題としては、国民の理解(PA)、資金調達の枠組みの構築などが挙げられる。
○新興の原子力発電導入予定国に対するIAEAの協力、取組
(IAEA:アパロ東京事務所長)(ハイノネン氏の代読)

- 今、原子力に対する関心が高まっている背景としては、原子力がエネルギーセキュリティを向上させ、エネルギー供給の多様化をもたらすほか、地球温暖化問題への対応策としても有効であり、低発電コストや信頼性の高いエネルギー源であることが挙げられる。
- 現在、途上国の電力需要が増えている。全世界で原子力発電所の建設を検討している国の半分は途上国で、アジアにおいてはタイ、インドネシア、ベトナムが導入検討中で、フィリピンも長期的な選択肢として検討中であり、マレーシアも国内で導入について議論をしている。
- 原子力発電導入には大きなインフラが必要で、特に安全分野のインフラが重要である。原子力発電は、10〜15年の計画期間が必要であり、全体としては100年間の長期のコミットメントを必要とする。
- 原子力発電導入のための主要な段階としては、原子力発電導入決定の前段階、建設準備段階、建設関連活動段階の3段階がある。原子力発電導入前には、核不拡散、安全、セキュリティ、長期の廃棄物管理、そして公衆の信頼確保についての検討が必要である。
- 原子力発電を導入しようとする国は、きちんとした国内計量管理制度(SSAC)を築くことが重要である。原子力エネルギーを利用する国にとって、特に3S(Safety, Security, Safeguards)は重要である。現在、3Sは、個別に捉えるではなく、連携させつつ包括的に推進するアプローチが模索されている。
- 各国の関係機関はIAEAの査察業務をサポートする重要な役割を担っている。そのため、IAEAは、各国の要請を受けて行うSSAC強化のためのサポートプログラムを提供しているほか、トレーニングコースも提供している。
- IAEAは法的文書の策定、国際的かつ地域的インフラの整備、安全基準の策定、レビュー等で中心的な役割を担っている。
- 原子力を利用する上で、インフラ整備、安全とセキュリティのための人材育成、国際原子力安全体制への完全なコミットメント、健全な国内計量管理制度の構築などの課題が挙げられる。
- 地域的な協力体制の構築を通して、透明性を高めていくことが重要である。
3. パネル1(6月24日14:30-18:00)
(1) テーマ
- 原子力平和利用の推進と国際協力
(2) モデレーター
- アジア原子力協力フォーラム(FNCA) 日本コーディネーター 町 末男氏
(3) パネリスト
| フランス原子力庁(CEA)企画・渉外局長兼国際部長 | オリバー・キャロン氏 |
| インドネシア原子力庁(BATAN)副長官 | カリヨノ氏 |
| 日本原子力産業協会 常務理事 | 石塚 昶雄氏 |
| 東京大学大学院工学系研究科教授 | 田中 知氏 |
| 韓国核不拡散核物質管理院(KINAC) 理事長 | リー・ハンギュ氏 |
| タイ・エネルギー省 技術顧問 | プリチャー・カラシュディ氏 |
| 米国エネルギー省(DOE)GNEP燃料サイクル技術担当次長 | カーター・サベージ氏 |
| ベトナム原子力委員会(VAEC) 副委員長 | レ・ヴァン・ホン氏 |
(4) 趣旨
基調講演で示されたアジア各国における原子力平和利用の拡大の動きを受け、エネルギー安全保障、地球温暖化防止の観点から、原子力の重要性を再確認するとともに、原子力発電の拡大に伴う様々な課題について議論し、更には新規原子力発電導入国に対する国際協力としてどういったことが考えられるか、また、多国間の協力枠組みの可能性について議論した。
(5) モデレーター・パネリストのプレゼンテーション、発言の骨子
1) 原子力の重要性、原子力発電の拡大に伴う課題について
町氏 「アジアにおける持続可能な成長に原子力が果たす役割」

(将来のエネルギー予測)
- 国際エネルギー機関(IEA)の2030年までのエネルギー見通し* 3によれば、化石燃料は主要なエネルギー源であり続け、中でも石炭の需要は73%増加することになる。電力需要は倍増することが予測されており、レフェレンスシナリオでは、二酸化炭素排出量は57%増加することになる。
(原子力発電を中心としたアジア各国(特に本フォーラムに参加していない国)のエネルギー状況のレビュー)
- オーストラリアの新政権は原子力を推進しない政策をとっているが、ウラン資源の輸出については継続していく方針である。
- バングラデシュは、ループール原子炉計画を有しているが、資金調達が最大の課題である。
- 中国は、石炭が主要なエネルギー源であり(70%)、大気汚染、酸性雨、地球温暖化の問題を引き起こしているため、石炭への依存度を下げるのが今後の課題である。また、石油の40%を輸入に依存しており、エネルギーセキュリティの確保が重要な問題になっている。エネルギー使用の効率化、水力発電の推進も課題として挙げられる。原子力に関しては、現在、11基、9GWの原子炉を運転中であり、先月、日本で開催された会議では、中国の参加者から、2030年までに原子力発電容量を80-120GWに拡大するとの目標が示された。これは2020年以降、毎年5-8基の原子炉を建設することを意味する。中型の原子炉については自前で建設する能力を有しているが、大規模な原子炉の国産化をいかに実現するかということが、今後の課題として挙げられる。
- インドでは、電力供給のうち60%が石炭によって賄われており、大気汚染、地球温暖化の問題が生じている。原子力に関しては、国産の重水炉を開発、建設、運転している点に特徴がある。現在、15基の原子炉を運転中であるが、設備容量は3.4GWであり、小型炉が中心である。2020年までに25-30GW(FBRを含む。)分の原子炉を増設する計画がある。
- 特に、中国、インドにおいては、今後、急速なエネルギー需要の増大が予想されており、地球温暖化ガスの排出を抑制することを目的とした協力が必要である。
- マレーシアは、原子力のオプションを真剣に検討中である。
- フィリピンは、電力源として、地熱発電の占める割合が多いのが特徴的である。原子力を含む国産のエネルギーを増やすことが必要とされている。約20年前にバターン原子炉(620MW)が完成したが、世論の反対等により運転の開始ができない状況が続いている。IAEAは、フィリピンにミッションを派遣し* 4、今後の運転が可能か否かの観点から同原子炉の検証を実施した。3年後にフィージビリティ調査を完了させ、同炉の運転の可否を決定することになる。
- また、原子力発電の導入を前提とした人材開発プログラムを既に開始している。

(FNCAの活動状況の紹介)
- 約20年前に日本政府の主導により開始された枠組みであり、8年位前から、より需要国側のニーズに合うよう、プログラムの再編成が行われた。
- 参加国は、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムであり、大臣級会合、コーディネーター会合が年1回、開催されている。
- 2000年の大臣級会合で採択された共同コミュニケの中で、原子力利用に関し、積極的な地域的パートナーシップを通じ、社会経済的発展を強化する有効なメカニズムとしてFNCAの役割が示されている。
- FNCAの枠組みで、農業利用、加速器利用、医学利用、放射性廃棄物管理、原子力安全文化等、11のプロジェクトが実施されるとともに、原子力エネルギーに関するパネルが設置されている。
- 原子力エネルギーのパネルは約4年前に設置されたものであり、FNCA参加国の原子力発電の専門家及びエネルギー政策決定者間の情報交換、意見交換の促進を目指すものである。
- 2007年のパネル会合では、(1) 原子力発電は確立された技術であること、(2) 原子力発電は運転の過程で地球温暖化ガスを排出せず、地球温暖化や環境汚染を緩和するものであること、(3) 原子力発電は京都議定書に規定されるCDM* 5に含まれておらず、COP* 6に対し、原子力発電をCDMに含めるよう求めていくことが重要であること、(4) 原子力発電の導入にあたっては、原子力安全規制、セキュリティシステム、人材育成、PA等の整備が求められることが確認された。
- 2007年12月のFNCA大臣級会合の共同コミュニケでは、(1) 核不拡散、原子力安全、核セキュリティを確保しつつ、原子力発電を推進すること、(2) 原子力発電をCDMに含めることが検討されること、「気候変動特別基金」を原子力発電施設に利用できるようにすることが述べられており、本文書はIAEAのINFCIRC文書として公表された。
- また、最近の動きとして、2008年6月にボンで開催されたCOPの小委員会において、日本政府が原子力発電をCDMに含めることの検討を提案しており、ポスト京都議定書の枠組みで、本問題がとりあげられることを期待している。
- 原子力エネルギーのパネルの第1フェーズは約1年半前に完了し、第2フェーズとして「アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル」が設置された。2007年10月に開催された最初の会合において、原子力導入のための人材育成に関する情報交換、人材育成のためのウェブサイトを立ち上げることに合意した。
- 人材育成に関しては、FNCAの活動の一部であるアジア原子力教育訓練プログラム(ANTEP)の下で原子力発電に関する基礎訓練を提供しており、経済産業省や文部科学省がワークショップを開催している。
- 2008年9月に原子力安全のためのインフラの整備をテーマとして、「アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル」の第2回会合が開催される予定である。
(将来の原子力発電の予測)
- 原子力を利用する上で、インフラ整備、安全とセキュリティのための能力の構築、国際原子力安全体制への完全なコミットメント、健全な国内計量管理制度の構築などの課題が挙げられる。
- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)のWorking GroupIIIやIAEAによる将来の予測において、原子力の果たす役割が認識されている。IPCCの報告では、原子力発電の占める割合は、現状の16%から、2030年には18%に上昇すると予測されている。IAEAによる予測では、原子力発電容量は、現状の370GWから2030年には690GWに増加するとされている。とりわけ原子力発電が拡大する地域は、米国とアジアであろう。
(原子力発電に関する最近の動き)
- 2008年5月にイタリアが原子炉建設を決定した。
- 湾岸諸国の間で原子力発電に対する関心が高まっている。
- IEAのエネルギー見通しでは、2050年までに地球温暖化ガスを半減させるために、年間32基の原子炉の建設が予測されている。
- 米国では、2016年までに4-8基の新たな原子炉が運転を開始することが想定されている。米国の新政権が原子力を推進することを期待しており、最近、共和党のマケイン候補は2030年までに米国において新規に建設される原子炉の数は45基に達するとの見通しを示している。
サベージ氏(DOE) 「国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)と不拡散」

(エネルギー、原子力の将来予測)
- DOE/エネルギー情報局(Energy Information Administration)は、IEAの予測と若干異なり、世界のエネルギー消費は2030年までに57%増加すると予測している。
- 地球温暖化防止の観点から原子力発電に関する関心が高まっており、今後25年間で新たに原子力発電を導入することが予想される国は25か国以上に上る。
(米国における原子力発電の状況)
- 2016年までに4-8基の原子炉の運転を開始する予定であり、9の電力会社が15基の原子炉の建設・運転一括許可を申請中である。
(GNEP)
GNEPの国際的な活動状況(7つの柱、「原則の声明」、参加国、構造、WGの状況)は以下のとおりである。
- 既存のWG(インフラ開発WG、信頼性が高い燃料供給サービスWG)以外に、小規模な系統に適合した原子炉の開発に関するWG、廃止措置中の核燃料サイクル施設における廃棄物管理を扱うWGの設置が検討されている。
- 次回の閣僚級会合は2008年10月にパリで開催され、2つのWGの検討状況の報告が予定されている。
- 核不拡散の観点からは、信頼性が高い燃料サービスを構築することが重要である。また、現状で、他の国からの使用済燃料の引取り、自国での処分を表明している国はなく、燃料供給保証システムの構築の障害となっている。
キャロン氏(CEA) 「フランスのエネルギー政策と原子力」

(フランスのエネルギー政策、原子力政策)
- フランスは、1970年代の石油危機後、原子力発電を導入する戦略的決定を行った。1973年から30年間でフランスにおける電力利用は3倍に拡大したが、原子力発電の導入、拡大によるところが大きい。また、フランスは世界最大の電力輸出国であるが、原子力発電が大きく寄与している。
- フランスには59基、63GWの設備容量の原子炉が立地し、フランスにおける電力供給の78%、世界の原子力発電の17%を占めているが、政府の強力な権限による原子力発電計画の実施、履行という点が特徴的である。
- 原子力産業のキャパシティの制約から、原子力ルネサンスには、懐疑的な見解もあるが、15年間で49基の原子炉を建設したというフランスの経験からは可能である。
- フランスの原子力政策のもう1つの特徴は、フルセットの核燃料サイクルを有することである。
- フランスは、EUの中で、1人あたりのCO2排出量は最小であるとともに、電力価格が最も安いが、これらは原子力によるところが大きい。
(原子力関係の立法の動き等)
- 2005年に制定されたエネルギー法では、供給保証、競争力のある価格の確保、環境・地球温暖化対応、エネルギーへのアクセスの提供を4つの目標とし、需要抑制、供給の多様化(再生エネルギーの開発、原子力オプションの保持)、研究促進、電力・ガスの輸送・貯蔵改善を4つの手段と規定した。
- 2006年に制定された原子力安全・情報開示法では、独立した規制当局を新たに設立するとともに、透明性のプロセスを改善した。
- 2006年には、廃棄物管理法の制定により、公衆の廃棄物管理に関する理解を増進させた。
- 原子力に対するフランス国民の支持は高く、緑の党の支持者の間でも、原子力の廃止を望んでいる人は半数に達していない。
- 2015年には、現在運転中の第2世代の原子炉をリプレースするか否かの決定がなされる予定である。
(欧州全体の動き)
- 欧州全体としては、20/20/20コミットメントと称される、2020年にはエネルギー需要の20%を再生可能エネルギーで賄うこと、地球温暖化ガスを20%削減する目標が設定されているが(2007年3月欧州サミット決定)、原子力なしではこの目標の達成は不可能であるということが、コンセンサスとなりつつある。
(国際協力の取組)
- 原子力発電の拡大には国際協力が不可欠であり、最近、フランスでは、原子力発電を導入する国への支援のための組織を設立した。
田中氏(東京大学) 「日本における原子力-現状と将来計画、核不拡散の重要性」

(日本のエネルギー政策、原子力政策)
日本の原子力利用の歴史、日本のエネルギー状況、原子力発電の状況、原子力政策(核燃料サイクル計画、原子力政策大綱、原子力立国計画、地球環境保全・エネルギー安定供給のための原子力のビジョンを考える懇談会(ビジョン懇談会* 7)報告書)、核不拡散の取組、FBRサイクルの研究開発動向、原子力産業の国際展開、原子力教育の現状(原子力学会の活動、東大原子力国際専攻、グローバルCOE)等について説明がなされたところ、主な発言は以下のとおりである。
- 1955年に制定された原子力基本法において平和利用に徹する旨が明記されている。原子力政策は約5年ごとに見直されているのが特徴の1つである。
- 55基の原子炉が運転中、2基の原子炉が建設中であり、六ヶ所再処理工場は近く運転を開始する予定である。
- 2005年に策定された原子力政策大綱においては、原子力発電の占める割合を30-40%あるいはそれ以上に増加させること、核燃料サイクルを基本政策とすること、FBRの実用炉は2050年頃に導入されることが重要項目として挙げられるが、核不拡散関連の政策については、平和利用の担保、国民による共通理解・国際社会への情報発信、核不拡散・軍縮体制の強化、新提案への参加、知識管理・人材育成・技術開発といった項目の中で述べられている。
- 2006年8月に採択された原子力立国計画では、原子力、再生可能エネルギーのどちらかではなく、両方とも活用していくことが示された。
- ビジョン懇談会の報告書では、原子力エネルギーの平和利用の世界的な拡大に向けた6つの取組が示されているが、取組2として、「原子力エネルギーの平和利用の前提となる核不拡散、原子力安全及び核セキュリティの確保のための国際的取組の充実」が挙げられている。
(人材育成)
- 原子力を専攻する学生の中で、近年、博士課程の学生数が増加している。原子力分野で世界的に活躍できる人材の育成が重要である。
カラシュディ氏(タイ・エネルギー省)

タイのエネルギー構成、原子力政策、原子力発電導入計画(サイト選定、フィージビリティスタディ(FS)等)、導入にあたってのコミットメント等が説明されたところ、注目される発言は以下のとおりである。
- 現在、電力の67%は天然ガスにより賄われているが、この割合を減少させるためには原子力が必要であり、2020年に2基、2021年に2基導入予定である。
- 濃縮、再処理施設は国内で建設しないことをコミットしている。また、使用済燃料については原子炉施設で40年間貯蔵することが計画されている。
- 一旦、原子力の導入決定がなされたら、政権交代によって変更がなされないようにすることが重要である。
2) 国際協力の重要性と協力のあり方
石塚氏(日本原子力産業協会(JAIF))
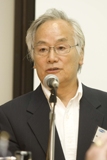
原子力開発のそれぞれの段階に応じた国際協力のあり方、官民の役割、JAIFのアジア諸国に対する協力の取組等が説明されたところ、主な発言は以下のとおりである。
- 新規原子力導入国に対する協力については、対象国に応じたきめ細かな協力が重要である。
- 原子力開発の段階は、インキュベーション期と呼ばれる原子力導入に向けた基盤づくりの段階、ビジネスモデルの形成期、ビジネスの開始期、ビジネスの定着・充実・拡大期の4つに分けられる。
- インキュベーション期とは、原子力発電導入の国家レベルでの政策決定に向けて検討がなされている段階であり、現在、かなりの数の国がインキュベーション期にあると位置づけられる。インキュベーション期の取組が重要であり、原子力先進国は、原子力開発の意義、法規制、開発体制、核不拡散、人材育成に関して、官民が協調して協力することが重要である。特に、日本の核不拡散分野での経験を伝えていくことは意義が大きい。
- 協力の手法として、セミナー、国際会議の開催、原子力発電所の見学、展示会の開催、訓練の提供等による人材養成が考えられる。
- 我が国は、政府間では、FNCA、原子力発電所運転管理等国際研修事業(千人研修)、アジア原子力安全ネットワーク等のプログラムの下で協力を実施してきた。また、民間レベルにおいては、早い段階からJAIFを窓口とした協力を実施してきた。
- 一方、実用段階の国際協力に関して、従来、我が国は原子力産業の海外展開に消極的であったが、原子力立国計画に原子力産業の国際展開支援が明記されたことにより官民の協力体制が強化されつつある。具体的な動きとして、2005年の中国の原子炉の受注にあたっての中川経済産業大臣による支援書簡の発出、2007年4月のカザフスタンへの官民合同ミッションの派遣、2008年5月のベトナムとの協力覚書の締結が挙げられる。
- ビジネスモデルの形成期(インドネシア、ベトナムがこの段階にある。)においては、コンサルタント契約を通じてFSに協力することが一般的となっている。
- 日本の原子力産業は、平和利用への限定、最新鋭の原子炉の建設、運転の実績、予算や建設スケジュールの厳守といった点に特徴があり、こうした特徴を認識して世界の原子力発電の発展に貢献していくべきである。
レ・ヴァン・ホン氏(VAEC)

- 原子力発電の導入は途上国にとって難しい決断であり、ベトナムの場合、決定のための調査に10年以上を要した。
- 日本の様々な機関から原子力の導入のための協力を得てきた。例えば、2000年に締結された、JAIFとベトナム原子力委員会(VAEC)との間のMOU、原子力法に関する海外電力調査会(JEPIC)との協力、ハノイのトレーニングセンターの整備に関する支援、ワークショップ、セミナーの開催、訓練の提供等を通じた協力、プレフィージビリティスタディ(プレFS)に関する協力が挙げられる。
- 特に、プレFSは全体で16章からなる膨大な文書の作成を必要とする調査であったが、日本の企業の協力を得て、共同で作成した。また、「原子力平和利用のための戦略」の作成にあたっても同様に、日本の専門家からの協力を得た。
- 人材の育成については、ベトナム電力(EVN)は昨日、人材育成計画を発表した。また、VAECも、規制機関、研究所、技術支援機関等のための長期的な人材育成計画を有しているが、この点においても日本からの協力を得てきた。
- 日本だけでなく、フランス、韓国等から支援を得てきており、専門家の派遣等においてIAEAも重要な役割を果たしてきた。今後も日本やフランスなど、原子力先進国からの更なる支援に期待したい。
カリヨノ氏(BATAN)

- インドネシアは1970年代から原子力発電導入計画を有している。1997年の原子力法により、推進と規制が分離され、規制を担当する機関として新たにインドネシア原子力規制庁(BAPETEN)が設立された。
- 原子炉立地場所の選定にあたっては、日本の企業が耐震等における経験等から立地場所選定の契約を勝ち取り、2004年に原子炉が運転を開始する予定であったが、政治危機及び経済危機により頓挫した。
- 現在は、原子力法や大統領令等により、2016年、2017年、2023年、2024年に原子力発電を導入する必要性が規定されている。
- 原子力発電の導入の準備にあたってはIAEAによる支援を受けてきた。
- 今後、原子炉の建設を開始するにあたって新たな大統領令の制定が必要になる。
- 原子炉建設にあたっての重要な要因は、一般の理解を得ること(PA)と財源の枠組みであり、原子炉建設の決定前だけではなく、廃止措置に至るまでの全ての期間にわたるPAが重要である。また、政府の支出を少なくすることや電力料金を安くする観点から、原子炉の建設にあたっての財源の枠組み整備も重要である。電力会社は原子炉の建設に積極的である。
- 原子炉の運転のための人材育成の適切な方法については検討してきた。
- これまでのJAIFによる協力やFNCAの枠組みでの協力に感謝している。

町氏
- インドネシアが他の国と異なる点は、原子力庁(BATAN)に3,000人以上のスタッフを擁している点である。従って人材開発は進んでいると言えるが、インドネシアが原子力導入を行うにあたりキーとなるのは、PAの問題であろう。
田中氏(東京大学)
- 日本の大学は、長期にわたり、アジアの学生・研究者の受け入れ等、人材育成に対し貢献してきた。
- 総合的、多角的な協力の中での意義付け、10年単位での長期スパンでの人材育成、どういった人材を育成するかについてのビジョンが重要である。
- 日本における人材育成の経験を良い点、悪い点を含めて伝えていきたい。
- 人材の優秀さの分布にばらつきがでるのは致し方ないが、分布の平均を高くする意識を持つことが重要である。
- 原子力の平和利用推進のための協力に関しては、日本のモデルを機械的にあてはめようとするのではなく、他の国に適用させるにあたり、どのような点に考慮すべきか、相手国の国情に合わせて、そのモデルをいかに変更する必要があるのかについて考察しながら実施することが、地に足がついた協力と言えるのではないか。
町氏
- 日本と韓国は人材育成における経験を伝えるにふさわしい立場にあると考える。また、協力を受ける側の国の人材育成戦略の確立も重要であり、そうすることによって供給側と受け入れ側のコミュニケーションが促進される。
リー氏(KINAC)

- 原子力発電のプロジェクトを進めるには人材育成が必要であり、また、原子力発電プロジェクトを進めることにより、人材が育成されていく。
- 韓国における包括的な人材育成戦略に基づき、米国でトレーニングを受けた科学者・技術者が当初の原子力研究コミュニティの中核をなし、韓国の原子力産業の形成に貢献してきた。しかしながら、海外で1回トレーニングを受けたとしても、教育トレーニングプログラムを確立するのと同等の効果はなく、人材育成はよりダイナミックなプロセスと位置づけることができる。
- 原子力産業は知識をベースとした産業であり、技術的な問題が生じれば、海外のコンサルタントや技術者に頼るという手法がとられるが、コストが高くつくと同時に時間もかかる。問題を国内で解決するためには自前の人材の養成が求められる。こうしたことから韓国の原子力関連機関は、それぞれの機関内でのトレーニングの提供や研究センターの設置といったことを実施している。自前の訓練以外にも、新たな訓練提供者を雇用したり、外部のセミナーやワークショップ等に参加させたりといった取組も実施している。
- こうした継続的な取組は、韓国における原子炉の運転実績の改善につながった。(韓国の原子炉の設備利用率は世界平均と比較して15%上回るという状況を過去20年間保つことができた。)
- 最近は優秀な人材を集めることが難しくなっており、より若い人たちが原子力分野に入ってくることを促進する世界的な取組が必要である。その意味において東京大学のグローバルCOEの取組に期待したい。
キャロン氏(CEA)
- 原子力発電に関心を示している国との間で、過去の経験を共有することは原子力先進国の責任である。
- フランスはこうした協力に関して多くの経験を有するが、中国に対する協力を通じた原子炉、技術、知識の移転はメーカー間、政府や公的機関間の協力の好例である。
- 中国の場合は、野心的な原子力導入計画や原子炉機器の製造の国産化の要請という特殊事情があったが、こうした状況は全ての国に当てはまるわけではなく、各国との協力にあたっては、相手国のニーズに合わせて柔軟に対応することが重要である。
- 原子力協力にあたっては、相手国が核不拡散、原子力安全、核セキュリティに関する国際的なコミットメントを遵守することが前提である。国際的なコミットメントとして、核不拡散に関しては、保障措置協定や追加議定書、原子力安全に関しては、原子力安全条約や原子力損害賠償責任に関する条約が挙げられる。
- IAEAが原子力発電の導入にあたってのマイルストーンやロードマップをまとめた文書を参考に、特定の国を評価し、原子力発電導入に際して何がクリティカルパスかを検討することが必要である。原子力先進国と新規原子力発電導入国の間の対話が求められる。
- 利用できる全ての条約や国際協力の枠組みを利用することが必要であり、GNEPは有効な手段の一つとして考えられる。
- フランスは昨年から公的機関による新規原子力発電導入国への支援を体系的に実施する取組を行っている。サルコジ大統領は昨年の国連総会の演説の中で、新規原子力発電導入国に対する原子力先進国の責任に言及した。また、CEAの中に原子力の民生利用に関心を持つ国それぞれに合った技術援助や支援のパッケージを提供する組織を設置した。
- ただ、国際協力が補完的な役割を果たすとしても、原子力への投資はあくまでも原子力導入国の責任である。原子力の難しい点は、導入の決定から原子炉の運転開始までに長い時間を要し、その間、多くの投資を必要とすることであるが、原子炉のライフサイクル全体で得られる便益と比較した場合、初期投資はわずかなものである。
町氏
- 燃料供給保証に関する国際的議論は前進していないように見えるが、将来の見通しはどうか。
サベージ氏(DOE)
- 信頼性のある燃料供給については、GNEPのワーキンググループだけでなく、IAEAの場やロシア等、燃料供給国になることに関心を示す国の間による議論が継続しており、様々な国や国のグループが低濃縮ウランの提供のコミットメントを行っている。長期的に見れば、こうした議論は何らかの成果につながっていくであろう。
- 一方、使用済燃料の引取りに関しては、詳細は決まっておらず、今後多くの作業が残されている。
- また、小規模な電力系統しか有しない途上国に対しては、500MW以下の炉が適しており、供給国により、多くの中小型炉の設計がなされている。

キャロン氏(CEA)
- 燃料供給保証に関しては、コンセプトは既に提示されており、いかに実現していくかという段階である。
- 今のところ、どの国においても燃料の確保に問題があるわけではない。また、将来、原子力発電が大幅に拡大する状況が生じた場合であっても供給能力の拡大により対応可能であろう。
- 問題は、非商業的、政治的な理由により燃料供給を受けられなくなるという例外的状況にいかに対応するかという点である。個人的には、こうした例外的なケースに対して、全体の供給枠組みの再構築を目指すのではなく、既に提案されている具体的な構想をとりあげ、短期のタイムスパンで履行していくというアプローチが望ましいと考える。
カラシュディ氏(タイ・エネルギー省)
- タイはターン・キー方式による最初の原子炉の導入を計画している。
- 短期的な取組が最も重要であり、これから2年半の間に、政府による原子力発電の導入決定のための全ての情報を提出する必要がある。
- タイの電力会社は多くの国のメーカーとの間で協力関係を有しており、これまでにフランス、日本、韓国、中国を訪問した実績がある。
- タイでは、原子炉導入サイト調査、フィージビリティスタディのための国際入札のプロセスを開始した。
- 国際協力に関しては、駐タイ日本大使との間で、許認可等のための人材育成の協力の議論を開始したところであり、中国との間ではMOUを締結している。
- IAEAの勧告やガイドラインを活用するとともに、IAEAから支援を受けている。
(6) 会場からの質疑応答
Q1
原子力導入にあたって最も重要なことは一般の理解を得ることと考えるが、チェルノブイリ事故後の原子力に対する世論の変化に対して、どのような戦略により対応したか教えて欲しい。
A1-1(キャロン氏(CEA))
- 政治的に機微な問題である。チェルノブイリ事故後、原子力への支持は減ったが、他に選択肢がないこともあり、透明性を高める努力により克服した。透明性の向上は2006年に制定された原子力安全・情報開示法にも反映されている。同法においては、原子力発電所の計画策定等の段階において、地方委員会等の場を通じた一般の関与が明確に規定されている。
- 統計によれば、経済的な利益を得られるとの理由から原子炉施設近隣住民の原子力発電への支持は高いが、施設から50kmの距離を超えた地域住民の支持は低下し、更に離れた地域では再び支持が上昇する。このようなことから、地域住民を関与させるシステムを作ることが重要である。
A1-2(石塚氏(JAIF))
- 原子力に対する理解を得るには信頼性、透明性の向上につきる。長い時間とエネルギーを要するものであり、王道はない。
- 日本は多くの失敗をしてきたが、これから原子力を導入する国にはそうした失敗に学んで欲しい。
Q2
米国では、多くの大学で原子力コースが閉鎖されたと聞いている。原子力導入にあたって重要な要因は人材育成であると考えるが、米国において、新たに原子力コースを開設する見通しがあるか、教えて欲しい。
A2-1(サベージ氏(DOE))
- 原子力専攻の学生数は長期にわたり減少傾向にあったが、ここ数年で原子力工学の学部卒業生数は増加に転じている。
- 米国において新たに50基の原子炉建設が想定されているように、原子力産業が活性化すれば、それをサポートする原子力工学プログラムも活性化することが期待される。アジアからの留学生の数は多く、今後も増えるであろう。
A2-2(キャロン氏(CEA))
- フランスにおける新規原子炉の建設は1995年以降、途絶えているものの、約60基の原子炉を運転しており、そのため、原子力工学を専攻する学生は一定レベルを保っている。今後は、原子力教育を拡大することが想定されており、フランス国内のニーズを満たすだけでなく、他の国の学生にもオープンなものとなることを確信している。
(7) モデレーターによる総括
- エネルギー安全保障、地球温暖化防止の観点から原子力発電の重要性が認識された。
- 二国間及び多国間の枠組みでの新規原子力発電導入国に対する国際協力が重要であり、3Sを含むインフラ整備の観点からできる限りの支援を実施していくべきである。GNEP、IAEA、ASEAN+3、FNCAといった枠組みが重要な役割を果たす。
- 原子力利用の拡大には課題もあるが、課題解決には段階的なアプローチが必要である。


注釈
* 3World Energy Outlook 2007
* 42008年2月。参照:http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2008/bataannpp.html
* 5クリーン開発メカニズム。京都議定書に規定されている、地球温暖化ガスの削減目標を達成するためのメカニズムの1つであり、途上国に対する協力により地球温暖化ガスの排出を削減できた分を自国の削減分としてカウントできる制度
* 6国連気候変動枠組条約締約国会議
* 7地球温暖化対策としての原子力エネルギーの利用拡大のための取組み:平成20年3月13日、地球環境保全・エネルギー安定供給のための原子力のビジョンを考える懇談会からの報告。なお原子力委員会は同日、「原子力委員会は、別添の地球環境保全・エネルギー安定供給のための原子力のビジョンを考える懇談会からの報告「地球温暖化対策としての原子力エネルギーの利用拡大のための取組みについて」の内容は妥当であると判断するので、関係府省においては、この報告に沿って取組みを行うべきである」との決定を行っている。出展:原子力委員会ホームページ
4. パネル2(6月25日9:40-12:30)
(1) テーマ
- 核不拡散、保障措置、核セキュリティの向上に向けて
(2) モデレーター
- 日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター 所長 須藤 隆也氏
(3) パネリスト
| オーストラリア外務貿易省 保障措置・不拡散局(ASNO) 部長 | ジェフリー・ショー氏 |
| 国際原子力機関(IAEA) 東京地域事務所 所長 | マッシモ・アパロ氏 |
| インドネシア原子力規制庁(BAPETEN) 次官 | スハルトノ・ザヒール氏 |
| 原子力機構 核不拡散科学技術センター(NPSTC) センター長 | 千崎雅生氏 |
| 韓国核不拡散核物質管理院(KINAC) 核管理部門 部長 | ユーン・ワン・キィ氏 |
| 米国エネルギー省(DOE) 国家核安全保障庁(NNSA) 不拡散・国際安全保障担当次官補代理 | アダム・シャインマン氏 |
(4) 趣旨
アジア太平洋地域における核不拡散、保障措置、核セキュリティの向上及び核拡散抵抗性強化の必要性、また、これらを進めるために解決しなければならない課題等の認識を踏まえ、課題解決のための方策として、地域的協力、ベストプラクティスの共有、国際協力の在り方、国際機関の役割等を議論した。
(5) モデレーター・パネリストのプレゼンテーション、発言の骨子
1) 各国の核不拡散、保障措置、核セキュリティの向上への取組
オーストラリアの取組:ショー氏(ASNO) 「地域保障措置及び核セキュリティを強化するオーストラリアの取組」

(アジア各国への保障措置、核物質防護、輸出管理分野での協力)
- オーストラリアは、アジア太平洋地域の保障措置、核物質防護及び核セキュリティの向上のために種々の活動を行っている。保障措置・不拡散局(ASNO)は、1980年代半ばからIAEAや日本と協力して、国内計量管理システム(SSAC)* 8トレーニングコースを開催している。また核物質防護に関しては、核セキュリティ基金(Nuclear Security Fund)に参加し、核セキュリティと核物質防護に係るトレーニングを開催、2009年後半には第3回のトレーニングコースを開催予定である。輸出管理に関しては、ASNOは DOE/NNSAと協力して、物質識別訓練(CIT)* 9や、戦略物質の移転解析を行うトレーニング(ASCOT)* 10を行ってきた。
(「アジア太平洋地域保障措置連合」の創設提案)
- ASNOは、IAEA、米国及び日本と協力してアジア地域における種々の保障措置支援プログラムを実施するとともに、IAEAの保障措置プログラムを支援するためのオーストラリア保障措置支援プログラム(ASSP)* 11を創設、環境サンプル分析や保障措置の実施等、種々の支援を行っている。またオーストラリアは、2007年6月、シドニーで開催されたAPEC閣僚会議に合わせ、アジア太平洋地域の保障措置に係る非公式高級レベル会合を開催、その際に「アジア太平洋地域保障措置連合(An Asia-Pacific safeguards association)」の創設について議論した。今年2月には、インドネシアと共同でこの連合の目的や活動、組織、参加条件及び資金等に関するディスカッション・ペーパーを配付し、今年6月までの期限で関係国にコメントを求めており、2009年初頭にはそのフォローアップ会合を開催すべく韓国と準備を進めている。「アジア太平洋地域保障措置連合」はIAEAの活動を補完するものであり、アジア太平洋地域において保障措置に関する知見や経験を共有するとともに、地域における原子力利用の透明性向上及び信頼性構築を図ることが可能であろう。原子力利用の拡大が見込まれる今こそ、今までの経験を基にアジア太平洋地域で保障措置に関するネットワークを創設し協力しあうことが必要であり、それによって核不拡散の懸念と核セキュリティのリスクを低減させることができるのではないか。
インドネシアの取組:ザヒール氏(BAPETEN) 「保障措置、核セキュリティを改善するインドネシアの活動」

(原子力規制体系等)
- インドネシアの原子力規制体系は、上位から1945年インドネシア共和国憲法、法令、政令、大統領令、BAPETEN長官令、BAPETEN長官ガイドラインがある。特にAct No. 10/1997原子力法は、インドネシアにおける原子力活動のベースとなっており、またこの法律は原子力推進と規制機関を分離(後者はBAPETEN)するとともに、それらの役割等を規定している。
- 保障措置に関しては、1999年に追加議定書に署名し2003年に統合保障措置に移行、核物質防護に関しては、2005年に改正核物質防護条約に署名、現在は同条約批准の手続を進めているところである。
(BAPETENの活動)
- BAPETENの役割は、IAEAの規制と国内の規制との調和を図ること、インドネシアにおける原子力施設と核物質の許認可、原子力施設の保障措置と核物質防護、人材育成(保障措置や原子力安全、輸出規制に係るトレーニングプログラムへの参加など)、査察方法・手順の向上、国レベルの設計基礎脅威(DBT)* 12の策定、施設レベルでの核物質防護の改善、保障措置関係研究機関の充実などである。
(課題及び今後の国際・地域協力)
- 今後、解決していかなければならない課題としては、原子力関連スタッフの高齢化と原子力施設の経年劣化への対応、商用原子炉初号機の導入、核テロリズムへの対応などである。
- 国際・地域協力に関しては、相互理解を基本として、核物質の平和利用と安全、セキュリティ及び保障措置に資することを目的に、既存のプログラムを拡大・強化する方向で進めるとともに、保障措置と核物質防護の強化のための地域トレーニングセンターが必要であると考える。
米国の取組:シャインマン氏(DOE) 「次世代保障措置イニシアティブ(Next Generation Safeguards Initiative(NGSI))

(次世代保障措置イニシアティブ(NGSI)の背景)
- 2008年2月に発表されたIAEA 20/20 Vision for the Future* 13にも述べられているように、現在、保障措置の強化の必要性が国際的に認識されている。既存の保障措置には幾つかの課題がある。それらは、(1) 世界規模での原子力利用の拡大と原子力施設の増加に伴い既存の保障措置に歪みが生じる可能性があること、(2) 機微な原子力技術の拡散防止には、保障措置と輸出規制の強化が必要であること(例えば、リビアのガス遠心分離機はカーン・ネットワークにより調達された種々のコンポーネントを組み合わせて作られたものであった)(3) IAEA保障措置対象施設の増加や、イラン、北朝鮮及びインド等への対応で、IAEAのリソースや保障措置の信頼性に歪みが生じる可能性があること、(4) 特に米国において保障措置の技術基盤が縮小していること、具体的には保障措置技術の陳腐化、予算削減及び人材不足である。
- DOEは上記に鑑み、現在及び今後25年の間に取り組むべき保障措置の課題について、政策、技術、人材及び財政的側面からレビューし、2007年10月に“International Safeguards – Challenges and Opportunities for the 21st Century”として取り纏めた。その中では、技術的資源や各国のパートナーシップ等により、保障措置に関して統合的なイニシアティブが必要との見解が述べられており、これをきっかけとして、DOEはNGSIに着手した。
(NGSIの目標、技術開発及び人材育成)
- NGSIの目標は、(1) 保障措置政策及びアプローチの強化、(2) 保障措置技術開発の活性化と人材基盤の充実、(3) 種々の国際協力プログラムを通じて保障措置の統合を図ること、(4) 原子力インフラ整備を通して「保障措置カルチャー」を促進することである。
- このうち、(2)の保障措置の技術開発について、原子力活動が申告されている施設については、保障措置をより効果的かつ効率的に行うことが必要であり、計量管理技術、遠隔及び非立会い監視システム、設計検証ツールや認証技術、情報収集や分析、核燃料サイクル施設に適用される先進保障措置などの開発を行う必要がある。また、未申告の施設における原子力活動の探知や調査に関する技術の開発も重要であり、持ち運び可能で多機能な機器や現場でのサンプリングとスクリーニングが可能な機器などの開発、追加的に保障措置分析所の認証も増やすことが必要である。
- 人材育成については、IAEAでも米国でも急務である。特に若年層の人材育成のために米国の大学や研究所で教育・訓練プログラムの充実を図るとともに、産業界を含め、現場で経験を積むことも重視している。
(IAEAの役割及び国際協力)
- IAEAは、既存の権限で、より広範囲のミッションを達成できるはずであり、追加議定書や改正少量議定書(SQP)* 14の普遍化、情報を重視した保障措置手法の開発、国レベルでのアプローチの強化、及び核拡散に関する情報共有など、可能なことはまだあるはずである。
- 一国のみでは国際的に保障措置を強化できるはずはなく、各国が核不拡散へのコミットメントを行い、二国間、地域間及び多国間での種々の協力形態を組み合わせていくことが重要と考える。
(NGSIの次のステップ)
- 今後は、各国との対話や情報交流を深めつつ、(1) 保障措置や人材育成及び国際的なアウトリーチ活動に関する5か年計画を立案していくこと、(2) 政府や学会、産業界における既存の保障措置技術やプログラムを調査すること、(3) NGSIの専門家育成のために試験的な保障措置コースを設けること、(4) 核燃料サイクル施設や新型炉に焦点を置いた保障措置技術開発を促進すること、(5) 今年9月にワシントンで10〜15か国の参加の下、保障措置に関して国際会議を開催することなどを予定している。総じて、NGSIはまだ始まったばかりのイニシアティブだが、IAEAや各国と協調しつつ進め、それが国際保障措置システム強化のきっかけとなることを望んでいる。
日本の取組:千崎氏(JAEA) 「核不拡散に関する日本の政策とJAEAの取組:アジア諸国との協力の取組」

(日本の核不拡散政策)
- 2006年の「原子力立国計画」では、核不拡散について、包括的保障措置と追加議定書の普遍化の促進と輸出規制に係る原子力供給国グループ(NSG)* 15での議論の進展、核不拡散強化のための新しいアプローチの積極的な模索の重要性、これらの分野における国際協力の必要性が述べられている。また、2008年3月の「地球温暖化対策としての原子力エネルギーの利用拡大のための取組」でも、原子力利用拡大に向けた国際的な枠組みの構築には、核不拡散、原子力安全、核セキュリティの3つのS(3S)の確保が不可欠であり、この3S確保にはIAEAを中心とした国際的取組が重要であって、世界各国と共同してこの取組の一層の充実に積極的に寄与していく必要性が述べられている。この3Sの重要性は、2008年6月8日のG8、中国、インド及び韓国エネルギー大臣会合共同声明でも指摘されている。
(日本の核不拡散への取組)
- 日本は1976年に核不拡散条約(NPT)を批准、77年にIAEAと包括的保障措置協定を締結、1999年に追加議定書を締結した。2004年にはIAEAから拡大結論* 16を得て、2004年9月から核燃料サイクル施設を有する初めての非核兵器国として、統合保障措置が順次適用されている。
- 日本の原子力平和利用のポイントは、(1) 原子力エネルギーの明確な必要性、(2) 核武装放棄への国家意思の明白性、(3) 原子力計画と活動の透明性、(4) 核不拡散規範遵守の優れた実績、(5) 核拡散防止や軍縮に関連する積極的な取組などであると考える。
(核不拡散の課題とJAEAの取組)
- 現在の核不拡散の課題としては、(1) IAEA保障措置の強化と効率化の必要性、(2) 核セキュリティの強化とコストパフォーマンスの良い効果的な措置の追及、(3) 核拡散抵抗性の技術開発、(4) 核軍縮の進展、(5)アジア諸国との協力推進、(6) 機微な技術の管理・強化への取組、(7) 核不拡散を強化するための新たな枠組みへの取組、(8) 国内外の核物質の輸送の円滑な実施、などが挙げられる。
- これらに鑑み、JAEAとしては、核不拡散政策への支援、核不拡散技術開発、非核化支援、人材育成を進めるとともに国内外の関係機関との積極的な協力を行っている。

(JAEAのアジア諸国への協力と今後の取組)
- JAEAは、アジア諸国との間では、これまで原子力の多くの分野で協力を行ってきているが、核不拡散分野の協力に関しては、政策研究の1つとして、アジア諸国における原子力の開発・利用の現状・将来計画、核不拡散・保障措置等への取組状況等の把握及び信頼性醸成・透明性の向上に向けた課題などの調査を行っている。
- これまでインドネシア、タイ、ベトナムを訪問し情報交換を行うとともに、今年2月には「アジア太平洋地域における核不拡散協力のための透明性技術に関するワークショップ」(東大G-COEと共催)を、さらに3月にはベトナムのVARANSACと核不拡散、保障措置、核セキュリティ等に関する専門家会合を開催した。保障措置の分野では、IAEAや我が国政府、核物質管理センター等と協力して、アジア各国を対象とした国内計量管理制度(SSAC)トレーニングコースを定期的に開催しており、2008年10月下旬にも開催予定である。
- JAEAは、今後もアジア各国について原子力利用や核不拡散の観点からの調査・研究・分析を行い、各国のニーズを確認しつつ夫々の国情や原子力開発の度合いに適したテーラーメードの取組を行ってアジア地域の核不拡散の進展に貢献していきたい。その際には、情報・意見交換を十分に行いつつ、二国間協力や多国間協力、国際機関との協力をベースに、段階的に進めていくことが重要だろう。
2) アジア太平洋地域における核拡散・核テロリズムのリスク低減と保障措置・核セキュリティの改善方策等について
ショー氏(ASNO)
- 保障措置は常に進化し続けており、今後も変遷を続けていくだろう。
- 核不拡散には政治的な側面と保障措置技術の強化という技術的な側面がある。昨年終了したIAEAのCommittee 25は、保障措置に関する技術的な議論を想定したものであったが、政治的な議論に巻き込まれてしまった。現在、核不拡散、核軍縮に関する政治的な議論は、NPT運用検討会議においても、ジュネーブ軍縮会議においても、国連総会の第1委員会においても停滞している。したがって、技術レベルで協力を推進して透明性と相互理解の向上を図ること、またそれと併せて政治的な因子を促進させて核不拡散という課題に立ち向かうことが必要だろう。追加議定書の普遍化、追加議定書を締結した国が同議定書で定める義務(申告等)を履行するための支援、包括的保障措置協定の未締結国を減らす取組などが重要である。
ユーン氏(KINAC)

- IAEAは、2008年6月の理事会で韓国に対する拡大結論を承認、これに伴い韓国は来月(2008年7月)から統合保障措置に移行する。韓国は2004年、2000年に韓国原子力研究所(KAERI)が実施したウラン濃縮実験をIAEAに申告したが、その後、原子力推進機関とは別に、核物質防護や保障措置、輸出管理等を一手に行うKINACを設立するなど、種々の不拡散への努力を行ってきた。IAEAによる拡大結論はその成果であると考える。
- 韓国は、核物質防護条約、核テロ防止条約、核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ(GICNT)* 17等にも参加している。核セキュリティ、特に核物質防護で重要なことは設計基礎脅威(DBT)で、韓国はこの10数年間、その策定に努力してきたが、IAEA及び米国との協力により、現在は策定の最終段階にある。
ザヒール氏(BAPETEN)
- アジア各国では、原子力インフラの構築とそれに伴う保障措置及び国内計量管理システム(SSAC)の強化が必要である。保障措置は、各国の協力やSSACトレーニングコースでの知識共有や品質向上、専門家の育成により、その強化が可能であると考える。
アパロ氏(IAEA)

- 核不拡散のためには追加議定書は重要であり、追加議定書の普遍化を訴えたい。アジア太平洋地域の未署名・未批准国は、オーストラリアや日本等に追随してもらいたいと思う。
- オーストラリアから提案があったアジア太平洋地域における保障措置のアソシエーションである「アジア太平洋地域保障措置連合」は、重要な役割を果たすことができるのではないか。例えば、欧州保障措置研究開発機構(ESARDA)* 18は、保障措置に関して重要な情報を共有し、欧州の加盟国及び事業者間の相互理解に貢献している。
シャインマン氏(DOE)
- 核テロのリスクには2つのシナリオがあり、第1にウランやプルトニウムそのものの盗取や原子力施設への攻撃であり、第2に秘密裡の濃縮や再処理能力の開発である。このような2つのシナリオにおいては、核物質防護と保障措置が重要であり、米国はロシアとの協力や、多額の予算を投じて(DOEの現在の核不拡散予算は16億ドル)核テロ対策、核物質の核兵器への流用防止を強化している。
- また米国は、新規原子力発電導入国自らが濃縮や再処理を行わない代わりに、核燃料の供給を保証することを目的とした核燃料供給保証の議論にも参加している。具体的な貢献として、米国での供給保証用の低濃縮ウラン備蓄のため、解体核起源の17.4トン高濃縮ウランのダウンブレンディングを行う。また、核脅威イニシアティブ(NTI)* 19が提案する燃料バンク設立のため、米国予算から5千万ドルを拠出する用意がある。核燃料供給保証に関する議論はIAEAでは政治的要因等が絡み進捗していないようであるが、将来的に議論が進展して供給保証メカニズムが構築され、第2のシナリオのような秘密裡に独自に濃縮や再処理を行う国の出現を防ぐことができればよいと思う。

千崎氏(JAEA)
- アジア太平洋地域では、今後この分野の協力は大変重要となると理解している。例えばJAEAはこれまで核物質防護策の強化を進めてきているが、それにはかなりの費用が必要となってきている。これは新規原子力発電導入国にとってもかなりの負担であり、国際協力で核セキュリティの技術開発を進め費用対効果を追求する必要があると考える。保障措置に関しても同様なことが言えるのではないか。また、核物質などの国際間輸送の問題も重要になってくると考える。
- 核拡散抵抗性のある技術を追求、評価することも重要である。核拡散抵抗性のある技術については、IAEAの革新的原子炉及び燃料サイクル国際プロジェクト(INPRO)や第4世代原子力システム国際フォーラム(GIF)の場での議論を加速してこれを着実に進めていく、併せて原子力施設の建設に当たっては、そのシステム設計の初期段階から保障措置と核物質防護の要件を盛り込んでこれを行うことが重要であり、そのため初期段階から政策担当者、設計担当者、核不拡散専門家などが一緒になって検討を進めることが必要だろう。
3) 核不拡散、保障措置、核セキュリティに対する地域協力・国際協力の重要性及び国際機関の活用について
千崎氏(JAEA)
- 我が国の今までの原子力平和利用の経験から、JAEAでは政策研究の一つとして、原子力平和利用の推進を行うために必要な要件・取組・努力などのモデル化の研究を進めている。このモデル化研究はアジア地域の新規原子力発電導入国にも参考となると思われ、近々研究成果を整理して国際的な場で発表し、コメントを頂戴したい。アジア各国は多様性に富んでいるが、日本の良い事例・経験も参考にしていただき、夫々の国の事情、原子力開発のプロセスやその時々のニーズに合わせて貢献できるように努力していきたい。
- また、アジア太平洋地域における信頼性醸成策や透明性向上技術などに関して、米国DOEやサンディア研究所と共同研究を行っているが、今後は、韓国のKINACとも協力していくべく、協定取り決めに向けて協議している。
ショー氏(ASNO)
- アジア太平洋地域での原子力利用拡大に伴い、今後は原子力利用の透明性向上が益々重要になっている。原子力安全面では、アジア太平洋地域ではすでに協力が行われており、保障措置面では、欧州ではすでにESARDAが機能している。今後は、それらを参考にして、「アジア太平洋地域保障措置連合」を構築し、アジア太平洋地域における保障措置能力向上や、原子力平和利用における透明性の向上に繋げていってはどうか。
ユーン氏(KINAC)
- 韓国は、1992年の朝鮮半島非核化共同宣言において、原子力の平和利用を宣言し、平和利用の4つの原則の1つとして原子力利用における透明性確保を掲げている。アジア地域での原子力平和利用の透明性向上のために、例えば米国、韓国、日本の3か国が核物質防護、保障措置、輸出管理に関する意見交換の場を設けて、それを近隣諸国に拡充していくことも可能であり、そのような活動が地域の緊張緩和にも役立つのではないか。その意味で、オーストラリアから言及があった「アジア太平洋地域保障措置連合」の創設に向けたイニシアティブを支持する。
ザヒール氏(BAPETEN)
- インドネシアにおいては、原子力規制の枠組み整備が重要であるとの認識に基づき、真摯にこれに取り組んできた。地域における核不拡散や保障措置の構築のためには、枠組み設定が重要であり、インドネシアでは、米国DOEやオーストラリアと二国間協力が進んでいる。今後は、地域ベースの原子力規制に関するトレーニングコースを実施していくことも重要と考える。
シャインマン氏(DOE)
- 核拡散抵抗性技術により、核拡散リスクを低減させることはできるであろうが、ゼロにすることは無理であろう。核不拡散問題は複雑でその対策には万能薬はなく、技術の開発に加えて、国際的な核不拡散の義務遵守+アルファを行うこと、二国間や多国間協力、透明性向上方策等、種々の方法を色々組み合わせて対応していくことが必要だろう。
- 米国はアジア各国に対して保障措置トレーニング等を実施している。これらの協力をより効果的なものにしていくためには、例えばIAEA等のトレーニング等とのコーディネーションを強化すること、トレーニングを標準化すること、ピアレビューを行うこと、専門的な経験や知識のプールなどが重要であろう。
- 中核的研究拠点(COE)という考え方も重要で、核不拡散及び保障措置分野でのCOEの果たす役割は大きく、他の地域での拡充も可能であると思う。
アパロ氏(IAEA)
- IAEAは加盟国に対して、加盟国自ら原子力安全、保障措置、核セキュリティの3Sの分野での対応を向上させることができるよう、その評価及び改善や向上のためのアドバイスを行っている。核物質防護に関しては、新しいガイドラインも作成しており、これを利用すれば、加盟国は核セキュリティのインフラを強化することができる。今後もこのようなガイドラインを策定し、加盟国の核物質防護の向上に貢献していきたい。
(6) 会場からの質疑応答
Q1
- 原子力利用の透明性を保障措置のクライテリア(Safeguards Criteria)に含めることは出来ないか。現行の保障措置では、原子力利用の透明性の高い国にも低い国にも、同様の保障措置アプローチが採られているが、これを改善できないか。現状のままだと、透明性の高い国への査察は過重となり、低い国への査察は不十分なものになる。
- 保障措置の合理化に関して、最先端の機器を投入するなど資金的に余裕があるため省力化して保障措置に対応しようとする国がある一方で、資金的に余裕がなく人海戦術で対応しようとする国もある。現在の保障措置アプローチは一つ(single way)だが、幾つかの代替アプローチを作り、国の設備や機器の実情に応じて選べるようにするという方法もあり得るのではないか。
A1-1(シャインマン氏(DOE))
- 保障措置対象施設の増加やイラン、北朝鮮等の対応で、保障措置の資源は有限であるにも拘わらずIAEAの保障措置の負担は増大している。保障措置対象国の中には、核不拡散上問題ない国もあり、例えば追加議定書の批准や統合保障措置が実施されている国に対しては保障措置の頻度は減るのではないか。また、例えば未申告の再処理を行っていない国には保障措置の負担を軽減しても良いと思う。
A1-2(アパロ氏(IAEA))
- IAEAは保障措置を差別化して行っていない。だが、統合保障措置は保障措置の効率化と最適化を目的に作られたものであり、現に日本では、統合保障措置により、軽水炉に対する保障措置への負担が300日/年から200日/年に削減されている。統合保障措置によりIAEAは国の事情を考慮することができ、IAEAの作業を可能な限り最適化することができる。
Q2
地域協力につき、例えば欧州原子力共同体(EURATOM)は1950〜60年代に欧州地域内の核燃料の安定供給の目的から始まり、現在は保障措置の分野での協力にも広がっている。現在は、アジアは一つとの機運もあり、アジア地域でも、燃料供給保証、保障措置及び核セキュリティ、ひいては核燃料サイクル施設も視野に入れた協力の枠組みは考えられるか。
A2-1(ショー氏(ASNO))
- オーストラリアが提案している「アジア太平洋地域保障措置連合」は、EURATOMをモデルにしているものではなく、またEURATOMのアジア版を提案しているわけでもない。EURATOMは欧州における査察の実施を主眼においているが、「アジア太平洋地域保障措置連合」は、アジア各国が保障措置のような国際的な義務を果たす上でのスキルの向上が目的で、IAEAの作業の補完に主眼を置いている。
A2-2(ユーン氏(KINAC))
- アジア地域においてまずやるべきことは、原子力安全、保障措置、核セキュリティの3Sの推進である。特に核セキュリティ、核物質防護は、国家安全保障にも係る機微な問題であるが、これをまず向上させていくことが必要なことであろう。核燃料の供給保証はその次のステップの話である。
Q3
核燃料の供給に関しては、現在、どのような議論がなされているのか。多国間協力であれば、原子力先進国と新規原子力発電導入国の間の協力をもっと進めるべきと思うが、どうか。
A3-1(シャインマン氏(DOE))
- 核燃料の供給保証に関しては種々の提案が出ているが、具体的な枠組み構築に繋がっていない。供給保証メカニズムにはIAEAの関与とIAEA理事会の承認が必要である。ロシアはアンガルスクの国際ウラン濃縮センターに係るモデル協定についてIAEAと交渉しており最終段階にあるようだが、供給保証メカニズムにより新たな差別が生まれないか、供給国間の一種のカルテルになるのではないか、消費国要件をどうするかなど解決すべき難問は残っている。しかし一方で、IAEAの9月理事会に向けて何らかの動きがでてくるかもしれない。
A3-2(千崎氏(JAEA))
- 我が国は、ウラン鉱石から成型加工までのフロントエンド全部を保証の対象とした「IAEA核燃料供給登録システム」を提案し、各国が有する夫々の供給能力を登録することにより市場の透明性を図ることを目的とする提案を行っている。我が国政府、そしてJAEAの中でも供給保証メカニズムなどについてさらなる議論を行っているところである。
- 供給保証システムの構築については、種々の制度的及び技術的な課題があるが、新規原子力発電導入国の意見を勘案すると本システムを一気に構築するのは困難なような気がする。国際的な議論を行いつつ、NTI提案の核燃料バンクやロシアのアンガルスクの国際ウラン濃縮センターなど現実的にコンセンサスが得られる可能性のある個別的なところから段階的に進めて行くということもできるのではないか。
(7) モデレーターによる総括

- アジア太平洋地域では、原子力平和利用の進展とともに、核不拡散・保障措置の向上、核セキュリティの強化が急務となっている。
- これらの国に対する協力は、夫々の国の原子力利用の発展段階、またそのニーズに応じてテーラーメードで行っていくことが重要である。一方で、既存の種々の協力については、そのコーディネーションを図り、各国間での知識や経験の共有も必要である。
- 国際協力や国際機関も交えたアジア太平洋地域における透明性向上及び信頼性醸成が積極的になされるべきである。その意味で、アジア太平洋地域保障措置連合を創設するとの提案もなされており、今後はこのような議論も推進していくべきであろう。


注釈
* 8SSAC:State System for Nuclear Material Accountancy and Control
* 9CIT:Commodity Identification Training
* 10ASCOT:Analysis of Strategic Commodity Transfers
* 11ASSP:Australian Safeguards Support Program
* 12DBT:Design Basis Threat
* 13http://www.iaea.org/NewsCenter/News/PDF/20-20vision_220208.pdf
* 14SQP:Small Quantity Protocol
* 15NSG:Nuclear Suppliers Group
* 16IAEA加盟国の保障措置活動を評価する年次報告書である「保障措置実施報告書(SIR)」で、日本に対する包括的な結論として、日本において申告された核物質の転用はなく、未申告の核物質や核活動もないことが認められたもの。
* 17GICNT:Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism
* 18ESARDA:European Safeguards Research and Development Association
* 19NTI:Nuclear Threat Initiative
5. パネル3(6月25日14:00-17:20)
(1) テーマ
- 信頼醸成、透明性、及び人材育成
(2) モデレーター
- 東京大学 グローバルCOE 教授 ジョーシャン・チョイ氏
(3) パネリスト
| オーストラリア外務貿易省 保障措置・不拡散局(ASNO) 部長 | ジェフリー・ショー氏 |
| 東京大学 客員教授/日本原子力研究開発機構 核不拡散科学技術センター次長 | 久野 祐輔氏 |
| マレーシア原子力庁 長官 | ビン・モハマッド・ダウド氏 |
| 韓国核不拡散核物質管理院(KINAC) 核管理部門部長 | ユーン・ワン・キィ氏 |
| タイ・エネルギー省 技術顧問 | プリチャー・カラシュディ氏 |
| 米国サンディア国立研究所 原子力・国際安全保障技術センター長 | シドニー・グティエレス氏 |
(4) 趣旨
核不拡散の担保の仕組みとしては、一方で、ハード面として保障措置・国際的取決めなどの制度的枠組みがあり、他方で、ソフト面としての透明性確保及び信頼醸成を目的とした取組がある。パネル3は、このソフト面としての透明性・信頼醸成についての概念及び地域的取組の可能性に焦点を当て、新規原子力発電導入検討国と原子力先進国のそれぞれの視点から議論が試みられた。
また、将来の人材不足といった、新規原子力発電導入検討国と原子力先進国に共通する課題について、問題意識を共有すると共に、効果的な人材育成について議論し、協力の可能性を模索した。
(5) モデレーター・パネリストのプレゼンテーション、発言の骨子
チョイ氏(東京大学)

- 歴史的・政治的・安全保障上の懸案事項によって、これまで地域の協力枠組み構築が難しかったというアジア地域の特徴を認識した上で、地域における核不拡散協力を実現するために何が必要かを考えることが重要ではないか。
- 田中明彦教授は基調講演で、「アジアは、少なくとも経済的には一つになりつつある」と指摘した。また、フォーラム開催直前に、東シナ海における日中共同開発について了解に至るといった画期的な出来事があった。しかし、ニューヨーク・タイムズ紙の記事には、日中両国ともに、それぞれが単独のアクターとして、アジア地域の繁栄、利益には目を向けず、アジア域外の世界にばかり目を向けてきたとの指摘があり、これは、アジア地域固有の物の見方(mind-set)を示唆する言葉として注目される。
- 特に、核不拡散分野において、このようなアジア地域の特徴といえる物の見方を変えるには、どのような取組が必要であるかを主眼に、トピック1:「アジア太平洋地域における原子力利用の拡大が核拡散リスクの増大に結びつかないようにするための透明性措置と信頼醸成」、トピック2:「アジア太平洋地域における原子力利用の拡大に必要となる人材の育成」の2つの課題について議論を進める。
- また、トピック1では、(1) 情報共有のレベル、効果的な透明性及び信頼醸成措置について、(2) 隣国の懸念を軽減する観点から、より効果的な透明性及び信頼醸成の取組、そして(3) アジア太平洋地域の原子力利用に関する協力的枠組み構築の準備状況、の3つの視点から、トピック2では、(1) 原子力産業界が直面する将来の人材不足という課題、(2) 核不拡散分野の専門職をやりがいのある職とする方法、(3) 関連性のある適正な教育プログラムのあり方、(4) 研修・実地訓練(IAEAのプログラムを含む)をより効果的にする方法の4つの視点で議論を進める。
1) 透明性措置と信頼醸成
久野氏(東京大学/JAEA)「原子力の平和利用における信頼醸成:アジア太平洋地域における透明性と人材育成」

(透明性の概観)
- IAEA保障措置、NPT、NSGといった国際的な枠組みの他にも、FNCA、RCA* 20、ARF* 21、ASTOP* 22など、アジアには原子力・不拡散に関連のある協力枠組みが存在し、共に、核不拡散体制にとって重要な役割を担っている。これらの国際的・地域的枠組みに共通する考え方として、透明性の確保と信頼醸成がある。
- 透明性は、1990年代にインターネット利用の拡大に伴い、軍備管理、IAEA保障措置、追加議定書の運用、安全情報の開示などと関連して、活発に議論された。日本においては、主に国民との情報共有を目的として、自治体、地元住民に対して原子力施設の運転状況に関する情報提供が行われた。
- 透明性の定義は一つではないが、一例として、JAEA引用の定義では「すべての関係者が安全と核物質の合法な取扱いを独自に評価できるようにするために、それらの関係者に対して情報を提供する協力的なプロセス」と定義している。
- 透明性は、自発的な情報開示以上のプロセスであり、独自の評価を可能にするために定量的かつ定性的でなければならないとの特徴を持つ。
(ワークショップでの議論)
- 「アジア太平洋地域における核不拡散協力のための透明性技術に関するワークショップ」(2008年2月20-22日、主催:JAEA、東京大学グローバルCOE)では、透明性技術、地域的信頼醸成の接点を模索する形で、主に透明性確保のための技術について議論がなされた。主な課題は、(1) 透明性とIAEA、(2) 透明性の脆弱性、透明性・データ認証・セキュリティの関係、(3) 透明性の費用対効果、(4) アジア太平洋地域における透明性、(5) 透明性教育の重要性であった。
会場からの質疑応答(1)
Q1
透明性においては情報量の多さよりも情報の完全性が重要と思うが、情報の完全性を評価するための研究がされているか?
A1(久野氏(東京大学/JAEA))
(情報の完全性が重要であるということには)同感である。今後、徐々に研究対象課題を広げていき、情報の完全性の評価手法についても研究したいと考える。重要なことは、出来ることから始め、成果を積み上げていくことだと考える。
ダウド氏(マレーシア原子力庁)「マレーシアの原子力:原子力発電開発における展望、信頼醸成、国際的透明性」

(マレーシアの原子力発電導入についての検討状況と展望)
- マレーシアは現時点では原子力発電の導入を公式には考えていないが、1-2か月の内にこの状況が変わる可能性はある。
- 原子力政策を検討する上で、1979年の国家エネルギー政策及びエネルギーの安全保障に主眼を置いたエネルギー源多様化政策が大きく影響する。
- 1979年の国家エネルギー政策は、安定した経済効率の高いエネルギーの供給のほか、効率の良いエネルギー消費、ならびに温室効果ガス排出量の削減などの環境保護を目標として掲げている。エネルギー源多様化政策については、1981年の政策では、石油、水力、天然ガス、石炭の4種類のエネルギー源、2000年の政策では、5番目のエネルギー源として再生可能エネルギーを加えた多様化政策を推進しており、将来、6番目のエネルギー源として原子力発電が検討されるかもしれない。
- マレーシアにおいて、原子力発電が6番目のエネルギー源として関心を高めている背景としては、需要側・供給側の経済的・環境的配慮がある。
- マレーシアは、経済的・産業的にも十分発展しており、送電網のグリッド容量も原子力発電に対応可能であり、また発電産業の革新的な飛躍を促進する上で重要となる電力部門の民営化も進んでいることから、原子力発電を導入する準備は整っている。
- 供給側の視点としては、原子力発電炉の設計の進化に伴い安全性、経済性の面で大幅な改善が図られたことも、原子力発電導入の支持への追い風となっている。
(原子力発電導入選択の妥当性)
- 国民1人当たりのGDPとエネルギー消費と原子力発電との相関図から、国民1人当たりのGDPとエネルギー消費がそれぞれマレーシアより高い国は既に原子力発電導入国であり、また、国民1人当たりのGDPとエネルギー消費がマレーシアより低い国の中にもタイ、インドネシアを始めとして原子力発電導入を検討している国が多い。つまり、国民1人当たりのGDPとエネルギー消費を、原子力発電導入の妥当性を評価する基準の一つとすると、マレーシアが原子力発電の導入を検討することは妥当であると評価できる。
(国際的な原子力管理システムと国際・地域協力枠組み及びイニシアティブを通じた信頼醸成と透明性:マレーシアの取組)
- 国際約束への参加としては、1970年にNPTを批准し、2005年に保障措置協定に署名した(未批准)。CTBTに関しては、1998年に署名し、2008年1月に批准した。
- 国際的枠組みへの参加としては、RCA(1975年)やFNCA(1990年)に参加しており、2001年にはIAEAの核物質及びその他の放射性物質に関する違法取引のデータベースに参加した。
- マレーシアはASEAN、ARFなどASEANを中心とした地域的枠組み* 23にも積極的に参加しており、東南アジア非核兵器地帯条約については2007年に合意された行動計画を積極的に推進している。
- 二国間のセキュリティ強化取組としては、米国との取決めによるコンテナ・セキュリティ・イニシアティブ(CSI)やメガポート・イニシアティブなどがある。
- 非同盟運動(NAM)ウィーン支部創設議長としてその中心的役割を担ってきており、2003‐2006年にはIAEAの理事会でNAM議長として積極的な役割を果たしてきた。
- 透明性に関しては、国内における原子力の政策決定の透明性確保が非常に重要と考えており、公聴会の開催や議会での議論を通じて透明性を確保している。現在、次の3課題を中心に国民の意見を聞き、議会で議論を展開している。(1) 原子力発電利用の可能性、(2) 人材育成を含めた国のキャパシティ・ビルディング、(3) 国際ビジネスとの協力を伴う民間部門の電力産業への参画。
(結び:透明性と信頼醸成についての考察)
- 国の約束義務履行を伴う国際的な原子力管理システムは、透明性確保と信頼醸成にあたり適切なものであり十分である。従って、現行の国際的なシステムと重複するような新たな地域的なシステムを構築する必要はない。特に、国の原子力計画を実施するに当たり、重複する国際的・地域的義務を課す新たな地域システムの導入は、無駄である。
- 原子力利用に関心を持つ国に対して、宗教的、民族的背景を理由とする型にはめた評価や、先入観による判断は、信頼醸成を踏まえ避けなければならない。
- 核不拡散、核セキュリティ及び原子力の安全に関する原子力先進国の懸念緩和の取組は、(関連条約、協定、取決めに準じた)原子力発電技術・核燃料サービスの提供の保証とのバランスを取った形で実施されるべきである。
- 広範な国際協力による原子力発電計画の支援は、透明性向上と信頼醸成に繋がる。
- 核不拡散に対する脅威は、グローバルかつ地域的な政治的要因や他の問題とも関連しており、そのような問題への取組には透明性と信頼醸成措置が必要である。
ユーン氏(KINAC)「透明性の向上と保障措置との調和」

(保障措置と透明性)
- 韓国が拡大結論を得たことが日本に与える影響、日本が拡大結論を得たことが韓国に与える影響、韓日の拡大結論が他の国、特にアジア地域の国々に与える影響は何か?透明性が確認されたことを意味するが、十分とは言えない。マルチだけでなく、バイの透明性確保を図るなどの補完的な措置が必要である。この点で、IAEAが関与を深める方法があるのではないかと考える。
(韓国の透明性へのアプローチ)
- 2004年9月18日、韓国は原子力平和利用に関する4原則を表明したが、その一つとして、透明性確保の重要性が謳われている。
- 韓国において、核不拡散の透明性は、保障措置、核物質防護、輸出管理を対象としたもので、バランスの取れたアプローチを実施しており、IAEA、近隣諸国、主要原子力発電国との協力という形で推進している。
(IAEA保障措置と透明性及び地域的な透明性のアプローチ)
- 透明性確保のための措置においては、IAEAの検認活動との重複を避けるべきであると考える。
- IAEAとの議論においても、透明性が以前にまして重要な課題となっており、IAEA保障措置に用いる機器・装置の共同使用や費用分担など、重複を避け、より費用対効果を高める方法や、無人の遠隔操作による検認技術の共同開発などについて議論を進めている。
- IAEAとメンバー国との間で相互に提供される情報量については非対称な関係がある。IAEAは当該メンバー国提供による情報、検認・評価を通じて得る情報、公開情報からの情報、関係国からの情報など多角的に情報収集することが可能であるが、守秘義務の制約からIAEAがメンバー国に情報を提供することはない。
- 地域的な透明性の取組においてはIAEAの関与が重要であるが、上述のように、現時点では、参加国とIAEAとの間での情報共有が限られており、将来に向けて、IAEAの保障措置とメンバー国による透明性のアプローチの調和方法等についての議論が必要と考える。
- IAEA保障措置と透明性を比較すると、まず保障措置においては「Trust and Verify」だが、透明性においては「Trust」とあるだけで検証する仕組みはない。透明性措置を保障措置に近づけるためには、検証に値する信頼の確保が必要であるが、現在はそこまでの信頼が確保されていない。
- IAEA保障措置は国とIAEAとの垂直関係による情報伝達がされるが、透明性においては参加国間で水平に情報伝達がされるとの違いがある。IAEA保障措置と国の透明性アプローチの調和が可能になった場合は、垂直方向と水平方向の結合により、包括的な透明性の確保が可能となる。
(技術を基にした透明性措置)
- 地域的な透明性アプローチについては、13-14年前からASIATOM, PACATOMなど幾つかのイニシアティブで議論がされてきたが実現はしなかったという経緯がある。しかし、技術ベースのアプローチならば、施設の運転に大きな影響を与えることなしに、より高いレベルの透明性を比較的低コストで継続的に実現することが可能であるとの利点があり、実現が可能であると考える。
- 潜在的な技術としては、遠隔監視、VPN* 24、メールボックスなどが有用であり、IAEA保障措置で用いられている検認技術を、自発的な意思の下、情報の認証などに関してはIAEA保障措置の基準より柔軟な対応で、活用することが望ましい。
- 技術を基にした透明性措置は、韓米間、日米間で10年間に渡り実施されてきたが、進展は非常に遅い。

(韓国の保障措置教育)
- 現在、韓国内で8つの大学に原子力工学部があるが、保障措置や核物質防護のプログラムを提供する大学はなく、保障措置教育は十分とはいえない。
- 卒業後の活動の場が限られていることも教育プログラムが充実しない要因になっている。他の原子力関連分野における専門家を再トレーニングするなどの方法も検討されている。
- 韓国には、保障措置義務の理解深化を目的とした核物質計量管理に関する教育プログラムがあり、研究者対象のコースと保障措置対応の施設運転者対象の2コースがある。核燃料サイクルの研究者、特にプロジェクトリーダーは、当プログラムの受講が法的に義務付けられている。
会場からの質疑応答(2)
Q2
日本は高い技術とリソースを持つため核兵器開発の可能性も指摘されるが、日本は透明性を確保しており、平和利用目的以外の原子力活動はしないという議論があるが、韓国から見た場合はどうか?韓国は、日本に核兵器開発疑惑などないと思っているのか?
A2(ユーン氏(KINAC))
日本の原子力活動の透明性は確保されていると評価している。
カラシュディ氏(タイ・エネルギー省)「透明性・信頼醸成と原子力の平和利用」

(タイの透明性アプローチ、国際約束・協力への関与)
- タイは、国際、地域、隣国に分けて、IAEAと協力しながら原子力活動の透明性確保に努めている。特に、国際条約への加盟を原子力活動に従事するに当たっての義務と考え、NPT、CTBT、核テロ防止条約、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約、包括的保障措置協定、追加議定書、東南アジア非核兵器地帯条約(バンコク条約)など主要な条約等には全て加盟している* 25。
- また、アジア原子力安全ネットワークにも参加しているが、将来的に原子力発電を導入するに当たって、同ネットワークは大変有用なネットワークであると考える。これは、タイ、インドネシア、ベトナム、マレーシア、フィリピンなどといった潜在的な新規原子力発電導入国と、日本、韓国、中国などのアジア地域の原子力発電の経験豊富な国々との原子力安全に関する情報・知識・経験を共有することを目的としたネットワークであり、原子力発電導入を検討する国の原子力安全に関する知識の確立と能力の向上に大変有益である。
- 将来、原子力発電を開始するに当たっては、原子力安全条約、核物質防護条約、使用済燃料管理の安全及び放射性廃棄物管理の安全に関する合同条約、原子力損害の補完的補償に関する条約などの国際条約に加盟しなければならないと考えており、段階的に対応を進めているところ、原子力安全条約への加盟に関しては既に検討を始めている。
(タイの原子力発電プログラム)
- 原子力発電プログラムの推進に当たって、タイは、以下の政策を掲げている。(1) 濃縮と再処理といった機微な核燃料サイクル技術の開発を行わず、オープンサイクルを適用する。(2) 使用済燃料は、原子力発電所の寿命期間、発電所の敷地内に保管する。(3) 使用済燃料の保管期間経過後の取扱いについては現在検討中であり、最終処分場の設置も選択肢の一つである。
(タイのIAEA保障措置)
- タイには現在、2MWのTRIGA型研究炉が1基あり、1962年の初臨界後、現在も稼働中である* 26。燃料はU-235の濃縮度が19%の低濃縮ウランを使用している。
- 93%の高濃縮ウランを使用していた材料試験炉(MTR)の使用済燃料は全て米国に返還された。現在、TRIGA型MTRの使用済燃料はサイト内に保管されている。タイは、再処理を行わないし、使用済燃料を使用した研究も行わない。
- 新たに10MWの研究炉をバンコク市外に建設予定である。
- タイは、IAEAと協力しながら、保障措置義務の遵守に努めてきた。核物質・施設の転用は一切ない。
(タイの原子力関連機関)
- IAEAの勧告の下、2006年、原子力研究開発の推進組織として「タイ原子力技術研究所(TINT)」がタイ原子力庁(OAP)から独立した研究所(公社)として設立された。以後、OAPは規制組織として、TINTは研究開発推進組織として、それぞれ独立しながらも緊密に協力しつつ、活動を行っている。
(国際協力)
- タイは積極的に国際協力にも関与している。FNCAやRCAなどに積極的に参加している。JAEA、CEA及びIAEAとの協力も活発に行っている。
- これらの国際協力は、これまで放射性同位体の利用を中心とするものであったが、今後は、原子力発電の部門に関する協力を強化したいと考えている。
(人材育成)
- タイには、30年ほど前にも原子力発電導入計画があった。1976年には、導入炉をBWR型として、建設予定地も定めた。こうした動きと並行して、IAEAの支援の下、大学の原子力工学部を中心に教育プログラムを実施し、人材育成に努めた。しかし、タイランド湾海底天然ガス田の発見の影響を受け、1979年、タイ政府はこの原子力発電導入プロジェクトの延期を決定した。その結果、人材は原子力以外の分野へ移り、専門家等も引退に近づいている。
- 原子力発電導入計画が延期されたことを受け、原子力工学部は放射性同位体利用を主としたプログラムに変更され、原子力工学の教育プログラムが削減された。しかし、今後、原子力発電導入計画を推進するに当たって、再度、大学レベルの原子力工学部門を設立・強化する必要がある。
- 原子力発電国の協力・支援が不可欠と考える。欧州委員会(EC)など、我々の原子力発電導入計画を支援してくれている。しかし、中には、我々に適用が困難な支援もある。原子力安全や核セキュリティについてのワークショップなどの協力も、我々のレベル・状況にあったプログラム作りをするというのが極めて重要である。
グティエレス氏(米国サンディア国立研究所(SNL))

- サンディア国立研究所は長年に渡り、米国ニューメキシコ州アルバカーキーとヨルダンのアンマン市のモニタリング・センター(米国エネルギー省・国家核安全保障庁:DOE/NNSA)の活動を通じて、透明性向上と信頼醸成に向けて取り組んできた。
- 信頼醸成に繋がる透明性を実現する要素として技術と情報がある。サンディア国立研究所は、科学技術研究所として、技術を透明性・信頼性向上を支援する重要な手段(tool)の一つと考えている。技術発展により、信頼性向上に向けた取組が、望ましい状態で実施されていることを確認することが可能となり、また、望まない活動が存在しないことを確証するための信頼性の高い検知能力が可能となる。つまり、技術は、望む活動の確認と望まない活動が存在しないことの確認の両方に資する。
- また、時宜に適った信頼性の高い情報を、指定された情報受領者に自動的に送信することを可能にするのも技術の力である。
- サンディア国立研究所はシステム研究所として透明性・信頼性確保のためのシステム・アプローチも重視する。すなわち、核物質取扱い施設・活動の初期の設計段階において、透明性・信頼性確保のためのシステムを組み込むといったアプローチを推奨する。不慮の事故・偶発事件・テロなどに対する対抗措置として、脆弱性分析及び対応のためのシステム構築も重要である。
- 情報が信頼醸成に資するためには、情報の信頼性と有用性を確保することが重要であり、その信頼性確保のために、たとえIAEAの定める認証基準以下のレベルであっても、認証(Authentication)を伴うことが不可欠である。
- 宇宙飛行士だった自らの経験から言えば、国際宇宙ステーションも、冷戦中には考えられなかった米露の協力を実現するプログラムとして信頼醸成の取組の一つと評価できる。この国際宇宙ステーション内で日米露仏の宇宙飛行士間で共有される情報に信頼性が不可欠であることは言うまでもないが、この様な透明性向上及び信頼醸成に向けたイニシアティブに共に取り組むこと自体も、信頼醸成に繋がる。
ショー氏(ASNO)

- 透明性を議論するに当たり次の4つのポイントを指摘したい。
- IAEAの立場から、保障措置の効果的な運用を可能にするためには、メンバー国は国内の保障措置実施機関に統一された法的権限を確立すること、保障措置運用に当たりIAEAに対してメンバー国の保障措置実施機関が協力し透明性を確保し、信頼醸成に努めることの二つが重要である。つまり、保障措置の実施に透明性・信頼性の確保が不可欠であることを強調したい。
- 早期に追加議定書を批准し統合保障措置へと移行した* 27オーストラリア政府の視点からは、IAEAとの緊密な協力が核不拡散における信頼醸成に重要であることを主張したい。オーストラリアは、追加議定書運用に際しての技術的手法開発において、積極的にIAEAに協力した。特に、追加議定書に従ってIAEAに提供される補完的なアクセスに関しては、オーストラリアはウラン鉱山へのアクセスを認めるなどの前例のない措置を実施することで、IAEAの検証能力の向上に協力した。
- 核不拡散における国家間の信頼醸成には、技術的要素の他に、人間同士の接触、つながり、及びネットワークが不可欠である。特に、地域協力の歴史の浅いアジア地域において、信頼醸成に向けた人のネットワーク作りの価値は高い。その観点から、オーストラリアが提案する「アジア太平洋保障措置連合」構想も、アジア太平洋地域の保障措置・核セキュリティの専門家同士のネットワーク作りを通じて、保障措置・核セキュリティ強化と共に、信頼醸成を図るという点で、潜在的に有益な手段ともなりえる。このような構想が有益となり得るためには、IAEA保障措置業務との重複を避けるといった配慮が重要であることは言うまでもない。
- 最後に、国家間の信頼醸成を図るに当たって、先入観、偏見にとらわれ他国を型にはめて判断することは、非生産的であるばかりではなく、逆効果であり、国家間の信頼を著しく損ねることに繋がる。信頼醸成を図る上で、このような偏見・先入観を排除して取り組むことが重要と考える。
久野氏(東京大学/JAEA)
- 信頼醸成措置として、IAEA保障措置との重複は避けなければならない。補完的アクセスは重要であるが、IAEA以外の国からのアクセスには議論の余地がある。
- IAEAとの間だけではなく、事業者レベルあるいは国家レベルにおいても、カメラ映像の交換などは意味あると考える。
ユーン氏(KINAC)
- 信頼醸成に関して、近隣諸国との関係という点で、近すぎる故の居心地の悪さが存在し、そのような場合、居心地の悪さを緩和するために、カメラ映像の交換など有用かと思う。
- 日韓の取組においても、米国の関与は非常に重要であり、日米韓の3か国間での透明性措置の構想では、米国にコーディネーターとしての役割を担ってもらうのがいいだろう。
カラシュディ氏(タイ・エネルギー省)
- 信頼の重要性に関連して、隣国とのコミュニケーションの重要性を強調したい。原子力活動について、コミュニケーションが取られていない場合は、隣国にとって多大な懸念事となりえる。仲裁者的な立場でのIAEAの関与も重要であり、IAEA主導で当事国においてセミナーなどの会合を開き、隣国を招いて情報共有を促すことを目的にコミュニケーションを図るのも有効である。
ダウド氏(マレーシア原子力庁)
- マレーシアは原子力発電については潜在的な新興国に過ぎないが、原子力政策・活動についての透明性確保・隣国とのコミュニケーションの確立は長年に渡り実行してきた。1980年代に、マレーシアが原子力発電導入を計画した際、シンガポールを始めとする隣国から強い反対があったため、ASEANの枠組みのなかで、セキュリティ、原子力安全について閣僚級レベルの会合を開いたこともある。重要なことは、何を計画しているのか伝えること、コミュニケーションをとる意志を示すことである。話すことで理解を助け、コミュニケーションを通して、信頼醸成を図ることが大切である。
会場からの質疑応答・コメント(3)
Q3
日本政府もFNCA、RCAなどに積極的に関与し、コミュニケーションを図ってきたが、保障措置の領域に関してはIAEAに委ねてきたという経緯がある。そこでオーストラリアASNOの提案するアジア太平洋地域保障措置連合構想について、そのコンセプトについて話して欲しい。何を期待しているのかを教えて欲しい。また、FNCAがこの構想にどのような役割を担うことが考えられるか。
A3(ショー氏(ASNO))
アジア太平洋地域保障措置連合は、アジア原子力安全ネットワークと同様のコンセプトであり、ANSNのコンセプトを保障措置に適用したものと考えて欲しい。すなわち、知識・経験の共有の場であり、あくまでも非政治的な連合(Association)である。ネットワーク作りの発想を基に、様々なアイデアが出されている段階であり、核物質防護を含めるか、メンバー国の条件などといった議論すべき課題はまだ多い。FNCAの役割の可能性についてだが、アイデアを出すなどの補完的な役割を担えると思う。第1回会合は2007年6月にシドニーで開催され、第2回会合は韓国で2009年に開催される可能性がある。

コメント
タイのカラシュディ氏が、発表の中で、タイが核燃料サイクルの機微技術開発を実施するつもりがないことを明確に表明したことにとても感銘を受けた。(タイ、インドネシア、ベトナムなどの)原子力発電導入を検討する国が、このような核燃料サイクルについての政策・方針を明確に示すことが重要だと考える。IAEAはこのような明確な意思表明に対して、核燃料供給のメカニズム構築の支援や燃料供給に関する保証などの対応で応えるべきと考える。
ショー氏(ASNO)
核燃料供給保証に関しては既に様々な提案がされているが、NPTの代替としての枠組みではなく、NPTを土台とする枠組みであるべきである。NPTで認められた権利の放棄を求めるような仕組みは受け入れられない。実現に向けては、今後、メンバー国間の政治的なレベルでの話し合いが必要になってくる。
ダウド氏(マレーシア原子力庁)
使用済燃料の取扱いについて、再処理するのか、燃料供給国に返還するのか、説明していかなければならないと考える。マレーシアも説明できるようにしたいと思う。
チョイ氏
- アジア太平洋地域における地域的な原子力協力は信頼醸成につながる。
- 協力の潜在的分野としては、原子力安全(事故通報、緊急対応を含む)、原子力発電開発計画の促進(パブリック・アクセプタンス促進のための活動など)、信頼できる核燃料供給、使用済燃料の取扱い、IAEA保障措置レジームを補完する地域的な検証構想、原子力研究開発などがある。
- 議論を始めるのは時期尚早と考えられる分野もあるが、既に議論が活発な分野もある。核不拡散に関して、ハード面での対応は、条約の批准であり、透明性確保・信頼醸成はソフト面での対応といえる。「公開しなくてもいい部屋」を敢えて隣人を招いて見せるというのが信頼醸成を目的とした透明性取組である。
- 国内の原子力プログラムの健全な発展を支えるために、地域的協力を考える機運が生まれつつあり、重要なことは、一歩ずつ段階的な歩み寄りで着実に協力関係を築くことである。
会場からの質疑応答・コメント(4)
コメント
信頼醸成で最も重要なことは、疑問を抱く国の疑問に応えることだと考える。その方法は、まず使用済燃料の取扱いを含めた原子力政策・方針を表明すること、どのような原子力施設があるか公にすることである。第2に、上記の表明、情報公開の証拠を提示することで、情報が正しいことを示すことである。そして第3に、未申告の核物質・活動がないことをはっきりと示すことである。この点で、IAEAがそのような物質・活動が存在しないことを保証するための能力強化にもっと重点を置くべきであると考える。
Q4
研究開発に関する透明性と知的財産保護の関係について、IAEAの守秘義務について説明して欲しい。
A4-1(グティエレス氏(SNL))
IAEA職員ではないので、私は宇宙計画に関与した際の経験から話したい。共有する情報のレベルは多様であり、知的財産権を損ねずに情報共有することは可能である。
A4-2(ダウド氏(マレーシア原子力庁))
透明性と知的財産権の保護や機密事項の遵守の両方のバランスをとることは難しい。家に招いて、「この部屋は見せられませんよ」ということにより、不安を残すことにはなるが、家に招かないよりは信頼醸成につながるのではないか。つまり“Non-disclosure Agreement”を締結することも時には必要である。
A4-3(会場)
以前、IAEA査察情報処理部長であった経験から話をすると、IAEAの保障措置関係者は保障措置に関する情報を開示してはならないという義務を負っており、それはIAEA退職後も同様である。コンピューター上でも、IAEAの他部門から保障措置に関する情報にはアクセスできないようになっている上、様々なアクセスのルールがある。情報対象国政府の許可がない限り、情報の公開は許されていない。
チョイ氏
- 一つの事例として、EURATOMの経験から何か学ぶことは出来ないか?
- アジアにおいてはこれまでASIATOM, PACATOMなど幾つかの取組が提案されたが実現しなかった。
- 恐らく、このような地域的な協力の枠組みが必要であるという点では、意見が一致すると思うが、問題は、どのように進めていくべきかで考えがまとまらないことだと思われる。
2) 人材育成について
グティエレス氏(SNL)
人材育成のためには、学生だけではなく教授もターゲットにするのが有効である。
ダウド氏(マレーシア原子力庁)
人材育成については、価値連鎖(value chain)全体を考える必要がある。すなわち、上は専門家や教授から下は学生に至るまでを見渡し、他の産業との人材獲得競争に勝つ方法を考えることが重要である。
カラシュディ氏(タイ・エネルギー省)
- 今、タイでは原子力工学プログラムのある大学が一つしかなく、将来の深刻な人材不足が懸念される。政府の支援の下で、人材育成計画を推進する必要がある。
- 現在、人材育成に関して、どのような人材が必要か、資金的な計画などの検討を進めている。
- 原子力発電導入が政府決定され、その後延期された30年前の経験から、導入決定があってから人材育成に着手するのではなく、人材育成の準備を進めた上で、原子力発電導入決定に導くべきだと考える。
- 既に、30歳以下の若い原子力関連作業者などを中心に、教育プログラムを開始している。また海外でトレーニングを受けさせることも検討している。
ユーン氏(KINAC)
- 原子力分野における人材育成の必要性については、見解が一致するところである。韓国では原子力ルネサンスを反映し、原子力工学に対する関心が高まりつつあるが、インセンティブの供与など、政府の後押しがもっと必要である。
- 資金不足の問題があり、今後の資金計画を含む人材育成に関するマスタープランを作成するべきであると考える。
久野氏(東京大学/JAEA)
核不拡散についての国際フォーラムなどへの学生の参加を促し、核不拡散の現場を見てもらうことが重要である。IAEAなどの国際機関に学生も派遣している。他の大学との交換留学制度も模索したいと考える。
会場からのコメント
- 産業界の関与が不可欠だと考える。産業界と連携し、職場内訓練などの機会を活用していくことが重要。特に核物質など機微な物質を取扱う従業員全てにこのような訓練を受けさせることが必要である。
- 文部科学省の研修制度は、アジア諸国の原子力の基礎知識の構築に大変有益である。しかし、まだ不十分であり、産業界の関与が深められること、保障措置についてのプログラムが充実することが求められる。
チョイ氏
(グローバルCOEプログラムについて紹介)
- 原子力社会学を柱として、核不拡散と原子力の平和利用の共存を目指したプログラムである。
- 技術的な問題に対する体系的な取組もプログラムに組み込んでいる。
- カリフォルニア大学バークレー校、AREVA、中国の清華大学との協力を実施している。
(6) モデレーターによる総括
- 社会形成において「信頼」が主要構成要素であるのと同じく、原子力の平和利用に関する国家間の信頼醸成が核不拡散体制の強化にとって不可欠である。
- 原子力の平和利用における透明性を確立することは、信頼醸成につながる。
- 信頼を醸成するには、人と人とのコンタクトを通じたネットワーク形成が不可欠であり、また段階的な取組により、小さなステップでも着実な前進を確実にすることが信頼醸成にとって重要である。
- 日韓間などの二国間においても、原子力の平和利用に関して、実行可能な協力の取組から段階的に実施していくことで、着実な信頼醸成が可能である。
- 同様に、原子力の平和利用に関する地域の協力の取組は地域の核不拡散についての信頼醸成にとって重要である。
- 原子力・核不拡散分野における将来の人材不足は深刻な懸念であり、有効な人材育成の方法について活発に議論された。
- 人材育成の重要性が強く認識され、効果的な人材育成を支援する上でも、国際協力が必要であるとの認識で一致した。


注釈
* 20Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology(原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定)
* 21ASEAN Regional Forum(アセアン地域フォーラム)
* 22Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation(アジア不拡散協議)
* 23ASEAN Nuclear Energy Safety Sub-Sector Network (NES-SSN), The ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) & ASEAN Senior Officials of Energy (SOE),The ASEAN Committee on Science & Technology (COST), など。
* 24virtual private network(仮想プライベート・ネットワーク)
* 25CTBTに関しては、1996年に署名しているが、現時点で未批准であり、核テロ条約に関しては2005年に署名済であるが、批准には至っていない。また、追加議定書については2005年に署名したが、現時点で未批准となっている。
* 261962年に93%の高濃縮ウランを燃料としたTRR-1として初臨界。1977年に低濃縮ウランを燃料とするTRIGA Mark IIIに改修し再臨界。名称を現在のTRR-1/M1と改名。
* 27オーストラリアは世界で最初に追加議定書を批准し(1997年12月12日)、世界で2番目に統合保障措置が適用された国となった。
6. 閉会挨拶
(東京大学大学院工学系研究科・教授/グローバルCOEプログラム拠点リーダー:岡 芳明)

- 原子力発電の有用性について注目が集まる中、核不拡散の重要性も認識される。当フォーラムにおいては、アジア太平洋地域における、原子力の平和利用と核不拡散の両立に向けた今後の取組について、核不拡散・原子力に関連する各界の代表的な方々との具体的な提案を含む率直な意見交換ができたという点で、大変有意義であったと認識する。
- 東京大学では、原子力社会学、原子力エネルギー、放射線応用の3分野からなる教育を、原子力国際専攻を中核専攻として、グローバルCOEプログラムの資金を得て行っている。核不拡散は、原子力社会学の中の主要プログラムの一つとして、JAEAの全面的な協力を得て進められている。
- 原子力利用は他のエネルギーに比べて多くの不確定要素を含むため、原子力利用の利点を有効に活用するためには、不確定要素の低減が不可欠である。原子力社会学はそのようなリスクの低減を目指したプログラムであり、核不拡散はリスク低減の最も重要な要素である。
- このように重要な核不拡散問題の協議の場としての本フォーラムの成功に皆様方の協力をいただいたことに感謝するとともに皆様方の益々のご活躍をお祈りする。
