一般寄附金
若手研究・技術者による斬新で挑戦的な活動へのご支援
研究者紹介
令和5年度萌芽研究開発制度
溶融塩電解による土壌粘土鉱物からの熱電変換材料創製
― ありふれた塩と土壌から、熱を電気に変える材料を創り出す ―
材料研究ティビジョン アクチノイド科学研究グループ マネージャー・研究副主幹 本田 充紀
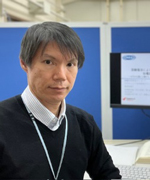
私の研究では、ありふれた塩と土壌から熱を電気に変える材料を創り出すことを目指しています。この目的のために、粘土鉱物から放射性セシウム(Cesium)を除去する技術である溶融塩法を活用しました。この技術は、風化黒雲母などの粘土鉱物にアルカリ混合塩を添加し熱処理する方法を応用したものです。このプロセスにより、高温動作する低環境負荷な熱電変換材料を作り出せることが判明しました。この研究での重要な成果の一つは、溶融塩法によって作製された結晶の熱電性能を、無次元評価指数ZTによって正確に評価したことです。ZTの算出には、ゼーベック係数、電気抵抗率、熱拡散率を同時に測定する必要があり、このために導入された熱電特性評価装置は試料形状が同一であり、より信頼性の高い測定が可能になりました。本研究は、粘土鉱物から熱電材料を創製する新たな可能性を開きました。これらの成果は廃熱回収技術の進展に貢献し環境に優しい熱電材料の開発に向けた一歩となります。イノベーションチームのサポートと協力により、当研究成果を基にした特許出願を行うことができました。今後はさらなる性能向上や応用範囲の拡大を目指しています。
この研究を支援してくださった寄附者の皆様には、心から感謝申し上げます。
令和5年度萌芽研究開発制度
超音速分子線を用いたグラフェンガスバリア特性評価のための要素技術開発
― 放射光精密分析で解き明かす材料表面酸化の年レベルの未来予想 -
材料研究ティビジョン エネルギー材料研究グループ 研究主幹 吉越 章隆
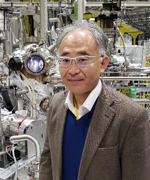
私の研究では、材料の腐食防止やより高度な材料の機能発現を引き起こすような2次元原子層コーティングに関連する研究開発に取り組んでいます。材料の腐食による経済損失はGDPの数%におよぶと言われており、世界全体でみれば膨大です。また、経済損失ばかりでなく公共インフラなどの劣化は生活基盤を揺るがす重要課題であり、その解決は安全・安心な国土強靭化の実現に不可欠です。私は、グラフェンなどの2次元材料の持つガスバリア特性に注目し、腐食現象を気体分子、例えば酸素ガスと材料表面の化学反応と捉え直し、その原子・分子レベルで起きる微視的世界の表面現象を大型放射光施設(SPring-8)の軟X線光電子分光による“その場”分析を使って調べています。特に並進エネルギーの大きな高速で動く分子は少ないながらも存在しますが、数年にわたって材料に衝突した場合、その影響は無視できません。そこで、超音速分子線技術を活用して数eVの並進エネルギーの分子が照射された状況を僅か数時間で実現し、数年先の材料の化学状態を調べる(予想する)ことに挑戦しています。
本研究では、2次元原子層コーティング材料であるグラフェンの物性制御の一環として、グラフェン中に添加された極めて微量なドーピング元素の検出とそれによる電子状態変化の精密分析に成功しました。また、電子放出材料として重要なLaB6上にグラフェンと同様の2次元原子層材料であるh-BNを被覆することによって、LaB6の仕事関数を下げることに成功し、電子放出量の増大とそのメカニズムの解明に成功しました。これらの成果はプレスリリースされるとともに内外から注目されています。以上の放射光表面分析実験の実現の一部に寄附金を活用させていただきました。今後は、本研究成果を発展させ、高効率電子源による電子顕微鏡、電子線描画装置、加速器などの実現に向けた研究開発に発展させ、これらの先端機器を活用した半導体微細加工や先端物質材料分析などのナノテクノロジーに関連するイノベーション研究を発展させたいと思っています。
寄附者の皆様には、萌芽研究開発制度の枠組みのもと、このような研究の機会を与えてくださったことに心から感謝を申し上げます。
令和4年度萌芽研究開発制度 ラジウムの電子状態評価による粘土鉱物への微視的吸着構造の精密決定

私の研究では、マクロな環境挙動をミクロな化学反応に基づいて理解することを目指しています。放射性元素を含むあらゆる元素はこの世界を循環していますが、その動き方は元素によって異なります。地球上で各元素がどう動くのか?というマクロな挙動を正確に理解するため、ナノメートルの世界で各元素がどのように存在し動くのか?というミクロな挙動を解明することを目指しています。
本研究では、ウランなどから生成する放射性元素のラジウムと、様々な元素の動きに影響を与える粘土鉱物に着目しました。広域X線吸収微細構造(EXAFS)法による測定やスーパーコンピューターを用いた第一原理シミュレーションにより、溶液中や粘土鉱物に吸着した時のラジウムイオンがどのような構造で存在しているのかをミクロに調べることができました。今回の手法は様々なシステムに応用できるため、ラジウムの分子レベル研究の先駆けとなる重要な研究になったと考えています。今後はより複雑な環境中での反応や生体内での反応に着目し、環境汚染防止や医薬品開発など、重要な課題解決に応用していきます。寄附者の皆様のご支援に心から感謝申し上げます。
令和3年度萌芽研究開発制度 半導体スイッチ電源の確立を目的とした特性インピーダンスのマッチング手法の開発
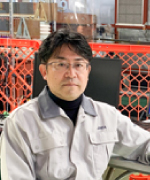
私の研究では、従来品より高耐圧・低損失の特性に優れる次世代パワー半導体を用いたスイッチ電源の開発に取り組んでいます。大電力を扱う変換器には放電管のスイッチが多く使われていますが、環境問題などから放電管の製造中止が見込まれています。そのため、パワー半導体による代替機の開発が不可欠です。しかしながら、次世代パワー半導体の性能を活かす基盤技術の開発があまり進んでいません。そこで私は、半導体スイッチ電源の回路構築に必要な、電力伝送導体部と高耐圧構造の最適設計に取り組みました。
本研究では、電位差由来のインピーダンスミスマッチを解消できる円錐型の導体と、高電圧出力時のコロナ放電を低減するセラミックス長尺絶縁筒碍子の製作に、寄附金を活用させていただきました。寄附者の皆様には、萌芽研究開発制度の枠組みのもと、このような研究機会を与えてくださったことに心から感謝申し上げます。今後は、本研究成果を発展させ、低炭素・省エネ社会の実現に向けた、革新的な半導体スイッチ電源の開発に努めて参ります。
令和3年度萌芽研究開発制度 配位高分子の微量イオントリガー型構造変化を利用した元素センサー

私の研究では、放射性元素を効率よく除去し、環境浄化する手法として、主に有害元素を吸着する材料の開発を行っています。例えばセシウムなどの有害な放射性元素は、主にゼオライトやプルシアンブルーといった吸着剤で比較的簡易に除去することができます。このような技術は原子力の分野では、主に放射性元素の施設外への漏洩を防ぐ目的で高度に発展してきました。また同分野では分離した元素を回収する技術の開発も盛んです。私もこの技術を学ぶとともに、有害な元素の処理処分法を学んできました。
近年、有害金属による広範囲な汚染や環境汚染問題が持ち上がる中で、私は原子力の元素分離回収技術をもっと広範囲な環境修復に応用し、より良いものにしたいと考えました。現在では、鉛やカドミウム等の有害元素による汚染が知られ、有用金属の回収も、資源確保に非常に重要な研究分野です。これらの技術は元素を効率よく除去し再生する、原子力で高度に発展した技術を応用すれば、改善できる可能性が高いです。
本研究では、様々な元素を様々な環境から除去回収や検出する技術の開発を目指して、イオン選択的な有害元素吸着剤の開発を行っています。この研究においては、配位高分子というこれまで殆ど吸着剤に用いられてこなかった材料を使って、元素のイオンサイズをこれまで以上に精密に認識することで、イオンを認識します。今回は有害金属である鉛の除去や検出を行い、汚染が見えにくく問題となっている鉛中毒に関連する問題に取り組みました。寄附者の皆様にはこの研究を支えてくださったことに、大変感謝しています。
あなたの寄附が研究を前進させます。ぜひご協力ください。
寄附をする