|
平成18年7月20日 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
|
|
ITER用プラズマ加熱装置で1000秒運転を達成 -ITER定常燃焼実験に向けた大きな一歩- |
|
独立行政法人日本原子力研究開発機構(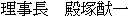 、以下「原子力機構」という)は、高周波を用いたITER用プラズマ加熱装置の開発を進めてきたが、このたび、同加熱装置の心臓部であるジャイロトロンと呼ばれる高周波発生装置において、ITERの実験に使用できる出力レベル600キロワットで、ITER標準運転時間の400秒を大きく上回る1000秒の連続出力に世界で初めて成功した。 、以下「原子力機構」という)は、高周波を用いたITER用プラズマ加熱装置の開発を進めてきたが、このたび、同加熱装置の心臓部であるジャイロトロンと呼ばれる高周波発生装置において、ITERの実験に使用できる出力レベル600キロワットで、ITER標準運転時間の400秒を大きく上回る1000秒の連続出力に世界で初めて成功した。ITERでは、プラズマを1億度以上に加熱し、400秒間核融合燃焼を持続させることを目標としている。さらに、核融合炉に必要な連続運転のデータを取得するため、1000秒以上の長時間運転を計画している。プラズマを加熱する手段の一つとして、高周波を用いる方式がある。これは、電子レンジの様に、高周波のエネルギーでプラズマを加熱するもので、プラズマ中の加熱位置を自由に選択できるという大きな特徴があるため、プラズマの制御や閉じ込めにも貢献でき、将来の核融合発電炉でも採用が有力視されている技術である(資料1)。 高周波加熱装置は、周波数170ギガヘルツの高周波(電子レンジの70倍の周波数)を生み出すジャイロトロンとそのエネルギーをプラズマまで伝える送電部、高周波をプラズマに打ち込むためのアンテナ部から成る(資料2・3)。これらのうちジャイロトロンの開発が最も重要な課題であり、日本をはじめ、ヨーロッパ、ロシアがITERで計画する長時間出力が可能な装置の開発にしのぎを削ってきた(資料8・9 )。 原子力機構は、これまでにもITER用ジャイロトロンについて、世界最高の効率の達成、人工ダイヤモンド窓の開発、1000キロワット級高周波の発振などを世界に先駆けて成し遂げ、開発をリードしてきたが、これまで内部での発熱や発振出力の低下等により、出力時間は100秒程度に留まっていた(平成15年、資料4)。 今回、①ジャイロトロン内部で散乱する不要な高周波を低減する技術を見いだし内部機器の温度上昇を抑えたこと、②大電力高周波の発振の安定化に成功したこと、③発振用電子ビームの質を向上させて発振効率を高めたこと、等により長時間運転が可能となり、ITERで使用できる高性能ジャイロトロンの開発に成功したものである(資料5・6・7)。 この成果により、高周波を用いたプラズマ加熱によるITER定常燃焼実験の実現性が一段と高まった。 今回の成果は、平成18年10月に中国の成都で開催される第21回IAEA核融合エネルギー会議で発表する予定である。 ・ITER用プラズマ加熱装置で1000秒運転 ITER定常燃焼実験に向けた大きな一歩(PDF、8335kB) ・資料1:高周波加熱とは(PDF、35kB) ・資料2:ITER用170ギガヘルツ高周波加熱装置(PDF、44kB) ・資料3:ジャイロトロンのしくみ(PDF、26kB) ・資料4:ITER用ジャイロトロン開発のこれまでの成果(PDF、20kB) ・資料5:今回の成果をもたらした改良点(PDF、3216kB) ・資料6:今回の成果をもたらした改良点(電子銃部)(PDF、89kB) ・資料7:今回の成果をもたらした改良点(高周波放射部)(PDF、3517kB) ・資料8:ジャイロトロン開発の進展(出力500kW以上)(PDF、19kB) ・資料9:ITER用ジャイロトロン開発の現状(出力500キロワット以上)(PDF、16kB) ・用語解説 |
|
| 以 上 |
|
|
もどる |
|