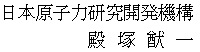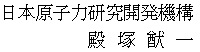平成18年1月4日
平成18年 年頭所感
原子力の未来を拓く幕開けの年として

昨年10月、日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構を統合して「日本原子力研究開発機構」が誕生いたしましたが、年頭にあたり、理事長としての所信を述べさせていただきます。
さて今年は、原子力機構として本格的な「成果を出す年」であり、真価が問われることになると考えています。
昨年は、原子力界に明るい兆し、一歩前進の出来事がありました。国内においては、原子力政策大綱の閣議決定、これを受けて関係する行政機関における委員会活動の立上げや、私共、原子力機構においても、法人発足はもとより、もんじゅ改造工事の着手、ITER計画の展開など、長年の懸案事項について、いくつかの進展がありました。また、国外においても、エネルギーセキュリティや地球環境問題等から原子力について再評価の動きが確実なものとなってきています。
このような情勢の下で、発足後、実質的に初年度を迎える本年、原子力機構の任務をきちんと果たすためには、先ず、しっかりと足元を固めて、磐石の礎を築くことに力を注ぐ必要があります。そのために、力を注がなければならない点は次の二点であると考えております。
一点目は、「安全確保を大前提に事業を確実に進展させること」です。原子力機構発足時に国から示された中期目標を受けて作成した中期計画を確実に実施していく必要がありますが、中でも重点事業についての平成18年における進展について触れたいと思います。
まず、高速増殖炉サイクル技術の実用化については、基礎・基盤的な研究開発のポテンシャルを結集しながら実用化像を描き、平成17年度末に実用化戦略調査研究のフェーズIIの成果とそれを基にした研究開発の重点化の考え方等について取りまとめを行い、外部の評価を受けるとともに、この評価結果に従って着実に研究開発を進めてまいります。また、その中でも中核となる原型炉「もんじゅ」については、運転再開に向けて改造工事を安全かつ着実に進めてまいります。
次に、核融合研究開発については、これまでのJT−60を活用した先導的な研究や超電導コイル技術など核融合工学技術開発を進め、ITER計画に貢献し、これをリードするような研究開発に積極的に取り組んでまいります。
次に、高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究については、北海道幌延町と岐阜県瑞浪市において進めている、地下深部の地層を研究するための施設建設を着実に進めてまいります。
また、量子ビーム応用の研究については、高エネルギー加速器研究機構と共同で東海村に建設を進めている大強度陽子加速器計画 J−PARCの推進に重点を置き、完成の暁には、生命科学、物質科学、素粒子物理など、我が国として世界に誇れる最先端科学技術の研究施設になるよう推進してまいります。
その他、原子力の安全と平和利用の推進に貢献し、産業界や大学との連携や原子力分野の人材育成においても、積極的な役割を果たしていけるよう努力してまいります。
二点目は、「チャレンジ精神溢れる組織風土を醸成すること」です。過去からの慣行、伝統に固執し、情勢の変化に適応力を失った組織は凋落をみることは必至であります。現代とは、取り巻く周辺環境の変化に如何に適応するかということに組織の存命がかかっている時代であります。変化に適応するための方策として、「チャレンジ精神溢れる組織風土」とはどういうものか、私なりに一つの例を挙げれば、「融合研究の推進」という課題であります。
私は、原子力機構設立の際、全職員に「融合と協力」を訴えてきました。これに対して機構内で具体的な連携などが進みつつあり、手応えを感じていますが、今年はより一層の推進を図るために、ニーズとシーズの出会いの場の設定等システム的に行っていきたいと考えています。
以上の二点に特に力を注ぎつつ、中期計画に沿って、1年間にできるだけ多くの「目に見える成果」を挙げられるよう取り組んでまいりますが、加えて私は、これらの成果を社会に示していくため、“one season one item”というスローガンで、職員を指導してまいります。我が機構の研究開発課題は、短期間でその成果が目に見えるものではありませんが、これだけ変化の早い時代にあっては、世界に冠たる研究開発機関として、存在感のある原子力機構を目指すには、それぞれの拠点、部門における研究開発成果を適切なスピード感をもって発信し続けることが不可欠であると確信しております。
原子力の未来は、私たちが背負って立っているという気概を持ち、原子力機構が、世界から信頼され、期待され、尊敬される組織となるよう、役職員一同力を合わせて、その道筋を切り拓く2006年としたいと考えております。
以 上